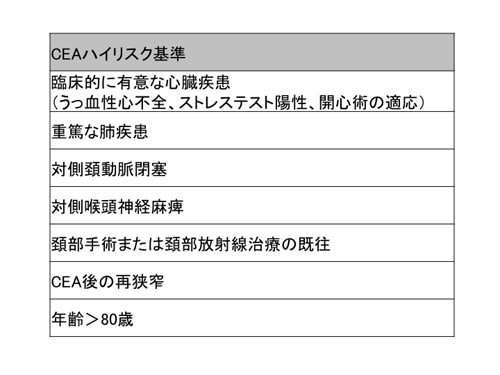昨日、母校である県立岐阜高校で授業をしてきました。
「なぜあなたが高校で授業を!?」とお感じでしょうが、これは高校とPTAが企画した「卒業生から生徒へメッセージを送る」ためのセミナーなのです。
私は1年5組と6組に25分ずつ授業をしました。
他に招かれていた方は、パイロット、女子大学教授、会社経営者、税理士、女性の大手銀行支店長などなど多彩でした。
私の話をどの程度理解して興味を持ってもらえたのか分かりませんが、母校で授業できるなどとは夢にも思っていなかったので、とてもうれしく思いました。授業後には生徒の人たちに無理をお願いして記念撮影をしました。
保護者や地域の人も参加できるということでしたが、実際、多くの方に聞いて頂けました。
一生に一度だろうと思い気合いを入れたつもりでしたが、大丈夫だったのかどうか、ちょっと不安です。
彼らから後日届くという感想文が楽しみです。
また恩師の先生にも会うことができました。
なんと教育実習で教えてもらった先生(水谷先生)です。
非常に面白い先生だったので、強く印象に残っていましたが、本当に水谷先生かどうか確信が持てるまで少しかかりました。
こんなに楽しい経験をさせてもらい、関係者の方々に心から感謝申し上げたいと思います。
「なぜあなたが高校で授業を!?」とお感じでしょうが、これは高校とPTAが企画した「卒業生から生徒へメッセージを送る」ためのセミナーなのです。
私は1年5組と6組に25分ずつ授業をしました。
他に招かれていた方は、パイロット、女子大学教授、会社経営者、税理士、女性の大手銀行支店長などなど多彩でした。
私の話をどの程度理解して興味を持ってもらえたのか分かりませんが、母校で授業できるなどとは夢にも思っていなかったので、とてもうれしく思いました。授業後には生徒の人たちに無理をお願いして記念撮影をしました。
保護者や地域の人も参加できるということでしたが、実際、多くの方に聞いて頂けました。
一生に一度だろうと思い気合いを入れたつもりでしたが、大丈夫だったのかどうか、ちょっと不安です。
彼らから後日届くという感想文が楽しみです。
また恩師の先生にも会うことができました。
なんと教育実習で教えてもらった先生(水谷先生)です。
非常に面白い先生だったので、強く印象に残っていましたが、本当に水谷先生かどうか確信が持てるまで少しかかりました。
こんなに楽しい経験をさせてもらい、関係者の方々に心から感謝申し上げたいと思います。