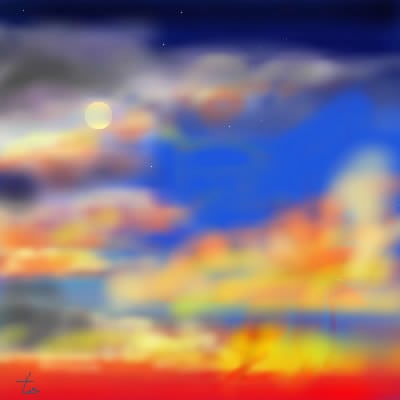今日、扉がひらかれる

第17話 祈諾、花笑―P.S:ext,side story「陽はまた昇る」
今日は11月3日、周太の生まれた日。
きっと今日、彼とは秘密を分け持つ事になる。
そうしてたぶん確認をする、彼と私はきっと同志。彼と私は同じ目的のために生きていく。
勤務先が経営する小売店舗の、10月度業績データの報告書。
どうにか午前中で終わらせた。ほっとしながら鞄を持って、デスクから立つのが嬉しい。
課長に半休と有休の挨拶を済ませてから、隣の課を覗きこんだ。
課長席の彼女はすぐに気がついて、微笑みながら席を立ってくれた。
「湯原さん、今から帰り?」
「ええ。予定通り上がれそうかな?」
同期入社で勤続する彼女と、寿退職していた私。
13年前に復職する前も後も、ずっと親しく友達でいる。
大丈夫よと微笑んで、彼女は嬉しそうに言ってくれる。
「ようやく一緒に旅行、行けるわね」
「長い約束だったね。なのに、一泊で、ごめんなさいね、」
そう、もう長い約束。
13年前の春に行く約束だった旅行。
子育てがひと段落したからと、久しぶりに一緒に旅行する予定だった。
けれどその数日前、あの人が亡くなってしまった。
昨夕、周太が恥ずかしそうに電話をくれた。
今日の誕生日の帰宅、宮田くんも連れてくると。
そして私はすぐに、彼女へ電話を掛けた。明日1泊で旅行に行けるかと。
彼女は快く、近くの温泉宿へとすぐ予約してくれた。
彼女は明るく笑って、言ってくれる。
「いいのよ、そのかわり一晩中をね、飲んで喋って笑おう?」
「あら、ずっと飲み続け?」
そんなふうに言いあって笑う。こんなふうに心から笑えて、本当に楽しい。
こんなふうに笑える日が、また来るなんて思っていなかった。
あの青年が現われるまで。
あの人が遺してくれた、ふるい木造の私達の家。
この季節は穏やかに、あの花の香が私を迎えてくれる。
馴染んだ軋みと一緒に門を開けると、楽しそうな声が聞こえた。
飛び石を踏んで、庭を覗きこむ。
「なあ、ナスって秋にとれるのな」
「ん。秋茄子って言うだろ、知らないのか」
周太と宮田くんが、並んで菜園で笑っていた。
微笑ましくて、ちょっとこのまま見ていたい。
だって、周太が笑っている。
「知らないけど?だって俺、料理とか出来ないし」
「いつか、退寮する時に困る。今から練習したら」
少し言葉は素っ気ないけれど、口調は穏やかに微笑んでいる。
周太はこんなふうにまた、話せるようになった。あの人と似た話し方、私の好きなトーン。
7ヶ月前には望めなかった、けれどずっと願っていた。もういちど、このトーンを聴かせてほしい。
そうして今、願いがまた一つ、叶っている。
そんなふうに見ている先で、きれいに笑って、宮田くんが言った。
「退寮する時はさ、周太と一緒に住む時だろ?だから困らない」
「…っばかみやたもうかってにきめんな」
ほら真っ赤になる、言葉が随分きつくなる。
けれど私には解ってしまう。あの子は今、恥ずかしがっているけれど、本当は嬉しくて仕方ない。
ほらきっと今、すごく困って途惑って。けれど幸せな微笑みは隠せない。
その隣では、きれいな笑顔が、幸せそうに咲いている。
真っ赤な顔を見つめて、穏やかに静かに佇んでくれている。
本当はずっと見ていたいけれど、そろそろ声をかけないといけない。
だって今日はこの後に、私には私の約束がある。
13年と7ヶ月も遅れた約束に、これ以上の遅刻は出来ない。
「ただいま、」
きっと今、私の顔も幸せそうに、きれいに笑っている。
渡された花束が、嬉しい。
私の好きな白い秋明菊、あわい薄紅のダリア、パステルカラーの秋バラ。あわい色彩の美しい花束。
そうしてアクセントのように、あの人の好きな花が咲いている。
「秋明菊と、チョコレートコスモスが嬉しいな」
「喜んで頂けたなら、俺も嬉しいです」
きれいな笑顔で笑ってくれる。
今日の宮田くんは、スーツでは無いけれど、なんだか改まった雰囲気。
趣味の良い着こなし、落着いた色合い。
たぶん今日の周太の服も、彼が選んだのだろうと、趣味の良さから解って楽しい。
「花言葉って、知っているかしら?」
「あまり詳しくは無いですけど」
「男の子だものね、」
男の子、と私は言った。
けれどもう彼は、男の子ではない。大人の男の顔になっている。
奥多摩地域の警察官として、山岳救助隊に彼はなった。そんな彼は、背中から大人びて頼もしい。
警察学校時代に会った時より随分と、彼は大人になった。
あの時からまだ2,3カ月。それなのにと少し、驚かされてしまう。
だからもう、こういう話も彼とは出来るだろう。
そっと内緒話のように、私は教えてみる。
「チョコレートコスモスの花言葉はね、移り変わらぬ気持ち」
「おふたりに、似合います」
ほら、やっぱり彼はすぐ理解できる。
あの人と私を、今も繋いでくれる、この花の意味。
そうして理解した彼は、今度は自分から私に訊いてくれた。
「その白い花、秋明菊の花言葉は何ですか?」
私の好きな花。その意味は寂しい、そして悲しい。
こんな意味だと知らずに、私はこの花を好きになった。
そして花の言葉のままに、私は生きる運命になっている。
そっと静かに、私は言葉を口にした。
「忍耐、」
告げると彼の、きれいな切長い目が揺れた。
ああきっと、私の事を想って心を動かしてくれている。
繊細で穏やかな、率直で健やかな彼の心。その心でずっと、周太の事をいつも考えてくれている。
けれど彼は、きれいに笑って、端正な口を開いてくれた。
「そういう姿は、一番きれいです」
忍耐。
その姿を、辛いだろう、悲しいだろうと痛ましがる人もいる。
けれど私は思っている。
すべての花々は、種の固い殻を破る痛みに耐えるから、花開く事ができる。
冷たい風、凍る雪、濡らす雨を素直に受けるから、花開いて実りを持つ事が出来る。
そのことをきっと、彼は解ってくれている。
だから私は微笑んでしまう。
「ありがとう、」
ほら彼も、きれいな笑顔で返してくれる。
だから確信してしまう。
きっと彼は私の同志、同じ目的の為に今日は来てくれた。
ほら彼は、立ち上がって微笑んでくれる。
「庭の花で、教えてほしい事があるんです」
きっとあの木の花のこと。
「いろいろ、きれいだったでしょう?」
「はい、」
庭を見てくると周太に告げて、二人で庭へ出た。
秋の陽光に、白い花が眩しく咲いている。
繊細で凛とした佇まいの白い花。花囲む常緑の葉は、冬の寒さにも夏の暑さにも輝く。
息子と似合う木、そんなふうに今は思う。
「困難に打ち勝つ。それが周太の花言葉。周太が生まれた時に、あのひとが植えたの」
怜悧で有能で温厚だった、あの人。
けれど趣味はなんだか可愛らしくて、花にも詳しかった。
そんな穏やかな優しさが、いつも私の心を開いてくれていた。
ふっと抜ける風に、白い花弁が一枚ずつ舞いおりる。
椿と似た花、けれど椿は、首落とすように花の命を終える。
そして山茶花は、ゆるやかに香を放ちながら散っていく。
だから私は椿より、山茶花の方が好きだ。
振り向いて見上げるときれいな切長い目が微笑んでいる。
端正な姿にも白い花弁が舞いおりて慕う。きれいな姿に見惚れてしまう、そして胸が痛い。
こんなに美しい存在を、私はこれから縛ってしまう。
「約束」
そんな名前の美しい束縛で、恵まれたはずの彼の人生をここに縛って留めてしまう。
その罪を解っている、けれど私には他にどんな道があるのだろう。
木蔭に据えられた、ふるいけれど頼もしい木のベンチに腰掛ける。
このベンチはあの人が作ってくれたもの。
私とこうして並んで座る、その為に忙しい合間を彼の手で作ってくれた。
懐かしい気配と温かな木漏日に坐りこんで、私は口をひらいた。
「これはわたしのひとりごと」
今から話す事は、あの人が抱えていた秘密。
私が知るはずの無い事、けれど私は気づいていた。
「25年前、夫はこんな事を言ったの、『肩代わりをしてしまった、すまない』そう言って、涙ひとつ零して、」
肩代わり―その言葉の重みは、きっと彼には解るでしょう。
静かに隣に座る端正な、静かな穏やかな気配。
私の独り言に寄り添って、佇んでいる穏やかさ。私はこの気配を、どこかで知っている?
「私の愛する人は、秘密を抱えていた。
その任務は家族にも話してはいけない、そういう場所で彼は戦っていた。
任務の為には人の命も断つ、そういう場所に彼はいた。
その事は、あの人が亡くなって、その時初めて知らされた。
けれどわたしは気付いていた。彼が何をして、何に苦しんでいたのか」
そう、私は気づいていた。
だって出会った時からずっと、私は、あの人ばかり、見つめていたのだから。
「だから思ってしまうの、優しいあの人は一瞬のためらいに撃たれたのだと…ずっと自分がそうしてきたように」
あの人はいつも、目の前の人を救ける事ばかり考えていた。
家族も友人も、犯罪被害者も、その周りも。そして犯罪者本人ですら。
救けたい、そして温めて笑わせたいと、そんな優しい人だった。
それなのに。
それなのに与えられた任務は、冷たいものだった。
任務だから、誠実だから、与えられたものから逃げられなかった。
けれど本当は、いつも心は泣いていた。そしていつも考えていた、いつか贖罪の日が来ると。
誠実で何事にも真剣だった、あの人。
誠実で真剣なだけ、有能で優秀な警察官だった。
そうして、あの人の有能さは、あの人自身を縛って堕として、苦しめた。
いま隣に座っている、端正な青年。
そのことすらも、彼はきっと解っている。そんな気がしてならない。
だから、ここからはあなたへ話したい。目で告げてから、私は話し始めた。
「息子もきっと同じ道へと引きこまれていくでしょう。彼の軌跡をたどろうと息子は同じ道を選んできたから…きっと同じ任務に、」
静かに佇んで、私の目を見つめ返して聴いてくれる。
きっと彼は、私と同じ事を考えている。
「でも息子は彼よりも潔癖という強さがあるわ、とても聡明で。だから同じ道にも方法を見つけるかもしれない、それに、あなたが傍にいる、」
私は女性で、警察官ですらもない。
あの人の軌跡も、それを辿る息子の道も、理解し追いかけることは、私には出来ない。
けれど、同じ男で警察官の彼になら、息子が選んでいく道を、理解し追いかけ守りぬける。
それは難しい事だと解っている、それでも彼にならと信じてしまう。
「彼の戦う世界で私は寄り添えなかったわ、でもあなたなら。息子と同じ男で同じ警察官なら息子の世界で、救う事が出来るかもしれない、」
きれいな笑顔、健やかな心。
そして息子への、真摯で純粋な真直ぐな想い。
どうか息子を追い掛けて、そして捕まえて救ってほしい。
「はい、」
やっぱり答えてくれる。短いけれど、真直ぐな答え。
きっと彼の願いは、私の願いと重なる。そう思って今日を待っていた。
そしてこれからきっと、私の願いを彼は、聴いてくれるだろう。
きれいな切長い目を見つめて、私は願いを告げていく。
「お願い、息子を信じて救って?何があっても受けとめて、決して独りにしないで。あの子の純粋で潔癖で、優しい繊細な心を見つめ続けて、」
どうかお願い、願わせて。
そしてこれから告げる願い、その残酷さを私は知っている。
残酷だと知りながら、私は言葉を止められない。
「そして我儘を言わせて?どうか息子より、先に死なないで、」
大切なひとと、死に別れること。
ひとり残される苦しみ、悲しみ、痛み。もう私は、知っている。
この端正な眼差しの、息子への想いの深さも、知っている。きっと彼は苦しむ、それも解っている。
けれどお願い願わせて、息子をこれ以上、苦しませたくはない。
「あの子の最期の一瞬を、あなたのきれいな笑顔で包んで幸福なままに眠らせて。
そして最後には生まれてきて良かったと息子が心から微笑んで、幸福な人生だと眠りにつかせてあげて欲しい」
自分勝手と解っている、けれど願わせて。
このまま息子は、あなたに幸せに浚われて、遠い未来に幸せに眠ること。
きれいな端正な姿、健やかで真直ぐな心。それを傷つける、そんな自分の我儘が、悲しい。
悲しくて、もう、涙が零れるのを止められない。
「あなたにしか出来ないわ、心開く事が難しい周太はあなたしか隣はいられない、私はあなたを信じるしか出来ないの。
愛するあの人と私のたった一つの宝物…あの子の幸せな笑顔を取り戻してくれたあなたにしか、あの子を託す事は出来ないの、」
涙が私をおおっていく。
ふるえる声が私の唇をゆらして告げる。
こんなふうに涙を流したこと、前はいったい、いつだったろう。
「とても私は身勝手だと解っています、あなたが本来生きるべきだった、普通の幸せを全て奪う事だと解っている。
けれど誰を泣かせても私はあの子の幸せを願ってしまうわ、あなたに願ってしまう、どうか願いを叶えて欲しい、そして、そして…」
涙の中に最後の言葉がうずもれてしまう。
ああ、さいごのことば。言いたい、けれど言うことをすら、許されるのか解らない。
ふっと頬に、なめらかな温もりがふれた。
「俺の願いも、お母さんと同じです」
きれいな長い指が、私の涙を静かに拭っていく。
きれいな低い声が、私に微笑む。
「俺はとても直情的です、だから自分にも人にも嘘がつけません。率直にものを言って、ありのまま生きる事しか出来ません。
だから卒業式の夜、俺はあなたの息子を離せませんでした。そしてそのまま離せません、何があっても傍にいたいってだけです、」
涙の底から彼を見つめる。
ありのままで「離せなかった」そう言ってくれた。
彼も今、この運命を望んでくれると言うのだろうか。
そんな想いと見上げる木洩日の照らす彼の髪は、陽に透けて煌めいていた。
「俺にとっての周太はきれいな生き方が眩しいです、そのままに純粋で綺麗な、黒目がちな瞳の繊細で強いまなざしが好きです。
あの瞳に見つめてもらえるのなら、俺はどんな事でもしますよ?それくらい本気なんです、こんなこと初めてなんですけどね、」
好き。ほんとうに?
どんな事でもする。ほんとうに?
ああどうか、彼が自から望んで、本当にそう願ってほしい。
だって周太は純粋で、真実の想いだけしか信じられない。
だから願ってしまう、この青年の想いだけは、真実であってほしい。
「警察官として男として誇りを持って生きること、誰かの為に生きる意味、何かの為に全てを掛けても真剣に立ち向かう事。
全てを俺に教えてくれたのは周太なんです、周太と出会えなかったなら山ヤの警察官として今、生きる事もありませんでした、」
誇らかな、大人の男の瞳。
きれいな笑顔は、大人の男の瞳で私を見つめてくれる。
それは全て、息子の存在があったから。
そんなふうに穏やかに微笑んで、私を見つめて告げてくれる。
「生きる目的を与えてくれた人。きれいな生き方で、どこまでも惹きつけて離さない人。静かに受けとめる穏やかで繊細な、居心地のいい隣。
得難くて大切な俺だけの居場所、それが俺にとっての周太です、周太の隣だけが俺の帰る場所です。他のどこにも帰る場所なんてありません、」
山茶花の香の風が、ゆるやかに頬を撫でていく。
この木を植えたひとの、想いがそっと寄り添ってくる。
「俺は身勝手です、だから絶対に離れません、誰にも譲らない俺だけを見てほしい。こんな独占欲は醜いかもしれないけど、もう孤独にはしません」
きれいに笑って彼は言った。
「だから許して下さい。ずっと周太の隣で生きて笑って、見つめ続けさせて下さい」
やさしい温もりの気配、静かに佇む穏やかさ。
私はこの気配を、どこかで知っている。
そう気づいた時に、そっともうひとつの気配が隣に座る。
怜悧で穏やかで、優しく私を見つめてくれた、あの瞳。
隠した秘密に寂しげに、それでも私を温めてくれていた。
いつも気づけばそっと、私の心を開いて寄り添って、佇んでいる穏やかさ。
ああ、あなた。ここに居てくれたのね
瞳の底から熱があふれだす。
心の底から熱が、瞳へと昇っていく。
そうして心の枷がひとつ、また外れて砕けて消える。
瞳に掛けられていた、後悔も贖罪も、全てが涙にとけて、拭われる。
きっと今、私の瞳は、明るい光をとりもどしている。
今この隣に座る青年、そして今も寄り添ってくれる、あの人。
どうか許して下さい、気づいていても解っていなかった。この私を許してほしい。
そしてどうか、願いを叶えてほしい。
どうぞお願い、告げさせて。
「私こそ許して。そして、息子をお願いさせて」
「はい、」
きれいな笑顔で頷いてくれる。
彼と私は同志、きっと同じ目的を抱いている、そう思っていた。
そして今お互いに、告げあって許しあえている。
「周太の花言葉は、困難に打ち克つ。あの子の困難は辛い、けれどもう独りじゃないのね?」
「はい、もう、独りには絶対にしません」
きれいなに笑って、約束をする。
彼はもう、約束してくれた。自ら進んで縛られようと、微笑んで佇んでくれた。
あなた、いま、託していいですね
私は掌を開いて、彼の前に差し出した。
「これを、あなたに持ってほしいの」
さっきからずっと、握りしめていた。13年前からずっと、使われていない鍵。
「周太の父の、合鍵です」
きれいな瞳が私に訊く「ほんとうに自分でいいのですか?」
そう、あなただからこそ、私達はこれを使ってほしい。
「あの人の想いも一緒に、あなたに持っていてほしいの」
「想いも、」
きれいな低い声が、そっと呟いた。
見つめる瞳に微笑んで、私は最後の願いを告げる。
「周太のために生きるなら、あの人の想いも背負う事になるでしょう。
あの人の想いを背負うなら、この家はあなたの家でもある。
だからあなたに渡したい、そして使ってほしい。
この鍵を使って、ただいまと帰って来て。そして私にも、お帰りなさいを言わせて欲しい」
きれいな切長い目。あの人と似ていて違う、瞳の気配。
少しだけどこか似ているのは、覚悟かも知れない。今を大切に生きていく、そんな意思が力強い。
「俺はここに、居場所と想いを求めて良いのですか?」
そっと笑って尋ねてくれる。
きれいな切長い目、どうぞ求めて欲しい。静かに頷いて、私は微笑んだ。
「ここに求めてほしいわ。そしてね、お帰りなさいと言うことを私に願わせて?」
きれいに笑って、彼は言ってくれた。
「はい、どうか俺だけに願って下さい」
嬉しそうな声と、きれいな笑顔。
やさしく笑いながら静かに見つめて言ってくれる。
「この鍵はずっと大切にします、だから周太の隣にずっといさせて下さい」
今日は11月3日、周太の誕生日。
私は13年ぶりに心を開いた、そして彼はこの家の鍵を受け取ってくれた。
この家ごと彼は笑って背負ってしまった。
あの人の真実も辛い現実も、私の痛みも喜びも、そして周太の背負うもの。
すべて抱きとめて軽々と、こんなふうに笑って背負ってくれる。
今、隣に佇んでくれるきれいな笑顔。
どうかずっとこのままで、きれいな笑顔のままで息子の隣にいてほしい。
きれいに笑って私は穏やかに隣へ告げた。
「ずっと約束して。大切にして、息子を隣から離さないで。そして幸せへと浚い続けて、あの笑顔を私に見せて」
きれいな笑顔が静かにそっと、答えてくれる。
「はい、必ず」
尋ねた彼の誕生日、花言葉は「常に微笑みを持って」
私が好きな花だった。彼に相応しい、そんなふうに私は思う。
そして願ってしまう、どうかこれからずっと、微笑んで生きてほしい。
そうして隣の息子の心を、温かく抱きしめて幸せへと浚い続けて。
台所を覗くと、周太は皿を選んでいた。ネイビーのカフェエプロン姿が懐かしくて嬉しい。
長めの前髪から覗く、黒目がちの瞳は幸せに微笑んでいる。
食器棚の前に立つ姿は、黒藍のジーンズの脚がきれいだった。
白いアーガイルニットは、藤色とブルーグレーにボルドーのポイントがかわいい。
こういう明るい色、きれいな色が、息子には良く似合う。
「おいしそうね、」
息子の横顔に声を掛ける。
振り向いた顔は、やっぱり明るく、きれいになっていた。
恋の力ねと、心裡の独りごとが楽しい。
けれど本当は知っている、恋という言葉だけでは、言えるような繋がりではない。
ひとの貌は、心でいくらでも変わる。
だからきっと息子の心は、きれいで純粋な想いに充ちている。
どうかその想いを、私と彼に守らせて。
この先きっと現われる、辛い現実と冷たい真実。純粋に過ぎる心には、きっと重たく痛すぎる。
けれど私は信じている。あの人が辿った軌跡には、必ず温かな想いも遺されている。
あの人の遺した温もりは、きっと息子の心を救ってくれる。
そしてまた、あの人の想いも意思も、きれいな笑顔が繋いでくれる。
「料理のね、皿が決まらないんだ」
ほら、こんなことにも一生懸命。
生真面目さはきっと、あの人譲り。
「この皿かな」
「ん、ありがとう」
渡しながら、きちんと受取ったのを目だけで確認する。落とされたら困るから。
それから私は訊いてみた。
「周太が着ているの、宮田くんが選んだ服?」
ほら、恥ずかしそうにする。首筋がもう赤い。
警察学校に入って、最初に帰宅した日。
息子は何度も言った「宮田がね」そして微笑んで話してくれた。
「…ん、そう」
答えてくれる、小さな声が、かわいくて。
こんなに大きくなったのに、純粋なままでいる周太。
こういう周太は簡単には、何度も誰かの名前を呼ばない。
だからあの時から、思っていた。きっと息子にとって特別な人になる。
だからあの時も、今も、彼の名前を出せばほら、首筋が赤くなる。
「よく似合ってる。ちゃんと周のこと見てくれている、それが解るな」
そうかなと、黒目がちの瞳が私に訊く。
きれいな明るい瞳、幸せに微笑んで。
確かな想いに抱かれる、安らぎと喜びを、もう知っている瞳。
「素敵ね、」
答える私の顔も、きっと明るい。嬉しそうに、周太も微笑んだ。
「ありがとう」
こんなふうに話せるのは、嬉しい。
息子が笑ってくれる、きれいな明るい笑顔。
そして私もきっと、明るい笑顔になっている。だって私はさっき、素直に涙を流せた。
そして、きれいな笑顔が佇んで、私の涙を拭ってくれた。
私は簡単には泣かない。
泣いて崩れる自分が、痛くて辛いから嫌い。
けれど13年前までは、私は自由に泣いていた。
25年前から13年前までの、12年間は自由に泣いて幸せだった。
あの人が亡くなって、私は書斎に籠る時間を持つようになった。
あの安楽椅子に座りこんで、そっと静かに瞳を閉じる。
遺された気配に抱かれて、かすかな残像に心を開く。
そんなときは、流せない涙もそっと、あの人の気配が癒してくれた。
あの人を失ってからの私と息子は、お互いだけしかいなかった。
ふたりだけで寄添う日々は、穏やかだけれど寂しくて。
相手の痛みが解るから、お互い涙を見せられない。そんなふうにお互いに、開けない心を持て余していた。
ふたりでいるのに本当は、孤独がふたつ並んでいるだけだった。
母親として抱きしめて、泣かせてやりたい。
けれど私には解ってしまう。息子は、簡単には心を開かない。
私たち母子は、あまりに似て、お互いを解りすぎて寄り添えない。
けれど今日、彼が私を泣かせてくれた。
静かに佇んで受けとめて、きれいに笑って涙を拭ってくれた。
息子のことを抱きしめる時、きっと彼は、私の事も抱きしめてくれている。
あの人の事も、この家の事も、全てを息子の為に抱きとめている。
花咲く庭、きれいな彼の笑顔。
彼の背中が大きく広くなったことを、私は教えられ安らいだ。
全てを掛けて、ずっと息子の隣に寄り添ってくれている。
きっと彼は、どんな場所からも息子を救ってくれる。
自分の誕生日に、私に手料理を作ってくれる。そういう息子が愛おしい。
あの人の分までもと、気遣ってくれる想いが嬉しい。
彼は7杯ごはんを食べた。
前に来てくれた時よりも、ずいぶん食べる。
息子の手料理をかみしめる、その口許が幸せそうで、嬉しかった。
「今まで食った中で、周太の肉じゃがが一番うまい」
そんなふうに健やかに笑う彼に、私も笑ってしまった。
それにしても、よく食べる。見ていて気持ちが良い。
山の警察官としての日々は、彼の性分に合って楽しそうだ。
奥多摩の山、あの人とも登ったことがある。
まだ幼い周太も連れて、山小屋に泊まってココアを飲んだ。
幸せな記憶のあの場所に、彼の笑顔はきっとふさわしい。
食事が済んで、ケーキでお茶をして。
それから私は、用意しておいた服に着替えて、鞄を持った。
台所を覗くと、ふたり並んで食器を片づけている。
きれいに笑って、彼が息子の顔を覗きこむ。
「なんかさ、新婚気分だよな」
「…ばかみやたくちよりてをうごかして」
可笑しくって、困る。
だってもう出かけるのに、楽しくて見ていたくなる。
けれど私はもう行かないと。13年越しの約束に、これ以上は遅れたくない。
「じゃ、お母さん出かけるね」
「え、」
自分とそっくりな黒目がちの瞳が驚いて、私を見つめている。
不意打ち驚いたでしょう?
でも隣に佇む、きれいな笑顔は動じていない。
楽しんできて下さいと、やさしく微笑んで目で伝えてくれている。
大人の男な彼のこと、きっと昨晩の電話で察していたのだろう。そうしてきっと、私の願いに答えてくれる。
「職場のお友達とね、温泉に行く約束なのよ」
「でも、」
急に言われて、周太は途惑っている。
聡明で怜悧な周太。けれど本質は、純粋なまま繊細で優しくて、大人に成りきれない。
だからこんな企みは、気づける訳もない。
そういう息子が可愛くて、私は微笑んだ。
「ずっとこの家で、私は毎晩を過ごしてきたもの。
お父さんの気配も、周太の事も、一人にしたくなかったから。
でも、今日は大丈夫だろうから、他の場所の夜を見に行こうと思って」
これだって、私の本音。
遺された気配と共に夜を過ごし、私は生きてきた。
あの人の気配をひとり置いては、行きたくなかった。
孤独な周太をひとり、置いていく事も出来なかった。
きれいに笑って、彼は言ってくれた。
「明日は仕事です。だから、夜明けまでなら留守番ひきうけます」
きれいな笑顔が、この家に居てくれる。
あの人の気配も周太も、ひとりにしないで私は外へ出られる。
「うれしいわ、お願いね」
黙って見つめていた周太も、頷いてくれた。
「ん、わかった。楽しんできて」
「楽しんでくるわ。でもお昼は家で食べたいな。たぶん、帰りはお昼過ぎ」
「ん、仕度しておく」
こんなふうに笑って、言えるのは嬉しい。
そっくりな私達母子、だから素直に甘えあう事なんて出来ない。
けれどやっぱり息子にも、少しは頼って甘えたい。
だって私が愛したひとの分身は、息子。
だからきっと、あの人が私を愛した想いのかけらが、息子の中にも遺されている。
だからきっと、そのために。家事だって上手に、息子はなってくれた。
純粋で繊細で、大人に成りきれない周太。だから頼って甘えることは出来ない。
けれど周太、あの人の面影を見せることは、あなただけにしか出来ない。
私の荷物を持って、門まで彼が見送ってくれた。
荷物を受け取りながら、悪戯っぽく私は微笑んだ。
「周太を、幸せな夜へ浚っておいて」
さすがに驚いたように、彼は私の瞳を見た。
そうね、母親にこんなことを頼まれるなんて、おかしいでしょう。
けれど私には、切実な我儘がある。私は微笑んで、口を開いた。
「あの子の幸せな笑顔を見たい。そんな私の我儘を叶えて」
内緒話のようにささやいて、切長い目を見つめて笑う。
そっと静かに微笑んで、彼は頷いてくれた。
「お母さんの我儘は、きっと俺の我儘でもあります」
大人の男の貌で、きれいに笑って答えてくれた。
やっぱりきっと、私達は同志。同じ願いに生きている。
あの人と私が過ごした夜は、本当に幸せだった。
だから願ってしまう、周太にも、もっと幸せを過ごしてほしい。
きっと「普通」から見たら可笑しいでしょう、でもそれは問題じゃない。
あの子の笑顔を守ること、その鍵を持てるのは、この青年ただひとり。
だからこれが正しい方法。あの子の笑顔と幸せの場所を、きっと私は見誤ってはいない。
だから私は、息子の隣に彼を選ぶ。
だからもう、あの人の鍵を彼に託した。
そして今、私は、この家をすこしだけ離れる。
一泊だけの小旅行。けれど私達にとって、13年間の枷を外す旅立。
見上げて、彼へと私は笑いかけた。
「宮田くん、明日は行ってらっしゃい。そして今度、またここへ帰って来て」
卒業式の翌朝、彼は母親に拒絶されたと聞いた。自分達母子の為に。
それでも、誰を泣かせても、私は息子の幸せを願ってしまう。
同じ母親として、彼女を悲しませる罪を、私は知っている。
きれいな笑顔、健やかな心。彼をここへ呼んだのは私。その罪の全てを抱いて、私は生きていく。
「はい、必ず。ただいまって言わせて下さい」
私は罪だと思っている。それなのに、きれいな笑顔は幸せだった。
きれいな切長い瞳にも、幸福が明るく揺るがない。
私の我儘は彼の我儘、さっき彼はそう言った。その言葉が真実だと、彼の眼差しが教えてくれる。
そうしてそっと気づかされる。誰に許されなくても、彼は私を許してくれている。
そうして私の貌に、きれいに笑顔が現われる。
「約束よ。お帰りなさいって言わせてね」
そんなふうに明るく笑って、軽やかに私は門を出た。

昼前に戻って、そっと玄関を開けた。
食事の匂い、けれど周太の気配が静まっている。
きっとあの子は眠っている、そう思うと嬉しかった。
あの人の書斎に、いつものように、ただいまを言いに行く。
開いた窓から、山茶花の香が頬を撫でた。重厚でかすかに甘い、あの人の残り香と重なっていく。
書斎机に活けた山茶花は、水を替えた気配がある。周太の繊細さは、こんなふうにも表われる。
花の陰、あの人の笑顔の傍に、一葉の写真が供えられていた。
青空を梢で抱いた、ブナの巨樹だった。
きっと彼が、大切にしている木なのだろう。
それをこうして、あの人に見せてくれる。そんな彼の想いが、嬉しかった。
そう、嬉しい。嬉しくて、幸せで、私の頬を熱が伝っておりていく。
明るい陽射がふるベッドで、周太は眠っていた。
久しぶりに見る息子の寝顔、懐かしくて、すこし違っている。
微笑んだ寝顔は幼げで、けれど初々しい艶がけぶっている。
きれいな頬にそえられた右腕には、赤く花のような痣がうかんでいた。
きっと彼が想いを刻み込んだ、その想いが嬉しくて、幸せな夜だったと教えてくれる。
見つめる視界の真中で、長い睫がゆれて、ゆっくり瞠かれた。
私の顔を見て、少し恥ずかしそうに笑ってくれる。
こんなふうに寝起きの顔、眺めるのは13年と7カ月ぶり。
あの夜からはもう、周太の寝顔は見なかった。
苦しい夢にうなされて、それでも独り立ち向かう。
凛とした孤独へは、踏み込むことが許されなかった。
「おかえり、お母さん」
恥ずかしそうで、けれど幸せに明るい瞳。
彼は私の我儘を、きれいに叶えてくれていた。
嬉しくて、私は微笑んでしまう。
「ただいま、周太」
blogramランキング参加中!

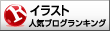
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

第17話 祈諾、花笑―P.S:ext,side story「陽はまた昇る」
今日は11月3日、周太の生まれた日。
きっと今日、彼とは秘密を分け持つ事になる。
そうしてたぶん確認をする、彼と私はきっと同志。彼と私は同じ目的のために生きていく。
勤務先が経営する小売店舗の、10月度業績データの報告書。
どうにか午前中で終わらせた。ほっとしながら鞄を持って、デスクから立つのが嬉しい。
課長に半休と有休の挨拶を済ませてから、隣の課を覗きこんだ。
課長席の彼女はすぐに気がついて、微笑みながら席を立ってくれた。
「湯原さん、今から帰り?」
「ええ。予定通り上がれそうかな?」
同期入社で勤続する彼女と、寿退職していた私。
13年前に復職する前も後も、ずっと親しく友達でいる。
大丈夫よと微笑んで、彼女は嬉しそうに言ってくれる。
「ようやく一緒に旅行、行けるわね」
「長い約束だったね。なのに、一泊で、ごめんなさいね、」
そう、もう長い約束。
13年前の春に行く約束だった旅行。
子育てがひと段落したからと、久しぶりに一緒に旅行する予定だった。
けれどその数日前、あの人が亡くなってしまった。
昨夕、周太が恥ずかしそうに電話をくれた。
今日の誕生日の帰宅、宮田くんも連れてくると。
そして私はすぐに、彼女へ電話を掛けた。明日1泊で旅行に行けるかと。
彼女は快く、近くの温泉宿へとすぐ予約してくれた。
彼女は明るく笑って、言ってくれる。
「いいのよ、そのかわり一晩中をね、飲んで喋って笑おう?」
「あら、ずっと飲み続け?」
そんなふうに言いあって笑う。こんなふうに心から笑えて、本当に楽しい。
こんなふうに笑える日が、また来るなんて思っていなかった。
あの青年が現われるまで。
あの人が遺してくれた、ふるい木造の私達の家。
この季節は穏やかに、あの花の香が私を迎えてくれる。
馴染んだ軋みと一緒に門を開けると、楽しそうな声が聞こえた。
飛び石を踏んで、庭を覗きこむ。
「なあ、ナスって秋にとれるのな」
「ん。秋茄子って言うだろ、知らないのか」
周太と宮田くんが、並んで菜園で笑っていた。
微笑ましくて、ちょっとこのまま見ていたい。
だって、周太が笑っている。
「知らないけど?だって俺、料理とか出来ないし」
「いつか、退寮する時に困る。今から練習したら」
少し言葉は素っ気ないけれど、口調は穏やかに微笑んでいる。
周太はこんなふうにまた、話せるようになった。あの人と似た話し方、私の好きなトーン。
7ヶ月前には望めなかった、けれどずっと願っていた。もういちど、このトーンを聴かせてほしい。
そうして今、願いがまた一つ、叶っている。
そんなふうに見ている先で、きれいに笑って、宮田くんが言った。
「退寮する時はさ、周太と一緒に住む時だろ?だから困らない」
「…っばかみやたもうかってにきめんな」
ほら真っ赤になる、言葉が随分きつくなる。
けれど私には解ってしまう。あの子は今、恥ずかしがっているけれど、本当は嬉しくて仕方ない。
ほらきっと今、すごく困って途惑って。けれど幸せな微笑みは隠せない。
その隣では、きれいな笑顔が、幸せそうに咲いている。
真っ赤な顔を見つめて、穏やかに静かに佇んでくれている。
本当はずっと見ていたいけれど、そろそろ声をかけないといけない。
だって今日はこの後に、私には私の約束がある。
13年と7ヶ月も遅れた約束に、これ以上の遅刻は出来ない。
「ただいま、」
きっと今、私の顔も幸せそうに、きれいに笑っている。
渡された花束が、嬉しい。
私の好きな白い秋明菊、あわい薄紅のダリア、パステルカラーの秋バラ。あわい色彩の美しい花束。
そうしてアクセントのように、あの人の好きな花が咲いている。
「秋明菊と、チョコレートコスモスが嬉しいな」
「喜んで頂けたなら、俺も嬉しいです」
きれいな笑顔で笑ってくれる。
今日の宮田くんは、スーツでは無いけれど、なんだか改まった雰囲気。
趣味の良い着こなし、落着いた色合い。
たぶん今日の周太の服も、彼が選んだのだろうと、趣味の良さから解って楽しい。
「花言葉って、知っているかしら?」
「あまり詳しくは無いですけど」
「男の子だものね、」
男の子、と私は言った。
けれどもう彼は、男の子ではない。大人の男の顔になっている。
奥多摩地域の警察官として、山岳救助隊に彼はなった。そんな彼は、背中から大人びて頼もしい。
警察学校時代に会った時より随分と、彼は大人になった。
あの時からまだ2,3カ月。それなのにと少し、驚かされてしまう。
だからもう、こういう話も彼とは出来るだろう。
そっと内緒話のように、私は教えてみる。
「チョコレートコスモスの花言葉はね、移り変わらぬ気持ち」
「おふたりに、似合います」
ほら、やっぱり彼はすぐ理解できる。
あの人と私を、今も繋いでくれる、この花の意味。
そうして理解した彼は、今度は自分から私に訊いてくれた。
「その白い花、秋明菊の花言葉は何ですか?」
私の好きな花。その意味は寂しい、そして悲しい。
こんな意味だと知らずに、私はこの花を好きになった。
そして花の言葉のままに、私は生きる運命になっている。
そっと静かに、私は言葉を口にした。
「忍耐、」
告げると彼の、きれいな切長い目が揺れた。
ああきっと、私の事を想って心を動かしてくれている。
繊細で穏やかな、率直で健やかな彼の心。その心でずっと、周太の事をいつも考えてくれている。
けれど彼は、きれいに笑って、端正な口を開いてくれた。
「そういう姿は、一番きれいです」
忍耐。
その姿を、辛いだろう、悲しいだろうと痛ましがる人もいる。
けれど私は思っている。
すべての花々は、種の固い殻を破る痛みに耐えるから、花開く事ができる。
冷たい風、凍る雪、濡らす雨を素直に受けるから、花開いて実りを持つ事が出来る。
そのことをきっと、彼は解ってくれている。
だから私は微笑んでしまう。
「ありがとう、」
ほら彼も、きれいな笑顔で返してくれる。
だから確信してしまう。
きっと彼は私の同志、同じ目的の為に今日は来てくれた。
ほら彼は、立ち上がって微笑んでくれる。
「庭の花で、教えてほしい事があるんです」
きっとあの木の花のこと。
「いろいろ、きれいだったでしょう?」
「はい、」
庭を見てくると周太に告げて、二人で庭へ出た。
秋の陽光に、白い花が眩しく咲いている。
繊細で凛とした佇まいの白い花。花囲む常緑の葉は、冬の寒さにも夏の暑さにも輝く。
息子と似合う木、そんなふうに今は思う。
「困難に打ち勝つ。それが周太の花言葉。周太が生まれた時に、あのひとが植えたの」
怜悧で有能で温厚だった、あの人。
けれど趣味はなんだか可愛らしくて、花にも詳しかった。
そんな穏やかな優しさが、いつも私の心を開いてくれていた。
ふっと抜ける風に、白い花弁が一枚ずつ舞いおりる。
椿と似た花、けれど椿は、首落とすように花の命を終える。
そして山茶花は、ゆるやかに香を放ちながら散っていく。
だから私は椿より、山茶花の方が好きだ。
振り向いて見上げるときれいな切長い目が微笑んでいる。
端正な姿にも白い花弁が舞いおりて慕う。きれいな姿に見惚れてしまう、そして胸が痛い。
こんなに美しい存在を、私はこれから縛ってしまう。
「約束」
そんな名前の美しい束縛で、恵まれたはずの彼の人生をここに縛って留めてしまう。
その罪を解っている、けれど私には他にどんな道があるのだろう。
木蔭に据えられた、ふるいけれど頼もしい木のベンチに腰掛ける。
このベンチはあの人が作ってくれたもの。
私とこうして並んで座る、その為に忙しい合間を彼の手で作ってくれた。
懐かしい気配と温かな木漏日に坐りこんで、私は口をひらいた。
「これはわたしのひとりごと」
今から話す事は、あの人が抱えていた秘密。
私が知るはずの無い事、けれど私は気づいていた。
「25年前、夫はこんな事を言ったの、『肩代わりをしてしまった、すまない』そう言って、涙ひとつ零して、」
肩代わり―その言葉の重みは、きっと彼には解るでしょう。
静かに隣に座る端正な、静かな穏やかな気配。
私の独り言に寄り添って、佇んでいる穏やかさ。私はこの気配を、どこかで知っている?
「私の愛する人は、秘密を抱えていた。
その任務は家族にも話してはいけない、そういう場所で彼は戦っていた。
任務の為には人の命も断つ、そういう場所に彼はいた。
その事は、あの人が亡くなって、その時初めて知らされた。
けれどわたしは気付いていた。彼が何をして、何に苦しんでいたのか」
そう、私は気づいていた。
だって出会った時からずっと、私は、あの人ばかり、見つめていたのだから。
「だから思ってしまうの、優しいあの人は一瞬のためらいに撃たれたのだと…ずっと自分がそうしてきたように」
あの人はいつも、目の前の人を救ける事ばかり考えていた。
家族も友人も、犯罪被害者も、その周りも。そして犯罪者本人ですら。
救けたい、そして温めて笑わせたいと、そんな優しい人だった。
それなのに。
それなのに与えられた任務は、冷たいものだった。
任務だから、誠実だから、与えられたものから逃げられなかった。
けれど本当は、いつも心は泣いていた。そしていつも考えていた、いつか贖罪の日が来ると。
誠実で何事にも真剣だった、あの人。
誠実で真剣なだけ、有能で優秀な警察官だった。
そうして、あの人の有能さは、あの人自身を縛って堕として、苦しめた。
いま隣に座っている、端正な青年。
そのことすらも、彼はきっと解っている。そんな気がしてならない。
だから、ここからはあなたへ話したい。目で告げてから、私は話し始めた。
「息子もきっと同じ道へと引きこまれていくでしょう。彼の軌跡をたどろうと息子は同じ道を選んできたから…きっと同じ任務に、」
静かに佇んで、私の目を見つめ返して聴いてくれる。
きっと彼は、私と同じ事を考えている。
「でも息子は彼よりも潔癖という強さがあるわ、とても聡明で。だから同じ道にも方法を見つけるかもしれない、それに、あなたが傍にいる、」
私は女性で、警察官ですらもない。
あの人の軌跡も、それを辿る息子の道も、理解し追いかけることは、私には出来ない。
けれど、同じ男で警察官の彼になら、息子が選んでいく道を、理解し追いかけ守りぬける。
それは難しい事だと解っている、それでも彼にならと信じてしまう。
「彼の戦う世界で私は寄り添えなかったわ、でもあなたなら。息子と同じ男で同じ警察官なら息子の世界で、救う事が出来るかもしれない、」
きれいな笑顔、健やかな心。
そして息子への、真摯で純粋な真直ぐな想い。
どうか息子を追い掛けて、そして捕まえて救ってほしい。
「はい、」
やっぱり答えてくれる。短いけれど、真直ぐな答え。
きっと彼の願いは、私の願いと重なる。そう思って今日を待っていた。
そしてこれからきっと、私の願いを彼は、聴いてくれるだろう。
きれいな切長い目を見つめて、私は願いを告げていく。
「お願い、息子を信じて救って?何があっても受けとめて、決して独りにしないで。あの子の純粋で潔癖で、優しい繊細な心を見つめ続けて、」
どうかお願い、願わせて。
そしてこれから告げる願い、その残酷さを私は知っている。
残酷だと知りながら、私は言葉を止められない。
「そして我儘を言わせて?どうか息子より、先に死なないで、」
大切なひとと、死に別れること。
ひとり残される苦しみ、悲しみ、痛み。もう私は、知っている。
この端正な眼差しの、息子への想いの深さも、知っている。きっと彼は苦しむ、それも解っている。
けれどお願い願わせて、息子をこれ以上、苦しませたくはない。
「あの子の最期の一瞬を、あなたのきれいな笑顔で包んで幸福なままに眠らせて。
そして最後には生まれてきて良かったと息子が心から微笑んで、幸福な人生だと眠りにつかせてあげて欲しい」
自分勝手と解っている、けれど願わせて。
このまま息子は、あなたに幸せに浚われて、遠い未来に幸せに眠ること。
きれいな端正な姿、健やかで真直ぐな心。それを傷つける、そんな自分の我儘が、悲しい。
悲しくて、もう、涙が零れるのを止められない。
「あなたにしか出来ないわ、心開く事が難しい周太はあなたしか隣はいられない、私はあなたを信じるしか出来ないの。
愛するあの人と私のたった一つの宝物…あの子の幸せな笑顔を取り戻してくれたあなたにしか、あの子を託す事は出来ないの、」
涙が私をおおっていく。
ふるえる声が私の唇をゆらして告げる。
こんなふうに涙を流したこと、前はいったい、いつだったろう。
「とても私は身勝手だと解っています、あなたが本来生きるべきだった、普通の幸せを全て奪う事だと解っている。
けれど誰を泣かせても私はあの子の幸せを願ってしまうわ、あなたに願ってしまう、どうか願いを叶えて欲しい、そして、そして…」
涙の中に最後の言葉がうずもれてしまう。
ああ、さいごのことば。言いたい、けれど言うことをすら、許されるのか解らない。
ふっと頬に、なめらかな温もりがふれた。
「俺の願いも、お母さんと同じです」
きれいな長い指が、私の涙を静かに拭っていく。
きれいな低い声が、私に微笑む。
「俺はとても直情的です、だから自分にも人にも嘘がつけません。率直にものを言って、ありのまま生きる事しか出来ません。
だから卒業式の夜、俺はあなたの息子を離せませんでした。そしてそのまま離せません、何があっても傍にいたいってだけです、」
涙の底から彼を見つめる。
ありのままで「離せなかった」そう言ってくれた。
彼も今、この運命を望んでくれると言うのだろうか。
そんな想いと見上げる木洩日の照らす彼の髪は、陽に透けて煌めいていた。
「俺にとっての周太はきれいな生き方が眩しいです、そのままに純粋で綺麗な、黒目がちな瞳の繊細で強いまなざしが好きです。
あの瞳に見つめてもらえるのなら、俺はどんな事でもしますよ?それくらい本気なんです、こんなこと初めてなんですけどね、」
好き。ほんとうに?
どんな事でもする。ほんとうに?
ああどうか、彼が自から望んで、本当にそう願ってほしい。
だって周太は純粋で、真実の想いだけしか信じられない。
だから願ってしまう、この青年の想いだけは、真実であってほしい。
「警察官として男として誇りを持って生きること、誰かの為に生きる意味、何かの為に全てを掛けても真剣に立ち向かう事。
全てを俺に教えてくれたのは周太なんです、周太と出会えなかったなら山ヤの警察官として今、生きる事もありませんでした、」
誇らかな、大人の男の瞳。
きれいな笑顔は、大人の男の瞳で私を見つめてくれる。
それは全て、息子の存在があったから。
そんなふうに穏やかに微笑んで、私を見つめて告げてくれる。
「生きる目的を与えてくれた人。きれいな生き方で、どこまでも惹きつけて離さない人。静かに受けとめる穏やかで繊細な、居心地のいい隣。
得難くて大切な俺だけの居場所、それが俺にとっての周太です、周太の隣だけが俺の帰る場所です。他のどこにも帰る場所なんてありません、」
山茶花の香の風が、ゆるやかに頬を撫でていく。
この木を植えたひとの、想いがそっと寄り添ってくる。
「俺は身勝手です、だから絶対に離れません、誰にも譲らない俺だけを見てほしい。こんな独占欲は醜いかもしれないけど、もう孤独にはしません」
きれいに笑って彼は言った。
「だから許して下さい。ずっと周太の隣で生きて笑って、見つめ続けさせて下さい」
やさしい温もりの気配、静かに佇む穏やかさ。
私はこの気配を、どこかで知っている。
そう気づいた時に、そっともうひとつの気配が隣に座る。
怜悧で穏やかで、優しく私を見つめてくれた、あの瞳。
隠した秘密に寂しげに、それでも私を温めてくれていた。
いつも気づけばそっと、私の心を開いて寄り添って、佇んでいる穏やかさ。
ああ、あなた。ここに居てくれたのね
瞳の底から熱があふれだす。
心の底から熱が、瞳へと昇っていく。
そうして心の枷がひとつ、また外れて砕けて消える。
瞳に掛けられていた、後悔も贖罪も、全てが涙にとけて、拭われる。
きっと今、私の瞳は、明るい光をとりもどしている。
今この隣に座る青年、そして今も寄り添ってくれる、あの人。
どうか許して下さい、気づいていても解っていなかった。この私を許してほしい。
そしてどうか、願いを叶えてほしい。
どうぞお願い、告げさせて。
「私こそ許して。そして、息子をお願いさせて」
「はい、」
きれいな笑顔で頷いてくれる。
彼と私は同志、きっと同じ目的を抱いている、そう思っていた。
そして今お互いに、告げあって許しあえている。
「周太の花言葉は、困難に打ち克つ。あの子の困難は辛い、けれどもう独りじゃないのね?」
「はい、もう、独りには絶対にしません」
きれいなに笑って、約束をする。
彼はもう、約束してくれた。自ら進んで縛られようと、微笑んで佇んでくれた。
あなた、いま、託していいですね
私は掌を開いて、彼の前に差し出した。
「これを、あなたに持ってほしいの」
さっきからずっと、握りしめていた。13年前からずっと、使われていない鍵。
「周太の父の、合鍵です」
きれいな瞳が私に訊く「ほんとうに自分でいいのですか?」
そう、あなただからこそ、私達はこれを使ってほしい。
「あの人の想いも一緒に、あなたに持っていてほしいの」
「想いも、」
きれいな低い声が、そっと呟いた。
見つめる瞳に微笑んで、私は最後の願いを告げる。
「周太のために生きるなら、あの人の想いも背負う事になるでしょう。
あの人の想いを背負うなら、この家はあなたの家でもある。
だからあなたに渡したい、そして使ってほしい。
この鍵を使って、ただいまと帰って来て。そして私にも、お帰りなさいを言わせて欲しい」
きれいな切長い目。あの人と似ていて違う、瞳の気配。
少しだけどこか似ているのは、覚悟かも知れない。今を大切に生きていく、そんな意思が力強い。
「俺はここに、居場所と想いを求めて良いのですか?」
そっと笑って尋ねてくれる。
きれいな切長い目、どうぞ求めて欲しい。静かに頷いて、私は微笑んだ。
「ここに求めてほしいわ。そしてね、お帰りなさいと言うことを私に願わせて?」
きれいに笑って、彼は言ってくれた。
「はい、どうか俺だけに願って下さい」
嬉しそうな声と、きれいな笑顔。
やさしく笑いながら静かに見つめて言ってくれる。
「この鍵はずっと大切にします、だから周太の隣にずっといさせて下さい」
今日は11月3日、周太の誕生日。
私は13年ぶりに心を開いた、そして彼はこの家の鍵を受け取ってくれた。
この家ごと彼は笑って背負ってしまった。
あの人の真実も辛い現実も、私の痛みも喜びも、そして周太の背負うもの。
すべて抱きとめて軽々と、こんなふうに笑って背負ってくれる。
今、隣に佇んでくれるきれいな笑顔。
どうかずっとこのままで、きれいな笑顔のままで息子の隣にいてほしい。
きれいに笑って私は穏やかに隣へ告げた。
「ずっと約束して。大切にして、息子を隣から離さないで。そして幸せへと浚い続けて、あの笑顔を私に見せて」
きれいな笑顔が静かにそっと、答えてくれる。
「はい、必ず」
尋ねた彼の誕生日、花言葉は「常に微笑みを持って」
私が好きな花だった。彼に相応しい、そんなふうに私は思う。
そして願ってしまう、どうかこれからずっと、微笑んで生きてほしい。
そうして隣の息子の心を、温かく抱きしめて幸せへと浚い続けて。
台所を覗くと、周太は皿を選んでいた。ネイビーのカフェエプロン姿が懐かしくて嬉しい。
長めの前髪から覗く、黒目がちの瞳は幸せに微笑んでいる。
食器棚の前に立つ姿は、黒藍のジーンズの脚がきれいだった。
白いアーガイルニットは、藤色とブルーグレーにボルドーのポイントがかわいい。
こういう明るい色、きれいな色が、息子には良く似合う。
「おいしそうね、」
息子の横顔に声を掛ける。
振り向いた顔は、やっぱり明るく、きれいになっていた。
恋の力ねと、心裡の独りごとが楽しい。
けれど本当は知っている、恋という言葉だけでは、言えるような繋がりではない。
ひとの貌は、心でいくらでも変わる。
だからきっと息子の心は、きれいで純粋な想いに充ちている。
どうかその想いを、私と彼に守らせて。
この先きっと現われる、辛い現実と冷たい真実。純粋に過ぎる心には、きっと重たく痛すぎる。
けれど私は信じている。あの人が辿った軌跡には、必ず温かな想いも遺されている。
あの人の遺した温もりは、きっと息子の心を救ってくれる。
そしてまた、あの人の想いも意思も、きれいな笑顔が繋いでくれる。
「料理のね、皿が決まらないんだ」
ほら、こんなことにも一生懸命。
生真面目さはきっと、あの人譲り。
「この皿かな」
「ん、ありがとう」
渡しながら、きちんと受取ったのを目だけで確認する。落とされたら困るから。
それから私は訊いてみた。
「周太が着ているの、宮田くんが選んだ服?」
ほら、恥ずかしそうにする。首筋がもう赤い。
警察学校に入って、最初に帰宅した日。
息子は何度も言った「宮田がね」そして微笑んで話してくれた。
「…ん、そう」
答えてくれる、小さな声が、かわいくて。
こんなに大きくなったのに、純粋なままでいる周太。
こういう周太は簡単には、何度も誰かの名前を呼ばない。
だからあの時から、思っていた。きっと息子にとって特別な人になる。
だからあの時も、今も、彼の名前を出せばほら、首筋が赤くなる。
「よく似合ってる。ちゃんと周のこと見てくれている、それが解るな」
そうかなと、黒目がちの瞳が私に訊く。
きれいな明るい瞳、幸せに微笑んで。
確かな想いに抱かれる、安らぎと喜びを、もう知っている瞳。
「素敵ね、」
答える私の顔も、きっと明るい。嬉しそうに、周太も微笑んだ。
「ありがとう」
こんなふうに話せるのは、嬉しい。
息子が笑ってくれる、きれいな明るい笑顔。
そして私もきっと、明るい笑顔になっている。だって私はさっき、素直に涙を流せた。
そして、きれいな笑顔が佇んで、私の涙を拭ってくれた。
私は簡単には泣かない。
泣いて崩れる自分が、痛くて辛いから嫌い。
けれど13年前までは、私は自由に泣いていた。
25年前から13年前までの、12年間は自由に泣いて幸せだった。
あの人が亡くなって、私は書斎に籠る時間を持つようになった。
あの安楽椅子に座りこんで、そっと静かに瞳を閉じる。
遺された気配に抱かれて、かすかな残像に心を開く。
そんなときは、流せない涙もそっと、あの人の気配が癒してくれた。
あの人を失ってからの私と息子は、お互いだけしかいなかった。
ふたりだけで寄添う日々は、穏やかだけれど寂しくて。
相手の痛みが解るから、お互い涙を見せられない。そんなふうにお互いに、開けない心を持て余していた。
ふたりでいるのに本当は、孤独がふたつ並んでいるだけだった。
母親として抱きしめて、泣かせてやりたい。
けれど私には解ってしまう。息子は、簡単には心を開かない。
私たち母子は、あまりに似て、お互いを解りすぎて寄り添えない。
けれど今日、彼が私を泣かせてくれた。
静かに佇んで受けとめて、きれいに笑って涙を拭ってくれた。
息子のことを抱きしめる時、きっと彼は、私の事も抱きしめてくれている。
あの人の事も、この家の事も、全てを息子の為に抱きとめている。
花咲く庭、きれいな彼の笑顔。
彼の背中が大きく広くなったことを、私は教えられ安らいだ。
全てを掛けて、ずっと息子の隣に寄り添ってくれている。
きっと彼は、どんな場所からも息子を救ってくれる。
自分の誕生日に、私に手料理を作ってくれる。そういう息子が愛おしい。
あの人の分までもと、気遣ってくれる想いが嬉しい。
彼は7杯ごはんを食べた。
前に来てくれた時よりも、ずいぶん食べる。
息子の手料理をかみしめる、その口許が幸せそうで、嬉しかった。
「今まで食った中で、周太の肉じゃがが一番うまい」
そんなふうに健やかに笑う彼に、私も笑ってしまった。
それにしても、よく食べる。見ていて気持ちが良い。
山の警察官としての日々は、彼の性分に合って楽しそうだ。
奥多摩の山、あの人とも登ったことがある。
まだ幼い周太も連れて、山小屋に泊まってココアを飲んだ。
幸せな記憶のあの場所に、彼の笑顔はきっとふさわしい。
食事が済んで、ケーキでお茶をして。
それから私は、用意しておいた服に着替えて、鞄を持った。
台所を覗くと、ふたり並んで食器を片づけている。
きれいに笑って、彼が息子の顔を覗きこむ。
「なんかさ、新婚気分だよな」
「…ばかみやたくちよりてをうごかして」
可笑しくって、困る。
だってもう出かけるのに、楽しくて見ていたくなる。
けれど私はもう行かないと。13年越しの約束に、これ以上は遅れたくない。
「じゃ、お母さん出かけるね」
「え、」
自分とそっくりな黒目がちの瞳が驚いて、私を見つめている。
不意打ち驚いたでしょう?
でも隣に佇む、きれいな笑顔は動じていない。
楽しんできて下さいと、やさしく微笑んで目で伝えてくれている。
大人の男な彼のこと、きっと昨晩の電話で察していたのだろう。そうしてきっと、私の願いに答えてくれる。
「職場のお友達とね、温泉に行く約束なのよ」
「でも、」
急に言われて、周太は途惑っている。
聡明で怜悧な周太。けれど本質は、純粋なまま繊細で優しくて、大人に成りきれない。
だからこんな企みは、気づける訳もない。
そういう息子が可愛くて、私は微笑んだ。
「ずっとこの家で、私は毎晩を過ごしてきたもの。
お父さんの気配も、周太の事も、一人にしたくなかったから。
でも、今日は大丈夫だろうから、他の場所の夜を見に行こうと思って」
これだって、私の本音。
遺された気配と共に夜を過ごし、私は生きてきた。
あの人の気配をひとり置いては、行きたくなかった。
孤独な周太をひとり、置いていく事も出来なかった。
きれいに笑って、彼は言ってくれた。
「明日は仕事です。だから、夜明けまでなら留守番ひきうけます」
きれいな笑顔が、この家に居てくれる。
あの人の気配も周太も、ひとりにしないで私は外へ出られる。
「うれしいわ、お願いね」
黙って見つめていた周太も、頷いてくれた。
「ん、わかった。楽しんできて」
「楽しんでくるわ。でもお昼は家で食べたいな。たぶん、帰りはお昼過ぎ」
「ん、仕度しておく」
こんなふうに笑って、言えるのは嬉しい。
そっくりな私達母子、だから素直に甘えあう事なんて出来ない。
けれどやっぱり息子にも、少しは頼って甘えたい。
だって私が愛したひとの分身は、息子。
だからきっと、あの人が私を愛した想いのかけらが、息子の中にも遺されている。
だからきっと、そのために。家事だって上手に、息子はなってくれた。
純粋で繊細で、大人に成りきれない周太。だから頼って甘えることは出来ない。
けれど周太、あの人の面影を見せることは、あなただけにしか出来ない。
私の荷物を持って、門まで彼が見送ってくれた。
荷物を受け取りながら、悪戯っぽく私は微笑んだ。
「周太を、幸せな夜へ浚っておいて」
さすがに驚いたように、彼は私の瞳を見た。
そうね、母親にこんなことを頼まれるなんて、おかしいでしょう。
けれど私には、切実な我儘がある。私は微笑んで、口を開いた。
「あの子の幸せな笑顔を見たい。そんな私の我儘を叶えて」
内緒話のようにささやいて、切長い目を見つめて笑う。
そっと静かに微笑んで、彼は頷いてくれた。
「お母さんの我儘は、きっと俺の我儘でもあります」
大人の男の貌で、きれいに笑って答えてくれた。
やっぱりきっと、私達は同志。同じ願いに生きている。
あの人と私が過ごした夜は、本当に幸せだった。
だから願ってしまう、周太にも、もっと幸せを過ごしてほしい。
きっと「普通」から見たら可笑しいでしょう、でもそれは問題じゃない。
あの子の笑顔を守ること、その鍵を持てるのは、この青年ただひとり。
だからこれが正しい方法。あの子の笑顔と幸せの場所を、きっと私は見誤ってはいない。
だから私は、息子の隣に彼を選ぶ。
だからもう、あの人の鍵を彼に託した。
そして今、私は、この家をすこしだけ離れる。
一泊だけの小旅行。けれど私達にとって、13年間の枷を外す旅立。
見上げて、彼へと私は笑いかけた。
「宮田くん、明日は行ってらっしゃい。そして今度、またここへ帰って来て」
卒業式の翌朝、彼は母親に拒絶されたと聞いた。自分達母子の為に。
それでも、誰を泣かせても、私は息子の幸せを願ってしまう。
同じ母親として、彼女を悲しませる罪を、私は知っている。
きれいな笑顔、健やかな心。彼をここへ呼んだのは私。その罪の全てを抱いて、私は生きていく。
「はい、必ず。ただいまって言わせて下さい」
私は罪だと思っている。それなのに、きれいな笑顔は幸せだった。
きれいな切長い瞳にも、幸福が明るく揺るがない。
私の我儘は彼の我儘、さっき彼はそう言った。その言葉が真実だと、彼の眼差しが教えてくれる。
そうしてそっと気づかされる。誰に許されなくても、彼は私を許してくれている。
そうして私の貌に、きれいに笑顔が現われる。
「約束よ。お帰りなさいって言わせてね」
そんなふうに明るく笑って、軽やかに私は門を出た。

昼前に戻って、そっと玄関を開けた。
食事の匂い、けれど周太の気配が静まっている。
きっとあの子は眠っている、そう思うと嬉しかった。
あの人の書斎に、いつものように、ただいまを言いに行く。
開いた窓から、山茶花の香が頬を撫でた。重厚でかすかに甘い、あの人の残り香と重なっていく。
書斎机に活けた山茶花は、水を替えた気配がある。周太の繊細さは、こんなふうにも表われる。
花の陰、あの人の笑顔の傍に、一葉の写真が供えられていた。
青空を梢で抱いた、ブナの巨樹だった。
きっと彼が、大切にしている木なのだろう。
それをこうして、あの人に見せてくれる。そんな彼の想いが、嬉しかった。
そう、嬉しい。嬉しくて、幸せで、私の頬を熱が伝っておりていく。
明るい陽射がふるベッドで、周太は眠っていた。
久しぶりに見る息子の寝顔、懐かしくて、すこし違っている。
微笑んだ寝顔は幼げで、けれど初々しい艶がけぶっている。
きれいな頬にそえられた右腕には、赤く花のような痣がうかんでいた。
きっと彼が想いを刻み込んだ、その想いが嬉しくて、幸せな夜だったと教えてくれる。
見つめる視界の真中で、長い睫がゆれて、ゆっくり瞠かれた。
私の顔を見て、少し恥ずかしそうに笑ってくれる。
こんなふうに寝起きの顔、眺めるのは13年と7カ月ぶり。
あの夜からはもう、周太の寝顔は見なかった。
苦しい夢にうなされて、それでも独り立ち向かう。
凛とした孤独へは、踏み込むことが許されなかった。
「おかえり、お母さん」
恥ずかしそうで、けれど幸せに明るい瞳。
彼は私の我儘を、きれいに叶えてくれていた。
嬉しくて、私は微笑んでしまう。
「ただいま、周太」
blogramランキング参加中!