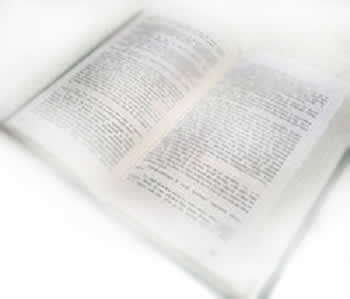過去と現在、意志からの対話、

第63話 残証act.4―another,side story「陽はまた昇る」
『La chronique de la maison』 Susumu Yuhara
今、この手には古くて美しい本が一冊、午後の陽射しに照らされる。
祖父が居たはずの研究室で、祖父が30年以上前に記した本が自分に手渡された。
これは現実だろうか、それとも居眠りでもしている?それなら何時から眠ったのだろう?
解らなくなって頬つねると痛い、 その傷みに我に返って周太は目の前の教授に首を振った。
「だっ、ダメです。これは貴重書で手に入らないって僕、知っています。こんな大切な本は受け取れません、」
言いながら本を差出し返そうとして、けれど教授の大きな手は腕組んだ。
その明敏な目が可笑しそうに周太を見、浅黒い日焼貌ほころんで笑いだした。
「大切だから上げるんだろう?自分が要らないものを他人様にさし上げたら嫌な奴じゃないか、なあ?」
「あ、…それはそうですけど、」
言われた通りだ?そう気がついて途惑ってしまう。
けれど本の価値を知るだけに周太は姿勢を但し、真直ぐ教授を見つめ微笑んだ。
「田嶋先生、これはフランス文学の貴重本です。それもこの研究室の先生が記念出版されたんですよね、ここの学生にも大切な本のはずです。
ここの研究生でも無い、フランス文学の勉強もしていない僕が受取るなんて出来ません。だから一度だけお借りして読ませて貰えたら良いんです、」
祖父がフランス文学に懸けた想いを受け留めたい、だからこそ自分に受取る資格は無いと解っている。
それでも本当は自分が受けとりたい、写真も知らない祖父の声を文字を通して聴いてみたい。
そんな願いが本当はある、それでも孫である自分が祖父の願いを壊したくない。
―きっと自分の後輩に役立てて欲しいはずだよね、お父さんが大学に自分の本を寄贈したみたいに、
まだ父が英文学を諦め警察官になった理由は見えない。
それでも大切な英文学書を母校に寄贈した想いは解かる、きっと祖父も同じ想いだろう。
まだ顔も知らない祖父、それでも自分を生んだ血をくれた人を理解し、その想いを護りたい。
どうか祖父の誇りを護ってあげたい、そのために本を書架へ戻し微笑むと教授は笑ってくれた。
「君は本当に本好きで、勉強好きなんだな?そうか、」
頷いて田嶋は踵返すと大股で歩き、電話の受話器を取った。
その足跡には床積みの本が崩おれて、また一冊ずつ拾いあげ埃を叩いて積み直す。
どれもが翻訳した本よりは新しいふうで、祖父が揃えた本は書架に納めてあると解って嬉しい。
やっぱり田嶋は祖父の教え子なのだろうか?そんな思案と本を拾う向こう田嶋教授は受話器を置いた。
「すぐ戻る、ちょっと二人とも待っていてくれなあ、」
どこへ行くのだろう?
訊こうと顔を上げた先、扉は開いてワイシャツの背中が出て行った。
ばたんと閉まった扉を見、書斎机のバリケードから手塚が笑いだした。
「あーあ、田嶋先生また俺様ペースだよ。ごめんな、周太?」
「ううん…さっき俺、断ったの悪かったかな?」
せっかくの厚意を断って気を悪くさせたろうか?
つい頑固に言いはるのは悪い癖だ、反省しながら本抱えると手塚は笑ってくれた。
「いま出て行くときの顔、ご機嫌だったよ。周太に言われた事が嬉しかったからだろ?」
「そう?」
心配になりながら訊いて、また本を積む。
その向こうで手塚もファイリング整理しながら、眼鏡の瞳ほころばせた。
「田嶋先生って大らかでさ、見ての通り研究以外は無頓着なんだよ。あの恰好もな、朝はちゃんとしてるのにアアなるんだよな、」
「朝はちゃんとしてるんだ?」
意外で釣り込まれ訊いてしまう。
そんな周太に友達は笑って教えてくれた。
「ああ、ちゃんとしてるよ。先生の奥さんが朝は整えてくれるらしいんだ、でも1限が終わったらアアなってるけどさ、」
「あ、そっか。奥さんはちゃんとするよね?」
応えながら可笑しくて笑ってしまう。
身なりも部屋も端整だった父との落差が、逆に父を思い出させる。
いま父を偲びながら祖父のいた場所で本を片づけ、一緒に夢を学ぶ友達と笑いあう。
こんな時間が自分に与えられた事が嬉しくて楽しい、笑いあい本積んで、また扉が開かれた。
「お、ずいぶん綺麗にしてくれたなあ?ありがとうな、」
快活な笑顔ほころばせ田嶋教授は扉を閉めた。
そのまま真直ぐ周太の前に来てくれる、そして一冊の本と笑ってくれた。
「さあ、今度こそ受けとってくれ。私から君へのバトンだよ、」
言いながら日焼けした手は周太の手から本を取り、代わりに一冊のハードカバーを持たせてくれる。
古びても紺青色あざやかな表装と銀文字のタイトルに作者名、その見覚えに息呑んで周太は表紙を開いた。
“Je te donne la recherche”
万年筆の筆跡が、よく知っているブルーブラックで綴られる。
家の書斎に遺された父の万年筆、それから祖父の蔵書に記された購入日とサインの文字。
どれも懐かしい記憶の筆跡と似たフランス語のメッセージに、声が震えた。
「あの、…これ、図書館のですよね?…書庫にある貴重図書の、ですよね?」
どうして、あの本が今ここにあるのだろう?
この本は大学附属図書館の書庫に納められていたはず、貴重書扱いで平日の閲覧しか出来ない。
複写も専門業者に依頼すると言われた、その手続時間には間に合わなくて複写申請すら出来なかった。
当然のよう禁貸出扱いで、指定された閲覧場所でしか読むめなくて、通し読みを一度するのが精一杯だった。
それなのにどうして今、仏文研究室で自分は見ているのだろう?途惑って顔上げた先、田嶋教授は楽しげに笑った。
「やっぱりコレを君は読んでたのか、今時この本を読んでるなんて仏文科以外では珍しいよ、大したもんだ、」
「はい…あの、この本って、持ち出し禁止ですよね?」
答えながらも今、この本が手にある状況が解らない。
ただ途惑って本を持ったまま見つめた先、田嶋は可笑しそうに教えてくれた。
「寄贈主が取り戻しただけだよ、書庫に入れっぱなしは勿体無いから君にあげたいんだ。もし学生が読みたければココのを読めばいい、
発行された時にも1冊はすぐに文学部の図書館に納められて、今もあるんだ。だから君がこれを受けとっても何の支障も無いはずだ、だろ?」
寄贈主が取り戻した、そう告げてくれる言葉に驚いてしまう。
この本を田嶋は2冊も持っていた?その事実に途惑う前から教授は微笑んだ。
「いま君にあげた本は私が図書館に寄贈したんだ、だが正確に言うと、預けられた本を私の名前で納めたんだよ、」
今、田嶋は「預けられた本」と言った。
この言葉に鼓動が止められ推測が瞳を開く、その向こうに真実はある?
そんな想いに竦んで見つめた学者は、笑って作業机の椅子に腰を下ろした。
「ほら、君も座りなよ?手塚もおいで、この本の話は本気で学問する人間なら聴くべきだからな、」
言われるまま椅子に座り、その隣へ手塚も来てくれる。
そして周太の手にある紺青色の本へ微笑んで、田嶋教授は口を開いた。
「その本は部活の先輩から貰ったんだよ、この本を書いたのは私の先生でな、その先輩のお父さんなんだ、」
告げられた事実が推測を、過去の現実という素顔にさせる。
自分が想っていた通り、この本は祖父が息子である父に贈ったものだった。
―それなら“Je te donne la recherche”は、お祖父さんがお父さんに宛てて書いたってことだね、
このメッセージを最初に読んだとき「recherche」の意味を考えあぐねた。
あのときから抱いている疑問と未知は今、このまま披かれ見えてくる?
その期待と緊張に鼓動ひとつ打った前、教授は語り始めた。
「先輩は1つ上で英文学の人だったけど、私がフランス文学に進みたがっているのを知ってすぐに、お父さんに紹介してくれたんだよ。
お蔭で1年のときからこの研究室に通わせてもらえてね、3年間いろいろ教えて頂いて嬉しかったよ。本当に湯原先生にはお世話になった、」
やっぱり田嶋は祖父の教え子だった。
しかも父に部活の後輩として直接祖父に紹介され、この研究室に入っている。
こんなに近しい人に会えると想わなかった、嬉しくて微笑んだ隣から手塚が口を開いた。
「田嶋教授の先生は、湯原先生とおっしゃるのですか?」
「ああ、湯原晉博士だよ、」
日焼顔が応えてくれる名前が心響いて、温かい。
嬉しく微笑んで、けれど隣の友人の驚きが見えるようで気恥ずかしい。その含羞が熱く昇せる前で教授は続けてくれた。
「湯原先生はパリ大の名誉教授でな、この研究室と戦後の文学界を担ったお一人だ。たくさんの研究書を書かれてるが、どれも名文だよ。
世界的仏文学者って言われる方だ、そんな先生が唯一書かれた小説がこの本なんだ。全文がフランス語の推理小説なんだが悔しい位に面白いよ、」
文学界を担った、名文、面白い、そんな賞賛が目の前で笑ってくれる。
こんなふうに評価を祖父と同じ仏文学者から聴ける、その率直な言葉たちがただ嬉しい。
―お祖父さん?もう30年以上経っても、こんなふうに教え子の人に言ってもらえるんだね?…良かったね、
祖父の為に嬉しい、そして父の為にも嬉しい。
父は学者の道を生きられなかった、けれど後輩は今こうして研究一筋に笑っている。
きっと父も祖父も今、喜んでくれているはず。そう確信と微笑む隣から手塚は気遣うよう、けれど率直に尋ねた。
「あの、先生。その湯原先生と息子さんは今、どうされているんですか?」
友達の質問にそっと周太は瞳を閉じ、ゆっくり見開いた。
その前でも教授の瞳が瞑目から披かれて、哀しげに微笑んだ。
「亡くなられたよ、お二人とも。湯原先生はパリ第3大学で客死されてな、私が3年になった春の終わりだった、」
並んで座る友達が、ひとつ呼吸する音が聞える。
もう聡明な手塚なら気づいたろう、いま友人の驚きと途惑いに佇んだ前から田嶋は続けてくれた。
「当時のフランスは火葬場が少なくてな、大学葬にしたいって東大の意志もあって、先生のご遺体は火葬されずに帰国されたんだ。
ご遺体を空輸するにはエンバーミングっていう防腐処理をせんといかんのだが、他にも色んな手続きや何やかでお金が掛かったそうだよ。
それもあって先輩はオックスフォード大の留学を辞退されてな…まだ祖母の方がご存命で、独り置いて行く事も出来ないって言ってたよ、」
祖父の異国での客死、それが惹き起した父の変転。
世界最高峰の英文学を学べる資格とチャンスが父にはあった、それなのに諦めざるを得なかった。
約束されたはずの栄光が鎖された、これが英文学者を諦めて警視庁の警察官になった理由なのだろうか?
―それでも他の方法は無かったの?お金が理由で就職するにしても、大学の助手とか出版社とかの方がお父さんらしいのに、
なぜ父は別の進路を選べなかったのだろう?
その疑問に思案めぐりだす隣、息ひとつ呑んだ気配から友達の声が訊いた。
「先生、オックスフォードに留学って相当優秀な方ですよね?その先輩はウチの大学院に進んだんですか?」
「進学しないで警察官になられたよ。先輩は優秀な射撃の選手でな、それで湯原先生の友達で警察庁にいた方から勧められたんだ、」
応えてくれる声が、ふっとため息吐いて微笑んでくれる。
きっと田嶋は父の最期を知っているだろう、そう見つめた先で教授は口を開いてくれた。
「国家一種は締め切ってたけどな、警視庁の採用試験には間に合うからって受験したんだ。オリンピックにも射撃の選手で出ていたよ、
だけど殉職された、もう14年になる。先輩は大学時代の仲間と縁遠くしていてな、私も新聞の記事で亡くなったことをを知ったんだよ。
それすら事件から1週間経ってたんだ、ちょうどパリ大のシンポジウムに出張していてな、帰国して、溜めこんだ新聞で初めて知ったんだ、」
14年前の殉職事件、その当時が幼い記憶から呼び起される。
あのとき自分が向きあった現実と涙、苦しんだ悪夢、そして父の記憶ごと涙を眠らせた。
あのときには忘却だけが自分を救う手段だった、けれど全てを今は抱きしめ見つめる前で田嶋はため息と微笑んだ。
「驚いて、すぐご自宅に電話したんだが番号が変っていてな。留守番電話も Fax も確かめたけど、何も連絡の跡は無かったんだ。
大学の仲間は誰ひとり先輩の新しい電話番号を知らなくて、訃報も無くてな…先輩は縁を切りたかったのかと思えて、そのままなんだ、」
敬愛する友人の死に何も連絡が無かった、その傷みが学者の瞳を揺らがせ堪えている。
この貌に父と田嶋が学生時代に培った時間が見えて、涙閉じこめながら周太は父へ問いかけた。
―山の仲間で、大切な友達だったんでしょう、お父さん…なのに、どうして連絡先まで消しちゃったの?
この友人のことは勿論、母校のことは何ひとつ家族に話さず父は逝った。
きっと連絡先すらも残していないだろう、父の電話帳に書かれた全員へ母は連絡したのだから。
けれど父が山の仲間を求めていたと知っている、あの過去の現実を想う前から教授は微笑んで教えてくれた。
「私が修士1年の夏だったよ、この研究室に先輩は訪ねてくれてな。先輩が集めた英文学の本を大学図書館に寄贈してきたって笑ってた。
もう自分は学者として本を研究に役立てられないから、後輩たちに代わりに読んでもらって研究の足しにしてほしいって話してくれたよ。
先輩は本当に英文学を愛してる人だって改めて思えて、大学に戻ってくれって私は言ったんだ。でも、ただ笑って私にこの本を渡したんだ、」
この本、そう言って田嶋は周太の手にある本をそっと触れた。
その指先に銀文字の表題は煌めいて、静かに手を離すと教授は微笑んだ。
「この本は父から息子の自分に贈られたものだ、だから自分が図書館に持ちこんでも遠慮されて、たぶん受けとってもらえないだろう。
でも父はこの本も学問に役立てて欲しいはずだ、だから教え子の君にこの本をどうすべきか決めてほしい。そう言って私に預けてくれてな、
それで大学図書館に私が寄贈したんだよ、でも貴重図書扱いになって書庫に仕舞い込まれてなあ、当て外れだが保管庫代りと思ってたんだ、」
語ってくれる言葉から、父と祖父の想いが自分の推測と重なってゆく。
いま三十数年を超えて届く二人の願いと聲が温かい、その温もりが瞳から一滴こぼれて周太は微笑んだ。
「田嶋先生、そんなに大切なご本をなぜ、僕に下さろうとするんですか?僕は文学部じゃなくて農学部の聴講生なのに、」
「でも、フランス語と文学を君も愛してるだろう?」
明敏な瞳が真直ぐ周太を見つめ訊いてくれる。
その言葉へと自分の頭は、無意識なほど素直に頷いて声が出た。
「はい、」
短い返答、けれど迷い無く自分から現われてくれる。
今までフランス語も文学も「愛している」なんて自覚したことは無い。
ただ幼い日から空気のよう傍にあって、父と母との楽しい記憶をたくさん贈ってくれた。
そんな時間たちへ改めて向かい、自覚した想いの前から日焼顔の文学博士は嬉しそうに微笑んだ。
「それなら君がこの本を持っていることは相応しいよ、これはフランス語とフランス文学を愛した人が全てを籠めて書いた小説なんだ。
これを贈られた人もフランス語と文学を愛してた。言葉と文学を愛した二人が本に想う気持と、同じことを君はさっき私に言ってくれたね?
文学を研究していない自分は受け取れない、そう言った君の言葉も貌も先輩と先生のことを思い出させたよ。だから君に渡そうって想ったんだ、」
祖父達を知る顕子は周太を祖母似だと教えてくれた、たぶん父と自分があまり似ていないよう祖父とも似ていない。
それでも田嶋教授は父と祖父を自分に見つけてくれた、その真直ぐな視線がこんなに嬉しくて優しくて、温かい。
きっと田嶋教授は前にいる聴講生が誰なのか気付いていない、それでも厚意の瞳は周太に笑ってくれた。
「二人の気持ちが解かる君だから、この本を渡したいんだ。きっと君が読んでくれるなら二人も喜ぶよ、受けとってくれるかい?」
父も祖父も、この本を自分が持つことを望んでくれる?
それを二人ともに縁ある人から告げられるなら信じたい、この願いの証を持っていたい。
いま三十年以上の時を超えて廻り会えた本、この一冊を抱きしめて周太は綺麗に笑った。
「はい、頂戴します…本当にありがとうございます、僕、ずっと大切にします、」
抱きしめた紺青色の本から、シャツもTシャツも透かして何か温かい。
この温もりが欲しくて自分は父の軌跡を辿り、父を祖父を探し求めて過去の欠片を集めてきた。
まだ10歳になる前から始まった探し物、もう14年になる願いの結晶をひとつ今この胸に抱きしめられる。
―お父さん、お祖父さん、やっと1つ見つけられたよ?
胸の本へ心つぶやき微笑んだ横顔、隣の友人が見つめている。
この友人が今思うことは自分にも解る、そして本音は真実を知ってほしいと思っている。
けれど自分からは言えないまま本を抱きしめる隣から、決意が背筋を伸ばして田嶋教授へ質問した。
「先生、その先輩には、ご家族は?」
「奥さんと息子さんが一人いるそうだ、他は親戚も無いらしいが、」
明敏な瞳を和ませ答えてくれる、その眼差しが温かい。
自分たち母子の存在も知ってくれていた、この感謝に微笑んだ前で田嶋は言ってくれた。
「先輩が亡くなった時、息子さんも小学生位のはずだ。きっと母子ふたりきりで大変だったろう、なのに何もしてあげられんかった。
でも湯原先生も来年は三十三回忌になられるんだ。教え子で集まろうって話が出ているから、お孫さんに連絡出来ないか考えてるとこだよ。
たぶん先輩は奥さん達に大学の事も先生の事も話していないだろう、でも、お孫さんはお祖父さんのことを聴きたいかもしれないって思ってな、」
祖父の年忌法要を憶えてくれている、そして孫の存在にも気遣ってくれる。
もう31年も昔のこと、それでも教え子は正確に覚えてくれている。その篤実が嬉しい。
こんな教え子がいるほど祖父は立派な教師で学者だった、それなのになぜ父は何も話さなかったのだろう?
―こういう方達がいるなら法事もお知らせするのが筋なのに、お祖父さんの十三回忌の時も家族三人だけで…どうして?
普通なら著名な学者で教師なら、年忌法要の連絡は教え子にもするだろう。
自分が工学部に在籍したときも研究室の担当教授が恩師の法事に出席していた。
それが学者の世界の礼儀だろう、それなのに礼儀作法に篤い父がなぜ連絡もしていない?
こんな「らしくない」父の意図はまだ解らなくて、それでも秘密にしたがった意志だけは解かる。
父は自身の父親を息子と妻から隠してしまった、その理由は何?
(to be continued)
blogramランキング参加中!

 にほんブログ村
にほんブログ村

第63話 残証act.4―another,side story「陽はまた昇る」
『La chronique de la maison』 Susumu Yuhara
今、この手には古くて美しい本が一冊、午後の陽射しに照らされる。
祖父が居たはずの研究室で、祖父が30年以上前に記した本が自分に手渡された。
これは現実だろうか、それとも居眠りでもしている?それなら何時から眠ったのだろう?
解らなくなって頬つねると痛い、 その傷みに我に返って周太は目の前の教授に首を振った。
「だっ、ダメです。これは貴重書で手に入らないって僕、知っています。こんな大切な本は受け取れません、」
言いながら本を差出し返そうとして、けれど教授の大きな手は腕組んだ。
その明敏な目が可笑しそうに周太を見、浅黒い日焼貌ほころんで笑いだした。
「大切だから上げるんだろう?自分が要らないものを他人様にさし上げたら嫌な奴じゃないか、なあ?」
「あ、…それはそうですけど、」
言われた通りだ?そう気がついて途惑ってしまう。
けれど本の価値を知るだけに周太は姿勢を但し、真直ぐ教授を見つめ微笑んだ。
「田嶋先生、これはフランス文学の貴重本です。それもこの研究室の先生が記念出版されたんですよね、ここの学生にも大切な本のはずです。
ここの研究生でも無い、フランス文学の勉強もしていない僕が受取るなんて出来ません。だから一度だけお借りして読ませて貰えたら良いんです、」
祖父がフランス文学に懸けた想いを受け留めたい、だからこそ自分に受取る資格は無いと解っている。
それでも本当は自分が受けとりたい、写真も知らない祖父の声を文字を通して聴いてみたい。
そんな願いが本当はある、それでも孫である自分が祖父の願いを壊したくない。
―きっと自分の後輩に役立てて欲しいはずだよね、お父さんが大学に自分の本を寄贈したみたいに、
まだ父が英文学を諦め警察官になった理由は見えない。
それでも大切な英文学書を母校に寄贈した想いは解かる、きっと祖父も同じ想いだろう。
まだ顔も知らない祖父、それでも自分を生んだ血をくれた人を理解し、その想いを護りたい。
どうか祖父の誇りを護ってあげたい、そのために本を書架へ戻し微笑むと教授は笑ってくれた。
「君は本当に本好きで、勉強好きなんだな?そうか、」
頷いて田嶋は踵返すと大股で歩き、電話の受話器を取った。
その足跡には床積みの本が崩おれて、また一冊ずつ拾いあげ埃を叩いて積み直す。
どれもが翻訳した本よりは新しいふうで、祖父が揃えた本は書架に納めてあると解って嬉しい。
やっぱり田嶋は祖父の教え子なのだろうか?そんな思案と本を拾う向こう田嶋教授は受話器を置いた。
「すぐ戻る、ちょっと二人とも待っていてくれなあ、」
どこへ行くのだろう?
訊こうと顔を上げた先、扉は開いてワイシャツの背中が出て行った。
ばたんと閉まった扉を見、書斎机のバリケードから手塚が笑いだした。
「あーあ、田嶋先生また俺様ペースだよ。ごめんな、周太?」
「ううん…さっき俺、断ったの悪かったかな?」
せっかくの厚意を断って気を悪くさせたろうか?
つい頑固に言いはるのは悪い癖だ、反省しながら本抱えると手塚は笑ってくれた。
「いま出て行くときの顔、ご機嫌だったよ。周太に言われた事が嬉しかったからだろ?」
「そう?」
心配になりながら訊いて、また本を積む。
その向こうで手塚もファイリング整理しながら、眼鏡の瞳ほころばせた。
「田嶋先生って大らかでさ、見ての通り研究以外は無頓着なんだよ。あの恰好もな、朝はちゃんとしてるのにアアなるんだよな、」
「朝はちゃんとしてるんだ?」
意外で釣り込まれ訊いてしまう。
そんな周太に友達は笑って教えてくれた。
「ああ、ちゃんとしてるよ。先生の奥さんが朝は整えてくれるらしいんだ、でも1限が終わったらアアなってるけどさ、」
「あ、そっか。奥さんはちゃんとするよね?」
応えながら可笑しくて笑ってしまう。
身なりも部屋も端整だった父との落差が、逆に父を思い出させる。
いま父を偲びながら祖父のいた場所で本を片づけ、一緒に夢を学ぶ友達と笑いあう。
こんな時間が自分に与えられた事が嬉しくて楽しい、笑いあい本積んで、また扉が開かれた。
「お、ずいぶん綺麗にしてくれたなあ?ありがとうな、」
快活な笑顔ほころばせ田嶋教授は扉を閉めた。
そのまま真直ぐ周太の前に来てくれる、そして一冊の本と笑ってくれた。
「さあ、今度こそ受けとってくれ。私から君へのバトンだよ、」
言いながら日焼けした手は周太の手から本を取り、代わりに一冊のハードカバーを持たせてくれる。
古びても紺青色あざやかな表装と銀文字のタイトルに作者名、その見覚えに息呑んで周太は表紙を開いた。
“Je te donne la recherche”
万年筆の筆跡が、よく知っているブルーブラックで綴られる。
家の書斎に遺された父の万年筆、それから祖父の蔵書に記された購入日とサインの文字。
どれも懐かしい記憶の筆跡と似たフランス語のメッセージに、声が震えた。
「あの、…これ、図書館のですよね?…書庫にある貴重図書の、ですよね?」
どうして、あの本が今ここにあるのだろう?
この本は大学附属図書館の書庫に納められていたはず、貴重書扱いで平日の閲覧しか出来ない。
複写も専門業者に依頼すると言われた、その手続時間には間に合わなくて複写申請すら出来なかった。
当然のよう禁貸出扱いで、指定された閲覧場所でしか読むめなくて、通し読みを一度するのが精一杯だった。
それなのにどうして今、仏文研究室で自分は見ているのだろう?途惑って顔上げた先、田嶋教授は楽しげに笑った。
「やっぱりコレを君は読んでたのか、今時この本を読んでるなんて仏文科以外では珍しいよ、大したもんだ、」
「はい…あの、この本って、持ち出し禁止ですよね?」
答えながらも今、この本が手にある状況が解らない。
ただ途惑って本を持ったまま見つめた先、田嶋は可笑しそうに教えてくれた。
「寄贈主が取り戻しただけだよ、書庫に入れっぱなしは勿体無いから君にあげたいんだ。もし学生が読みたければココのを読めばいい、
発行された時にも1冊はすぐに文学部の図書館に納められて、今もあるんだ。だから君がこれを受けとっても何の支障も無いはずだ、だろ?」
寄贈主が取り戻した、そう告げてくれる言葉に驚いてしまう。
この本を田嶋は2冊も持っていた?その事実に途惑う前から教授は微笑んだ。
「いま君にあげた本は私が図書館に寄贈したんだ、だが正確に言うと、預けられた本を私の名前で納めたんだよ、」
今、田嶋は「預けられた本」と言った。
この言葉に鼓動が止められ推測が瞳を開く、その向こうに真実はある?
そんな想いに竦んで見つめた学者は、笑って作業机の椅子に腰を下ろした。
「ほら、君も座りなよ?手塚もおいで、この本の話は本気で学問する人間なら聴くべきだからな、」
言われるまま椅子に座り、その隣へ手塚も来てくれる。
そして周太の手にある紺青色の本へ微笑んで、田嶋教授は口を開いた。
「その本は部活の先輩から貰ったんだよ、この本を書いたのは私の先生でな、その先輩のお父さんなんだ、」
告げられた事実が推測を、過去の現実という素顔にさせる。
自分が想っていた通り、この本は祖父が息子である父に贈ったものだった。
―それなら“Je te donne la recherche”は、お祖父さんがお父さんに宛てて書いたってことだね、
このメッセージを最初に読んだとき「recherche」の意味を考えあぐねた。
あのときから抱いている疑問と未知は今、このまま披かれ見えてくる?
その期待と緊張に鼓動ひとつ打った前、教授は語り始めた。
「先輩は1つ上で英文学の人だったけど、私がフランス文学に進みたがっているのを知ってすぐに、お父さんに紹介してくれたんだよ。
お蔭で1年のときからこの研究室に通わせてもらえてね、3年間いろいろ教えて頂いて嬉しかったよ。本当に湯原先生にはお世話になった、」
やっぱり田嶋は祖父の教え子だった。
しかも父に部活の後輩として直接祖父に紹介され、この研究室に入っている。
こんなに近しい人に会えると想わなかった、嬉しくて微笑んだ隣から手塚が口を開いた。
「田嶋教授の先生は、湯原先生とおっしゃるのですか?」
「ああ、湯原晉博士だよ、」
日焼顔が応えてくれる名前が心響いて、温かい。
嬉しく微笑んで、けれど隣の友人の驚きが見えるようで気恥ずかしい。その含羞が熱く昇せる前で教授は続けてくれた。
「湯原先生はパリ大の名誉教授でな、この研究室と戦後の文学界を担ったお一人だ。たくさんの研究書を書かれてるが、どれも名文だよ。
世界的仏文学者って言われる方だ、そんな先生が唯一書かれた小説がこの本なんだ。全文がフランス語の推理小説なんだが悔しい位に面白いよ、」
文学界を担った、名文、面白い、そんな賞賛が目の前で笑ってくれる。
こんなふうに評価を祖父と同じ仏文学者から聴ける、その率直な言葉たちがただ嬉しい。
―お祖父さん?もう30年以上経っても、こんなふうに教え子の人に言ってもらえるんだね?…良かったね、
祖父の為に嬉しい、そして父の為にも嬉しい。
父は学者の道を生きられなかった、けれど後輩は今こうして研究一筋に笑っている。
きっと父も祖父も今、喜んでくれているはず。そう確信と微笑む隣から手塚は気遣うよう、けれど率直に尋ねた。
「あの、先生。その湯原先生と息子さんは今、どうされているんですか?」
友達の質問にそっと周太は瞳を閉じ、ゆっくり見開いた。
その前でも教授の瞳が瞑目から披かれて、哀しげに微笑んだ。
「亡くなられたよ、お二人とも。湯原先生はパリ第3大学で客死されてな、私が3年になった春の終わりだった、」
並んで座る友達が、ひとつ呼吸する音が聞える。
もう聡明な手塚なら気づいたろう、いま友人の驚きと途惑いに佇んだ前から田嶋は続けてくれた。
「当時のフランスは火葬場が少なくてな、大学葬にしたいって東大の意志もあって、先生のご遺体は火葬されずに帰国されたんだ。
ご遺体を空輸するにはエンバーミングっていう防腐処理をせんといかんのだが、他にも色んな手続きや何やかでお金が掛かったそうだよ。
それもあって先輩はオックスフォード大の留学を辞退されてな…まだ祖母の方がご存命で、独り置いて行く事も出来ないって言ってたよ、」
祖父の異国での客死、それが惹き起した父の変転。
世界最高峰の英文学を学べる資格とチャンスが父にはあった、それなのに諦めざるを得なかった。
約束されたはずの栄光が鎖された、これが英文学者を諦めて警視庁の警察官になった理由なのだろうか?
―それでも他の方法は無かったの?お金が理由で就職するにしても、大学の助手とか出版社とかの方がお父さんらしいのに、
なぜ父は別の進路を選べなかったのだろう?
その疑問に思案めぐりだす隣、息ひとつ呑んだ気配から友達の声が訊いた。
「先生、オックスフォードに留学って相当優秀な方ですよね?その先輩はウチの大学院に進んだんですか?」
「進学しないで警察官になられたよ。先輩は優秀な射撃の選手でな、それで湯原先生の友達で警察庁にいた方から勧められたんだ、」
応えてくれる声が、ふっとため息吐いて微笑んでくれる。
きっと田嶋は父の最期を知っているだろう、そう見つめた先で教授は口を開いてくれた。
「国家一種は締め切ってたけどな、警視庁の採用試験には間に合うからって受験したんだ。オリンピックにも射撃の選手で出ていたよ、
だけど殉職された、もう14年になる。先輩は大学時代の仲間と縁遠くしていてな、私も新聞の記事で亡くなったことをを知ったんだよ。
それすら事件から1週間経ってたんだ、ちょうどパリ大のシンポジウムに出張していてな、帰国して、溜めこんだ新聞で初めて知ったんだ、」
14年前の殉職事件、その当時が幼い記憶から呼び起される。
あのとき自分が向きあった現実と涙、苦しんだ悪夢、そして父の記憶ごと涙を眠らせた。
あのときには忘却だけが自分を救う手段だった、けれど全てを今は抱きしめ見つめる前で田嶋はため息と微笑んだ。
「驚いて、すぐご自宅に電話したんだが番号が変っていてな。留守番電話も Fax も確かめたけど、何も連絡の跡は無かったんだ。
大学の仲間は誰ひとり先輩の新しい電話番号を知らなくて、訃報も無くてな…先輩は縁を切りたかったのかと思えて、そのままなんだ、」
敬愛する友人の死に何も連絡が無かった、その傷みが学者の瞳を揺らがせ堪えている。
この貌に父と田嶋が学生時代に培った時間が見えて、涙閉じこめながら周太は父へ問いかけた。
―山の仲間で、大切な友達だったんでしょう、お父さん…なのに、どうして連絡先まで消しちゃったの?
この友人のことは勿論、母校のことは何ひとつ家族に話さず父は逝った。
きっと連絡先すらも残していないだろう、父の電話帳に書かれた全員へ母は連絡したのだから。
けれど父が山の仲間を求めていたと知っている、あの過去の現実を想う前から教授は微笑んで教えてくれた。
「私が修士1年の夏だったよ、この研究室に先輩は訪ねてくれてな。先輩が集めた英文学の本を大学図書館に寄贈してきたって笑ってた。
もう自分は学者として本を研究に役立てられないから、後輩たちに代わりに読んでもらって研究の足しにしてほしいって話してくれたよ。
先輩は本当に英文学を愛してる人だって改めて思えて、大学に戻ってくれって私は言ったんだ。でも、ただ笑って私にこの本を渡したんだ、」
この本、そう言って田嶋は周太の手にある本をそっと触れた。
その指先に銀文字の表題は煌めいて、静かに手を離すと教授は微笑んだ。
「この本は父から息子の自分に贈られたものだ、だから自分が図書館に持ちこんでも遠慮されて、たぶん受けとってもらえないだろう。
でも父はこの本も学問に役立てて欲しいはずだ、だから教え子の君にこの本をどうすべきか決めてほしい。そう言って私に預けてくれてな、
それで大学図書館に私が寄贈したんだよ、でも貴重図書扱いになって書庫に仕舞い込まれてなあ、当て外れだが保管庫代りと思ってたんだ、」
語ってくれる言葉から、父と祖父の想いが自分の推測と重なってゆく。
いま三十数年を超えて届く二人の願いと聲が温かい、その温もりが瞳から一滴こぼれて周太は微笑んだ。
「田嶋先生、そんなに大切なご本をなぜ、僕に下さろうとするんですか?僕は文学部じゃなくて農学部の聴講生なのに、」
「でも、フランス語と文学を君も愛してるだろう?」
明敏な瞳が真直ぐ周太を見つめ訊いてくれる。
その言葉へと自分の頭は、無意識なほど素直に頷いて声が出た。
「はい、」
短い返答、けれど迷い無く自分から現われてくれる。
今までフランス語も文学も「愛している」なんて自覚したことは無い。
ただ幼い日から空気のよう傍にあって、父と母との楽しい記憶をたくさん贈ってくれた。
そんな時間たちへ改めて向かい、自覚した想いの前から日焼顔の文学博士は嬉しそうに微笑んだ。
「それなら君がこの本を持っていることは相応しいよ、これはフランス語とフランス文学を愛した人が全てを籠めて書いた小説なんだ。
これを贈られた人もフランス語と文学を愛してた。言葉と文学を愛した二人が本に想う気持と、同じことを君はさっき私に言ってくれたね?
文学を研究していない自分は受け取れない、そう言った君の言葉も貌も先輩と先生のことを思い出させたよ。だから君に渡そうって想ったんだ、」
祖父達を知る顕子は周太を祖母似だと教えてくれた、たぶん父と自分があまり似ていないよう祖父とも似ていない。
それでも田嶋教授は父と祖父を自分に見つけてくれた、その真直ぐな視線がこんなに嬉しくて優しくて、温かい。
きっと田嶋教授は前にいる聴講生が誰なのか気付いていない、それでも厚意の瞳は周太に笑ってくれた。
「二人の気持ちが解かる君だから、この本を渡したいんだ。きっと君が読んでくれるなら二人も喜ぶよ、受けとってくれるかい?」
父も祖父も、この本を自分が持つことを望んでくれる?
それを二人ともに縁ある人から告げられるなら信じたい、この願いの証を持っていたい。
いま三十年以上の時を超えて廻り会えた本、この一冊を抱きしめて周太は綺麗に笑った。
「はい、頂戴します…本当にありがとうございます、僕、ずっと大切にします、」
抱きしめた紺青色の本から、シャツもTシャツも透かして何か温かい。
この温もりが欲しくて自分は父の軌跡を辿り、父を祖父を探し求めて過去の欠片を集めてきた。
まだ10歳になる前から始まった探し物、もう14年になる願いの結晶をひとつ今この胸に抱きしめられる。
―お父さん、お祖父さん、やっと1つ見つけられたよ?
胸の本へ心つぶやき微笑んだ横顔、隣の友人が見つめている。
この友人が今思うことは自分にも解る、そして本音は真実を知ってほしいと思っている。
けれど自分からは言えないまま本を抱きしめる隣から、決意が背筋を伸ばして田嶋教授へ質問した。
「先生、その先輩には、ご家族は?」
「奥さんと息子さんが一人いるそうだ、他は親戚も無いらしいが、」
明敏な瞳を和ませ答えてくれる、その眼差しが温かい。
自分たち母子の存在も知ってくれていた、この感謝に微笑んだ前で田嶋は言ってくれた。
「先輩が亡くなった時、息子さんも小学生位のはずだ。きっと母子ふたりきりで大変だったろう、なのに何もしてあげられんかった。
でも湯原先生も来年は三十三回忌になられるんだ。教え子で集まろうって話が出ているから、お孫さんに連絡出来ないか考えてるとこだよ。
たぶん先輩は奥さん達に大学の事も先生の事も話していないだろう、でも、お孫さんはお祖父さんのことを聴きたいかもしれないって思ってな、」
祖父の年忌法要を憶えてくれている、そして孫の存在にも気遣ってくれる。
もう31年も昔のこと、それでも教え子は正確に覚えてくれている。その篤実が嬉しい。
こんな教え子がいるほど祖父は立派な教師で学者だった、それなのになぜ父は何も話さなかったのだろう?
―こういう方達がいるなら法事もお知らせするのが筋なのに、お祖父さんの十三回忌の時も家族三人だけで…どうして?
普通なら著名な学者で教師なら、年忌法要の連絡は教え子にもするだろう。
自分が工学部に在籍したときも研究室の担当教授が恩師の法事に出席していた。
それが学者の世界の礼儀だろう、それなのに礼儀作法に篤い父がなぜ連絡もしていない?
こんな「らしくない」父の意図はまだ解らなくて、それでも秘密にしたがった意志だけは解かる。
父は自身の父親を息子と妻から隠してしまった、その理由は何?
(to be continued)
blogramランキング参加中!