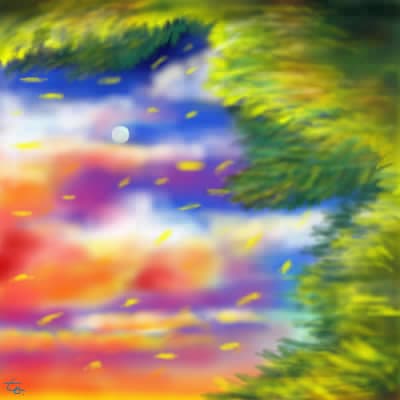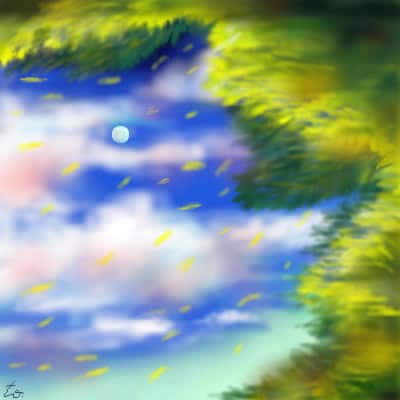奥津城―おくつき 死体遺棄による古代葬法、柩を置く場所
奥深い所にある遮断された境域

奥津城、掌の中―side story「陽はまた昇る」
目覚めると青空が眩しかった。奥多摩の稜線が、あざやかに目に映る。
カーテンが開いたまま、掌には携帯が握りしめられていた。
湯原と電話を繋いだまま、昨夜は眠ってしまったらしい。布団も掛けていないけれど、体調は爽やかだ。
湯原の声を聴いて眠った効果だなと、英二は我ながら可笑しかった。
昨夜、青梅署で吉村医師を見送った後、隣接する寮へそのまま帰ってきた。
着替えだけ持って、すぐ浴場で体中を洗った。
死体見分の死臭が染みついているようで、早く洗い落してしまいたかった。
多少さっぱりはしたけれど、心は本音重かった。
自室に戻って気が付いた携帯の着信メールに救われた。
あの声を聴いて眠って、今の気持は随分と晴れている。湯原の声が仄暗い心を静かに拭ってくれた。
一晩中ずっと声を聴いたはずなのに、今また声を聴きたい。
洗面を済ませて着替えると、気持は大分落着いていた。
きちんと腹も減っている。
頬をぱんと両手で叩いて、英二は食堂へ歩いていった。
朝食のトレイを受取って振り返ると、同じ御岳勤務の国村が立っていた。
おはようございますと声を掛けると、国村が一緒に食おうと誘ってくれた。
ちょうど空いていた窓際に、向かい合って座る。山嶺が目に眩しかった。
いただきますと合掌して箸を持つと、国村が口を開いた。
「宮田くんはタフだね」
英二が箸を止めようとすると、食べながらで良いからと国村は笑ってくれた。
警察官は上下関係が厳しい、けれどここでは皆が気さくだ。山の所為なのかなと英二は思う。
昨日はお疲れさまと労って、国村は続けた。
「僕はね、最初の見分の後、食事できなかった」
「国村さんが?」
意外だった。
物静かだけれど冷静な雰囲気の国村が、そんなふうになるとは想像し難い。
駐在所は二種類ある。隣接の官舎に居住常駐する警察官一人の駐在所と、複数の警察官が勤務する複数駐在所。
そして英二が勤務する御岳駐在所は複数駐在所で、二人勤務制になっている。
ここは御岳山から大岳山を管轄にもつため巡回パトロール時間も長く、単独駐在では不在がちになる為だった。
現在は岩崎が居住常駐し、青梅署付設の独身寮から二名が交替で通勤駐在をしている。
そのため、国村と英二が一緒に勤務する事はごく稀になる。
まだ勤務を共にはしていないが、署付の独身寮でよく顔を合わせていた。
けれど国村が感情を揺るがす姿は、まだ英二は見た事が無い。
食事中の会話じゃないけどねと微笑んで、国村が言った。
「2,3日は肉系は食べられなかったかな」
そう言う人けっこう多いよ。言いながら国村も箸を運んだ。
自分は結構、無神経なのだろうか。口を動かしながら、英二は考え込んだ。
ちょっと英二を見、国村が微笑んだ。
「山岳救助の適性、宮田くんは有ると思う」
「俺がですか?」
思わず「俺」と言ってしまった。
慌てて言い直そうとする英二に、気にしなくて良いと国村が軽く手を振った。
「期は僕の方が先輩だけど、年齢は変わらないと思うから」
僕は高卒で入ったからと国村が言った。
落着いているから、もっと年上だと英二は思っていた。
そんな英二を眺めて国村は、すこし悪戯っぽく口の端をあげた。
「意外だって顔してる」
「いや。国村さん落着いているから」
よく言われるよと国村は味噌汁を啜り、そうだとまた口を開いた。
「来週、訓練あるって聴いている?」
青梅署では山岳救助隊の訓練が多いことは知っている。けれど来週の話はまだ、聴いていなかった。
昨日の事件で、岩崎は話しそびれたのだろうと、国村は軽くうなずいた。
「雲取山で合宿訓練になるから」
雲取山は標高2,017m、警視庁管轄では最高峰になる。決して高い標高ではないが、遭難者も多い。
奥多摩は観光地と山岳地が重複する。ある種、特異なエリアになっていた。
それだけに、軽い気持ちで装備も持たず、入山して下山できなくなる例が多い。
「初訓練だね、宮田くん」
「はい、」
訓練は、厳しいと聞く。警察学校時代の訓練など、楽に感じるのだろう。
山岳訓練で湯原を背負った、遠野教官の背中が懐かしい。
絶対にあの背中を越えてやろう。昨夜すこし曲げられた背筋が、すっと伸びた。
今日は本来当直の日だが、岩崎が常駐している為、実際は日勤になる。
朝早くから、登山届の受付が多い。
日々あざやかになる黄葉に惹かれて、山を歩いてみたくなるのだろう。
世田谷の街中で生まれ育った英二は、その気持は分かるなと思う。
駐在所の入口には、よく晴れた青空と稲穂の黄金が眩しい。
遠く子供の声が響く、登校時間なのだろう。
さっき届を出したハイカーの夫婦の、楽しそうな話声が遠ざかっていく。
のどやかな田舎の、平和な風景だった。
それでもここでは、昨日のような事が起きる。
相反する表裏を持つ場所。昨夜と今朝の落差に、少し途惑う。
けれど思っていたより、自分は落着いている。
警察学校の資料で、鑑識資料など湯原と眺めてはいた。死体見分の写真も見てはいる。
昨夜は実物の凄みに混乱もした。けれど、どこか冷静に行動する自分がいた。
顔を強打するような異臭にも、吐くようなことは無かった。
ぽつんと英二は呟いた。
「立籠り事件のせい、かな」
遠野教官が狙撃され、実物の血を見つめ臭いを嗅いだ。
犯人の狂気も間近に見つめた。
あの経験が、冷静になる基盤となったのかもしれない。
あの事件は何時間も続いた。
その間なんども英二は、湯原の瞳を見た。
理不尽な拘束にも勁さを失わない、湯原の瞳がきれいだった。
自分もあんなふうに、強くなれたらいい。
ぼんやり眺めていた田園風景に、のっそり岩崎が入ってきた。
おはようございますと英二が挨拶すると、おやっと岩崎が微笑んだ。
おはようと答えながら、英二の前の椅子に腰を掛ける。
「宮田は、良い男だな」
「なんですか。急に」
朝から何を言うのだろう。英二は笑った。
岩崎も目を和ませて、口を開いた。
「昨日の後なのに、今朝も良い笑顔だ」
「ありがとうございます」
英二は微笑んで、登山届のファイルを渡した。
既に提出された通数を申し送りし、朝の巡回パトロールに出かける。
自転車には、緊急用のザイルや懐中電灯を積んでいく。
行ってきますと通りへ出ると、自転車牽引のリヤカーがやってきた。
いっぱいに野菜を積上げて、おばさんは重そうに漕いで行く。
英二は笑顔で声を掛けた。
「おはようございます」
「おはよう、」
頬を紅潮させながら、おばさんは笑いかけてくれた。
その荷台から黄色いカボチャが、ごろんと道へ転げた。
拾い上げて呼びかけたけれど、おばさんは気付かない。漕ぐので精一杯なのだろう。
駐在所の入口から、岩崎さんが笑った。
「それ多分、娘さんに届けに行くのだと思うぞ」
おばさんの娘は、御岳山の旅館へ嫁いでいた。出す料理の食材として、毎朝届けに行っている。
御岳駐在所の巡回コースには御岳山も含む。崖崩れなどの不備や遭難者がいないか、確認のため登山道を毎朝歩く。
怒られるかなと思いながら、英二は口を開いた。
「このカボチャ、巡回の途中で届けてはいけませんか?」
「ああ、全く構わないよ」
そうしてやってくれると助かると、岩崎は微笑んだ。
御岳駐在所は、こんなふうに穏やかだ。こういう所が好きだなと英二は思う。
田園風景を抜けて、渓谷沿いの道を自転車で走る。
ゆるやかな傾斜が、結構きつい。これも全部が訓練になる。
強健な足腰が山岳救助には欠かせない。遠野の背中からも英二が学んだ事だった。
ボルダリングやラフティングを楽しむ人達が、早くも渓谷に入り始めている。
滑落や転覆が起きないよう祈りながら、渓谷にかかる橋を渡った。
滝本駅の隅に自転車を置かせてもらい、登山道を登っていく。
最初はきつい巡回だと思ったが、随分慣れたと足許から感じる。
梢から降る木洩れ日が、山道に揺れている。落葉の色も、日毎に色鮮やかになってきた。
11月には紅葉が見ごろだろうと、町の人たちが言っていた。
11月には、全国警察けん銃射撃競技大会が行われる。出る事になったと、昨夜の電話で湯原が言っていた。
「これが終われば、時間作れると思う」
どこか含羞んだように言われて、かわいくて嬉しかった。
昨夜は事件の後だったというのに。どれだけ自分は、湯原中心なのだろう。
山上につくと、新宿方面が遠望できる。秋晴れの今日は空気も澄んで、遠い市街地が見えた。
湯原はどうしているだろう、今日は日勤だったはずだ。
昨日は週休だったけれど、特錬の練習後には急きょ日勤になったと言っていた。
きちんと体を休めているのだろうか。
カボチャを届けると、若い女将さんは喜んでくれた。
母さんたら仕方ないと言いながら、丁寧に礼を述べてくれる。
「御礼にサービスするわよ。お友達といらっしゃいな」
「これくらいで、気にしないでください」
微笑んで英二は辞すと、ハイキングコースへと戻った。
ロックガーデン、綾広の滝と廻ったが、特に異常は無い。
水の色がきれいだ。ここも東京なのだと思うと、不思議な感じもする。
―山歩きとか、小さい頃は行ったりも、していたんだけど
初めてあの公園を歩いた時、湯原はそんなことを話してくれた。
連れてきたら喜ぶのかなと考えながら、周囲に目を配りつつ下山へ向かった。
駐在所に戻ると、岩崎の妻が昼食を用意してくれていた。
いつもながら申し訳なくて、英二は頭を下げた。
「若者は気にしないでいいの。それより、たくさん食べてね」
ごはんを丼によそって手渡してくれる。見た目と違って、結構豪快な奥さんだ。
駐在所の裏には家庭菜園も作ってある。
見た目は華奢なのに、しっかりと地に足をつけた穏やかさが、湯原の母に少し似ている。
外泊日に一度泊めてもらって以来、彼女には会っていない。きちんと挨拶に行こう、考えながら英二は箸をとった。
午後、昨夜一緒に見分を行った刑事が、英二を尋ねてくれた。
刑事課の澤野だと改めて名乗ると、早速に話を切りだした。
「死体見分調書は、あのまま上へ上げさせてもらったよ」
ありがとうございますと言いながら、すこし英二は安堵した。初めて公式に書くことは、やはり緊張する。
初めてなのに良く書けていたと、澤野に褒められて気恥ずかしかった。
湯原と勉強した日々が、こんなふうに生きている。それが英二には嬉しい。
茶を一口啜ると、澤野は口を開いた。
「昨日の女性の、遺書の話をしに来たんだ」
掌に握られていた、封筒の事だろう。
縊死自殺者は普通、遺書を残さない事が多い。そのために身元特定が苦労させられる。
けれど昨日の遺体は、遺書を握りしめていた。出来心では無く、覚悟の上での自死だった事が分かる。
自分が見つけた遺体なら、その想いも聴いてやる義務がある。小さく息を吸って、英二は澤野を真直ぐ見た。
「はい、伺わせて頂きます」
澤野は微笑んで、軽くうなずいた。
胸ポケットからメモを取り出し、眺めながら話しだす。
「理由は、ご主人を亡くしたからという事だった」
数年前から、彼女は夫の闘病生活を支えていたらしい。
夫の葬儀と後事を全て済ませた上で、彼女はあの場所を訪れた。
「夫と共に逝きたいと、遺書の最後には書かれていた」
まだ40歳だったそうだと言って、澤野は小さくため息を吐いた。
警察医の吉村先生から伝言だと、澤野は続けた。
「離婚も多いこの頃と言うが、深い繋がりが保たれている夫婦はいるのだね。
自殺は悲しい事だ。それでもその繋がりは美しいと、むしろ心が安められた」
吉村医師の言うとおりだとも思う。
けれど生きてこそ、出会える喜びもあったかもしれない。
ふと気になって、英二は訊いてみた。
「ご両親は、どうされているのですか」
「彼女の両親は既に亡くなっているそうだ。妹さんが今夕、引取りに来る」
そうですかと呟いて、英二は唇を結んだ。
もし自分だったら、どうするのだろう。もし湯原を失っても、自分は立っていられるのだろうか。
とても考えられない、英二は頭を振った。
業務を終えて青梅署に戻ると、ロビーで吉村医師と会った。
若い女性と話している様子に、英二は会釈をして通り過ぎようとした。
ところが吉村は静かに手を上げて、英二を呼び止めた。
「すまないが、すこし時間はあるかい」
「はい、」
こちらへと薦められ吉村の隣に立つ。
いいかい、と目だけで吉村に訊かれ、英二は気が付いた。
前に立つ女性が、深々と頭を下げる。
「この度は、姉がお世話になりました」
ゆっくり上げた顔は、昨夜の面影に重なった。けれど生きている顔だった。
すこし憔悴したような、それでも透明な笑顔が、英二に微笑みかける。
「姉から言付かっていたんです。お詫びとお礼を伝えて欲しいと」
どういうことなのだろう。英二は黙ったまま彼女の顔を見つめた。
すこし潤んだ瞳で英二を見上げ、彼女は言った。
「遺書に、書かれていました。自分を見つけた方へ伝えて欲しいと」
見知らぬ誰かに、何かを託し、託される。
不思議だけれど、そうなのかと納得させられる何かが、英二に響く。
黙ったままの英二の前で、彼女は口を開いた。
「私を見つけることは、その方に辛い思いをさせるでしょう。
けれど見つけてもらえなくては、私は夫の隣に葬ってもらえない。
ご迷惑は本当に申し訳ありません。けれど見つけて頂いて、心からの感謝を申し上げます」
これが姉からの伝言です。言い終わって彼女はまた、深く頭を下げた。
静かに英二は息を吐いた。
―見つけてもらえなくては、隣に葬ってもらえない
見つけて頂いて、心からの感謝を申し上げます
握りしめられていた、命を失った白い掌。
その掌の中に、彼女の真実が握られていた。
―このような死に方を選んだ人の気持ちが、少し解るなと思うようになりました
吉村医師の言葉が今、解る。
いつか命終わる時を迎えたら。きっと自分も、湯原の隣に葬られたいと願うだろう。
死んだ彼女と自分は、きっと同じ思いを抱いている。
英二は口を開いた。
「お姉さまに、お線香をあげさせて頂けますか?」
自分にも姉が居るんですと、英二は微笑んだ。
前に立つ彼女の目から、涙が零れ落ちた。
食堂へ行くと、ちょうど藤岡と入口で一緒になった。
お互い腹が減っている。しばらく箸を動かす事に専念し、丼飯をお替りしたところで、藤岡が口を開いた。
「昨夜の事、訊いたよ」
ひとこと言って、藤岡は英二を見つめた。
人好い藤岡の困ったような顔が、なんとなく可笑しい。英二は笑ってしまった。
なんだよ宮田と、すこし拗ねたように藤岡も笑った。
「お前の事、タフだって先輩たちが言ってた」
「ん、よく言われる」
軽く冗談が出るようになっている。自分はもう、大丈夫だなと英二は思えた。
お互い食べ終わって、茶を啜りながら英二は口を開いた。
「さっき、検案所で線香上げさせてもらった」
そうかと頷いて、藤岡は湯呑を置いた。
両腕を机において、聴こうと姿勢で示してくれる。同期っていいなと英二は微笑んだ。
「警察医の吉村先生にさ、言われたんだ。
いくつも見ていくうちに、この死に方を選んだ人の気持ちが、少し解るなと思うようになるって。
そうしたら、ご遺体を同情の気持ちで見られるようになって、気持ち悪さは無くなるだろうと」
うんと藤岡は頷いて、英二に訊いた。
「宮田は同情の気持ちで、見られたのか」
「ん。ついさっきだけどね」
検案所の霊安室で、彼女は横たわっていた。焚かれる香が、静かにくゆらされている。
眼窩と小鼻が落ちた様子は、死者の顔だった。縊死の跡を隠す、包帯の白が痛々しい。
けれど彼女の顔は、透明な明るさに満ちてみえた。
美しい、と英二は思った。
整えられても遺体は、冷たく無残な事は否めない。
けれど彼女の表情は、彼女が抱いて逝った想いが表われて、美しかった。
生命が消えた遺体にも、心の軌跡は残されていた。
冷たい静謐の底には、温もりがある事を、英二は初めて知った。
―このような死に方を選んだ人の気持ちが、少し解るなと思うようになりました
ご遺体を同情の気持ちで見られるようになっていました
そして、気持ち悪さは無くなっていきました
吉村の語った言葉。真実の先を示す鍵を、今なら感じとれる。
彼女が掌の中に遺した遺書、最期の表情。
彼女が遺してくれた想いが、教えてくれた。
彼女に出会えて良かった。
最初に出会えたのが、彼女で良かった。
心から線香を手向け、英二は合掌した。
風呂でまた一緒になった藤岡と、来週の山岳訓練の話をしながら浴槽に浸かった。
気持はすっかり、爽やかになっている。
部屋へ戻ってカーテンを開けると、今夜も星がふるように見える。
彼女は荼毘に付され、妹に抱かれて夫の元へと帰った。
自分もいつかは、この世と別れを告げるだろう。
そのときは、湯原の隣に眠る事ができるのだろうか。
きっと今日は、湯原は眠かっただろう。
それでも今日も、声を聴かせて欲しいと願ってしまう。
携帯を開いて、発信履歴を英二は呼び出した。
「はい、」
いつもの落着いた声が、英二に響く。
ああこの声が好きだ。今すぐに、逢えたらいい。