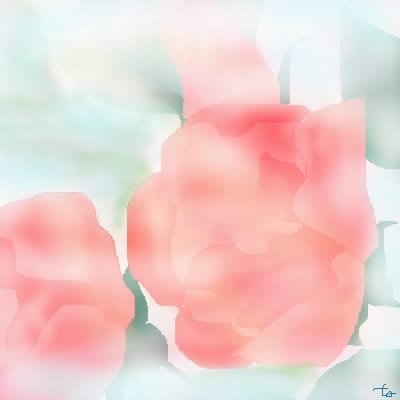出会っていくこと、そして一緒に

第30話 誓暁act.6―another,side story「陽はまた昇る」
黄昏の陽射しが台所の窓からも暖かい。
いつもの紺色のエプロンを着て周太は台所に立っていた。
その包丁を持つ手元へ少し濡れた髪から一つ、滴がぽつりと落ちて手が止められた。
…あ、
髪が少し濡れている、そのことの想いが首筋へ熱を昇らせてしまう。
止まってしまった手で周太はエプロンのポケットにふれた、そこにはクライマーウォッチが入っている。
これは英二から贈られた大切な腕時計だから、水仕事で濡らしたくなくて調理前に外してポケットにしまいこんだ。
―腕時計はね、婚約の贈り物にもするんだ
だって周太、俺にプロポーズして腕時計までくれた。もちろん俺の答えはYesだ。
だからね、婚約は成立しちゃったよ?だからもう周太はね、いつか俺の嫁さんになるんだ
さっき英二に言われたばかりの言葉に、こうして手を動かしていても首筋が熱くなってくる。
この髪が濡れているのはシャワーを浴びたばかりの所為、それが明るいうちに英二に求められたことを思い出させて気恥ずかしい。
それも心の準備も出来ていなくて本当は途惑った、だって「絶対の約束」は夜だって言っていたのに。
…こんなこと考えているとよけいに恥ずかしい、
ほっとため息を吐くと周太は、刻んだ玉ねぎをボールへ移して軽く塩をふった。
それから野菜を切ってオーブンに並べていく、これで食べる15分前になったら火を入れればいい。
それを済ませて周太は蒸した南瓜をすり鉢に入れて白玉粉と一緒に練り始めた。
そのすり鉢とすりこぎにまた、ふっと周太の手が止まった。これを使って昼間、英二はクルミを砕いてくれた。
その掌の温もりが名残にある、そんな気がして周太はまた真赤になってしまった。
…だって、婚約とか、およめさんとか言われたら…どんな顔すればいいの?
こんなこと言われるのは慣れていない「初めて」ばかりで途惑ってしまう。
周太は父が殉職してから13年間ずっと友達すら作らなかった、だから恋愛なんて全く考えたこともなかった。
あの13年間は父の軌跡を追うこと母を守ること、その2つが精いっぱいで他人に構う余裕なんて少しもなかった。
なにより「父の殉職」への好奇心や無神経な善意が大嫌いで辛くて哀しくて、誰も近寄らせたくなかった。
けれど英二だけは違っていた。
初対面は大嫌いだと思ってしまった、要領のいい人間特有の冷たさが端正な貌なだけに冷酷に感じた。
そんな英二に努力ばかりで生きている自分を嘲笑されているようで、悔しくて哀しくて嫌いだった。
けれど本当は気がついていた、そんな冷酷な仮面の向こうには実直で真直ぐな穏やかな静謐が深く隠されていること。
そして英二がずっと願ってきた想いにまで気づいてしまった。
―そのままの自分で生きていたい、生きる意味、生きる誇りをずっと探している―
そっと想いに問いかけてくる切長い目と、隠された本当の姿に惹かれて気になってしまっていた。
そんな英二はある時から、毎日と周太の部屋に座りこむようになった。そして勉強やトレーニングを教えてと笑いかけてくれた。
そう乞われるまま手助けするうち、気がついたら自分の方が英二に援けられていた。
援け合える友人が嬉しくて時折ふと父の話をするようになった。
聴くたび英二は父を男として警察官の先輩として、心から尊敬し憧れてくれた。
「周太の父さんって、本当にかっこいいな。俺もそういう男でいたい、周太の父さんみたいに笑顔の警察官になりたい」
そんな真直ぐな英二の心が本当にうれしかった。
そんなふうに英二の隣で日々を過ごすうち、周太は少しずつ笑えるようになって友達も何人か出来ていた。
それでも英二の隣で過ごす時間はいちばん楽しくて、穏やかな静謐が居心地良くて周太の安らぎだった。
そして気がついた時にはもう、きれいな笑顔が大好きになってしまっていた。
いつも英二が隣に居ないと寂しいと想うようになっていた、離れたくないと心の底では願っていた。
いつか自分は父の想いを追う危険のために孤独を選ばなくてはいけない、いくらそう自分に言い聞かせても本音は誤魔化せなくて。
だから卒業式の夜に英二が自分を求めて泣いてくれた時、周太は迷わず英二に応えてしまった。
…でも全部が、この9ヶ月のことだから…あんまりにもいっぺん過ぎる、よね?
初めての友達が出来て、その友達が初恋と気がついて。
初恋に気がついた瞬間そのまま求められて体ごと心も想いも繋ぎとめられて。
それから3ヶ月も経たない今日、ついさっき婚約と言われて。
そんなの本当に心の準備も何も出来ない。だって自分はまだ恋愛は9ヶ月の子供と同じ、途惑ってしまう。
こんなに急に全てを通るなんて?ちょっと急すぎて途惑いが大きくなってしまう。
…うれしい、けれど途惑う…
ほっとため息を吐いて周太は、練り上げた南瓜を片栗粉をつけた掌に置くと鶏餡を入れて丸めた。
すぐにいくつも丸め終わって、出した蒸籠にきれいに並べて蓋をする。これは食べる20分くらい前に蒸せばいい。
とりあえず支度が終わってしまって、周太は手持無沙汰は困ると茶を淹れる支度を始めた。
手を動かしていないとまた考え始めそうで困る、けれど手を動かしてもやっぱり同じ事が頭を巡り始めてしまう。
…婚約、しちゃったんだ、ね
知らなかった、腕時計の交換がそんな意味になるなんて。しかも自分の言ったことは結婚の申し込みのまんまだった。
さっきパソコンでちょっと確認をしてみたら、ほんとうに英二の言った通りだった。
何にも知らないで、想ったままを贈り物に選んで言っただけだったのに。
ほんとうに自分は世間に疎い、これも13年間を殻に閉じこもっていたからなのだろう。
…でも、婚約のことは、…途惑うけれど、うれしい
自分のしでかしたことは恥ずかしくて、けれど英二の「婚約者」になれたことは幸せだと想ってしまう。
だってより特別な存在になれたのだから。こんなふうに近づけるのはやっぱり、うれしい。
眺めていたケトルから湯の沸く音がたって周太は火を止めた。急須と湯呑を一旦湯で温めてから、急須に茶葉を入れて湯を注ぐ。
ゆっくり茶葉が開かれながら、清涼な香りが湯気に立ち昇っていく。こんなふうに茶を淹れるのは気持ちが落ち着いていい。
ほっと息をついて湯呑をもって振り返ると、すぐ近くに英二が立っていた。
「…っ」
驚いて落としかけた湯呑を、きれいに長い指の掌が受けとめてダイニングテーブルに置いてくれる。
それから長身をすこし傾けて周太に笑いかけてくれた。
「周太、シャワーのついでに風呂掃除してきた。ざっとだし、勝手に道具とか使ったけど良かったかな、周太?」
そういえば戻ってくるのが遅かった。
きっと独り暮らしの母を気遣って掃除してくれたのだろう、こんな細やかな優しさが英二はある。
こんなところが好きで幸せで周太は微笑んだ。
「ん…ありがとう、英二。今夜はね、お風呂沸かすから…一番風呂して、ね?」
周太の「ありがとう」に、きれいな笑顔が嬉しそうに英二に咲いた。
ほらこんなに英二は喜んでくれる、こんな率直なひとが自分は大好きで幸せな気持ちになる。
そんな幸せに見上げる先で英二は笑顔で応えてくれた。
「うん、ありがとう周太。でもね、周太?俺、周太と一緒に風呂入りたいな」
「…それはだめです…」
どうしてこんなことばかりいうの?
いつもこう、なにかと真っ赤にさせられてしまう。
とくに今ほんとうに困ってしまうそんな提案、だだでさえ「婚約」で頭がぐるぐるするのに。
お願い英二、今はちょっとかんべんしてね?そんな想いで見上げたのに、英二は構わず笑いかけてくる。
「なんで、周太?だって警察学校の時はさ、毎晩一緒に風呂入っていただろ?ね、周太。たまには一緒に風呂入りたいよ?」
「…いまはだめ…」
いまはだめ、絶対にダメ。
だって警察学校の時は友達だから意識しなかった、それに「あの時間」を自分は知らなかった。
けれど今はもうダメ、きっとすごく困ってしまう。
「どうして今はダメなの?だって今はもう婚約者だよ、周太。婚約者なんだからさ、今の方が一緒に入るの当然だろ?」
今もう婚約者だから、だから余計にだめ。
絶対にダメ恥ずかしい困ってしまう、断固として周太はダメ出しをつづけた。
「…だめです…いまはだめ…あ、ご飯にしよう?ね、英二?」
「うん、腹減ってるから飯は食いたいけど。でも、周太?なんで今はダメなんだ?だって周太、新宿署の寮も共同浴場だろ?」
だって英二?あなたと同僚では全然違うんだから。
いくら同じ男でも好きな人のそんな姿は意識しちゃうんだから?
そんなふうに自分をしたのは英二なんだから、あなたの所為だから勘弁してね?
「…でも、だめです…お願いえいじちょっとかんべんして…ね?」
なんとか返事しながら真赤になっても手は動かして、周太は夕食の支度を仕上げた。
朝と昼が洋食の献立だったから夕食は和風に作ってある。いつも「山では握り飯」という英二だから一日一回は米を食べたいはず。
ご飯おいしく炊けていると良いな。そう考えながら味噌汁の仕上げをする隣から、やっぱり英二は覗きこんでおねだりしてくる。
「ね、周太?俺、寂しがりなんだから、一緒に風呂入ってよ。この家の風呂ちょっと広くて俺、寂しくなるんだから」
「だめです。…おふろひろくても山でひとりぼっちよりさびしくないでしょ…ね?」
「山と風呂は違うよ、周太?ダメなんて言わないでよ、一緒に入ってよ周太、」
…ね、駄々っ子みたいだよ英二?
ちょっと意外な英二の一面に、すこし周太は驚きながら食事の支度を進めていた。
本来の英二は怜悧で実直な性質で、穏やかな静謐と端正な佇まいが落ち着いている。
そうした本来の性分は卒業配置後はより前面に出て、山ヤの誇らかさも備えた英二は大人の男になった。
そんな英二は同期には「背中から宮田かっこよくなった」と褒められるし、青梅署でも真面目で聡明だと頼られ始めている。
なのにこの英二は、まるで小さい子が一生懸命におねだりするみたい。なんだか可愛くて、周太は手を動かしながら微笑んだ。
それでも食卓にきちんと配膳すると、英二の注意は食事の方へと向いてくれた。
「今夜はね、たくさん炊いてあるから…たくさん食べてね?英二」
「うん、ありがとう周太。俺ね、なんだかすごい腹減ってるんだ。さっき周太としたからかな?ね、周太?」
「…そういうことは…ごはんのせきでは、ね、英二?あ、冷めないうちに食べて?」
こんな2人だけの食事は久しぶりで、周太の手料理を2人だけで摂るのは初めてだった。
ひとつ英二が口に運ぶたびつい気になって見てしまう、ちゃんと英二の口に合うだろうか?
なんだか少し緊張するな、思いながら周太は英二のご飯のお代わりをよそっていた。
「周太、これ旨いね。南瓜のなんだろ?」
「ん、…それはね、南瓜の生地の中に、鶏挽肉を詰めて蒸すんだ」
「へえ、凝ってるな。周太ってほんと料理上手いな。こっちの牛肉のとかさ、すごい旨いよ?周太」
「あ、それ?…牛肉のたたきにね、玉ねぎと醤油バターでたれをかけたんだ…添え物の焼野菜も食べてね、英二?」
口に入れるたび幸せに微笑んで、うれしそうに英二は周太に訊いてくれる。
おいしそうに次々平らげていく姿が気持ちいい、そんな英二は大きめの茶碗でご飯を8杯食べた。
こんな食卓の風景は普通に幸せなのだろう、けれど自分には宝物の時間。うれしくて周太は微笑んで見ていた。
そんな食事の時が終わってからも、一緒に皿を洗いながら英二は素直に周太の料理を喜んだ。
「やっぱり俺、周太の作ってくれたものがね、一番好きだな」
「ん、そう?…今日は何が一番おいしかった?」
「昼の鶏のクルミのやつと、夜の牛肉のが双璧かな?
でもさ、本当になんでも旨いよ。俺、周太を嫁さんに出来て幸せだな。ほんと嬉しいよ。ね、周太?」
…嫁さんに、出来て
洗う周太の手から皿が一枚つるり水桶に滑り込んだ。
だってさっきも考え込んでいたこと見透かされたようで気恥ずかしい。
それにそんな「嫁さん」って言われても面映ゆい困ってしまう、首筋に熱を感じながら遠慮がちに周太は口を開いた。
「およめさんとかはずかしい…ね、英二、おれおとこなんだし…」
「だって周太、俺にプロポーズしてくれたろ?…あ、それとも俺が嫁さんなのか?でも周太、それは変だよ」
「あの、…ね、英二?」
ちょっとその話は恥ずかしいな?そう英二を周太は見上げた。
だって今日はもう散々そんな話をしているのに?けれど英二はわざと気づかぬふうに話を続けてくる。
「どうみても俺のが旦那だろ?俺のがでかいし、するのは俺だし。ね、周太?されるほうがさ、嫁さんだよ」
いろいろ恥ずかしい言葉が並べられていく、それも幸せに輝くきれいな美しい笑顔で。
こんな美しい笑顔でこんなこと言われると、何て答えていいのか本当に途惑ってしまう。
知らなかったとはいえ自分は色んな意味で大変なことをしたのかな、周太はそっと英二にお願いしてみた。
「あ、の…おさらおとしたらこまるから…お願い…これいじょうはかんべんして赤くさせないで…」
「なんで周太?だってさ、周太が俺にプロポーズしたんだよ。キスして、時計くれて。ね、周太?」
そう、自分からしてしまった。
まさかプロポーズになるなんて意識もなくて、けれど言われる通りだったのが恥ずかしい。
こんなに困っているのに英二は尚更、きれいな幸せな笑顔で笑いかけてくれる。
「だからね、周太は俺の嫁さんになるよ?だって俺、そう決めてるしね」
「あの、…ん、決めちゃったの?…でも女の子じゃないから…ね、英二?」
もうさっき説明してくれたから、英二の主張が正しいのは解っている。
けれど今はちょっと恥ずかしくて逃げ口上に「女の子じゃない」を使ってしまう。
でもこんなこと言って本当は「男女とか関係ない」とまた言って欲しくて仕方ない。
そんな自分は甘えていて恥ずかしいな、そう思っていると英二が言ってくれた。
「周太はさ、女の子だとか関係ないよ?ただ俺は、周太だけが欲しいんだ。だからね周太、俺の奥さんになって?」
― 俺の運命のひとは周太だ。他の誰でもない、男も女も関係ない ―
ついさっきベッドでも言ってくれたこと。
また言って欲しいと思っていたら本当に言ってくれた、うれしくて幸せになってしまう。
そんな想いは本当に幸せで、けれど余計に気恥ずかしくさせられて思わず周太は逃げてしまった。
「ん…うれしいけど、赤くなるから…ちょっと…今はダメ、」
そう言い置いて周太は片付け終えると廊下への扉を開いた。
歩き出す廊下の冷たい空気が火照った頬に気持ちがいい、ほっと息を吐いて周太は気配に隣を見あげた。
見あげた先にはやっぱり、ちゃんと英二がくっついて歩きながら周太に笑いかけてくる。
「ダメなんて言わないでよ?周太、俺の時間を全部あげたんだからさ、」
「ん、うれしい、な?…でも、今はね、ちょっとダメ…」
真っ赤な顔で答えながら周太は洗面室の扉を開いた、この奥が浴室になっている。
せっかく着いてきたのだし調度いい、周太はバスタオルを用意すると英二に手渡した。
もうこのまま英二には風呂に一人で入ってもらおう、その隙にすこし自分を落着かせたい。
「はい、英二。…お風呂、沸いてるから入って、ね?」
そう言って微笑むと周太は急いで廊下へと逃げた。ぼんやりしていたら、きっと掴まって困らされるに違いない。
そのまま2階へあがって振向くと、浴室から微かな水音が聞こえ始めた。
おとなしく諦めて一人で風呂に入ってくれたらしい、ほっと微笑んで周太は自室へと入った。
入ってデスクライトを点けると周太は自分の鞄を開いて覗きこんだ。
そしてすぐに見つけて手帳を取り出すと、はさんでおいた1通の封書を手にとり微笑んだ。
「美代さんからね、周太にって。味噌のレシピと、お便りだって言っていたよ?」
そんなふうに微笑んで英二が渡してくれた、美代からの便りの封書。
美代は国村の幼馴染で恋人で、11月に雲取山に登った後で4人で河原で一緒に飲んだ。
そのときに1度会っただけだけれど、珍しく周太にも話しやすい女の子だった。
そして本当に珍しいことに、また会いたくて話したい友達だなと自然と素直に思えていた。
そしてこんなふうに友達から手紙をもらうことは、周太にとって初めてのことだった。
…こういうのが、仲良しの友達、っていう感じなのかな?
ほんとうは英二をそう最初は思っていた。
けれど似ていて全く違う感情だと気付かされてしまっている。
英二は周太にとって唯ひとり特別なひとだった、それは他の友達とも全く違う想いと距離なのがもう解っている。
そんなことを考えながら封書を持って周太は、屋根裏の小部屋へあがるとフロアーライトを点け揺り椅子へ腰かけた。
いつものように立膝で座り込むと、きれいな白い封筒から美代の手紙をひらいた。
拝啓 雪の花うつくしい頃になりました、いかがおすごしですか?
約束のレシピをおくります、本当に手前味噌だけれど私のは結構おいしかったでしょ?
湯原くんならもっとおいしく作れるね、作ったらぜひ味見させてね。
自分と同年代で「拝啓」から始まる手紙を書くことに周太は少し驚いた。
きちんとして可愛らしい字が真白な便箋から周太に話しかけてくれる。
…美代さんの方がね、上手だと思うな…でも、作ったら味見してほしいな
そんなふうに周太は自然と微笑んで手紙に心で返事しながら、次の文面に目を留めた。
きっとこの手紙を開くときには、最高峰の話を聴いていると思います。
だからお礼を言わせてね?
すこし意外で周太は首を傾げて考え込んだ。
…俺に、お礼を言うの?
どういうことだろう?思いながら次の文章へと目を通した。
宮田くんがいてくれるから、光ちゃんは最高峰でも独りではありません。
それは私にとって本当に幸せなことです。
だって最高峰はいちばん危険なところなのでしょう?でも2人なら援けあって無事に帰ってこられる。
そうやって、生涯のアイザイレンパートナーはお互いを絶対に援けあうそうです。
…きっと美代さん、ずっと不安に泣いていた、よね?
そっと周太は唇をかんだ、美代の静かな覚悟が自分にはわかる。
もうずっと美代は国村の「最高峰を踏破する」夢を聴いて育っている。
きっと成長につれて危険を理解して、けれど止められないことも心底から理解して。
そんな美代にとって国村にアイザイレンパートナーがいないことは、どんなに不安だったろう?
アイザイレンパートナーは命綱を結びあう相手。
お互いの体格や技量が同等であることが、お互いの生命を守る大切な条件になる。
特に最高峰を目指すクライマーは過酷な条件下で行動を共にすることになる、だから相性と人間性も問われる。
国村は最高峰に立つ運命を託され最高のクライマーとして嘱望されている。
そんな国村は技量も山ヤの精神性も抜群に過ぎて、高校時代は警視庁最高のクライマーで両親の友人である後藤がパートナーを組んだ。
けれど国村の体格は身長180cmは充分に超える大柄に成長した、この体格差に加え加齢もあって後藤でも国村と組めなくなった。
国村に拮抗する技量を備え友人になれる精神、そして180cmを超える大柄を支えきれる体格と体力。
そういう条件のクライマーは簡単には見つからない、だから国村はずっと単独クライマーでいた。
そして国村は単独クライマーとして国内の名峰に単独でも登頂してきた。
国内なら両親や田中や後藤と踏破済みでいるから初登頂ではない、それでも単独では美代は不安だったろう。
そんな国村はきっと世界の名峰でも単独で踏破するつもりだった、けれど未経験の山での単独登頂は危険が大きくなる。
それでも国村は本当に自分が認められないアイザイレンパートナーだったら組まない、きっと単独行を選んでしまうだろう。
いつも飄々としている国村だけれど、あの底抜けに明るい細目には「意思」が強く深く輝いている。だから決意は遂げてしまう。
そのことを周太は知っている、そして美代がそれを気づかないはずがない。
…ね、美代さん…ほんとうは、何回もう泣いている…?なのにどうして、そんなに明るく笑える?…
不安を見つめても明るい美代の瞳は、心から尊敬できる瞳だ。
そんな想いにそっと微笑んで周太は次を読んだ。
だから私は湯原くんに約束します。
必ずどんな時でも、どんな場所でも、光ちゃんが絶対に宮田くんを援けます。
それは山以外の場所でも警察官としても必ずです。それが生涯のアイザイレンパートナーだから。
そうして必ず宮田くんが湯原くんのところへ無事帰れるように、光ちゃんは絶対に宮田くんを援けます。
だから笑っていてね、湯原くん。光ちゃんを信じて宮田くんを信じて、笑っていて?
「…約束、」
この「約束」は、美代の国村に対する深い信頼が無くてはできない。
きっと国村は美代に約束をしている「だって山に登るだけだろ?ちゃんと無事に帰るに決まってるね」たぶんこんな調子で。
それを美代は真直ぐに信じて、国村と英二の繋がりを真直ぐに見つめている。
…美代さん、あなたは、ほんとうに強くて、きれいなんだね?
自分もこんなふうに英二を信じて国村も信じて真直ぐ見つめる強さがほしい。
こんな強い女の子もいるんだ、周太は美代の明るい瞳を想いながら微笑んだ。
こんなひとから手紙をもらえて嬉しい、そっと2枚目の便箋に周太は持ち替えた。
そしてね湯原くん、私はこう想うのよ?
世界一の最高峰に大好きなひとが立って、そこから自分を想ってくれる。これほど愉快なことって他に無い。
きっと世界一に愉快なことだって、私は想います。
だからね、湯原くん。私と一緒に世界一愉快なことを楽しんで?
私は湯原くんと一緒に笑いたいなって想うのよ?だって私も独り待つのはね、ほんとうは寂しかったから。
そんなふうに一緒に世界一愉快なことを楽しめる友達がいることは、私にとって本当に幸せです。
だからお礼を言いたいの、湯原くん。
宮田くんを光ちゃんと出会わせてくれて、ありがとう。
そして湯原くんが私と出会ってくれて、本当に嬉しい。私と出会ってくれて、ありがとう。
また御岳に来てね、待っています。こんどは家にも是非来てね、私の作った野菜も結構おいしいのよ? 敬具
読み終わっても周太は手紙を見つめた。
この手紙を書いてくれた友達の心と想いを見つめていた。
美代は一緒に「世界一愉快なこと」を楽しもうと笑ってくれる。独り待つのは寂しい気持ちをわかってくれる、そして、
「…出会わせてくれて…出会ってくれて…ありがとう」
こんなふうに「ありがとう」を言われること、どうしたらいいの?
こんな手紙を自分がもらえるなんて、1年前には想像もできなかった。
ただ孤独に生きて独り壁を作って籠りきっていた、それは傷つくことは減っても寂しかった哀しかった。
けれど英二と出会って孤独を壊されて、引っ張り出された世界はこんなに温かい。
そして英二の隣で生きることで、こんなふうに「ありがとう」を言ってもらえた。
…英二の隣でいること、間違っていないのかな
そんな想いが嬉しくて幸せで周太は微笑んだ。
そして便箋と封筒とペンを下の部屋から持ってくると、屋根裏の小部屋で手紙を書き始めた。
この便箋も封筒も事務的な目的にしか使ったことがない、けれど今は友達への手紙を書いている。
こんなふうに友達に手紙を書くことは普通のことかもしれない、でも周太には初めてで幸せなことだった。
「…ん、御岳にね、また行くね?」
そっと微笑んで周太は手紙を書き終えると、きちんと畳んで封筒へ納めた。
手紙と自分の返信を持って立ち上がる。きちんとフロアーライトを消し、それから天窓を振り仰いだ。
きれいな星が夜空に見えている、明日はきっと晴れるだろう。
明日は英二と散歩もいいな、そう思いながら梯子階段を周太は降りた。
そして下の部屋に降りたとき目を上げて周太の瞳が大きくなった。
…なんで英二、ここで服着ているの?…あ、勢いでお風呂に置いてきたから、か
ひろやかな白皙のすっきりした背中が周太へと向けられている。
背中はデスクライトに照らされて、ゆるやかな筋肉の陰影が頼もしい。
そんな後姿は逞しくて端麗にきれいで、周太は見惚れてしまった。
…きれいだな、
そう思って見つめる背中の肩に、ふと周太の目が留まった。
肩から背中の上にかけて赤い線のようなものが見える。それは痣のように紐状になって両肩をはしっていた。
あんな痣は英二にあっただろうか?不思議に見つめる先で少しずつ痣は薄れ始めた。
きっと風呂上りの火照りが治まると消える痣なんだな、そう思いかけて周太は息をのんだ。
…あのときの、ザイルの擦過傷の痕
きっと警察学校での山岳訓練の時が原因だ、そう思い当って周太は真直ぐに英二の傷痕を見つめた。
あのとき崖下へ滑落した周太を救けてくれたのは英二だった。
滑落で足を痛めた周太をザイルで背負って英二は、雨で地盤の緩みきった崖を登攀してくれた。
本来なら初心者の英二が救助できるような現場ではなかった、けれど英二は志願して本当に周太を救助してみせた。
でもあのときの英二は山自体が初心者で、肩にはザイルを喰い込ませて痛々しかった。
「大丈夫だよ、ほら?傷痕なんかないだろ?」
山岳訓練から数日後、そう言って英二は風呂の前に脱衣所で肩を見せてくれた。
けれど本当は痕になって残っている、きっと英二は周太を気遣って隠していた。
自分が英二に傷をつけてしまった、それが哀しくて周太は呆然と白い肩を見つめていた。
そうして見つめる背中が静かに振り返ると、きれいな笑顔で英二が笑ってくれた。
「周太、」
きれいな低い声で名前を呼んでくれる。
なにか言わないと謝らないと。そんな想いで周太は英二を見つめた、けれど声が詰まって出てこない。
そんな周太を見て英二は着かけたシャツの手を止めて、周太の顔を覗き込むと笑いかけてくれた。
「どうした、周太?」
どうしたのか言って欲しいな?やさしく目で訊いてくれる。
こんなきれいな肩に傷痕を残させた自分に、気遣って英二は隠してくれていた。
どうしていつもそうなの英二?あんまり優しくて、どうしていいか解らなくなる。
とにかく今からでも、きちんと訊いて謝りたい。英二を見あげると周太は唇を開いた。
「ね、英二…その、肩の赤い線は?」
「ああ、これ?…うん、山岳訓練の時のだよ」
「俺が、怪我した時のザイルの…痕になってるの?」
すかさず訊いた周太に、すこし首かしげて英二は微笑んだ。
なんて答えようか英二は困っている、やっぱり自分の所為でついた傷に違いない。
こんな大切なこと気づけないでいた、それでも今からでも謝まりたくて周太は英二を見上げて言った。
「…俺のせいで、英二に傷をつけて…ごめんなさい、ずっと気づかなかった」
「周太、この痕はね?俺にとっては、うれしいものなんだ」
そう言って英二は微笑んでくれる。
傷痕がうれしい?意外で周太はそっと訊いてみた。
「…うれしい、の?」
「うん、うれしいよ?」
頷いて英二は周太の顔を覗き込んでくれる。
そして微笑んで英二は、穏やかに周太に言ってくれた。
「俺がね、初めて周太を背負った記念だろ?だからね、うれしいんだ。それにさ、ちょっと赤い糸みたいだろ?」
初めて・記念・赤い糸、どれも幸せそうな言葉たち。
そんな言葉を告げて、きれいに笑って英二は周太の肩へと腕を回してくれる。
どうか笑って欲しいな?そう見つめながら周太の頬へ長い指の掌でふれてくれた。
「周太、笑ってほしいよ?だってね、これが赤い糸ならさ、周太は俺の嫁さんだって証拠だろ?」
「…証拠、なの?」
これが赤い糸で自分が英二のお嫁さんだという証拠。
そんな運命だと言ってくれるの英二?そんな想いが嬉しくて周太は微笑んだ。
そう微笑んだ周太の唇に静かに英二が唇を重ねた。
「うん、俺の嫁さんって証拠。愛してるよ、周太」
重ねた唇といっしょに体ごと想いを抱きしめてくれる。
抱きしめる腕の温もりがうれしくて、抱きしめられる鼓動が温かくて、ほほ触れる深い香が愛しい。
ふれる熱い唇が深く重ねてくれる、しずかに繋がる温もりと微かな樹木の香が愛おしい。
そっと唇を離して瞳の視線をからめとると、英二は周太に微笑んだ。
「ね、周太?続き、したらダメ?」
続きってどの続き?
そう思った瞬間に午後の「あの時間」が答えのように思い出された。
そんなの真赤になってしまう、周太は急いで答えた。
「…っ、今は…ダメです」
「じゃあさ、周太?後でならいい、そういうこと?」
そんなふうに訊かないで?周太は瞳を伏せてしまった。
だって今夜は「絶対の約束」だって昼間に新宿でも英二は言っていた。
けれど午後にも英二は求めてくれた、それでも今夜は「絶対の約束」をするのだろう。
伏せたままの瞳に左腕のクライマーウォッチが映り込んで、そっと周太は唇を開いた。
「ん、…だって、…絶対の約束だから…ね、」
そう英二に告げて周太は、やっぱり気恥ずかくて微笑んだ。
そんな周太をすこし驚いて見つめる切長い目が、すこし大きくなっている。
この顔かわいいな、思いながら英二の長い腕からそっと抜け出すと周太は笑いかけた。
「あの、…風呂、冷めちゃうから…」
そして着替えを持つと手紙をしまって、周太は部屋から廊下に出た。
(to be continued)
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955

 にほんブログ村
にほんブログ村

第30話 誓暁act.6―another,side story「陽はまた昇る」
黄昏の陽射しが台所の窓からも暖かい。
いつもの紺色のエプロンを着て周太は台所に立っていた。
その包丁を持つ手元へ少し濡れた髪から一つ、滴がぽつりと落ちて手が止められた。
…あ、
髪が少し濡れている、そのことの想いが首筋へ熱を昇らせてしまう。
止まってしまった手で周太はエプロンのポケットにふれた、そこにはクライマーウォッチが入っている。
これは英二から贈られた大切な腕時計だから、水仕事で濡らしたくなくて調理前に外してポケットにしまいこんだ。
―腕時計はね、婚約の贈り物にもするんだ
だって周太、俺にプロポーズして腕時計までくれた。もちろん俺の答えはYesだ。
だからね、婚約は成立しちゃったよ?だからもう周太はね、いつか俺の嫁さんになるんだ
さっき英二に言われたばかりの言葉に、こうして手を動かしていても首筋が熱くなってくる。
この髪が濡れているのはシャワーを浴びたばかりの所為、それが明るいうちに英二に求められたことを思い出させて気恥ずかしい。
それも心の準備も出来ていなくて本当は途惑った、だって「絶対の約束」は夜だって言っていたのに。
…こんなこと考えているとよけいに恥ずかしい、
ほっとため息を吐くと周太は、刻んだ玉ねぎをボールへ移して軽く塩をふった。
それから野菜を切ってオーブンに並べていく、これで食べる15分前になったら火を入れればいい。
それを済ませて周太は蒸した南瓜をすり鉢に入れて白玉粉と一緒に練り始めた。
そのすり鉢とすりこぎにまた、ふっと周太の手が止まった。これを使って昼間、英二はクルミを砕いてくれた。
その掌の温もりが名残にある、そんな気がして周太はまた真赤になってしまった。
…だって、婚約とか、およめさんとか言われたら…どんな顔すればいいの?
こんなこと言われるのは慣れていない「初めて」ばかりで途惑ってしまう。
周太は父が殉職してから13年間ずっと友達すら作らなかった、だから恋愛なんて全く考えたこともなかった。
あの13年間は父の軌跡を追うこと母を守ること、その2つが精いっぱいで他人に構う余裕なんて少しもなかった。
なにより「父の殉職」への好奇心や無神経な善意が大嫌いで辛くて哀しくて、誰も近寄らせたくなかった。
けれど英二だけは違っていた。
初対面は大嫌いだと思ってしまった、要領のいい人間特有の冷たさが端正な貌なだけに冷酷に感じた。
そんな英二に努力ばかりで生きている自分を嘲笑されているようで、悔しくて哀しくて嫌いだった。
けれど本当は気がついていた、そんな冷酷な仮面の向こうには実直で真直ぐな穏やかな静謐が深く隠されていること。
そして英二がずっと願ってきた想いにまで気づいてしまった。
―そのままの自分で生きていたい、生きる意味、生きる誇りをずっと探している―
そっと想いに問いかけてくる切長い目と、隠された本当の姿に惹かれて気になってしまっていた。
そんな英二はある時から、毎日と周太の部屋に座りこむようになった。そして勉強やトレーニングを教えてと笑いかけてくれた。
そう乞われるまま手助けするうち、気がついたら自分の方が英二に援けられていた。
援け合える友人が嬉しくて時折ふと父の話をするようになった。
聴くたび英二は父を男として警察官の先輩として、心から尊敬し憧れてくれた。
「周太の父さんって、本当にかっこいいな。俺もそういう男でいたい、周太の父さんみたいに笑顔の警察官になりたい」
そんな真直ぐな英二の心が本当にうれしかった。
そんなふうに英二の隣で日々を過ごすうち、周太は少しずつ笑えるようになって友達も何人か出来ていた。
それでも英二の隣で過ごす時間はいちばん楽しくて、穏やかな静謐が居心地良くて周太の安らぎだった。
そして気がついた時にはもう、きれいな笑顔が大好きになってしまっていた。
いつも英二が隣に居ないと寂しいと想うようになっていた、離れたくないと心の底では願っていた。
いつか自分は父の想いを追う危険のために孤独を選ばなくてはいけない、いくらそう自分に言い聞かせても本音は誤魔化せなくて。
だから卒業式の夜に英二が自分を求めて泣いてくれた時、周太は迷わず英二に応えてしまった。
…でも全部が、この9ヶ月のことだから…あんまりにもいっぺん過ぎる、よね?
初めての友達が出来て、その友達が初恋と気がついて。
初恋に気がついた瞬間そのまま求められて体ごと心も想いも繋ぎとめられて。
それから3ヶ月も経たない今日、ついさっき婚約と言われて。
そんなの本当に心の準備も何も出来ない。だって自分はまだ恋愛は9ヶ月の子供と同じ、途惑ってしまう。
こんなに急に全てを通るなんて?ちょっと急すぎて途惑いが大きくなってしまう。
…うれしい、けれど途惑う…
ほっとため息を吐いて周太は、練り上げた南瓜を片栗粉をつけた掌に置くと鶏餡を入れて丸めた。
すぐにいくつも丸め終わって、出した蒸籠にきれいに並べて蓋をする。これは食べる20分くらい前に蒸せばいい。
とりあえず支度が終わってしまって、周太は手持無沙汰は困ると茶を淹れる支度を始めた。
手を動かしていないとまた考え始めそうで困る、けれど手を動かしてもやっぱり同じ事が頭を巡り始めてしまう。
…婚約、しちゃったんだ、ね
知らなかった、腕時計の交換がそんな意味になるなんて。しかも自分の言ったことは結婚の申し込みのまんまだった。
さっきパソコンでちょっと確認をしてみたら、ほんとうに英二の言った通りだった。
何にも知らないで、想ったままを贈り物に選んで言っただけだったのに。
ほんとうに自分は世間に疎い、これも13年間を殻に閉じこもっていたからなのだろう。
…でも、婚約のことは、…途惑うけれど、うれしい
自分のしでかしたことは恥ずかしくて、けれど英二の「婚約者」になれたことは幸せだと想ってしまう。
だってより特別な存在になれたのだから。こんなふうに近づけるのはやっぱり、うれしい。
眺めていたケトルから湯の沸く音がたって周太は火を止めた。急須と湯呑を一旦湯で温めてから、急須に茶葉を入れて湯を注ぐ。
ゆっくり茶葉が開かれながら、清涼な香りが湯気に立ち昇っていく。こんなふうに茶を淹れるのは気持ちが落ち着いていい。
ほっと息をついて湯呑をもって振り返ると、すぐ近くに英二が立っていた。
「…っ」
驚いて落としかけた湯呑を、きれいに長い指の掌が受けとめてダイニングテーブルに置いてくれる。
それから長身をすこし傾けて周太に笑いかけてくれた。
「周太、シャワーのついでに風呂掃除してきた。ざっとだし、勝手に道具とか使ったけど良かったかな、周太?」
そういえば戻ってくるのが遅かった。
きっと独り暮らしの母を気遣って掃除してくれたのだろう、こんな細やかな優しさが英二はある。
こんなところが好きで幸せで周太は微笑んだ。
「ん…ありがとう、英二。今夜はね、お風呂沸かすから…一番風呂して、ね?」
周太の「ありがとう」に、きれいな笑顔が嬉しそうに英二に咲いた。
ほらこんなに英二は喜んでくれる、こんな率直なひとが自分は大好きで幸せな気持ちになる。
そんな幸せに見上げる先で英二は笑顔で応えてくれた。
「うん、ありがとう周太。でもね、周太?俺、周太と一緒に風呂入りたいな」
「…それはだめです…」
どうしてこんなことばかりいうの?
いつもこう、なにかと真っ赤にさせられてしまう。
とくに今ほんとうに困ってしまうそんな提案、だだでさえ「婚約」で頭がぐるぐるするのに。
お願い英二、今はちょっとかんべんしてね?そんな想いで見上げたのに、英二は構わず笑いかけてくる。
「なんで、周太?だって警察学校の時はさ、毎晩一緒に風呂入っていただろ?ね、周太。たまには一緒に風呂入りたいよ?」
「…いまはだめ…」
いまはだめ、絶対にダメ。
だって警察学校の時は友達だから意識しなかった、それに「あの時間」を自分は知らなかった。
けれど今はもうダメ、きっとすごく困ってしまう。
「どうして今はダメなの?だって今はもう婚約者だよ、周太。婚約者なんだからさ、今の方が一緒に入るの当然だろ?」
今もう婚約者だから、だから余計にだめ。
絶対にダメ恥ずかしい困ってしまう、断固として周太はダメ出しをつづけた。
「…だめです…いまはだめ…あ、ご飯にしよう?ね、英二?」
「うん、腹減ってるから飯は食いたいけど。でも、周太?なんで今はダメなんだ?だって周太、新宿署の寮も共同浴場だろ?」
だって英二?あなたと同僚では全然違うんだから。
いくら同じ男でも好きな人のそんな姿は意識しちゃうんだから?
そんなふうに自分をしたのは英二なんだから、あなたの所為だから勘弁してね?
「…でも、だめです…お願いえいじちょっとかんべんして…ね?」
なんとか返事しながら真赤になっても手は動かして、周太は夕食の支度を仕上げた。
朝と昼が洋食の献立だったから夕食は和風に作ってある。いつも「山では握り飯」という英二だから一日一回は米を食べたいはず。
ご飯おいしく炊けていると良いな。そう考えながら味噌汁の仕上げをする隣から、やっぱり英二は覗きこんでおねだりしてくる。
「ね、周太?俺、寂しがりなんだから、一緒に風呂入ってよ。この家の風呂ちょっと広くて俺、寂しくなるんだから」
「だめです。…おふろひろくても山でひとりぼっちよりさびしくないでしょ…ね?」
「山と風呂は違うよ、周太?ダメなんて言わないでよ、一緒に入ってよ周太、」
…ね、駄々っ子みたいだよ英二?
ちょっと意外な英二の一面に、すこし周太は驚きながら食事の支度を進めていた。
本来の英二は怜悧で実直な性質で、穏やかな静謐と端正な佇まいが落ち着いている。
そうした本来の性分は卒業配置後はより前面に出て、山ヤの誇らかさも備えた英二は大人の男になった。
そんな英二は同期には「背中から宮田かっこよくなった」と褒められるし、青梅署でも真面目で聡明だと頼られ始めている。
なのにこの英二は、まるで小さい子が一生懸命におねだりするみたい。なんだか可愛くて、周太は手を動かしながら微笑んだ。
それでも食卓にきちんと配膳すると、英二の注意は食事の方へと向いてくれた。
「今夜はね、たくさん炊いてあるから…たくさん食べてね?英二」
「うん、ありがとう周太。俺ね、なんだかすごい腹減ってるんだ。さっき周太としたからかな?ね、周太?」
「…そういうことは…ごはんのせきでは、ね、英二?あ、冷めないうちに食べて?」
こんな2人だけの食事は久しぶりで、周太の手料理を2人だけで摂るのは初めてだった。
ひとつ英二が口に運ぶたびつい気になって見てしまう、ちゃんと英二の口に合うだろうか?
なんだか少し緊張するな、思いながら周太は英二のご飯のお代わりをよそっていた。
「周太、これ旨いね。南瓜のなんだろ?」
「ん、…それはね、南瓜の生地の中に、鶏挽肉を詰めて蒸すんだ」
「へえ、凝ってるな。周太ってほんと料理上手いな。こっちの牛肉のとかさ、すごい旨いよ?周太」
「あ、それ?…牛肉のたたきにね、玉ねぎと醤油バターでたれをかけたんだ…添え物の焼野菜も食べてね、英二?」
口に入れるたび幸せに微笑んで、うれしそうに英二は周太に訊いてくれる。
おいしそうに次々平らげていく姿が気持ちいい、そんな英二は大きめの茶碗でご飯を8杯食べた。
こんな食卓の風景は普通に幸せなのだろう、けれど自分には宝物の時間。うれしくて周太は微笑んで見ていた。
そんな食事の時が終わってからも、一緒に皿を洗いながら英二は素直に周太の料理を喜んだ。
「やっぱり俺、周太の作ってくれたものがね、一番好きだな」
「ん、そう?…今日は何が一番おいしかった?」
「昼の鶏のクルミのやつと、夜の牛肉のが双璧かな?
でもさ、本当になんでも旨いよ。俺、周太を嫁さんに出来て幸せだな。ほんと嬉しいよ。ね、周太?」
…嫁さんに、出来て
洗う周太の手から皿が一枚つるり水桶に滑り込んだ。
だってさっきも考え込んでいたこと見透かされたようで気恥ずかしい。
それにそんな「嫁さん」って言われても面映ゆい困ってしまう、首筋に熱を感じながら遠慮がちに周太は口を開いた。
「およめさんとかはずかしい…ね、英二、おれおとこなんだし…」
「だって周太、俺にプロポーズしてくれたろ?…あ、それとも俺が嫁さんなのか?でも周太、それは変だよ」
「あの、…ね、英二?」
ちょっとその話は恥ずかしいな?そう英二を周太は見上げた。
だって今日はもう散々そんな話をしているのに?けれど英二はわざと気づかぬふうに話を続けてくる。
「どうみても俺のが旦那だろ?俺のがでかいし、するのは俺だし。ね、周太?されるほうがさ、嫁さんだよ」
いろいろ恥ずかしい言葉が並べられていく、それも幸せに輝くきれいな美しい笑顔で。
こんな美しい笑顔でこんなこと言われると、何て答えていいのか本当に途惑ってしまう。
知らなかったとはいえ自分は色んな意味で大変なことをしたのかな、周太はそっと英二にお願いしてみた。
「あ、の…おさらおとしたらこまるから…お願い…これいじょうはかんべんして赤くさせないで…」
「なんで周太?だってさ、周太が俺にプロポーズしたんだよ。キスして、時計くれて。ね、周太?」
そう、自分からしてしまった。
まさかプロポーズになるなんて意識もなくて、けれど言われる通りだったのが恥ずかしい。
こんなに困っているのに英二は尚更、きれいな幸せな笑顔で笑いかけてくれる。
「だからね、周太は俺の嫁さんになるよ?だって俺、そう決めてるしね」
「あの、…ん、決めちゃったの?…でも女の子じゃないから…ね、英二?」
もうさっき説明してくれたから、英二の主張が正しいのは解っている。
けれど今はちょっと恥ずかしくて逃げ口上に「女の子じゃない」を使ってしまう。
でもこんなこと言って本当は「男女とか関係ない」とまた言って欲しくて仕方ない。
そんな自分は甘えていて恥ずかしいな、そう思っていると英二が言ってくれた。
「周太はさ、女の子だとか関係ないよ?ただ俺は、周太だけが欲しいんだ。だからね周太、俺の奥さんになって?」
― 俺の運命のひとは周太だ。他の誰でもない、男も女も関係ない ―
ついさっきベッドでも言ってくれたこと。
また言って欲しいと思っていたら本当に言ってくれた、うれしくて幸せになってしまう。
そんな想いは本当に幸せで、けれど余計に気恥ずかしくさせられて思わず周太は逃げてしまった。
「ん…うれしいけど、赤くなるから…ちょっと…今はダメ、」
そう言い置いて周太は片付け終えると廊下への扉を開いた。
歩き出す廊下の冷たい空気が火照った頬に気持ちがいい、ほっと息を吐いて周太は気配に隣を見あげた。
見あげた先にはやっぱり、ちゃんと英二がくっついて歩きながら周太に笑いかけてくる。
「ダメなんて言わないでよ?周太、俺の時間を全部あげたんだからさ、」
「ん、うれしい、な?…でも、今はね、ちょっとダメ…」
真っ赤な顔で答えながら周太は洗面室の扉を開いた、この奥が浴室になっている。
せっかく着いてきたのだし調度いい、周太はバスタオルを用意すると英二に手渡した。
もうこのまま英二には風呂に一人で入ってもらおう、その隙にすこし自分を落着かせたい。
「はい、英二。…お風呂、沸いてるから入って、ね?」
そう言って微笑むと周太は急いで廊下へと逃げた。ぼんやりしていたら、きっと掴まって困らされるに違いない。
そのまま2階へあがって振向くと、浴室から微かな水音が聞こえ始めた。
おとなしく諦めて一人で風呂に入ってくれたらしい、ほっと微笑んで周太は自室へと入った。
入ってデスクライトを点けると周太は自分の鞄を開いて覗きこんだ。
そしてすぐに見つけて手帳を取り出すと、はさんでおいた1通の封書を手にとり微笑んだ。
「美代さんからね、周太にって。味噌のレシピと、お便りだって言っていたよ?」
そんなふうに微笑んで英二が渡してくれた、美代からの便りの封書。
美代は国村の幼馴染で恋人で、11月に雲取山に登った後で4人で河原で一緒に飲んだ。
そのときに1度会っただけだけれど、珍しく周太にも話しやすい女の子だった。
そして本当に珍しいことに、また会いたくて話したい友達だなと自然と素直に思えていた。
そしてこんなふうに友達から手紙をもらうことは、周太にとって初めてのことだった。
…こういうのが、仲良しの友達、っていう感じなのかな?
ほんとうは英二をそう最初は思っていた。
けれど似ていて全く違う感情だと気付かされてしまっている。
英二は周太にとって唯ひとり特別なひとだった、それは他の友達とも全く違う想いと距離なのがもう解っている。
そんなことを考えながら封書を持って周太は、屋根裏の小部屋へあがるとフロアーライトを点け揺り椅子へ腰かけた。
いつものように立膝で座り込むと、きれいな白い封筒から美代の手紙をひらいた。
拝啓 雪の花うつくしい頃になりました、いかがおすごしですか?
約束のレシピをおくります、本当に手前味噌だけれど私のは結構おいしかったでしょ?
湯原くんならもっとおいしく作れるね、作ったらぜひ味見させてね。
自分と同年代で「拝啓」から始まる手紙を書くことに周太は少し驚いた。
きちんとして可愛らしい字が真白な便箋から周太に話しかけてくれる。
…美代さんの方がね、上手だと思うな…でも、作ったら味見してほしいな
そんなふうに周太は自然と微笑んで手紙に心で返事しながら、次の文面に目を留めた。
きっとこの手紙を開くときには、最高峰の話を聴いていると思います。
だからお礼を言わせてね?
すこし意外で周太は首を傾げて考え込んだ。
…俺に、お礼を言うの?
どういうことだろう?思いながら次の文章へと目を通した。
宮田くんがいてくれるから、光ちゃんは最高峰でも独りではありません。
それは私にとって本当に幸せなことです。
だって最高峰はいちばん危険なところなのでしょう?でも2人なら援けあって無事に帰ってこられる。
そうやって、生涯のアイザイレンパートナーはお互いを絶対に援けあうそうです。
…きっと美代さん、ずっと不安に泣いていた、よね?
そっと周太は唇をかんだ、美代の静かな覚悟が自分にはわかる。
もうずっと美代は国村の「最高峰を踏破する」夢を聴いて育っている。
きっと成長につれて危険を理解して、けれど止められないことも心底から理解して。
そんな美代にとって国村にアイザイレンパートナーがいないことは、どんなに不安だったろう?
アイザイレンパートナーは命綱を結びあう相手。
お互いの体格や技量が同等であることが、お互いの生命を守る大切な条件になる。
特に最高峰を目指すクライマーは過酷な条件下で行動を共にすることになる、だから相性と人間性も問われる。
国村は最高峰に立つ運命を託され最高のクライマーとして嘱望されている。
そんな国村は技量も山ヤの精神性も抜群に過ぎて、高校時代は警視庁最高のクライマーで両親の友人である後藤がパートナーを組んだ。
けれど国村の体格は身長180cmは充分に超える大柄に成長した、この体格差に加え加齢もあって後藤でも国村と組めなくなった。
国村に拮抗する技量を備え友人になれる精神、そして180cmを超える大柄を支えきれる体格と体力。
そういう条件のクライマーは簡単には見つからない、だから国村はずっと単独クライマーでいた。
そして国村は単独クライマーとして国内の名峰に単独でも登頂してきた。
国内なら両親や田中や後藤と踏破済みでいるから初登頂ではない、それでも単独では美代は不安だったろう。
そんな国村はきっと世界の名峰でも単独で踏破するつもりだった、けれど未経験の山での単独登頂は危険が大きくなる。
それでも国村は本当に自分が認められないアイザイレンパートナーだったら組まない、きっと単独行を選んでしまうだろう。
いつも飄々としている国村だけれど、あの底抜けに明るい細目には「意思」が強く深く輝いている。だから決意は遂げてしまう。
そのことを周太は知っている、そして美代がそれを気づかないはずがない。
…ね、美代さん…ほんとうは、何回もう泣いている…?なのにどうして、そんなに明るく笑える?…
不安を見つめても明るい美代の瞳は、心から尊敬できる瞳だ。
そんな想いにそっと微笑んで周太は次を読んだ。
だから私は湯原くんに約束します。
必ずどんな時でも、どんな場所でも、光ちゃんが絶対に宮田くんを援けます。
それは山以外の場所でも警察官としても必ずです。それが生涯のアイザイレンパートナーだから。
そうして必ず宮田くんが湯原くんのところへ無事帰れるように、光ちゃんは絶対に宮田くんを援けます。
だから笑っていてね、湯原くん。光ちゃんを信じて宮田くんを信じて、笑っていて?
「…約束、」
この「約束」は、美代の国村に対する深い信頼が無くてはできない。
きっと国村は美代に約束をしている「だって山に登るだけだろ?ちゃんと無事に帰るに決まってるね」たぶんこんな調子で。
それを美代は真直ぐに信じて、国村と英二の繋がりを真直ぐに見つめている。
…美代さん、あなたは、ほんとうに強くて、きれいなんだね?
自分もこんなふうに英二を信じて国村も信じて真直ぐ見つめる強さがほしい。
こんな強い女の子もいるんだ、周太は美代の明るい瞳を想いながら微笑んだ。
こんなひとから手紙をもらえて嬉しい、そっと2枚目の便箋に周太は持ち替えた。
そしてね湯原くん、私はこう想うのよ?
世界一の最高峰に大好きなひとが立って、そこから自分を想ってくれる。これほど愉快なことって他に無い。
きっと世界一に愉快なことだって、私は想います。
だからね、湯原くん。私と一緒に世界一愉快なことを楽しんで?
私は湯原くんと一緒に笑いたいなって想うのよ?だって私も独り待つのはね、ほんとうは寂しかったから。
そんなふうに一緒に世界一愉快なことを楽しめる友達がいることは、私にとって本当に幸せです。
だからお礼を言いたいの、湯原くん。
宮田くんを光ちゃんと出会わせてくれて、ありがとう。
そして湯原くんが私と出会ってくれて、本当に嬉しい。私と出会ってくれて、ありがとう。
また御岳に来てね、待っています。こんどは家にも是非来てね、私の作った野菜も結構おいしいのよ? 敬具
読み終わっても周太は手紙を見つめた。
この手紙を書いてくれた友達の心と想いを見つめていた。
美代は一緒に「世界一愉快なこと」を楽しもうと笑ってくれる。独り待つのは寂しい気持ちをわかってくれる、そして、
「…出会わせてくれて…出会ってくれて…ありがとう」
こんなふうに「ありがとう」を言われること、どうしたらいいの?
こんな手紙を自分がもらえるなんて、1年前には想像もできなかった。
ただ孤独に生きて独り壁を作って籠りきっていた、それは傷つくことは減っても寂しかった哀しかった。
けれど英二と出会って孤独を壊されて、引っ張り出された世界はこんなに温かい。
そして英二の隣で生きることで、こんなふうに「ありがとう」を言ってもらえた。
…英二の隣でいること、間違っていないのかな
そんな想いが嬉しくて幸せで周太は微笑んだ。
そして便箋と封筒とペンを下の部屋から持ってくると、屋根裏の小部屋で手紙を書き始めた。
この便箋も封筒も事務的な目的にしか使ったことがない、けれど今は友達への手紙を書いている。
こんなふうに友達に手紙を書くことは普通のことかもしれない、でも周太には初めてで幸せなことだった。
「…ん、御岳にね、また行くね?」
そっと微笑んで周太は手紙を書き終えると、きちんと畳んで封筒へ納めた。
手紙と自分の返信を持って立ち上がる。きちんとフロアーライトを消し、それから天窓を振り仰いだ。
きれいな星が夜空に見えている、明日はきっと晴れるだろう。
明日は英二と散歩もいいな、そう思いながら梯子階段を周太は降りた。
そして下の部屋に降りたとき目を上げて周太の瞳が大きくなった。
…なんで英二、ここで服着ているの?…あ、勢いでお風呂に置いてきたから、か
ひろやかな白皙のすっきりした背中が周太へと向けられている。
背中はデスクライトに照らされて、ゆるやかな筋肉の陰影が頼もしい。
そんな後姿は逞しくて端麗にきれいで、周太は見惚れてしまった。
…きれいだな、
そう思って見つめる背中の肩に、ふと周太の目が留まった。
肩から背中の上にかけて赤い線のようなものが見える。それは痣のように紐状になって両肩をはしっていた。
あんな痣は英二にあっただろうか?不思議に見つめる先で少しずつ痣は薄れ始めた。
きっと風呂上りの火照りが治まると消える痣なんだな、そう思いかけて周太は息をのんだ。
…あのときの、ザイルの擦過傷の痕
きっと警察学校での山岳訓練の時が原因だ、そう思い当って周太は真直ぐに英二の傷痕を見つめた。
あのとき崖下へ滑落した周太を救けてくれたのは英二だった。
滑落で足を痛めた周太をザイルで背負って英二は、雨で地盤の緩みきった崖を登攀してくれた。
本来なら初心者の英二が救助できるような現場ではなかった、けれど英二は志願して本当に周太を救助してみせた。
でもあのときの英二は山自体が初心者で、肩にはザイルを喰い込ませて痛々しかった。
「大丈夫だよ、ほら?傷痕なんかないだろ?」
山岳訓練から数日後、そう言って英二は風呂の前に脱衣所で肩を見せてくれた。
けれど本当は痕になって残っている、きっと英二は周太を気遣って隠していた。
自分が英二に傷をつけてしまった、それが哀しくて周太は呆然と白い肩を見つめていた。
そうして見つめる背中が静かに振り返ると、きれいな笑顔で英二が笑ってくれた。
「周太、」
きれいな低い声で名前を呼んでくれる。
なにか言わないと謝らないと。そんな想いで周太は英二を見つめた、けれど声が詰まって出てこない。
そんな周太を見て英二は着かけたシャツの手を止めて、周太の顔を覗き込むと笑いかけてくれた。
「どうした、周太?」
どうしたのか言って欲しいな?やさしく目で訊いてくれる。
こんなきれいな肩に傷痕を残させた自分に、気遣って英二は隠してくれていた。
どうしていつもそうなの英二?あんまり優しくて、どうしていいか解らなくなる。
とにかく今からでも、きちんと訊いて謝りたい。英二を見あげると周太は唇を開いた。
「ね、英二…その、肩の赤い線は?」
「ああ、これ?…うん、山岳訓練の時のだよ」
「俺が、怪我した時のザイルの…痕になってるの?」
すかさず訊いた周太に、すこし首かしげて英二は微笑んだ。
なんて答えようか英二は困っている、やっぱり自分の所為でついた傷に違いない。
こんな大切なこと気づけないでいた、それでも今からでも謝まりたくて周太は英二を見上げて言った。
「…俺のせいで、英二に傷をつけて…ごめんなさい、ずっと気づかなかった」
「周太、この痕はね?俺にとっては、うれしいものなんだ」
そう言って英二は微笑んでくれる。
傷痕がうれしい?意外で周太はそっと訊いてみた。
「…うれしい、の?」
「うん、うれしいよ?」
頷いて英二は周太の顔を覗き込んでくれる。
そして微笑んで英二は、穏やかに周太に言ってくれた。
「俺がね、初めて周太を背負った記念だろ?だからね、うれしいんだ。それにさ、ちょっと赤い糸みたいだろ?」
初めて・記念・赤い糸、どれも幸せそうな言葉たち。
そんな言葉を告げて、きれいに笑って英二は周太の肩へと腕を回してくれる。
どうか笑って欲しいな?そう見つめながら周太の頬へ長い指の掌でふれてくれた。
「周太、笑ってほしいよ?だってね、これが赤い糸ならさ、周太は俺の嫁さんだって証拠だろ?」
「…証拠、なの?」
これが赤い糸で自分が英二のお嫁さんだという証拠。
そんな運命だと言ってくれるの英二?そんな想いが嬉しくて周太は微笑んだ。
そう微笑んだ周太の唇に静かに英二が唇を重ねた。
「うん、俺の嫁さんって証拠。愛してるよ、周太」
重ねた唇といっしょに体ごと想いを抱きしめてくれる。
抱きしめる腕の温もりがうれしくて、抱きしめられる鼓動が温かくて、ほほ触れる深い香が愛しい。
ふれる熱い唇が深く重ねてくれる、しずかに繋がる温もりと微かな樹木の香が愛おしい。
そっと唇を離して瞳の視線をからめとると、英二は周太に微笑んだ。
「ね、周太?続き、したらダメ?」
続きってどの続き?
そう思った瞬間に午後の「あの時間」が答えのように思い出された。
そんなの真赤になってしまう、周太は急いで答えた。
「…っ、今は…ダメです」
「じゃあさ、周太?後でならいい、そういうこと?」
そんなふうに訊かないで?周太は瞳を伏せてしまった。
だって今夜は「絶対の約束」だって昼間に新宿でも英二は言っていた。
けれど午後にも英二は求めてくれた、それでも今夜は「絶対の約束」をするのだろう。
伏せたままの瞳に左腕のクライマーウォッチが映り込んで、そっと周太は唇を開いた。
「ん、…だって、…絶対の約束だから…ね、」
そう英二に告げて周太は、やっぱり気恥ずかくて微笑んだ。
そんな周太をすこし驚いて見つめる切長い目が、すこし大きくなっている。
この顔かわいいな、思いながら英二の長い腕からそっと抜け出すと周太は笑いかけた。
「あの、…風呂、冷めちゃうから…」
そして着替えを持つと手紙をしまって、周太は部屋から廊下に出た。
(to be continued)
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955