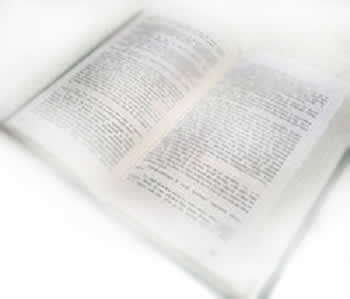昇りゆく先に、

第66話 光芒act.4―side story「陽はまた昇る」
指揮車のライトが消えて、黄昏の闇が視界を塞ぐ。
見上げる壁の涯から尖塔へザイルは続く、その先から下降。
そんなコースラインを視認して英二は上官へ微笑んだ。
「宮田、始めます、」
「はい、どうぞ、」
からり笑った声に雪白の指が薄闇に動く。
すぐストップウォッチのスイッチ微かに鳴って、英二は壁のザイルを掴んだ。
握りしめる感覚はグローブ越しに馴染む、そのまま壁へ踏み出す登山靴の底は垂直へ昇らす。
―斜度はキツい、でも足場は平らで楽だな?
独り確認を踏みしめて英二はコンクリートの壁を駈けだした。
ザイルを手繰り垂壁を空へ走り登る、その感覚に北壁の時間が映りだす。
あの冷厳に風も凍てつかす岩壁の世界は踏み間違えば惹きずりこまれる死があった。
けれど今このコンクリートには強風も氷雪も無い、そしてオーバーハングの反転すらも無い。
―アイガー北壁もマッターホルンも、こんなもんじゃない、
斜度90度の垂壁、足場の無い平面、それは確かに登り難いとも言えるだろう。
それでも気温は高く凍傷の危険は無い、高低差もアイガー1,800mに較べたら短すぎる。
そんな比較を考えたなら今、新隊員訓練の疲労などハンデにも言い訳すらにもなりはしない。
何よりもこの先に登ってゆく山を考えたなら、人工施設での訓練に甘える余裕など自分には一瞬も無いだろう。
六千メートル峰、八千メートル峰、そして世界最高峰と最高難度の山頂。
そこで光一のビレイヤー兼レスキューとしてアンザイレンパートナーを自分が務める。
それが山岳レスキューに抜擢してくれた後藤たちへの報恩で、そして自分の夢で誇りで、この道しか自分にはない。
山と救命救急の技術を卓越して山岳警察でセカンドになる、それが大切な唯ひとりを護って生きる道に繋がるのだから。
―約束したんだ、何度も何度も約束した、それなのに俺から壊したんだ、だからもう次は無い、
唯ひとつの想い、そう信じて自分は約束をした。
唯ひとり想い続けて護って生きる、そう自分の未来を信じて約束を結んだ。
それなのに自分はアイガー北壁で約束を壊してしまった、それが不実だと今は自分を赦せない。
だからこそ昨夜も今朝も縋りたくて、一瞬でも長く多く周太を抱きしめて時を過ごしていたかった。
そんな自分の弱さも狡さも、今朝に見てしまった薬袋の記憶ごと心を刺して罪と罰だと思い知らされる。
こんなにも自分は身勝手で愚かで、それでも共に生きる免罪符を得たくて今も資格を掴みに奔ってゆく。
そんな想いごと英二は壁を駆けあがり、そのまま空中を渡すザイルへ移ると真直ぐ尖塔に向かい進んだ。
―絶対に負けない、ここにいる誰よりも速く正確になりたい、
絶対に負けたくない、誰より優れていると認められるしか自分の道は無い。
そう肚底に言い聞かせるまま尖塔に辿りつき、すぐ懸垂下降に入る。
そして地面へ両足が着くとテノールが愉快に笑った。
「おつかれさん、で、暫定1位は現在宮田です。皆さん、遠慮なく宮田の記録を破っちゃってくださいね、」
暫定1位、その言葉に覚悟がまた肚に笑う。
今は自分がトップに立った、けれど必ず2位に落される。
そんな確信をしてしまう、きっと記録を告げてくれた本人がレコード更新者になる。
それこそ自分にとって何より高い壁だろう?そう想えることが何だか楽しくて微笑んだ空、黄昏は夜を呼ぶ。
―今日が終わるな、そしたら10月に一日また近づくんだ、
仰ぐ空の色彩に「瞬間」は現実へと変貌を近づける。
あの書斎で初めて一冊の本を手にした、それが現実を予感させた。
そして一つの合鍵が書斎机から目覚めさせた日記帳が現実の姿を教えてくれた。
その合鍵は今も出動服の下、紺色Tシャツと肌の狭間で堅く小さな輪郭に揺れる。
―馨さん、どうか周太を護らせて下さい、こんな俺だけど本気だから、
合鍵の元の持主に願う、この想いに偽りは今まで無い。
けれど一ヶ月前の自分が甘えてしまった罪は、現実でいる。
だからこそ願ってしまう、あの罪があるからこそ自身の本音も見える。
アイガー北壁の夜、自分は光一を抱いた。
その翌日も肌を重ねる時を過ごした、あの時間は幸せだったと今も言える。
けれど最期に選びたい相手は唯ひとりしかいない、そんな覚悟を見つめる世界は今、黄昏に赤く染まる。

湯船に浸かる体、疲労が溶けだし溜息こぼれだす。
そんな吐息に気づかされる、新隊員訓練と夜間訓練は体にきつかった。
―俺、疲れてたんだな、
心裡に自覚が笑う、そんな感覚が可笑しい。
だって2年前の自分には、今の自分は考えつかなかったのに?
こんな予想外に微笑んで湯の掌に髪かき上げる、その視界に二日目の笑顔が映った。
「お疲れさまです、って言ってもタフですよね?」
湯気を透かす向こう、あわい日焼の顔が笑いかけてくれる。
この端正な顔は昨夜も今日も見た、そして光一に聴いた話に英二は微笑んだ。
「お疲れさまです、浦部さん。俺ってそんなにタフですか?」
「新隊員訓練の直後で2位になれたら、タフでしょ?」
答えて端正な顔が笑いだす、その笑いは声から明るい。
気さくだけれど穏やかな賢明が浦部にはある、そんな空気感へ好意と笑いかけた。
「綱渡りは黒木さんの方が速いですよ、」
「それでも2位ってことは、壁登りが抜群に速いってことだよ、」
明るいトーンに笑いながら浦部は両手で顔を拭った。
湯に擦った顔は快さげに笑って、涼やかな目が英二に笑んだ。
「宮田さんて山の現場はやっと1年なんですよね?なのにあれだけ速い登攀が出来るのは、才能と努力が両方揃わないと無理だ。
アイガーとマッターホルンの記録もね、正直なとこ国村さんに引っ張られてるって想ってけど。それだけじゃないって良く解ったよ、」
率直な言葉から自分への噂と評価と、そして立場が告げられる。
どれも青梅署に居る時から解ってはいた、けれど遠い話のようにも想っていた。
それが今こうして聴かされるまま「現実」が解かる、その理解に英二は素直なまま笑った。
「ありがとうございます、戴いた評価をガッカリさせないように頑張りますね、」
現時点の評価は、少し油断すれば覆る可能性だってある。
それは期待される分だけ裏返しが怖い、そう解かるまま覚悟と笑った湯気の向こう先輩も笑ってくれた。
「やっぱり宮田さん、すごく良い貌で笑いますね?笑顔が良くて人気だって噂は聴いてたけど、ウチの皆からも支持されてますよ?」
「そうなんですか?なんか恥ずかしいです、俺、」
率直な感想と笑いかけて、また先輩も笑ってくれる。
その笑顔は賢明の明るさが頼もしい、きっと信頼出来る相手だろう。
そんな観察に隊員名簿と上官のコメントが記憶からデータを紡ぎだす。
浦部康利巡査部長 26歳 第七機動隊第2小隊所属
長野県松本出身、卒業配置は五日市署で初任総合修了4ヶ月後に第七機動隊へ異動。
日本大学山岳部OBで北アルプスのルートは熟知、地元に近い穂高連峰を得意とするアルパインクライマー。
『第2小隊で黒木の次席は浦部だよ、階級は同じだけど年次と年齢が4つ後輩だから黒木の次ってカンジでさ、人望は浦部のがあるね、』
光一から聴いた通りだと今、会話の相手を観察してしまう。
こんなふうに風呂ですら相手を計っている、そんな自分を一年前は想像できなかった。
―こういうことが日常になるんだな、これから先はずっと、
常に「立場」から物を見る、そんな感覚がもう意識の底に根付いてしまった。
それは今の湯の時間だけじゃない、今朝の食事にも感じて、きっと夕食には尚更強くなる。
(to be continued)
blogramランキング参加中!

 にほんブログ村
にほんブログ村

第66話 光芒act.4―side story「陽はまた昇る」
指揮車のライトが消えて、黄昏の闇が視界を塞ぐ。
見上げる壁の涯から尖塔へザイルは続く、その先から下降。
そんなコースラインを視認して英二は上官へ微笑んだ。
「宮田、始めます、」
「はい、どうぞ、」
からり笑った声に雪白の指が薄闇に動く。
すぐストップウォッチのスイッチ微かに鳴って、英二は壁のザイルを掴んだ。
握りしめる感覚はグローブ越しに馴染む、そのまま壁へ踏み出す登山靴の底は垂直へ昇らす。
―斜度はキツい、でも足場は平らで楽だな?
独り確認を踏みしめて英二はコンクリートの壁を駈けだした。
ザイルを手繰り垂壁を空へ走り登る、その感覚に北壁の時間が映りだす。
あの冷厳に風も凍てつかす岩壁の世界は踏み間違えば惹きずりこまれる死があった。
けれど今このコンクリートには強風も氷雪も無い、そしてオーバーハングの反転すらも無い。
―アイガー北壁もマッターホルンも、こんなもんじゃない、
斜度90度の垂壁、足場の無い平面、それは確かに登り難いとも言えるだろう。
それでも気温は高く凍傷の危険は無い、高低差もアイガー1,800mに較べたら短すぎる。
そんな比較を考えたなら今、新隊員訓練の疲労などハンデにも言い訳すらにもなりはしない。
何よりもこの先に登ってゆく山を考えたなら、人工施設での訓練に甘える余裕など自分には一瞬も無いだろう。
六千メートル峰、八千メートル峰、そして世界最高峰と最高難度の山頂。
そこで光一のビレイヤー兼レスキューとしてアンザイレンパートナーを自分が務める。
それが山岳レスキューに抜擢してくれた後藤たちへの報恩で、そして自分の夢で誇りで、この道しか自分にはない。
山と救命救急の技術を卓越して山岳警察でセカンドになる、それが大切な唯ひとりを護って生きる道に繋がるのだから。
―約束したんだ、何度も何度も約束した、それなのに俺から壊したんだ、だからもう次は無い、
唯ひとつの想い、そう信じて自分は約束をした。
唯ひとり想い続けて護って生きる、そう自分の未来を信じて約束を結んだ。
それなのに自分はアイガー北壁で約束を壊してしまった、それが不実だと今は自分を赦せない。
だからこそ昨夜も今朝も縋りたくて、一瞬でも長く多く周太を抱きしめて時を過ごしていたかった。
そんな自分の弱さも狡さも、今朝に見てしまった薬袋の記憶ごと心を刺して罪と罰だと思い知らされる。
こんなにも自分は身勝手で愚かで、それでも共に生きる免罪符を得たくて今も資格を掴みに奔ってゆく。
そんな想いごと英二は壁を駆けあがり、そのまま空中を渡すザイルへ移ると真直ぐ尖塔に向かい進んだ。
―絶対に負けない、ここにいる誰よりも速く正確になりたい、
絶対に負けたくない、誰より優れていると認められるしか自分の道は無い。
そう肚底に言い聞かせるまま尖塔に辿りつき、すぐ懸垂下降に入る。
そして地面へ両足が着くとテノールが愉快に笑った。
「おつかれさん、で、暫定1位は現在宮田です。皆さん、遠慮なく宮田の記録を破っちゃってくださいね、」
暫定1位、その言葉に覚悟がまた肚に笑う。
今は自分がトップに立った、けれど必ず2位に落される。
そんな確信をしてしまう、きっと記録を告げてくれた本人がレコード更新者になる。
それこそ自分にとって何より高い壁だろう?そう想えることが何だか楽しくて微笑んだ空、黄昏は夜を呼ぶ。
―今日が終わるな、そしたら10月に一日また近づくんだ、
仰ぐ空の色彩に「瞬間」は現実へと変貌を近づける。
あの書斎で初めて一冊の本を手にした、それが現実を予感させた。
そして一つの合鍵が書斎机から目覚めさせた日記帳が現実の姿を教えてくれた。
その合鍵は今も出動服の下、紺色Tシャツと肌の狭間で堅く小さな輪郭に揺れる。
―馨さん、どうか周太を護らせて下さい、こんな俺だけど本気だから、
合鍵の元の持主に願う、この想いに偽りは今まで無い。
けれど一ヶ月前の自分が甘えてしまった罪は、現実でいる。
だからこそ願ってしまう、あの罪があるからこそ自身の本音も見える。
アイガー北壁の夜、自分は光一を抱いた。
その翌日も肌を重ねる時を過ごした、あの時間は幸せだったと今も言える。
けれど最期に選びたい相手は唯ひとりしかいない、そんな覚悟を見つめる世界は今、黄昏に赤く染まる。

湯船に浸かる体、疲労が溶けだし溜息こぼれだす。
そんな吐息に気づかされる、新隊員訓練と夜間訓練は体にきつかった。
―俺、疲れてたんだな、
心裡に自覚が笑う、そんな感覚が可笑しい。
だって2年前の自分には、今の自分は考えつかなかったのに?
こんな予想外に微笑んで湯の掌に髪かき上げる、その視界に二日目の笑顔が映った。
「お疲れさまです、って言ってもタフですよね?」
湯気を透かす向こう、あわい日焼の顔が笑いかけてくれる。
この端正な顔は昨夜も今日も見た、そして光一に聴いた話に英二は微笑んだ。
「お疲れさまです、浦部さん。俺ってそんなにタフですか?」
「新隊員訓練の直後で2位になれたら、タフでしょ?」
答えて端正な顔が笑いだす、その笑いは声から明るい。
気さくだけれど穏やかな賢明が浦部にはある、そんな空気感へ好意と笑いかけた。
「綱渡りは黒木さんの方が速いですよ、」
「それでも2位ってことは、壁登りが抜群に速いってことだよ、」
明るいトーンに笑いながら浦部は両手で顔を拭った。
湯に擦った顔は快さげに笑って、涼やかな目が英二に笑んだ。
「宮田さんて山の現場はやっと1年なんですよね?なのにあれだけ速い登攀が出来るのは、才能と努力が両方揃わないと無理だ。
アイガーとマッターホルンの記録もね、正直なとこ国村さんに引っ張られてるって想ってけど。それだけじゃないって良く解ったよ、」
率直な言葉から自分への噂と評価と、そして立場が告げられる。
どれも青梅署に居る時から解ってはいた、けれど遠い話のようにも想っていた。
それが今こうして聴かされるまま「現実」が解かる、その理解に英二は素直なまま笑った。
「ありがとうございます、戴いた評価をガッカリさせないように頑張りますね、」
現時点の評価は、少し油断すれば覆る可能性だってある。
それは期待される分だけ裏返しが怖い、そう解かるまま覚悟と笑った湯気の向こう先輩も笑ってくれた。
「やっぱり宮田さん、すごく良い貌で笑いますね?笑顔が良くて人気だって噂は聴いてたけど、ウチの皆からも支持されてますよ?」
「そうなんですか?なんか恥ずかしいです、俺、」
率直な感想と笑いかけて、また先輩も笑ってくれる。
その笑顔は賢明の明るさが頼もしい、きっと信頼出来る相手だろう。
そんな観察に隊員名簿と上官のコメントが記憶からデータを紡ぎだす。
浦部康利巡査部長 26歳 第七機動隊第2小隊所属
長野県松本出身、卒業配置は五日市署で初任総合修了4ヶ月後に第七機動隊へ異動。
日本大学山岳部OBで北アルプスのルートは熟知、地元に近い穂高連峰を得意とするアルパインクライマー。
『第2小隊で黒木の次席は浦部だよ、階級は同じだけど年次と年齢が4つ後輩だから黒木の次ってカンジでさ、人望は浦部のがあるね、』
光一から聴いた通りだと今、会話の相手を観察してしまう。
こんなふうに風呂ですら相手を計っている、そんな自分を一年前は想像できなかった。
―こういうことが日常になるんだな、これから先はずっと、
常に「立場」から物を見る、そんな感覚がもう意識の底に根付いてしまった。
それは今の湯の時間だけじゃない、今朝の食事にも感じて、きっと夕食には尚更強くなる。
(to be continued)
blogramランキング参加中!