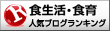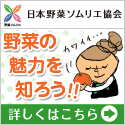遅めの昼食をとって向かったのが、また別の集落。
「とうぢしゃ」のタネを探すべく、
コチラにお住いのNさんというおばあちゃんのところにお伺いしました。
Nさん曰く、
「とうぢしゃ」は、鉄分豊富で、おひたしにすると美味しいとおっしゃってました。
「とうぢしゃ」は、フダンソウ(スイスチャード)の一種。
それもそのはず。
食品栄養成分表(2015年ですが)より、
「フダンソウ」に含まれる鉄分は、
生が3.6g、加熱すると2.0g。
ほうれん草が、生で2.0g、加熱すると0.9g。
空心菜が生で1.5g、加熱すると1.0g。
圧倒的に多く含まれます。
ちなみに、市販のタネ「うまい菜」とは育ち方や姿が違うそうで、
こちらの集落で「うまい菜」を育てると、
葉だけがやたら大きく育つそうです。
一方、とうぢしゃは葉は割とスマートになるそうです。
また、Nさんは年に2回タネを播くとおっしゃってました。
秋播き春収穫、春播き(4月ごろ)秋収穫だそうです。
また、種播きした後、畑の隅っこに移植するそうです。
ところで、コナも作られているそうで、
お話をお伺いすると、最初にお伺いしたAさんところとほとんどカタチは同じ。
こちらの集落では、在来種であること協調(区別)するために「ムカシコナ」と呼んでいるそうです。
昔は、竹の皮で束ねていたとのこと。
また、コナは川上村の郷土食、「菜めし」の材料。
「菜めし」とは、こんな郷土食です。
2014年3月に頂いたことがあります。
コナと合わせて、ご覧ください→コチラへ。
Nさんところ(こちらの集落全体のことを指している可能性もあります。)ではおじゃこのだしで炊いていたそうです。
タネ採りの場合、1本だけ残すだけでタネが採れるそうです。
また、コチラでも在来の豆が作られているとのこと。
インゲン豆は冬の貴重なおかずになっていたそうです。
大きくは「うずら豆」と「秋豆」に分けられます。
うずら豆はさらに2つに分かれていて、
にど豆(1年に2回栽培可能なことからそう呼ばれる)
よど豆(1年に4回栽培可能なことからそう呼ばれる)
が、あるそうです。
ここは、インゲン豆のことを1年に3回栽培可能なことから「三度豆」と呼ばれるのと同じようについた名前ですね。
また、秋豆は、紫と白を育てているとおっしゃってました。
さらに、Nさんところでは、野崎白菜を育ててらっしゃるそうです。
野崎白菜は、日本で一番最初にデビューした、結球型の白菜。
愛知県の伝統野菜の1つでもあり、今、私たちが食べている白菜の原種なのです。
8月末~9月半ばに種まきし、60日で収穫出来る(年内に収穫できる)極早生の白菜です。
Nさん曰く、
「原種を大事に育てて、大事に味わいたい」との想いで毎年育てているそうです。
ところで、Aさんところにお土産としてお持ちしました、
「でんがらもち」。
こちらの集落では「朴の葉ちまき(ほのはちまき)」とよばれるそうです。
生地の材料は、米粉(こちらではお団子の粉)。
粘り気を出したい場合、もち米を少し加えるそうです。
また、きび、とうきび、粟なども使われ、
様々な種類があったそうです。
昔は生の生地にあんを包み、
蒸す、または、茹でていたそうです。
また、「朴の葉ちまき」は、毎年6月7日の「山の神」の神事に合わせて作られるそうです。
こちらの集落では6月7日と、11月7日の年2回、山の神の神事が行われます。
これは、昔、5月末まで残雪があったことと、
11月には雪が積もっていたため、山仕事が出来るのが6月7日~11月7日と設定。
山仕事の仕事始めと、仕事納めに、神事を行われていて、今日に至ります。
ちなみに、11月7日は、地域の男性の方が
お餅に山菜、野菜をお供えするそうです。
イメージとしては、地蔵盆のような感じだとのことです。
さて、集落をぶらりとすると、葉の切れ込みが深く、
見たことのないイチジクの木がありました。


最初にお伺いした集落のAさんところにも同じものが植えられていましたが、
Aさん曰く、相当古い品種だろうとのこと。
どんな味か?気になりますね。
丸1日、川上村での聞き取りに同行させて頂き、
在来野菜、伝統食の作り方について、
集落ごと、各家庭ごとに微妙に違いがあることが、
あたらめて勉強になりました。
さらに、お会いしたお三方共に御年80代後半。
なのに、動きが軽やか!
気持ちが皆さんお若く、むしろゲンキをもらいました。
ワタクシも、野菜ソムリエさんのイベントなどで、
他府県の伝統野菜の農家さんや伝統食に携わっている方とお会いする機会がありますが、
とにかく皆さんお年を重ねていても元気!元気!です。
在来種、郷土食。他にないパワーを感じました。
お世話になりました皆様、ありがとうございました。
****************************************
◆◆ブログランキングに参加中◆◆
~クリックして下さればありがたいです↓~
続いて向かった集落。
Aさんに同行頂き、最初にお伺いした集落から車で15分くらい走りましたでしょうか。
細い道を進み、途中から坂はきつく、ヘアピンカーブの連続。
本当に集落があるのか?不安になるところでした。
そして、突然視界が開けて、到着。


そこはまるで昭和一色。そして水墨画の世界・・・。
鴬を初め、小鳥のさえづりだけが大きくこだまし、
雨粒もゆっくりと落ちている感じでした。
Aさんがお尋ねしたのが、Tさんという女性のお宅。
しばらくお会いされてなかったのか、立ち話が始まるとずーっと止まりませんでした。
そのまま、「とうぢしゃ」の話題へ。
Tさんはあいにく今は、とうぢしゃは作られてませんでしたが、
かつては作られていたとのこと。
Tさんは、天ぷらにして食べるとおっしゃってました。
それから、秋豆も育てられているとのこと。
「秋豆」とは、つるありインゲン豆の一種で、
Tさんのお話によると、白色、紫色、黒色があるとのこと。

こちらが、紫色の秋豆です。
ちなみに秋豆は7月頃に種まきをして、9月~11月に収穫します。
つるが結構伸びます。
支柱をしっかり立てないと、台風で倒れてしまうそうです。
ところで、ワタクシの秋豆の逸話ですが、
まず、白い方の秋豆ですが、
上北山村の知人が、よく似たものを栽培されている方がいると
聴いたことがあります。
また、紫色の秋豆は、ワタクシが以前育てていた、
野迫川村の「キョロ豆」と大変良く似ていました。
(私はキョロ豆は7月末~8月上旬、1回目のキュウリを植えた後に種まきします。)

こちら、Tさんの秋豆。

こちら、自宅から偶然出てきたキョロ豆。
(3~4年ほど前のタネの為、発芽は期待できません。)
それから、一番最初にキョロ豆を育てた時、キュウリネットだけではちゃんとツルが巻いてくれませんでした。
そこで、スス竹を立てると、ツルが巻いてくれるようになりました。
また、こちらの集落では「北山コナ」を育てられていたとのこと。
お話をお伺いすると、コチラと同じだそうです。
それ以外に、自家製お茶の作り方や、栃の実のあく抜き方法などのお話もお伺いしました。
集落によって、ご家庭によって茶葉の揉み方、栃の実のあく抜きの方法、微妙に違います。
・・・と、いろいろお話で盛り上がり、何時間お話したことでしょう。
Tさんから、自家製のお茶をごちそうしていただきました。

これがまるで高級茶のように絶品!
味は濃厚なのに、苦みが少なく、すっと口にできます。
冷やしても美味しいでしょうね。
Aさんところでも自家製お茶をたっぷり頂いたのに、ついつい飲んでしまいました。

Tさんのところで乾燥中の「ばしょう(赤高菜)」のタネ。

こちらの集落でも、ちしゃが作られてました。
かつては大家族(拡大家族)の世帯が多く、
戦後、100人いたこの集落の人口も、今やたった5人。
携帯の電波も圏外。まさに別世界です。
Tさんいわく、以前はうぐいすも飼っていたこともあるとおっしゃってました。
本当に自然と共存していたのでしょうね。
で、たった5人の集落。
どなたもお年を召されて、
集落の生命線である、国道に通じる唯一の道はコケのわだちが出来つつあり、
集落全体のお手入れはもちろん、氏神様でさえも管理が行き届かなくなっているとのこと。
由緒ある神社は注目される一方で、
管理が行き届かなくなり、荒れて魂も感じなくなりつつある神社の現状も知って欲しいと感じました。
で、Aさんをご自宅まで送り、近藤さんとワタクシは、また別の集落に向かいます。
出会ったのが、すごいおばあちゃんでした。
次回に続きます。
****************************************
◆◆ブログランキングに参加中◆◆
~クリックして下さればありがたいです↓~
 にほんブログ村 野菜ソムリエ
にほんブログ村 野菜ソムリエ
 にほんブログ村 半農生活
にほんブログ村 半農生活
Aさんに同行頂き、最初にお伺いした集落から車で15分くらい走りましたでしょうか。
細い道を進み、途中から坂はきつく、ヘアピンカーブの連続。
本当に集落があるのか?不安になるところでした。
そして、突然視界が開けて、到着。


そこはまるで昭和一色。そして水墨画の世界・・・。
鴬を初め、小鳥のさえづりだけが大きくこだまし、
雨粒もゆっくりと落ちている感じでした。
Aさんがお尋ねしたのが、Tさんという女性のお宅。
しばらくお会いされてなかったのか、立ち話が始まるとずーっと止まりませんでした。
そのまま、「とうぢしゃ」の話題へ。
Tさんはあいにく今は、とうぢしゃは作られてませんでしたが、
かつては作られていたとのこと。
Tさんは、天ぷらにして食べるとおっしゃってました。
それから、秋豆も育てられているとのこと。
「秋豆」とは、つるありインゲン豆の一種で、
Tさんのお話によると、白色、紫色、黒色があるとのこと。

こちらが、紫色の秋豆です。
ちなみに秋豆は7月頃に種まきをして、9月~11月に収穫します。
つるが結構伸びます。
支柱をしっかり立てないと、台風で倒れてしまうそうです。
ところで、ワタクシの秋豆の逸話ですが、
まず、白い方の秋豆ですが、
上北山村の知人が、よく似たものを栽培されている方がいると
聴いたことがあります。
また、紫色の秋豆は、ワタクシが以前育てていた、
野迫川村の「キョロ豆」と大変良く似ていました。
(私はキョロ豆は7月末~8月上旬、1回目のキュウリを植えた後に種まきします。)

こちら、Tさんの秋豆。

こちら、自宅から偶然出てきたキョロ豆。
(3~4年ほど前のタネの為、発芽は期待できません。)
それから、一番最初にキョロ豆を育てた時、キュウリネットだけではちゃんとツルが巻いてくれませんでした。
そこで、スス竹を立てると、ツルが巻いてくれるようになりました。
また、こちらの集落では「北山コナ」を育てられていたとのこと。
お話をお伺いすると、コチラと同じだそうです。
それ以外に、自家製お茶の作り方や、栃の実のあく抜き方法などのお話もお伺いしました。
集落によって、ご家庭によって茶葉の揉み方、栃の実のあく抜きの方法、微妙に違います。
・・・と、いろいろお話で盛り上がり、何時間お話したことでしょう。
Tさんから、自家製のお茶をごちそうしていただきました。

これがまるで高級茶のように絶品!
味は濃厚なのに、苦みが少なく、すっと口にできます。
冷やしても美味しいでしょうね。
Aさんところでも自家製お茶をたっぷり頂いたのに、ついつい飲んでしまいました。

Tさんのところで乾燥中の「ばしょう(赤高菜)」のタネ。

こちらの集落でも、ちしゃが作られてました。
かつては大家族(拡大家族)の世帯が多く、
戦後、100人いたこの集落の人口も、今やたった5人。
携帯の電波も圏外。まさに別世界です。
Tさんいわく、以前はうぐいすも飼っていたこともあるとおっしゃってました。
本当に自然と共存していたのでしょうね。
で、たった5人の集落。
どなたもお年を召されて、
集落の生命線である、国道に通じる唯一の道はコケのわだちが出来つつあり、
集落全体のお手入れはもちろん、氏神様でさえも管理が行き届かなくなっているとのこと。
由緒ある神社は注目される一方で、
管理が行き届かなくなり、荒れて魂も感じなくなりつつある神社の現状も知って欲しいと感じました。
で、Aさんをご自宅まで送り、近藤さんとワタクシは、また別の集落に向かいます。
出会ったのが、すごいおばあちゃんでした。
次回に続きます。
****************************************
◆◆ブログランキングに参加中◆◆
~クリックして下さればありがたいです↓~
7/7(土)、
吉野の水源地の村「川上村」へ。
大和高原を中心に郷土食や民俗学を研究する「大和高原民族文化研究団」で
ご一緒させて頂いております近藤夏織子さんと、
3か所の集落に在来野菜や「でんがらもち」をはじめとする
郷土食などの聞き取りに行かせていただきました。

1か所目の集落へ。
コチラにお住いのAさんというおばあちゃんところをお尋ねしました。
こちらでは、ちしゃ、ばしょう、こな(まごな)、とうぢしゃなどを栽培されております。
ご存知ない方のためにご紹介しますと、
●ちしゃ
キク科の植物で、サニーレタスやサンチュなど、葉をかいて食べるレタスの原種。
●ばしょう
赤高菜。
吉野では他に「からし菜」と呼ばれます。漬物がメイン
●こな(まごな)
アブラナ科の一種で、シロナに似ているが、シロナと違って茎はやや緑っぽく、
ややギザギザ。葉は白菜の外葉に近い。
実は2014年3月にこちらの地区にお伺いした時に実物を拝見しました。
その時のブログがあります。
コチラ
をご覧ください。
●とうぢしゃ
フダンソウ(ヒユ科フダンソウ属)の一種。
ほうれん草よりも大型で茎や葉は太い。
まずは、近藤さんがご用意くださいました「でんがらもち」を頂きながら
色々お話をお伺いしました。


これは、2日前に近藤さんが2日前に東吉野村で手習いした「でんがらもち」を
お土産として片手に、お伺いしました。
固くなったら、そのまま何度でもゆで直せて、しかも日持ちします。

そしてAさん手作りのおかき菓子を頂きながら、色々お話をお伺いしました。
塩加減が絶妙!美味しかったです。
お話をお伺いした後、実際に畑も見学させてもらいました。

こちら、タネ採りを待つ「ちしゃ」です。

在来のコンニャクイモも育てられています。
身内の方が買ってきて植えた市販の品種の種イモと共生していました。
ところが、市販の種イモを植えてから、病気にかかり育ちが悪くなったとのこと。



姿は微妙に違いました。
在来種は、枝の本数が違います。
また、茎のまだら模様が濃く、しかも育ちが小さいころから現れてます。
(市販の方は、育ちが小さいころはまだら模様が表れてません)

Aさんの畑は、敷き藁の代わりにカヤを使われてました。
もともとこの地域は田んぼがないため、カヤが使われていたそうです。
ところで、Aさんの「とうぢしゃ」ですが、
近藤さん曰く、葉がツルムラサキのように緑が濃く、葉はツヤツヤしている。
そして、タネは赤っぽいとのこと。
そんな「とうぢしゃ」ですが、今年、生えてこなかったそうです。
Aさんが育てているとうぢしゃは、
かなり昔に東吉野村某所からタネを頂いて育てたそうです。
事前に近藤さんがそちらで、在来野菜(とうぢしゃ)と
思われる野菜(とうたちした状態)を頂いてこられました。

新子谷さんとご一緒に観察した結果、フダンソウの仲間ではありますが、どうも姿が違う。
市販の「うまい菜」かもしれない。という話に・・・。
Aさんが育てていた「とうぢしゃ」。
お近くで作ってらっしゃる方がいれば・・・。
というわけで、続いて向かったのが、Aさんのご友人がお住いのとある集落です。
****************************************
◆◆ブログランキングに参加中◆◆
~クリックして下さればありがたいです↓~
 にほんブログ村 野菜ソムリエ
にほんブログ村 野菜ソムリエ
 にほんブログ村 半農生活
にほんブログ村 半農生活
吉野の水源地の村「川上村」へ。
大和高原を中心に郷土食や民俗学を研究する「大和高原民族文化研究団」で
ご一緒させて頂いております近藤夏織子さんと、
3か所の集落に在来野菜や「でんがらもち」をはじめとする
郷土食などの聞き取りに行かせていただきました。

1か所目の集落へ。
コチラにお住いのAさんというおばあちゃんところをお尋ねしました。
こちらでは、ちしゃ、ばしょう、こな(まごな)、とうぢしゃなどを栽培されております。
ご存知ない方のためにご紹介しますと、
●ちしゃ
キク科の植物で、サニーレタスやサンチュなど、葉をかいて食べるレタスの原種。
●ばしょう
赤高菜。
吉野では他に「からし菜」と呼ばれます。漬物がメイン
●こな(まごな)
アブラナ科の一種で、シロナに似ているが、シロナと違って茎はやや緑っぽく、
ややギザギザ。葉は白菜の外葉に近い。
実は2014年3月にこちらの地区にお伺いした時に実物を拝見しました。
その時のブログがあります。
コチラ
をご覧ください。
●とうぢしゃ
フダンソウ(ヒユ科フダンソウ属)の一種。
ほうれん草よりも大型で茎や葉は太い。
まずは、近藤さんがご用意くださいました「でんがらもち」を頂きながら
色々お話をお伺いしました。


これは、2日前に近藤さんが2日前に東吉野村で手習いした「でんがらもち」を
お土産として片手に、お伺いしました。
固くなったら、そのまま何度でもゆで直せて、しかも日持ちします。

そしてAさん手作りのおかき菓子を頂きながら、色々お話をお伺いしました。
塩加減が絶妙!美味しかったです。
お話をお伺いした後、実際に畑も見学させてもらいました。

こちら、タネ採りを待つ「ちしゃ」です。

在来のコンニャクイモも育てられています。
身内の方が買ってきて植えた市販の品種の種イモと共生していました。
ところが、市販の種イモを植えてから、病気にかかり育ちが悪くなったとのこと。



姿は微妙に違いました。
在来種は、枝の本数が違います。
また、茎のまだら模様が濃く、しかも育ちが小さいころから現れてます。
(市販の方は、育ちが小さいころはまだら模様が表れてません)

Aさんの畑は、敷き藁の代わりにカヤを使われてました。
もともとこの地域は田んぼがないため、カヤが使われていたそうです。
ところで、Aさんの「とうぢしゃ」ですが、
近藤さん曰く、葉がツルムラサキのように緑が濃く、葉はツヤツヤしている。
そして、タネは赤っぽいとのこと。
そんな「とうぢしゃ」ですが、今年、生えてこなかったそうです。
Aさんが育てているとうぢしゃは、
かなり昔に東吉野村某所からタネを頂いて育てたそうです。
事前に近藤さんがそちらで、在来野菜(とうぢしゃ)と
思われる野菜(とうたちした状態)を頂いてこられました。

新子谷さんとご一緒に観察した結果、フダンソウの仲間ではありますが、どうも姿が違う。
市販の「うまい菜」かもしれない。という話に・・・。
Aさんが育てていた「とうぢしゃ」。
お近くで作ってらっしゃる方がいれば・・・。
というわけで、続いて向かったのが、Aさんのご友人がお住いのとある集落です。
****************************************
◆◆ブログランキングに参加中◆◆
~クリックして下さればありがたいです↓~