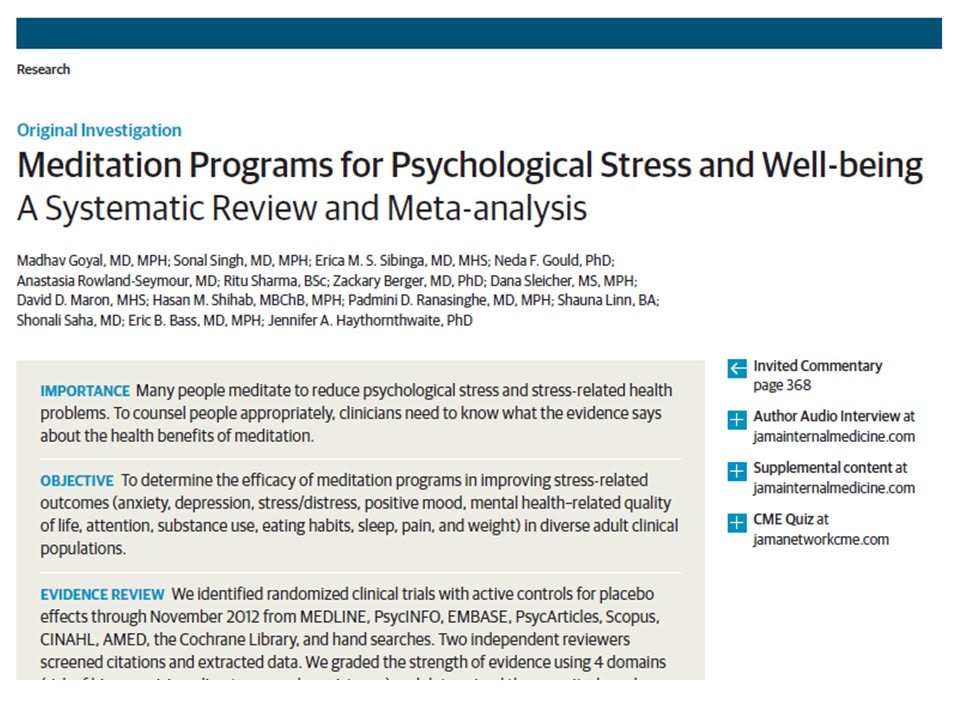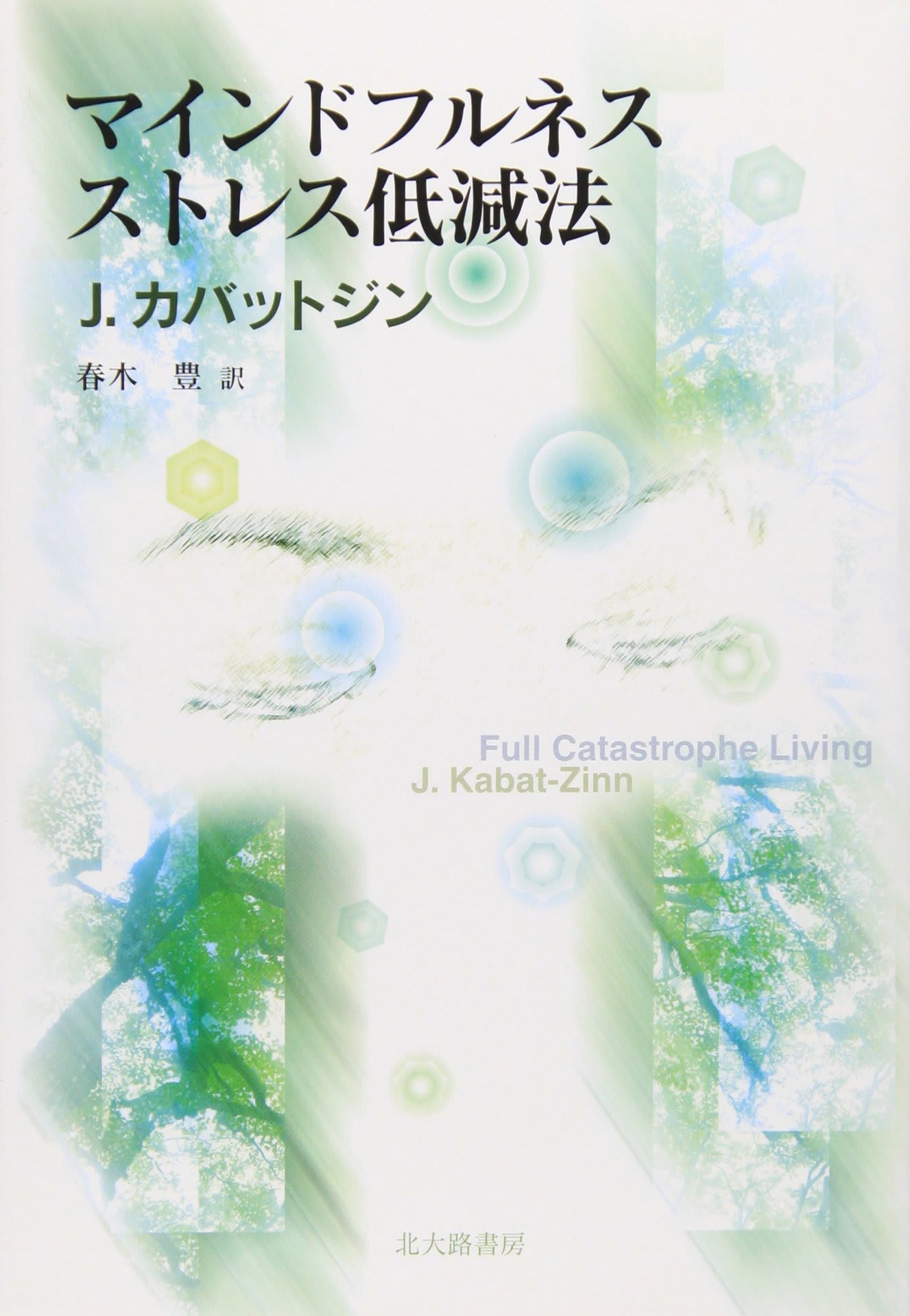入院中によく見ていたのが、円覚寺管長の横田南嶺氏のYoutubeです。コロナ禍でできなくなった坐禅会での講話や大学での講演の代わりに、動画収録してYoutubeにアップしてくれています。そんなYoutubeビデオ法話の中に、林香寺住職で精神科医の川野泰周氏との対談「お寺で対談 – 第二回 –」が5回に分けて公開されていて、おもしろく見ていました。
川野住職によると、他人の心がわからない人が自閉スペクトル症候群(ASD)で、それとは反対に繊細過ぎて他人の感情が強く入ってきてしまう人がHSP(過敏性)であり、なにか全く異なる人たちであるような説明の仕方をしていましたが、どちらも根はいっしょであることがわかってないなと、突っ込みどころもありました。一方で、こうした人たちへのマインドフルネスの利用の仕方をその人のタイプに合わせて工夫しているという話は興味深いものでした。HSPの人たちは自分を責めてしまっているために自分に思いやりの気持ちを向ける慈悲の瞑想はうまくできないが、体験を観察していくシンプルな瞑想、例えば「食べる瞑想」は自分のことに気持ちを向けるいいきっかけになるといいます。また、HSPの人はそれぞれ過敏な感覚器官があるので、そうした感覚器官を使わない瞑想法が向いているそうです。うつ病などで自分を責める気持ちが強いうちは瞑想しようとしてもそうした気持ちがグルグル回ってしまうので、休息と薬物で症状を和らげてから、マインドフルネスをやってみるとうまくいくということです。
【お寺で対談⑤】マインドフルネスと禅の違い、HSPとマインドフルネス、マインドフルネス治療の効果 | 林香寺住職/精神科医 川野泰周氏・臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師
横田管長は、セルフコンパッション(自慈心)についての話の中で、臨済録の中の一節を紹介していました。その内容は「仏道においてするべきことは、大便小便すること、服を着ること、ご飯を食べること、疲れたら寝るだけのこと。それ以外になにも求めるものはない、それが「無事」である」というものです。それが人間の根底にある尊厳であると言います。
私の入院生活についていうと、手術中は麻酔にかかっていて自分でできることは何もない、手術後には寝ることくらいはできて、だんだんと服を着る、小便大便する、ご飯を食べるというふうにできることが増えてきて、そのたびに安堵して人間らしさが戻ってきた感じがしました。なかなかこういう体験ができることはなく、あらためて自らを振り返ることができたのでした。
横田管長はさらに続けて言います。上記以外のことは、飾りや付けたしであるというものの見方ができるとアクセクしなくてすみます。つい業績を上げないといけない、評価されないといけないと考えてしまうが、そんなことは枝葉末節のことであって、上記のことができていればいいという考えが根底にあれば、それこそセルフコンパッションの最たるものだと最近になってやっと気がついたと言います。
【お寺で対談③】声の可能性、セルフ・コンパッション/自慈心 | 林香寺住職/精神科医 川野泰周氏・臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺老師