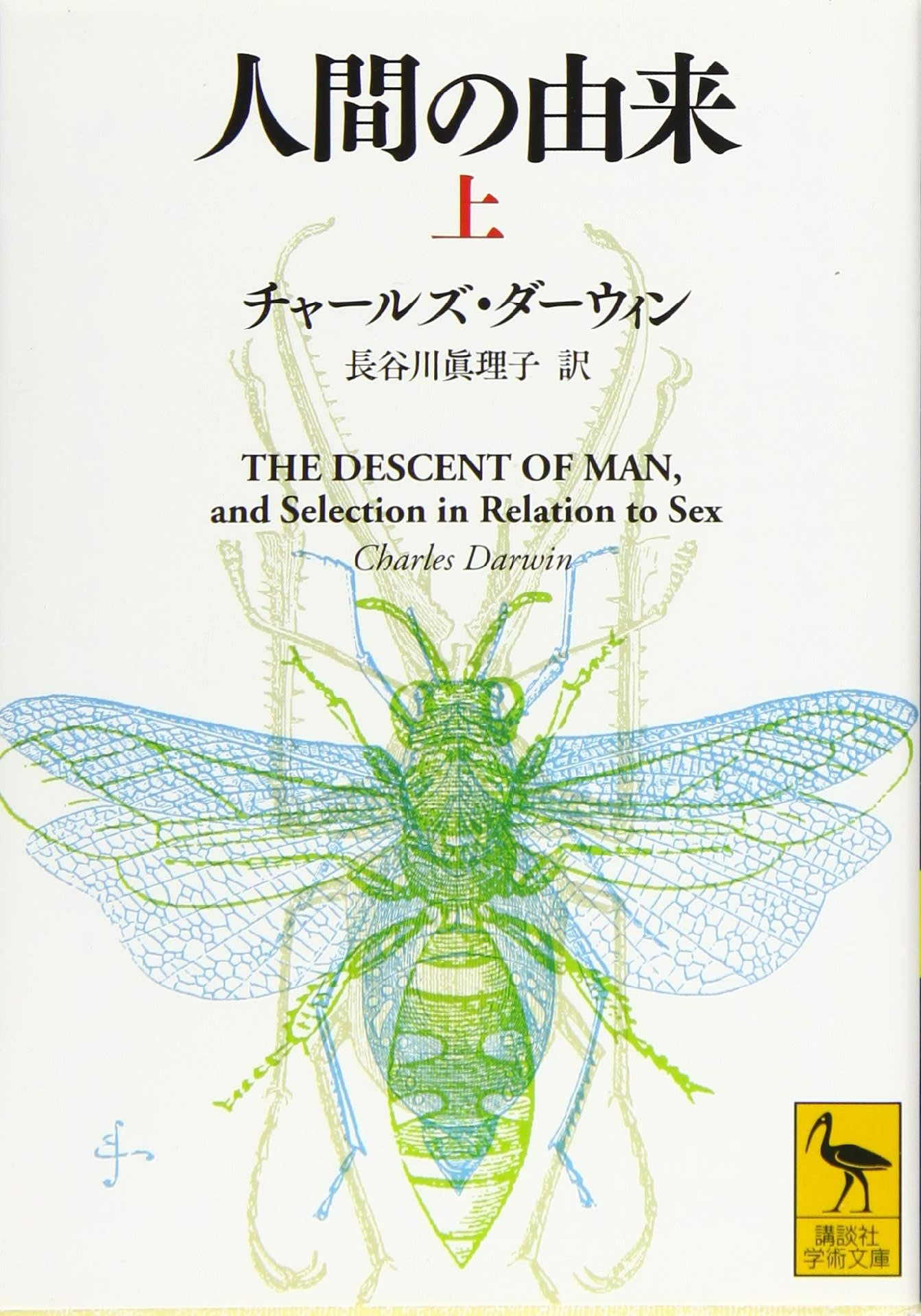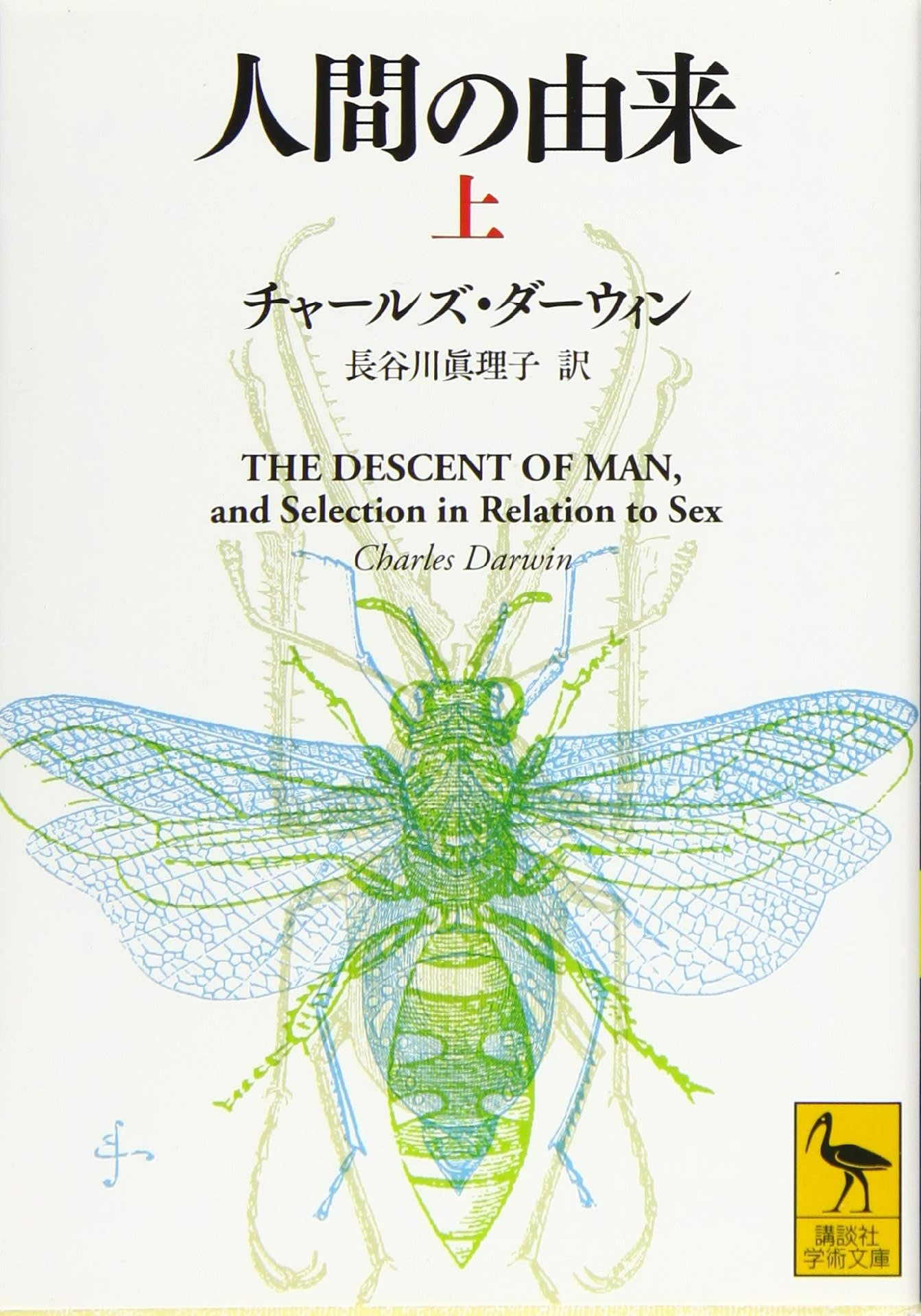
本書はチャールズ・ダーウィンによる1871年の著、「The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex」の長谷川眞理子氏による日本語訳である。当初、日本語訳は1999-2000年に「人間の進化と性淘汰」として刊行されているので、「人間の由来」より、そちらのほうがタイトルとしては的確である。その時代におけるダーウィンの先見性や、これでもかといわんばかりの綿密な情報と考察の積み重ねにはすばらしいものがあるが、現代の進化生物学の常識から考えたらどうしても時代性を感じてしまう。なかなか読み通すのには苦労したが、人類や動物の進化学という学問がここから始まったのだと考えれば、その分野に興味のある人は一度読んでおいてもいい本かもしれない。長谷川眞理子氏による訳注が章ごとに付いているので、現代の進化生物学における見解などもわかるようになっている。
上下巻を合わせると、「第Ⅰ部 人間の由来または起源」に約300ページ、「第Ⅱ部 性淘汰」に約700ページがさかれていて、後者の分量が多い。上巻の構成と、章ごとに気になった内容を下記に列記した。
第Ⅰ部 人間の由来または起源
第1章 人間が何らかの下等な形態のものに由来することの証拠
・今では動物福祉の観点から許されないような実験がこの当時はされていて、その1例がサルにアルコールや煙草を摂取させる実験だ。「多くのサル類は、お茶、コーヒー、強い酒を好み、私は自分の目で見たことがあるが、喜んで煙草を吸うようになる。ブレーム...は自分が飼っていたヒヒの何頭かが酔っ払ったのを見たことがあり、彼らの行動や奇妙なしかめっ面について、おもしろい話を書いている。その翌朝には、ヒヒたちは非常に機嫌が悪かった。彼らは痛む頭を両手ではさみこみ、実に惨めな表情をしていた。...このような些細な事実は、サル類と人間の味覚の神経がいかに類似しているかということの証拠であり、両者の全神経系が同じような影響を受けることを物語っている。」
第2章 人間と下等動物の心的能力の比較
・ダーウィンは、人間の心の原型はすで霊長類にあったと考えていた。「本章での私の目的は、人間と高等哺乳類との間には、心的能力において本質的な差はないということを示すことにある。」
・言語を生物の進化とのアナロジーで考察しているのは慧眼ではないだろうか。「言語も、生物と同様、大きな集団とそれに属する小さな集団とに入れ子のように分類することができ、その由来によって自然分類することもできれば、他の性質によって人工的に分類することもできる。優位な言語や方言は広範囲に広まり、他の言語を徐々に絶滅に追いやっていく。...言語も、生物種と同様、一度絶滅すると二度と復活することがない。二つの異なる場所から同一の言語が発生してくることもない。異なる言語どうしは、かけ合わさったり、混合したりすることがある。」
第3章 人間と下等動物の心的能力の比較(続き)
・驚くべきは、すでにこの時代に共感の進化について論じていることである。現代につながる問題意識である。「私たちが他人に同情して親切な行動を示すときには、何かよいお返しがあることを期待しているものであるし、共感が習性によって大いに強化されることも間違いないからだ。この感情がどんなに複雑な様相で始まったとしても、それはたがいに助け合ったり守り合ったりするすべての動物にとって非常に重要な感情なので、自然淘汰によって増強されるに違いない。つまり、最も共感的な個体を最も多く有する集団が最も栄え、より多くの子どもをあとに残したに違いないからである。」
第4章 人間がどのようにして何らかの下等な形態から発達してきたのかについて
・人間だけでなく動物の心には多様性があることを述べている。「人間の心的能力には、同じ人種の中にも変異と多様性があり、異なる人種間ではさらに大きな差があることはよく知られているので、ここで多くを述べる必要はないだろう。...このことは下等動物の間でさえみとめられる。動物園で働いていた人々は、誰もがこの事実を認めており、イヌや他の家畜を見ても容易にわかることだ。」
第5章 原始時代および文明時代における、知的、道徳的能力の発達について
・他人との互恵性や共感に再び触れている。「同じ部族に属する人間の中で、...各メンバーの推論の力と予測の力とが向上してくるにつれ、各自は自分の経験から、誰かを助ければふつうはお返しを得るということを素早く学習するに違いない。このような下賤な理由から、人間は仲間を助ける習慣を身につけたのかもしれない。そして、仲間に対して慈愛に満ちた行動を取る習慣が、最初に慈愛に満ちた行動を取らせる衝動を与えている共感の感情をさらに強めることになったに違いない。そして、何世代にもわたって従われてきた習慣は、遺伝するようになるのだろう。」
第6章 人間の近縁関係と系統について
第7章 人種について
第Ⅱ部 性淘汰
第8章 性淘汰の諸原理
・性淘汰とは何か。「雄が現在のような構造を獲得したのは、存続のための争いで生き残ることに適していたからではなく、他の雄と比べて有利だったからであり、そのような有利な形質が雄の子のみを通じて受け継がれたからだと考えられる。そこには性淘汰がはたらいているに違いない。」
・去年の冬、私が水辺で観察していて、北から渡ってきたキンクロハジロが最初オスばかりなのが気になっていた。渡り鳥の行動として繁殖を行う春では、このようなことがあり得ることを示すダーウィンの記述があった。「雌の心的能力が選り好みを行うのに十分だと仮定するならば、雌たちは多くの雄の中から一頭を選び出すことができるだろう。しかし、多くの場合、なるべくたくさんんの雄たちの間に闘争が生じるよう、あたかも特別に仕組まれているかのように見える。例えば、渡り鳥では、ふつう雄が雌より先に繁殖地に到着するので、それぞれの雌が現れるたびに、多くの雄がその雌をめぐってすぐに闘い始める。」
第9章 動物界の下等な綱における第二次性徴
・雄と雌との交尾行動は猟奇的なまでに危ういことがある。クモの仲間において「雄は雌に近づくにあたって非常に用心深いが、それは、雌のはにかみかたが危険なところまで推し進められているからである。ド・ギア―は、ある一匹の雄が「交尾前の愛撫の真っ最中に、彼の注意の対象によって捕らえられ、彼女の網に包まれてむさぼり食われてしまった」のを見たが、それは彼の心を「恐ろしさと義憤で満たす」光景だった。」
第10章 昆虫における第二次性徴
第11章 昆虫(続き)―鱗翅目