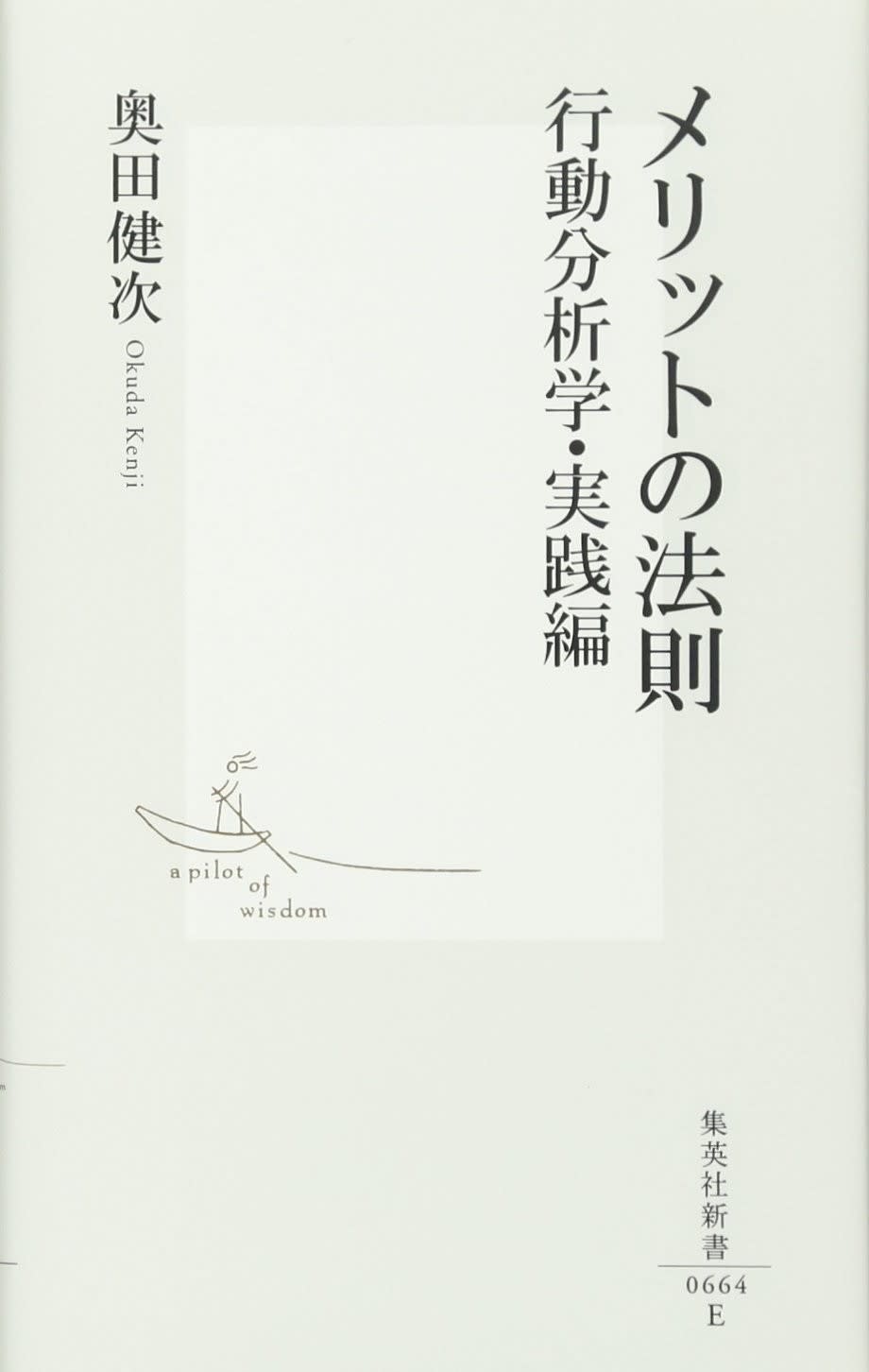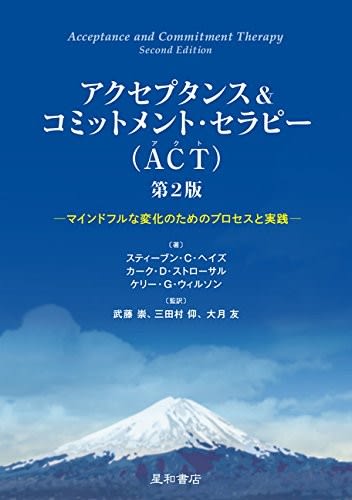精神疾患の6分野の最新の治療法について、それぞれの専門家が分担執筆した本だと思っていたが、読んだら違っていた。読売新聞などで記事を書いていた医療ジャーナリストである佐藤光展氏が、これらの専門家に取材しつつ持論を展開する内容であった。期待の持てる最新の治療法を取り入れようとしてきた専門家たちの努力が紹介されているのだが、そうした治療法についての医学的な解説というよりは、それらの日本への導入が遅れていることや、日本の精神医療全体の問題について、日本の制度に原因があることを明らかにしている。社会問題を追及するジャーナリスト的な著作である。
それぞれの精神疾患などが、7章に分けて取り上げられている。各章のあとには、コラムも付いている。備忘録として、下記にポイントを引用しておきたい。
第1章 依存症「ヒトは生きるために依存する」(松本俊彦)
・薬物依存症の人たちが、刑罰によってますます追い込まれていく負の連鎖が日本にはあるが、松本医師は、海外で成果を上げるハームリダクション(薬物を止めさせることよりも、使用による悪影響の緩和を優先する支援)と似た取り組みとして、薬物を再使用しても、打ち明けられるような関係づくりを行うことで回復していくSMARPPというプログラムを実施している。
・日本では薬物療法偏重の精神医療が行われてきた。その理由は、国が精神科に薄利多売を押しつけてきたため、クリニックが外来患者の面接に長い時間をかけると経営が厳しくなる。それで、診療報酬上もっとも効率が良い5分で診察を回して、面接よりも薬一辺倒の診療になっているからである。
第2章 発達障害「精神疾患の見方が根底から変わる」(原田剛志)
・発達障害は統合失調症と誤診されることが多かった。統合失調症と診断されて薬物治療を受け続ける人の中には、子どもの頃に継続的ないじめを受けたり、親からの虐待を受け続けたりした経験のある人が多い。彼らに生じた「幻聴」や「妄想」の多くは、聴覚性フラッシュバックや被害関係念慮であり、誤診だった可能性がある。しかし、抗精神病薬を長く飲み続けると、脳機能の一部が変化して「ドパミン過感受性精神病」という医原病が生じることがある。薬を減らすと統合失調症のような症状が表れるので誤診が覆い隠されてしまう。
・自閉スペクトラム症や「薄い自閉」がある人は、傍目から見るとそこまで重くないように思えるストレス体験の積み重ねでも、複雑性PTSDのような状態になりやすいと考える専門家は多くいる。聴覚性フラッシュバックはその症状のひとつとみることもできる。
・自閉スペクトラム症の人に多い過敏症に対しては、特定の薬の少量使用が有効だという。原田医師は、「過敏症は脳の神経の問題なので、適切に使えば薬は有効です。・・・カウンセリングや認知行動療法をいくら受けても知性では処理できません。薬を使わなければ過敏さは取れないのです。この場合、抗精神病薬エピリファイが効きます。ほぼ一択で、量は3ミリまでしか使いません。・・・ところが、使い方を間違っている医者が多くて、12ミリとか24ミリとか入れていることもあります。副作用が出るからダメです。4ミリや5ミリになると、じっとしていられずに動き回るアカンジア(静座不能症)が出ます」と言う。
・子どもへエピリファイの処方をすることで、子どもが失敗を経て学び、成長する機会を摘み取ることにはならないのか?「自閉スペクトラム症が濃い目の子どもは、なぜ自分が怒られているのか理解できないので失敗から学べません。例えば、癇癪を起こした子どもがAちゃんを叩き、叩き返されると、こういう子どもはAちゃんが叩いたと騒ぎます。自分が最初に叩いたからAちゃんが怒って叩き返したという流れを理解できないのです。・・・トラブルを減らすには薬が有効です。子どもの場合は特に量を少なくして、止めることも視野に入れた使い方をしていきます」
第3章 統合失調症「開かれた対話の劇的効果」(斉藤環)
・精神科専門医たちが「一生治らない」「生涯服薬」と決めつけたがる統合失調症(苦しい幻聴や妄想などが続いて生活に支障が出る精神障害)が、丁寧な対話の繰り返しで治るケースが次々と報告されている。統合失調症などの精神症状を、対話の力で消失(寛解)させたり、治癒させたりするこの手法は、フィンランドで生まれた「オープンダイアローグ」(開かれた対話)と呼ばれている。
・オープンダイアローグは例えば次のように進められる。急激に悪化した幻聴や妄想に苦しみ、混乱の只中にある急性期の患者の家に、オープンダイアローグの治療チーム(心理士、看護師、ソーシャルワーカー、精神科医の2人か3人で構成)は24時間以内に駆けつける。そして、家族、友人、会社の同僚らを交えたオープンな対話を、ほぼ毎日60分から90分程度、最大2週間を目途に繰りかえしていく。この対話の最中に治療チームのメンバー同士が、患者の話を聞いてこころを動かされたことや、浮かんできたイメージ、アイデアなどを話し合い、それを患者が間近で聞く機会(リフレクティング)も設ける。こうした「開かれた対話」から生まれる相互作用によって、患者の症状は短期間で劇的に改善していく。
第4章 うつ病・不安症「砂粒を真珠に変える力」(大野裕)
・「アントニオ猪木さんがよく、『元気があれば何でもできる』と言っていました。でも、認知行動療法では逆の見方をします。『元気があるからやれる』のではなく、『やるから元気が出る』のだと。元気が出るまで待っていては、いつまでも元気が出ないかもしれません。興味を持ったことは、考え過ぎずにやってみる。すると、やっているうちにどんどん面白くなって、元気が湧いてきます」
・「考え方を整理する、現実をみる、行動を変える、気分転換をする、日記をつける、などの認知行動療法で使うスキルは、私たちの日常の知恵とあまり変わりません。・・・10年以上前に私費で立ち上げたのが、幅広い層を対象にしたWebサイト『認知行動療法活用サイト~こころのスキルアップトレーニング』です。」このサイトは年会費1500円(税別)で、認知行動療法の考え方や基礎を実践的に学べる。
・大野医師はさらに、進化するAI技術を活用したチャットボット開発にも取り組んでいる。筆者は無料公開版(2023年夏時点)を試した。チャット画面に進むと、「今回はどんなことをしてみたいか、教えてもらえますか?」の質問と共に、解答につき3つの選択肢が示され、一つを選んで進んでいく。こうした対話を進めていくと、5秒間の深呼吸の提案などの”気遣い”もあり、視野を広げるコツなどをリラックスした状態で学べる。ーーーウェブ検索したら「こころコンディショナー」というサイトが見つかった。
第5章 ひきこもり「病的から新たなライフスタイルへ」(加藤隆弘)
・加藤医師が始めた家族向け支援プログラムが成果をあげている。「ひきこもり研究ラボ@九州大学」のWebサイトで学ぶことができる。肝になるのが「声かけ」の方法を身につけることである。「親御さんはどうしても、『みんなはもう働いている』『先のことを考えなさい』などと否定的なことを言ってしまいがちです。そこで私たちの家族教室では、肯定的なコミュニケーションを学びます。『私を主語にして話す』『具体的に話す』『自分の感情に名前をつける』などの練習をおこないます。『みんな』ではなく、『私』を主語にすると、言葉が柔らかくなります。・・・『(私が)心配だ』という気持ちを伝えるようにします。こうした言葉かけのちょっとした変化で、ひきこもりの人の様子は柔らかくなります」
・「ひきこもりは病的なものだけでなく、ライフスタイルのひとつでもあると私は考えています。小説家、研究者、ネットトレーダー、修行僧など、ひきこもらないとできない仕事はたくさんあります」「病的ひきこもりの支援でも、大事なのはポジティブな面にまず目を向けることです。物理的にひきこもらざるをえない心境に共感を示し、心の中に安心してひきこもれる場所を作ってあげることが治療の要です」
・(コラム・田邊友也)精神病院では、負の連鎖が頻繫に起こっている。田邊氏によると「精神疾患を発症する人の多くは、過去に深刻なトラウマ体験があります。その人たちを強制入院させて雑な扱いをすると、トラウマ体験の再演となるので情動がますます乱れていきます。大抵の医師や看護師は、これを病状の悪化だと単純に捉えるので、薬を更に増やしたり、隔離や身体拘束をしたりして、患者さんをますます追い込んでいきます」
第6章 自殺「なぜ自ら死を選ぶのか」(張賢徳)
・(コラム・樋口輝彦、野村総一郎)国立精神・神経医療研究センターの理事長・総長を長く務めた精神科医の樋口輝彦氏は、防衛医科大学校病院院長などを務めた精神科医の野村総一郎氏らと共に、東京・四谷に六番町メンタルクリニックを2015年に開設した。他にも経験豊富な精神科医が多数在籍し、外来を担当している。精神科は診療報酬が低く、精神科医が患者の話に15分、20分と耳を傾けても報酬は増えない。5分以上、30分未満の精神保健指定医診察は一律3300円と決められているからだ。このため、外来診療は5分程度の短時間面接が普通なのだが、六番町メンタルクリニックでは、必要に応じて医師に話をしっかり聞いてもらえる。野村氏は語る。「病院で時間に追われていた頃に比べると、薬を使う患者さんの割合がだいぶ減りました。精神疾患には生物学的な要素があるので、薬を否定しているわけではなく、むしろ私は薬を積極的に使う方です。それでも、面接時間が長くなると患者さんの回復度が上がり、薬が減っていくのです。今、私の外来で薬を使っている患者さんは3割くらいです」
・樋口氏によると、「日本の精神科医療は非常に低い医療費で行われており、それゆえの困難な現実に直面してきました。長らく精神科特例というものがあって、医師1人が入院患者さん48人を担当するという、現実にはありえない状況に置かれてきたのです。これに対して一般診療科では、例えば内科では16人に1人、というふうに精神科とは全然違います。それに伴って、診療報酬も精神科は一般診療科の半分以下や3分の1に抑えられています」
第7章 入院医療「新時代を切り拓く民間病院」(堀川公平、渡邉博幸)
・堀川医師は、久留米市内の精神科病院「野添病院」を買い取って、1994年に理事長に就任した。この病院も長期入院の患者が大半を占め、理事長就任時の平均在院日数は2156日、入院期間の平均は12年半にも及んでいた。患者を社会復帰に導く意欲に乏しいスタッフばかりだったが、妻で精神科医の百合子さんとの二人三脚で、すぐに改革に着手した。「日本の精神科病院は社会に認知されていません。こっそり隠れていることで、はじめて存在が許されている。だからスタッフの自己評価が低く、その結果、病院自体が病気になっていると感じたのです。病院から治さなければ、入院している患者さんを治せるはずがない」「まず、組織や体制、経営面などを抜本的に見直しました。その上でスタッフたちに、『社会で傷つき、こころを病んだ人たちは安心して過ごせる場所を求めている。快適な入院環境と良好な人間関係の提供が我々の役目』という意識を植え付けていきました」