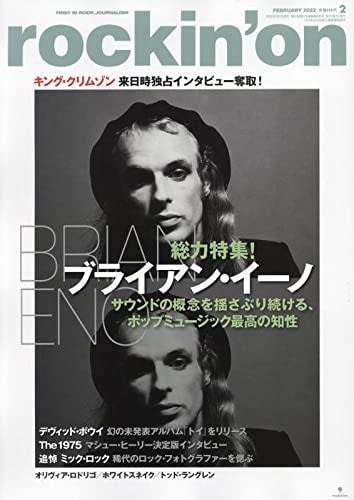一目見て買ってしまった。今までこんな本はなかった。ロックを、進化心理学、人類学・霊長類学、心理学、哲学などにおける、最近の学説や理論を元に分析している。そして読んでみたら、ロックを代表例として(ネタとして)、現代の社会や文化をより科学的な思考法で解釈してみようと試みている本であることがわかった。様々な学説や理論が出てくるが、書きぶりはとてもわかりやすく、著者の引き出しの深さ、知識の豊富さにも感心した。また、著者が専門のロック評論家ではないということも、本書がマニアックなロック本ではなく、ロックを外から客観的に評論したものになっている理由だろう。最後に付いている「参考文献という名のブックガイド」で紹介されている本のリストは充実しており、本書が多くの文献からの知識を元に書かれていることがわかるし、今後読むべき本の参考にもなる。
あまり気張らずに一気に読んで、楽しめる本でもあった。いくつか、気になったポイントを書き留めておきたい。
・チンパンジーにバントフートという行動がある。「フー、ホー、フーホー、フーキー、フーホー、ホワーォ、ホォォォ」という鳴き声をあげながらコミュニケーションするのだ。目の前にいる仲間チンパンジーのバントフートの発声に合わせて、自分もバントフートをかぶせていく。バントフートにはドラミングが伴うことも多い。これは手で自分の体や、すぐ側にある木なんかをリズミカルに叩くのだ。我々ホモ・サピエンスが音楽の演奏に合わせて手拍子を叩いたりするのに似ている。霊長類の脳と認知の専門家であるディーン・フォークはチンパンジーやゴリラのバントフートに、音楽の原型があるのではないかと考えている。人間が歌を歌うのも、チンパンジーやゴリラのバントフートも、仲間と集まって皆で我を忘れてノリノリになるという点が重要だと著者は指摘する。
・戦争などの過去の悪い出来事を、長い時間が経った後で批判するのは簡単なのだが、その時その時で批判するのはかなり難しい。客観視、メタ的な認知は人間の叡智だが、オンタイムでそれを行うのはかなり難しいのである。
・互恵的利他主義というのがある。近所のおばさんとかクラスメイトに親切にするなど、同じ共同体の仲間に親切にしておくと、いずれ自分が困ったときに彼らが助けてくれるというものだ。しかし、我々は見ず知らずの他人にも親切にする。このヒトの互恵的な性質について、最近、オランダの進化心理学者であるマルク・ファン・フフトという人が競争的利他主義という仮説を唱えている。我々ヒトは赤の他人に親切にすることを競い合っているというのだ。この仮説によると、困っている人がいたとして、その人を誰が助けるかというレースをしているということになる。我々は、善人であることすらも競い合う動物なのだ。私は親切な貴方よりも、より一層親切なんですよ、というマウンティングでもって親切心を競い合うのだ。
・ロナルド・ノエとピーター・ハマースタインは、生物学的市場理論(バイオロジカルマーケット)という概念を提唱している。生物学に経済学の考え方を導入したようなものだ。例えば、ドクターフィッシュの入った水槽に足を突っ込むと、寄ってきたドクターフィッシュが足の垢を食べてくれる。我々は垢が取れて気持ち良いし、魚の方はご飯が食べられるわけでウィンウィンである。これは、経済学的なやりとりである、というのが生物学的市場理論である。クマノミとイソギンチャクの共生もこれと同じで、自然界にはこういった例が数多く存在する。我々は市場経済をヒトが発明したように考えがちだが、少なくとも市場経済の土台、プロトタイプと考えて良いような経済的な行動は、ホモ・サピエンスが誕生する遥か以前から自然界にあったのである。
・ヒトは長い時間をかけて道徳を進化させてきた。だから、百年、二百年といった単位で帝国主義がじわじわと衰退していった。しかし、ロシア革命、共産主義革命といったものは、帝国そっくりの独裁体制を生んでしまった。アメリカも物騒な国家ではあったが、少なくとも独裁者が統治するような仕組みを作らずに済んだようである。ポイントは制度である。制度設計が成功しているか否かである。ロシア革命も壮大な社会実験だったし、アメリカの独立も壮大な社会実験だった。そして、ソヴィエト連邦や中国のような国においては、結局は独裁主義になってしまった。これは制度設計が失敗しているのだ。アメリカという国家が今も多くの問題を抱えているのは事実であるが、それでも今のロシアや中国よりはマシなのである。
・ヒトの互恵的利他主義から来る共産主義を求める思考は、赤ちゃんの頃から公平さを求めるヒトの本能に結びついてるわけだが、バイオロジカルマーケット理論の視点から見ると、市場経済によって成立する資本主義もまたヒトの本能と結びついている。だとしたら、共産主義か資本主義か?といった二択を問題視したのは、歴史的なミス、というか認識論的な誤謬だったのではないだろうか。人類は馬鹿なようでいて賢い動物なので、妥協とか適当なところで手を打つという選択肢がある。我々は妥協という言葉をあまり良くないニュアンスで使うことが多いが、妥協こそヒトの叡智なのだ。たとえば過去には、固有資産や市場経済を否定しない社会主義というものも考えられたことがあったのである。そして今はベーシックインカムが注目されている。色んなアイデアをかき集めて、いいとこ取りするのが最善の道なのだ。
・本書のテーマである、ロックの正体とは何か?ロックの誕生は、そもそも言葉や音楽といった文化を奪われて歴史を切断された黒人奴隷の音楽を、10代の白人が物真似したことに始まる。それは、黒人奴隷にとってはゼロからのスタートだったために、人類の歴史の、大きな転換期に起きた出来事をもう一度再現するような出来事であった。物真似から初めて、未来を創造する行為、それこそがロックの正体である。それを著者は、広域スペクトル革命の文化的な再現と呼んでいる。
・ロックの未来がどうなるかは、おそらく誰にもわからない。60年代的な意味の反逆のロックはとうに終わったし、70年代的なロックも蕩尽の果てに終わったが、ローリング・ストーンズは今も「サティスファクション」を演奏している。「サティスファクション」の歌詞に込められた反逆のロック的な理念は、形骸化することで歴史になったのだ。ミックがお爺さんになった今も歌い続けているのは、歴史を歴史として表象するためである。何事であれ歴史として記録することはヒトの叡智なのだ。本当に色々あったけれども、ロックを愛する人たちが老人になることで、この文化はようやく完成したのである。
・最後に付いているブックガイドが充実している。本書を構成する16章全てに参考文献が割り付けられている。とくに気になったのは、ヒトの脳の使い方について考えを改め、より良い頭の使い方を知りたい人のために以下の4冊をお勧めするーと推薦されているのが、「ダニエル・C・デネット/思考の技法ー直観ポンプと77の思考術」「ヤン・エルスター/社会科学の道具箱ー合理的選択理論入門」「戸田山和久/思考の教室ーじょうずに考えるレッスン」「植原亮/思考力改善ドリルー批判的思考から科学的思考へ」である。60年代のカウンターカルチャーは躓いてしまったが、大勢の若者がサルトルと共に間違えるよりも、多くの人びとが科学的思考を身につけた方が社会はより良い方向に進むのだと著者は述べている。