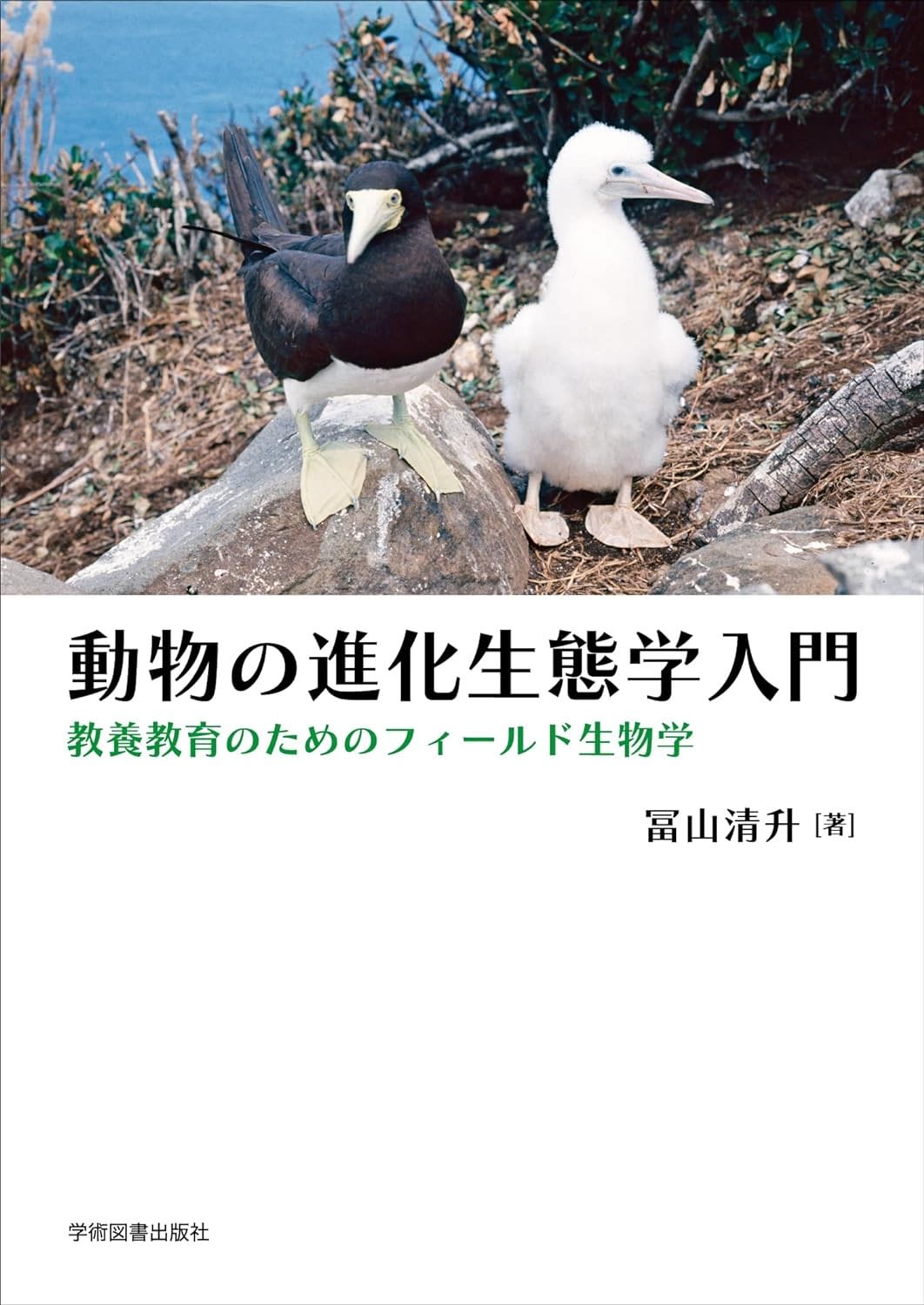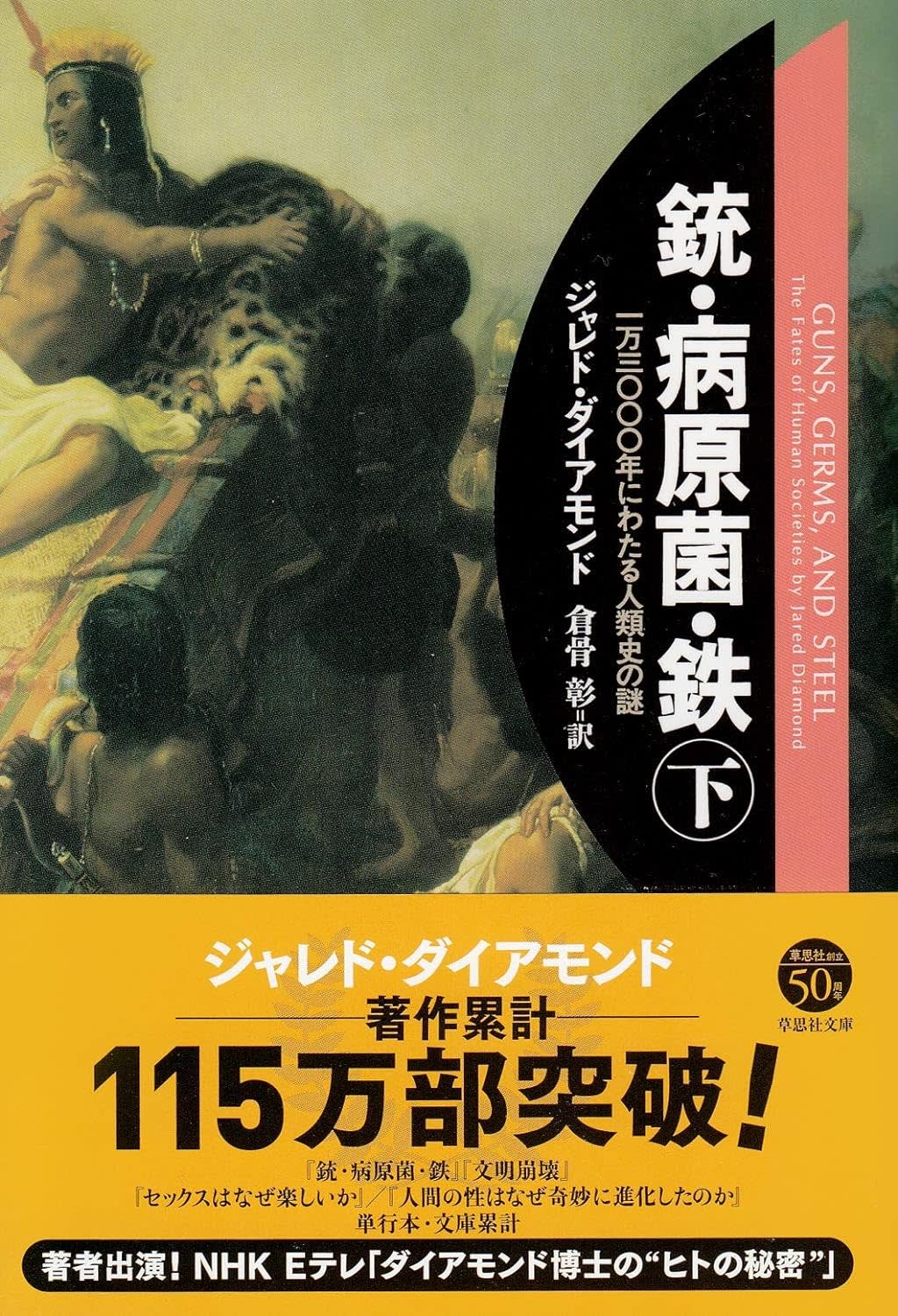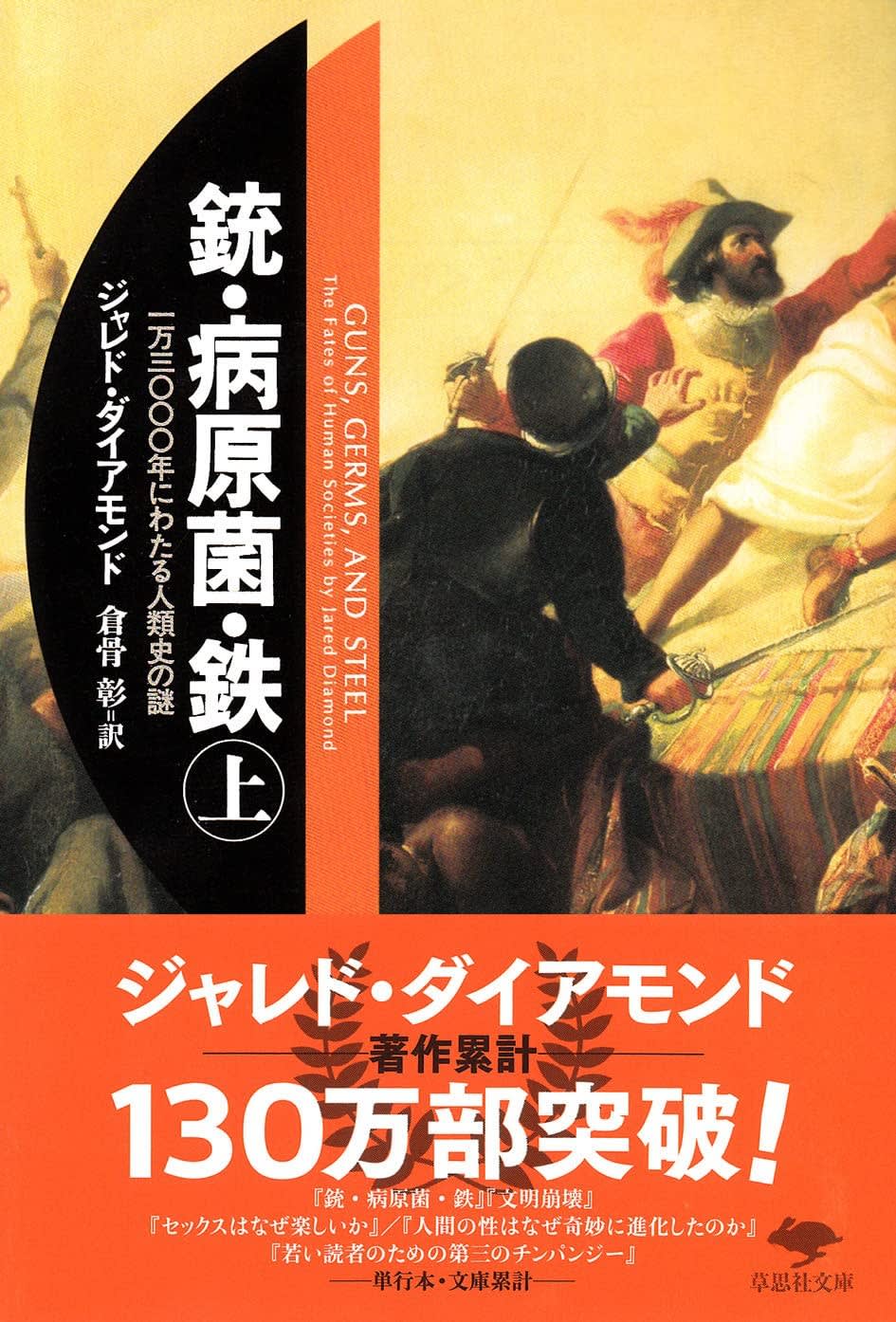生物の進化は、系統樹で表されるようにどんどん枝分かれして多様性が拡大していくが、本書では、現生人類(ホモ・サピエンス)が脊椎動物初期の魚類からどのように進化してきたか、その一本道をていねいにたどって描いている。著者の専門である古生物学の知見を主としながら、分子進化学の知見も取り入れて、人類進化史の現在の知見の到達点をわかりやすく概説した好著である。本書では、人類に至るまでの道程において獲得してきた特徴を、70の道標として注目している。また、一本道を辿るうえで人類への道から「わかれた動物」にも注目している。このように、初期魚類から辿る人類史の見取り図(ガイド)として役立ちそうだ。
章ごとに気になったポイントを記録しておきたい。
【黎明の章】
・有羊膜類から竜弓類と単弓類が分かれた。竜弓類は爬虫類とその近縁のグループ、単弓類は哺乳類とその近縁のグループである。ひと昔前は、哺乳類は爬虫類から進化したことになっていたが、現在の理解では、どちらのグループもその根幹に近い段階で、袂を分かっていた。
【雌状の章】
・広い意味での哺乳類である「哺乳形類」は、その初期において、二生歯性(生涯に1度だけ歯が生えかわる特徴)、二次口蓋の形成(口腔と鼻腔の分離)とそれによる嗅覚の鋭敏化、耳の骨の複雑化とそれによる聴覚の発達などの特徴を獲得した。
・初期の哺乳形類として化石が見つかっているモルガヌコドンは、大きい眼窩を備えていた。そのことから眼球も大きかった可能性が高く、集光能力が高いことから、夜行性だったとの見方が有力だ。この三畳紀後期からジュラ紀中期は恐竜類が世界を支配していた。そんな世界で、小型ですばしっこいモルガヌコドンは、単弓類後の獣弓類、そして哺乳形類の命脈をしっかり残すことにつながった。
・哺乳形類を構成するグループの1つとして、「哺乳類」が登場したのは、ジュラ紀から白亜紀の”どこか”だ。耳の骨と下顎の骨が離れ、哺乳類が生まれた。ただし、初期の哺乳類の耳の骨と下顎の骨は完全には分かれておらず、「メッケル軟骨」という軟骨を介して、互いに接していた。そして、哺乳形類の中でも「単孔類」以降に登場したものたちが「哺乳類」と定義づけられている。
・2010年、ディーキン大学(オーストラリア)のクリストフ・M・ルフェーヴルたちが、子に乳を与える現生哺乳類の3グループー単孔類、有胎盤類、有袋類のミルク成分を分析し、ある種のタンパク質がこの3グループに共通していることを見出した。このことは、単孔類、有胎盤類、有袋類の共通祖先の段階で、そのタンパク質を含むミルクが獲得されていたことを示唆している。つまり、この時点で、乳腺が発達し、哺乳を開始していた可能性が高い。
・中生代にも胴長80センチメートルとやや大型で動物食の哺乳類、レベノマムスがいた。レベノマムスの化石の胃があったとみられる場所からは、植物食恐竜の幼体の化石が発見されている。また、植物食恐竜を襲ったその瞬間のポーズのまま、植物食恐竜とともに化石となった標本も報告された。中生代の哺乳類が「恐竜類から逃げるだけの存在」ではなかったことを物語っている。
・白亜紀後期の地層から発見されたフィリコミスは、「社会性をもつ哺乳類」として、知られている限り最も古い存在だ。フィリコミスは、亜成体数匹と成体数匹の化石が同じ場所で発見される。このことから、フィリコミスの例は、「異なる世代が集まった哺乳類集団」の最古の例であり、哺乳類の集団営巣の最古の例であり、哺乳類における地中の巣の最古の例であるという。
・白亜紀前期の地層から発見されたオリゴレステスという小型の哺乳類は、耳の骨と下顎の骨が完全に分かれていた。この骨の変化は単純に骨だけの変化に限定されるものではなく、筋肉も伴っていたという。すなわち、かつて、咀嚼に用いられていた筋肉が「中耳」と呼ばれる空間を作り出すことで、外から入ってくる音を減衰させ、蝸牛、前庭、三半規管といった重要器官の並ぶ「内耳」を保護する役割を担うことになったという。
【躍進の章】
・有胎盤類は、アフリカ獣類、異節類、ローラシア獣類へと分かれた。これらは、”理屈”上では(分子進化学ではという意味だろう)、白亜紀(中生代)までに”ヒトに至る系譜”(新主齧類のことだろう)と分かれていた可能性が高いとみられているが、決定的な証拠となる化石は発見されていない。
・オナガザル類が”ヒトに至る系譜”と分かれた。ともにアフリカ大陸を故郷とし、ユーラシア大陸へと拡散していった。オナガザル類の中には、現在まで子孫を残すグループ「コロブス類」がいる。彼らは生息域を広げていく中で、日本にも約300万年前に到達していた。神奈川県愛川町から「カナガワピテクス」というコロブス類の頭骨化石が報告されている。オナガザル類の中でもコロブス類とは別の系譜として進化を重ねた”狭い意味のオナガザル類”もある。マカクやヒヒなどが属している。現代日本で私たちとともに生きるニホンザルもこれに属している。
【人類の章】
・交雑することで、ホモ・サピエンスの中にはホモ・ネアンデルターレンシスやデニソワ人の遺伝子が残っている。デイヴィッド・ライクは著書「交雑する人類」の中で、ホモ・ネアンデルターレンシスから継承された遺伝子の中で、生殖能力に関する部分が自然選択によって強力に排除されていったことに言及している。そもそも動物全般に通じる現象として、本来、交雑で生まれた子孫は繁殖能力が低くなる。しかし、ホモ・サピエンスでは、そうはならなかった。篠田謙一の「人類の起源」の中で、ホモ・サピエンスがホモ・ネアンデルターレンシスやデニソワ人から継承しなかった”生殖に関する遺伝子”に注目し、「案外、私たちが残ったのは、単により子孫を残しやすかったためなのかもしれません」と綴っている。(様々な人類種が生まれた中でホモ・サピエンスだけが生き残った理由として、社会性や言語能力などが様々に議論されているが、これは興味深い視点だと思った)