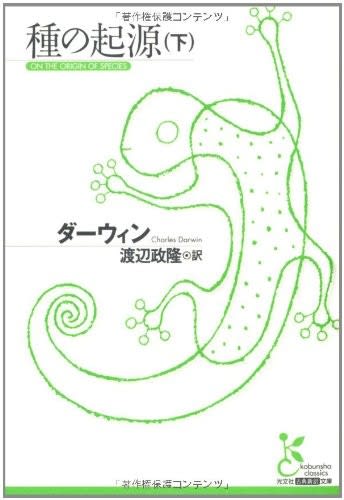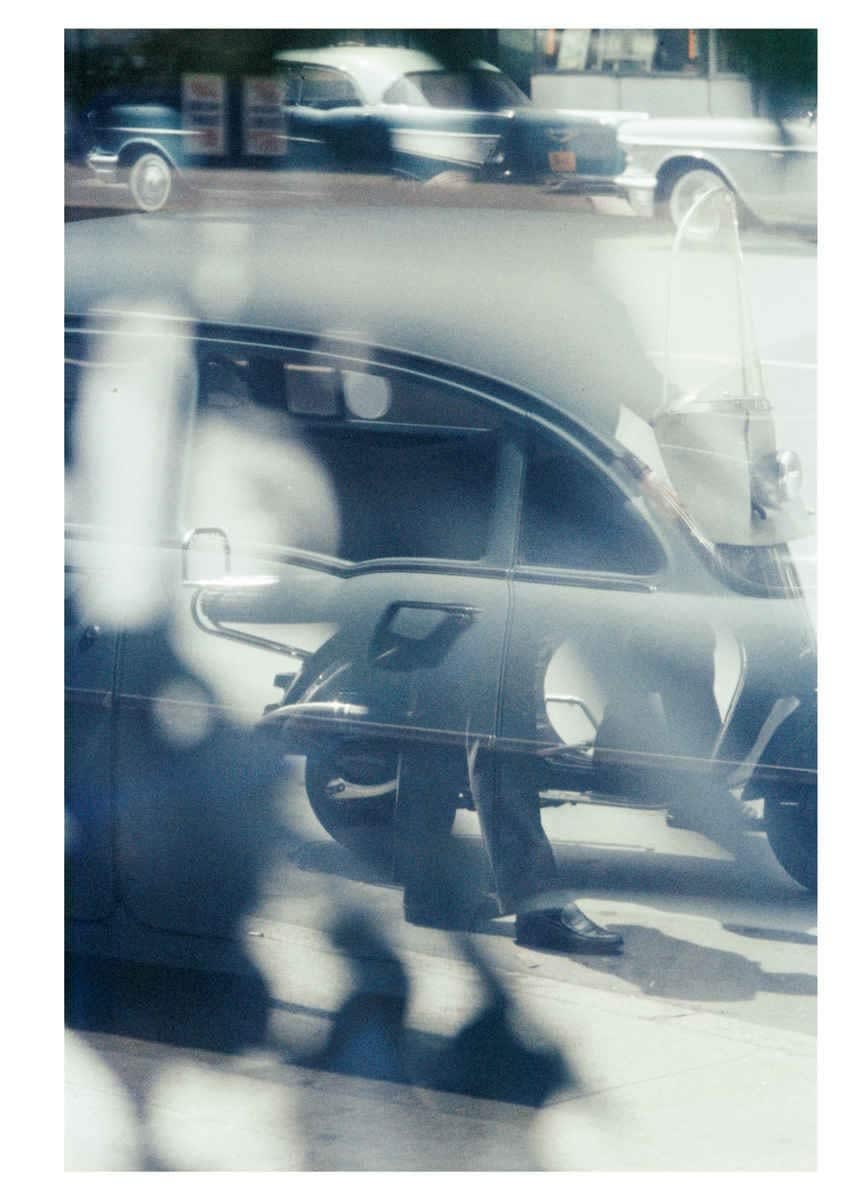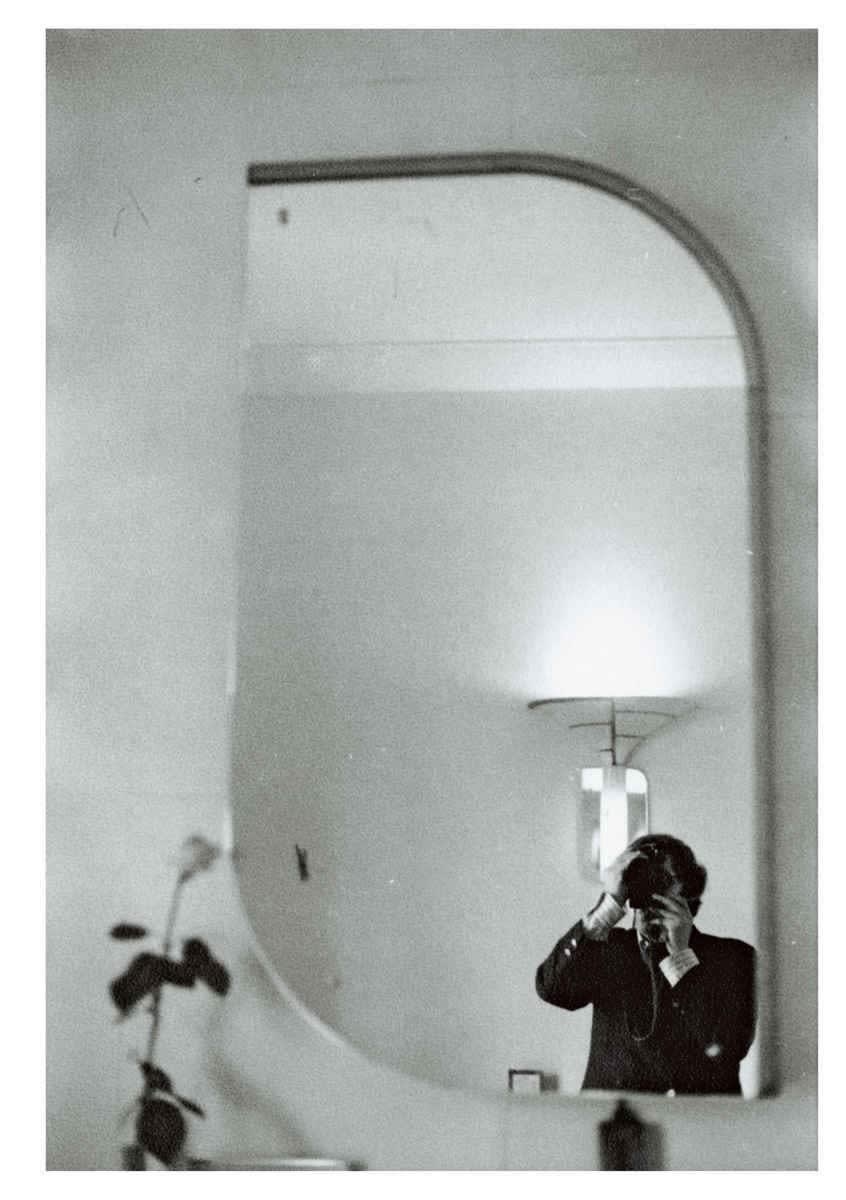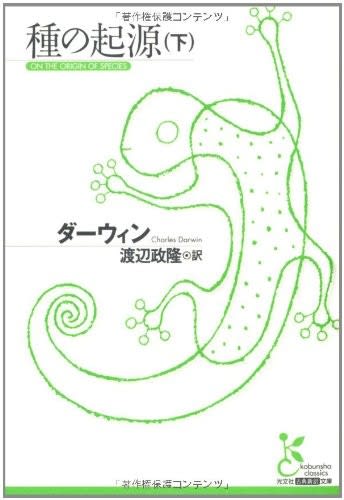
「種の起源」下巻では、地質学(化石)における進化の証拠の不完全さについて延々と議論していく。化石が残るかどうかは、地殻の上昇・下降など様々な自然の要因に影響を受けている。したがって、化石が連続的な進化の様相を示していないからといって、ある種から変種が生まれ、さらに新たな種へと変化していくという連続的な進化は起きていないと結論付けるのは無理があると主張している。そして下に示すように、現代の生物学の課題となっているような現象への気づきがすでにあったのは驚きである。
「すでに優勢な立場にある種類、あるいはその生息地で他の種類よりも何がしかの利点をそなえている種類からは、当然のごとく新しい変種、すなわち発端種がいちばん出現しやすい。(p.145)」と述べる。個体数が多ければ、それだけ遺伝子変異のバリエーションも多くなるので変種が生まれやすくなるという、現代でも通じるような考え方をしている。
生物種が一部地域に限定されて分布しているように見えても、実は広い地域で普遍的に分布していることを考察している。「有袋類は主にオーストラリアだけの種類であるとか、...という言い方もできない。なぜなら古代のヨーロッパにもたくさんの有袋類がいたことがわかっているからだ。(p.169)」私は初めて知ったのだが、有袋類はオーストラリアで独自の進化を遂げたのではなく、多くの地で絶滅しオーストラリアでのみ生き残った種類だということになる。
「そこのすむ生物にとっていちばん重要な要因は土地の物理的環境であるという見方こそが、根の深い誤解なのだ。実際には、成功を収める上でそれと少なくとも同じくらい重要な要因は、競争相手となる他の生物であり、一般には疑問の余地なくこの要因のほうがはるかに重要であると、私は確信している。(p.265)」と述べ、その種が繁栄できるかどうかは、物理的環境以上に競争相手となる他の生物がいるかどうかの影響が大きいと主張している。有袋類がオーストラリアでのみ生き延びることができたのは、そこに競争相手がいなかったからだということになる。
「生物の地理的分布をめぐる主要な事実は、移住(一般にはかなり優勢な生物種の移住)とそれに続く変化、そしてその後の新種の形成という説で説明がつくと思われる。(p.276-277)」とし、その場所で新種が形成された後に移住するという順番ではないとしている。
「コウモリの翼と脚はまったく異なる目的に使用されているのに、それぞれの構造を支えるためになぜ同じ骨が創造されねばならなかったのだろう。たくさんの部品で構成されたきわめて複雑な口器をもつ甲殻類は、結果として必ず肢の数が少ないのに対し、たくさんの肢をもつ甲殻類の口器は、逆に単純な構造をしている。これはなぜなのだろう。個々の花の萼、花弁、雄しべ、雌しべは、それぞれひどく異なる目的に適合しているのに、すべて同じパターンで構築されている。なぜなのだろう。(p.323)」近年になって、ホメオティック遺伝子のはたらき(後述)として説明できるようになった現象に対する問題意識がすでにあった。
最後のほうで、「遠い将来を見通すと、さらにはるかに重要な研究分野が開けているのが見える。心理学は新たな基盤の上に築かれることになるだろう。それは、個々の心理的能力や可能性は少しずつ必然的に獲得されたとされる基盤である。やがて人間の起源とその歴史についても光が当てられることだろう。(p.401)」と述べ、現代の進化心理学などの隆盛も予想していたかのようだ。
訳者の渡辺正隆氏による巻末の解説において、ダーウィン以後の進化学の流れが簡潔にまとめられていたので、そこを読むだけでもとても勉強になった。備忘録として下記にまとめておく。
・1859年の「種の起源」の後、1866年にオーストリアのグレゴール・メンデルがメンデルの遺伝の法則を発表した。1900年にこの法則が再発見されたとき、遺伝形質は離散的であるとの認識が広まり、小刻みに少しずつ連続的に作用する自然淘汰はさして有効でないと考えられるようになった。
・1930年代に集団遺伝学が隆興し、生物集団中に生じた遺伝的変異が集団中に広まって定着していく過程において、自然淘汰が大きな役割を演じうることを数学的に証明した。これにより、メンデル遺伝学と自然淘汰説との融合が成立した。そうした理論的予測は、ショウジョウバエなどの実際の生物集団を用いた実証的研究によっても裏付けられていった。
・1940年代に、分類学、体系学、古生物学、生態学などの最新の成果が持ち寄られ、自然淘汰説を中心に進化の総合学説として体系化された。一方で、発生学者の進化生物学離れが起きていた。
・1960年代に分子生物学が興隆したが、当初は進化生物学の進展には結びつかなかった。しかし、1968年に木村資生が中立説を発表し、タンパク質レベルでの変異の多くは中立であり、自然淘汰の網の目にかからないとした。中立的な分子の置換は時計のようにほぼ一定の速度で起こると想定する分子時計という概念も導入された。この後、分子進化の研究は一気に加速した。また、大野乾は遺伝子重複による進化説を提唱した。中立説も重複説も、自然淘汰とは無関係に起こる進化の仕組みであるが、そうやって生じた新しい遺伝子がいったん有利になれば、そこからは自然淘汰の出番となる。
・1980年代半ばに発生生物学において、脚、触覚、体節の発達を制御するホメオティック遺伝子群の存在が明らかとなった。その遺伝子群には、ホメオボックスという共通の配列の領域が含まれ、それはほぼすべての動物群や植物などにも存在し、それを調節する遺伝子がはたらく場所やタイミングを変更することで多様な身体づくりがなされることがわかってきた。そうして、発生生物学および分子生物学から進化学へのアプローチが可能となり、進化発生生物学(Evolutionary Developmental Biology)、略してエボデボが誕生し急速に進展している。そうした既存の遺伝子の使い回しで多様性を増大させていることを、遺伝子のブリコラージュ(間に合わせの器用仕事)と言うことができる。
・1960年代半ばに動物行動学によって提唱された包括適応度という考え方を基盤とする血縁淘汰説によって、社会性昆虫のワーカー個体の利他行動の進化が、自然淘汰説と矛盾することなく説明できるようになった。これを機に、1970年代初めには、動物行動学、動物社会学などの各分野が統合されて社会生物学あるいは行動生態学と呼ばれる分野が誕生し、動物の適応的行動に関する研究が加速された。リチャード・ドーキンスによる利己的遺伝子もその一環だった。また、血縁関係のない個体間での互恵的な利他行動などはゲーム理論を適応して説明されるようになった。動物の行動は自然淘汰が進化させた適応形質であるとのアプローチは、現在、心理学、言語学、人類学、医学などの分野にも援用されつつある。
・生態学では、1950年代以降、自然淘汰の有効性を生態学的に研究する進化生態学が盛んになった。さらに、理論生態学、カオス理論や複雑系としての解析などの動きも出てきた。
・古生物学では、1970年代に、スティーヴン・ジェイ・グールドとナイルズ・エルドリッジによる断続平衡説の提唱により、進化の進み方は漸進的か断続的をめぐる論争が勃発した。現在では、隕石衝突のような外的な要因による突発的で大規模な絶滅と進化が起こることと、そうした激変が収まると再び自然淘汰の出番が回ってくることという、両面で理解されているようだ。



 池の北から南を見る。
池の北から南を見る。 池の南から北を見る。
池の南から北を見る。