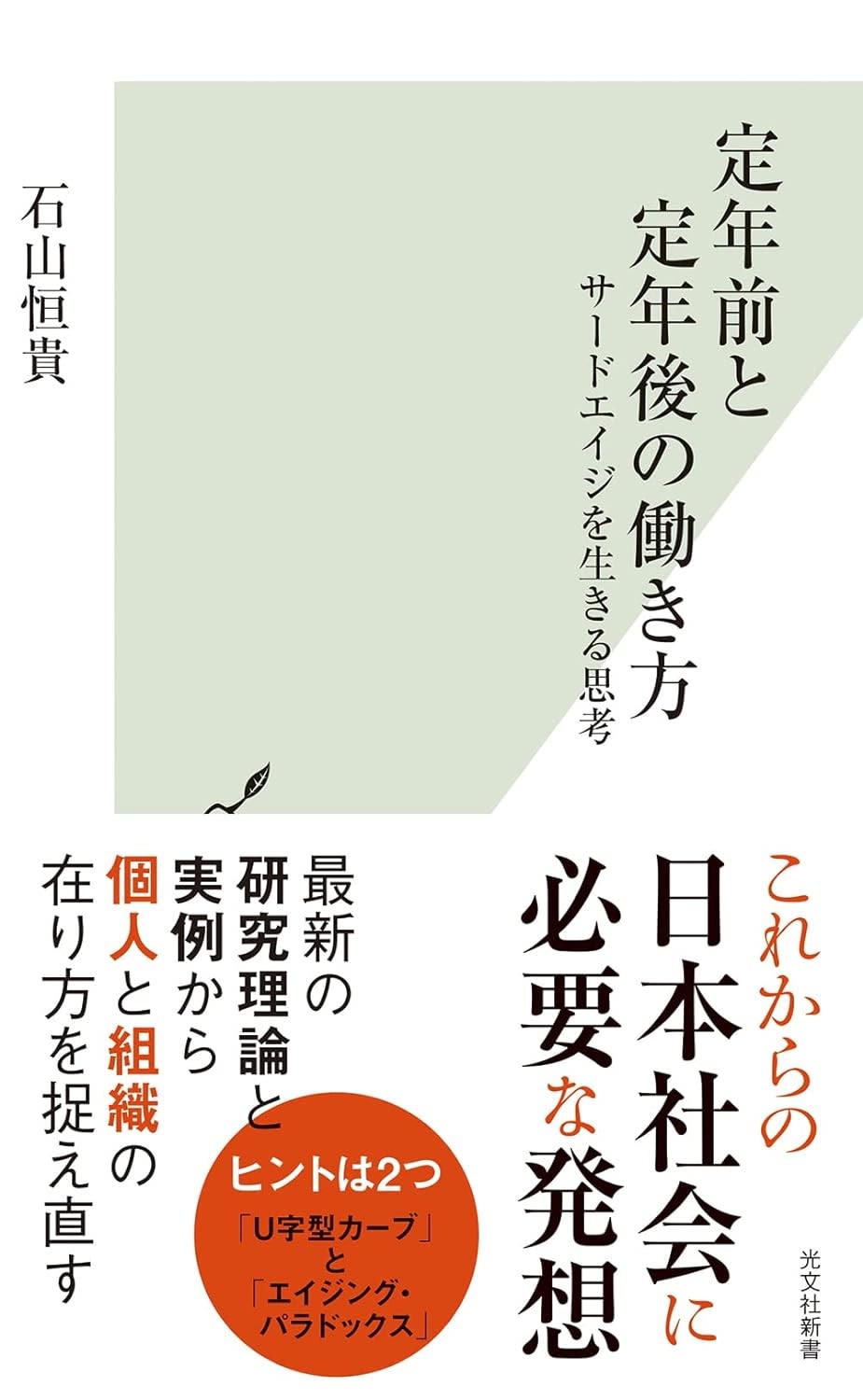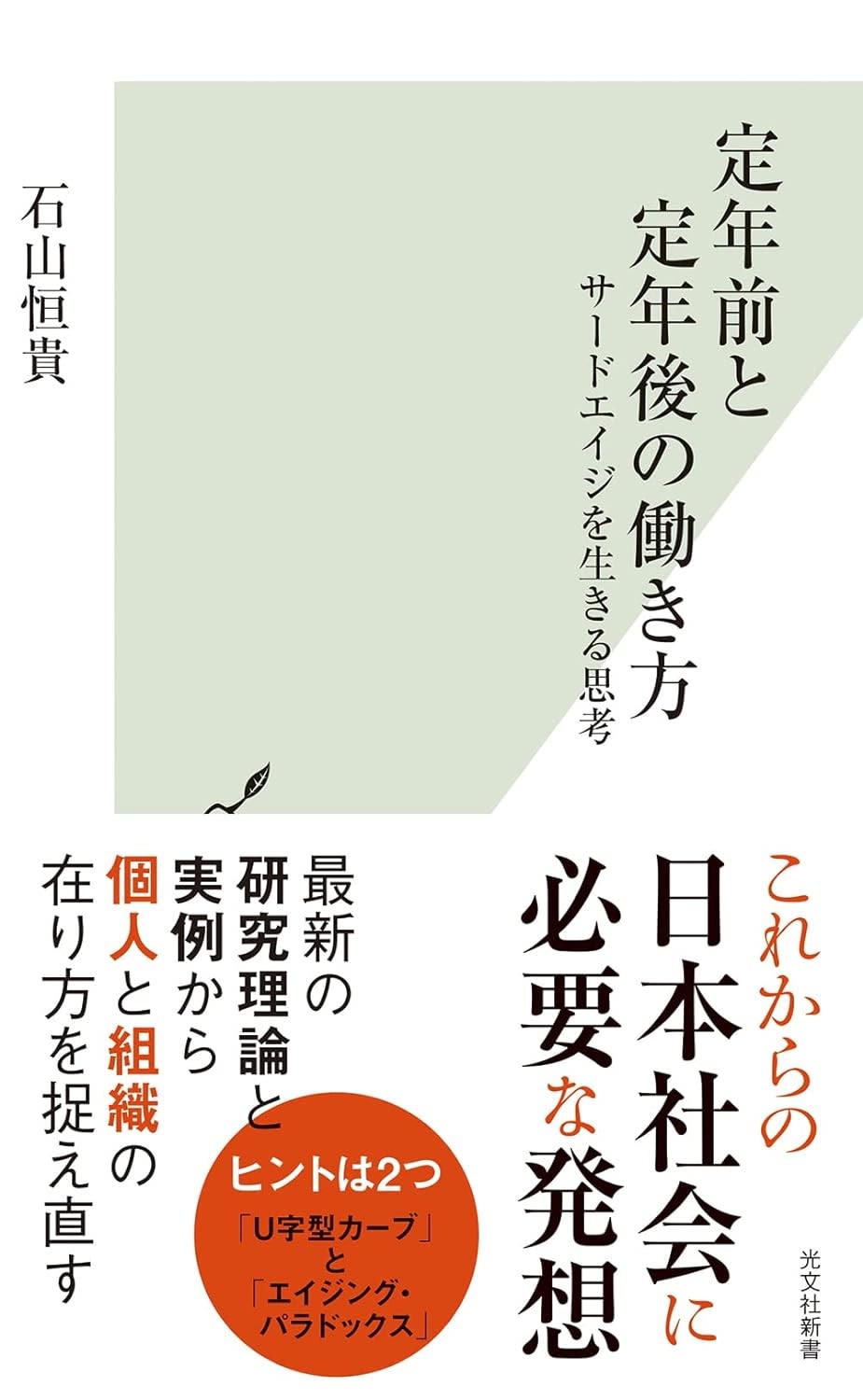
私は、今年の9月に60歳で定年退職になり、10月からは同じ会社で再雇用によるエキスパート社員として働いている。このような働き方が最善なのかどうかはわからない。収入の面と自らのスキルの活用という面では、ある程度理にかなった働き方だとは思うが、定年後に他にどんな働き方があるのか知りたいと思い本書を読んでみた。
本書の章の構成と、私なりに気になった点を下記に記したい。一つの組織内での働き方を提案している第3・4・5章より、より多様な形態での働き方を提案している第6章以降がおもしろかった。
第1章 シニアへの見方を変えるーエイジズムの罠
・これまでの日本の実態では、50代以降のシニアの働き方を補助的なものとしか考えていなかった。それを象徴する言葉が「福祉的雇用」である。企業はシニアが職場の戦力として中核になるとは、さらさら考えていない。しかし、社会的責任としてシニアを雇用する必要がある。そこで、本当は職場でさほど必要とされていない業務を作り出し、しぶしぶシニアを雇用する。これが、これまでの福祉的雇用の意味だった。これからの日本社会では、一刻も早く福祉的雇用の考えを脱し、シニアを職場の中核と考える必要がある。結晶性知能も流動性知能も定年前後の60代では高く維持され、明確に低下していくのは80代以降だとする研究も示されている。定年年齢の60歳以降に急にシニアの能力が衰えるという見方は非現実的である。
第2章 幸福感のU字型カーブとエイジング・パラドックス
・幸福は、ハピネス(感情)、サティスファクション(生活評価)、ウェルビーイング、エウダイモニアという4つの言葉で使い分けられている。エウダイモニアとはアリストテレスが唱えた考え方であり、観照的生活を意味し、哲学者のためのような生活であり、善を目指して生きることなのだという。言い換えると、人生における意義や目的を考えながら生きるということになる。本書の結論は、エウダイモニアの実現こそが、シニアの働き方思考法なのである。
・幸福感は年齢にともなってU字型カーブを描く。つまり、シニアから加齢にともない幸福感が高まっていく。シニアになり加齢していくと、様々な喪失や衰えがあるはずなのに、幸福感が高まっていくことは矛盾(パラドックス)と受け取れるので、エイジング・パラドックスと呼ばれる。エイジング・パラドックスを説明する様々な理論の中に、シニアの幸福感を高める働き方思考法を実現するヒントがあると考えられる。
第3章 エイジング・パラドックスの理論をヒントに働き方思考法を考える
(SSTとSOT理論の説明があるが省略)
第4章 主体的な職務開発のための考え方ージョブ・クラフティング
(ジョブ・クラフティングの説明があるが省略)
第5章 組織側のシニアへの取り組み
(組織からシニアへの権限移譲の大切さの説明があるが省略)
第6章 シニア労働者の働き方の選択肢
・シニアが何をしたいかという選択は、個人が自由に行えばいいと考える。何もしないという選択肢ももちろんある。
・定年後の仕事のあり方には、現職継続、転職、起業の他に、時間や場所に縛られない柔軟な就業形態であるフリーランスという選択肢が付け加わる。
・さらに、モザイクという考えを選択肢に加えることができる。現役世代は、家計を支える観点からも、フルタイム労働でしっかり収入を確保したいというニーズが強い。しかしシニアには、働きたい時間、働きたい場所だけで働くというニーズもある。そこで各人の就労をモザイク的に組み合わせ、それによって複数人でひとり分のフルタイム就労に相当する仕事に対応するという発想である。
・モザイク型就労が進んでいくと、フルタイムで働く従来型の現職継続、転職、起業、フリーランスにくわえて、モザイク型の現職継続、転職、起業、フリーランスという選択肢が誕生する。たとえば、現職継続の場合、定年再雇用の際には、週5日ではなく、週2~3日だけ働く、午前だけ働く、といういうようなモザイク型現職継続が可能は企業はすでにある。そうなると、もっと選択肢は増える。モザイクの組み合わせである。モザイク型現職継続+モザイク型フリーランス、モザイク型転職+モザイク型フリーランスなどの組み合わせだ。シニアの働き方の選択肢は、より多様化が進んでいくと思われる。
・フリーランスの区分の一つにギグワークがある。デジタル・プラットフォームを利用した単発の仕事がギグワークと呼ばれるようになった。リモート性や裁量性の高いギグワークとして、スキルシェアサービスがあり、スポットコンサルティング(ビザスクなど)、得意なスキルのシェア(ココナラなど)、講師スキルのシェア(ストアカなど)などがある。
・モザイク型フリーランスとして、オンライン・リモート副業がシニアの新しい選択肢になり得る。副業については「本業は雇用+副業も雇用」という組み合わせだけでなく、「本業は雇用+副業は業務委託契約(=フリーランス)」という組み合わせが一般的である。オンライン・リモート副業は大別すると、中堅・中小企業の経営者の相談相手となるメンター型と、一定の期間(たとえば3か月や半年)を目途に具体的に定めた目標をプロジェクト的に達成していくタスク型に区別できる。オンライン・リモート副業の普及を先駆的に推進してきた企業が、「JOINS」である。
第7章 シニアへの越境学習のススメ
・越境学習、つまりアウェイでの学習がシニアにとって有効だとしている。理由として、自分にとって意義ある目的が見つけやすくなること、多世代かつ多様な人々と対話をすることによって年齢・地位・役職の上下にこだわらないコミュニケーションができるようになること、葛藤を経験し自己調整できることの3つがあげられている。
・チャールズ・ハンディは、人生の役割として4つのワークを定義した。4つのワークとはそれぞれ、賃金を得るための活動である「有給ワーク」、家庭の様々な活動を行う「家庭ワーク」、社会や地域に貢献する「ギフトワーク」、多種多様な学習活動を行う「学習ワーク」である。越境学習におけるアウェイの場とは、この4つのワークの中で、自分がアウェイと感じられる場はすべからく該当する。
・シニアの越境学習の場の事例として、「はちおうじ志民塾」、「八王子市市民活動支援センター」、「川崎プロボノ部」が紹介されている。同様の組織は、それ以外の各地域にもあるのだろう。
第8章 サードエイジを幸福に生きる
・シニアの働き方にとっては「個人事業主マインド」が重要だという。個人事業主マインドとは、雇用されているか否かに拘わらず、個人事業主のような気持で働いていくことだ。そのためには収入は細く長く考える、働き方は組み合わせる、蓄積してきたスキル(専門性)を重視することが大事だという。
・そのようは働き方思考の醸成や専門性・スキルを棚卸するために、シニアがキャリアコンサルタントや教育機関を活用することも望ましい。筆者が関わってきた団体がいくつか紹介されている。「シニアセカンドキャリア推進協会」は、シニアのセカンドキャリアに関するセミナーや研修、勉強会を実施している。「ライフシフト社」は、80歳まで現役で活躍するために、シニアに様々な研修プログラムを提供している。「フリーランス協会」は、自分のキャリアを自律的に歩みたいと考える全ての人のためのインフラとコミュニティづくりを目指す団体である。「インディペンデント・コントラクター協会」は、インディペンデント・コントラクターと呼ばれる専門性の高い期限付きの業務を請負契約によって働く人々の場づくりの団体である。