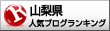昨日Facebookのアカウントを作りました。
初めてログインして、こんなにたくさんの人が実名で登録していることに驚きました。
匿名性の高いツイッターが、個人のつぶやきを大勢のフォロワーが追いかける構造だとしたら、Facebookは明らかに個人同士の交流の場の提供です。
ただし、その見知らぬ個人同士が「友達」になっていく過程は、既存の友人関係が取っ掛かりになっているのだと強く感じました。
というわけでリアルな友人の少ない私としては、写真か日記(Facebookの世界では“ノート”といいます)をアップして、誰か知人がアクセスしてくれるのを気長に待つしかないわけですが...。
写真はともかく、日記についてはブログで書いたことをまたFacebookに書き直すのも面倒だし、ということで両者を連携させる方法を調べてみました。
探した結果、ネットに掲載されていたのは主に3つ。
1.“ノート”に自分のブログ記事を「インポート」する方法
2.アプリ「My Blog Posts」を使ってFacebook側のニュースフィードにブログ記事を自動で取り込む方法
3.「Share on Facebook」というボタンをブラウザに付けて、表示したブログ記事を掲示板に書き込む方法
しばらく様子を見ながら、対応を考えたいと思います。
初めてログインして、こんなにたくさんの人が実名で登録していることに驚きました。
匿名性の高いツイッターが、個人のつぶやきを大勢のフォロワーが追いかける構造だとしたら、Facebookは明らかに個人同士の交流の場の提供です。
ただし、その見知らぬ個人同士が「友達」になっていく過程は、既存の友人関係が取っ掛かりになっているのだと強く感じました。
というわけでリアルな友人の少ない私としては、写真か日記(Facebookの世界では“ノート”といいます)をアップして、誰か知人がアクセスしてくれるのを気長に待つしかないわけですが...。
写真はともかく、日記についてはブログで書いたことをまたFacebookに書き直すのも面倒だし、ということで両者を連携させる方法を調べてみました。
探した結果、ネットに掲載されていたのは主に3つ。
1.“ノート”に自分のブログ記事を「インポート」する方法
- インポート作業そのものは簡単ではありますが、私が今日やってみた限りでは見出し画像がインポートできない(あくまでもテキストのみ)ことと、元のブログへのリンクが張られないことが難点です。Facebookとしては自分のユーザをブログ側に取られたくないのでしょう。
また、自動で更新できるという話でしたが、私のブログからは自動で更新できませんでした。
2.アプリ「My Blog Posts」を使ってFacebook側のニュースフィードにブログ記事を自動で取り込む方法
- この方法が一番スマートなのですが動作がいまひとつ不安定で、自動で更新できないばかりか手動でも思ったものとは違う生地を取り込んでしまったりして、今のところ使い物になりません。どうやら特定のブログとの間でだけ動作するのではないかと思えるフシがあります。ネットにも「使えねえ!」という書き込みがどっさり。
3.「Share on Facebook」というボタンをブラウザに付けて、表示したブログ記事を掲示板に書き込む方法
- 手動での取り込みではありますが操作も簡単でブログへのリンクも付くし、自分だけでなく他人の記事も同じように取り込むことができるので汎用性は高いです。見出し画像も取り込めました。
残念なのは、他の方法のように記事の導入部を表示する機能がなく、毎回ブログの紹介コメントが表示されてしまうことで、記事の内容をコメント欄に書かなければならない点でしょうか。
しばらく様子を見ながら、対応を考えたいと思います。