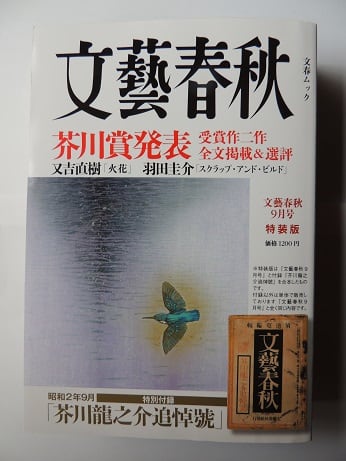私は東京郊外の調布市に住む年金生活の70歳の身であるが、
朝の6時半過ぎ洗面した後、庭のテラスに下り立ち、襟を正して黙祷した・・。
私は1944年〈昭和19年)9月に東京郊外で農家の三男坊として生を受け、
翌年の1945年〈昭和20年)8月15日に日本は連合国に降伏し、敗戦となった時、
一歳未満の乳児であったので、戦争を知らない世代のひとりである。
しかしながら少なくとも沖縄戦が事実上終結した6月23日の『沖縄慰霊の日』には沖縄本島に向い、
対戦中のアメリカが、人類史上初めて広島市の市街に原子爆弾を投下された8月6日の『原爆の日』には広島市に、、
その後まもない9日の長崎にも原子爆弾が投下された『原爆の日』には長崎市に向い、黙祷をしてきた。
そして本日の15日の敗戦なのに『終戦記念日』称しているこの日の朝、都心の皇居に向かい黙祷した・・。
こうした根底には、かの大戦に於いて、余りにも多くの方たちが亡くなわれて、
尊い犠牲の上で、今日の日本の平和の礎(いしずえ)である、と思いながら、
戦争を知らない私でも深い心の傷として、今日に至っている。
このような思いから、私は国民のひとりの責務として、ここ48年黙祷をして尊い命のご冥福を祈っている。
そして私はいつも感じることは、若き10、20代の諸兄諸姉に対して、
少なくとも日本の過去には、こうした現実があった、と認識して欲しい、固く願っているひとりである。

私は、皇居に向って黙祷をする真情は、 かの大戦の当時の国民風潮として、
『天皇陛下の御為と国の為に死ぬ事が日本人の美徳と教えられ、
戦死したら靖国神社に神として祀(まつ)られ、
崇(あが)められると信じて疑わない殆どの国民がいた・・』
と当時の時代の風潮の中で生き、亡くなわれた人々に哀悼の意を表しているに他ならない。
いずれにしても、戦争は多くの場合は外交の破綻から発生し、
最悪の場合は戦争となるが、勝戦国となる国民も敗戦国となる国民も余りにも過酷で悲惨である。
私はここ9年ばかり、この15日に於いては、
都心の千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑の碑に刻まれた両陛下の詠まれた歌に、思いを重ねたりしている。
国のため いのちささげし
人々の ことを思えば 胸せまりくる
昭和天皇
戦なき 世を歩みきて
思ひ出づ かの難き日を 生きし人々
平成天皇
私はこの歌を深く拝読するたびに、思わず胸が熱くし、
その時代を少し学んできた歳月に思いを馳せ、まぎれない鎮魂曲のように感じている。

この昭和天皇の歌の思いは、
靖国神社から程近い所にある千鳥ケ淵戦没者墓苑は、
訪れる人も少なく、この季節は蝉時雨が響き渡る情景の中、 詠まれた伝えられている。
平成天皇の歌は、戦後60年の年の歌会始の儀で詠まれた、と報じられていた。
そして昭和天皇の御製の碑と向き合う形で、
2005年(平成17年)9月に平成天皇の御製の碑が完成した、
と確か読売新聞で読んだりし、私はつたない身ながら学び、思いを深めている・・。

私は高校生の時に、近現代史にも関心して以来、数多く本を乱読してきた・・。
どうしてあのような無謀な世界第二次大戦を、日本は開始してしまったのだろうか、
と重く心によどんだりしてきた・・。
私はアメリカが計画してきたオレンジ計画に、日本の軍部の上層部は、深く対処できずに、
怜悧な総合戦略も思案できず、それぞれ思惑で迷走を重ねて、やがて戦争に突入してしまった、
このような思いで、ここ十年ばかり思ったりしてきた。
オレンジ計画はアメリカ海軍が戦間期(1920年代から1930年代)において、
起こり得る大日本帝国(日本)との戦争へ対処するために立案された、
アメリカは交戦可能性のある全ての国を網羅してそれぞれ色分けされ計画されたもので、
日本はオレンジ色に識別したが、日本だけを特別敵視していたわけではない。
そして計画は1919年に非公式に立案され、1924年初頭に陸海軍合同会議で採用されていた。
アメリカはスペインとの戦争によりフィリピン、グアムを獲得した。
そしてアメリカが西太平洋をそのまま西進して行き着く方向には、
日本が日清戦争により朝鮮半島含め大陸へと進出し始めていた。
わずか半世紀前にマシュー・ペリー率いる自国の東インド艦隊が訪問して開国させた日本が、
富国強兵策を取って中国へ進出してきたことは、
スペインとの戦争を終えたアメリカにとって潜在的な警戒すべき問題となっていた。
この頃からアメリカは対日本戦争計画の研究作業を開始する。
日露戦争が終結すると中国問題が日米間で重要問題化しだし、両国間の緊張が高まりだす。
アメリカは日本を仮想敵国とした戦争計画の策定に本腰を入れ始め、
一連のカラーコード戦争計画の一つであるオレンジ計画が誕生する。
オレンジ計画では初期の頃より『日本が先制攻撃により攻勢に出て、消耗戦を経てアメリカが反攻に移り、
海上封鎖されて日本は経済破綻して敗北する』
という日米戦争のシナリオを描いてシミレーションされ、実際の太平洋戦争もこれに近い経緯を辿っていく。
日露戦争の最中、第一次世界大戦といった日本と協調関係にあった時期でも、
対日本戦争計画、オレンジ計画は研究され続けていた。

昨日、私が購読している読売新聞の朝刊に於いて、『戦後70年』の連載記事を読んだりした。
『[戦後70年 あの夏]どう負けた 皆知らない 作家 半藤一利さん 85歳』
と題された記事を襟を正して読んだりした。
もとより作家の半藤一利(はんどう・かずとし)さんは、昭和史研究家として突出されたお方である。
一部を無断ながら、転記さらて頂く。
《・・敗戦の原因は、日本人固有の精神構造にあると思います。
情報を直視せず、自分に都合のいい結論のままどんどん行った。
ミッドウェー海戦では、敵機動部隊は出てこないと決めつけ、
ガダルカナル島の戦いでも、敵はすぐに引くと根拠もなく信じた。
兵站へいたんが限界を超えても出て行った。
陸海軍合わせ240万人の戦死者のうち、7割が餓死か栄養失調か、それに伴う病死でした。
そんな無残な死に方をする戦争なんてありえません。
国全体が集団催眠にかかり、勢いで突き進んだ結果でした。・・》

この後、半藤一利さんにインタビューされた編集委員・服部真さんが、
半藤一利さんの思いの記事が掲載されていた。
《・・「一等国」意識の暴走 背景に国民の熱狂
明治から昭和にかけての歴史は、日露戦争(1904~05年)でいったん切った方がわかりやすいと、
半藤さんは言う。
日露戦争までは、欧米列強に植民地にされるのを回避するため、近代化を急いだ時期だ。
巨額の軍事費をまかなうため、国民は重い負担に耐えた。
ロシアに対して、世界中が日本が負けると思っていた戦争を始めたのも、自衛のためだった。
日露戦争から昭和の初めまでは、日本が大国として振る舞った時期だ。
戦争に勝ち、「一等国」の仲間入りをしたと国民は確信するが、そこから日本が変わっていく。
自分たちは一等国民だという意識で動き始めたようだ。
例えば、第1次世界大戦の戦後処理を決める1919年のパリ講和会議では、
分け前を声高に主張してひんしゅくを買う。
国際社会で孤立を深めた日本は、英米に敵対感情を抱くようになり、33年には国際連盟を脱退する。
当時の指導者たちは、情勢を直視せず、国際法を顧みずに暴走した。
そして、米国を相手に、勝ち目のない戦争へと突き進んだ。
その背景に国民の熱狂があったことが、半藤さんの話から伝わってくる。 (服部)・・》
私はこうしたあの時代に、現世の私は心を痛め、ただ黙祷し、項垂(うなだ)れたりした。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村

朝の6時半過ぎ洗面した後、庭のテラスに下り立ち、襟を正して黙祷した・・。
私は1944年〈昭和19年)9月に東京郊外で農家の三男坊として生を受け、
翌年の1945年〈昭和20年)8月15日に日本は連合国に降伏し、敗戦となった時、
一歳未満の乳児であったので、戦争を知らない世代のひとりである。
しかしながら少なくとも沖縄戦が事実上終結した6月23日の『沖縄慰霊の日』には沖縄本島に向い、
対戦中のアメリカが、人類史上初めて広島市の市街に原子爆弾を投下された8月6日の『原爆の日』には広島市に、、
その後まもない9日の長崎にも原子爆弾が投下された『原爆の日』には長崎市に向い、黙祷をしてきた。
そして本日の15日の敗戦なのに『終戦記念日』称しているこの日の朝、都心の皇居に向かい黙祷した・・。
こうした根底には、かの大戦に於いて、余りにも多くの方たちが亡くなわれて、
尊い犠牲の上で、今日の日本の平和の礎(いしずえ)である、と思いながら、
戦争を知らない私でも深い心の傷として、今日に至っている。
このような思いから、私は国民のひとりの責務として、ここ48年黙祷をして尊い命のご冥福を祈っている。
そして私はいつも感じることは、若き10、20代の諸兄諸姉に対して、
少なくとも日本の過去には、こうした現実があった、と認識して欲しい、固く願っているひとりである。

私は、皇居に向って黙祷をする真情は、 かの大戦の当時の国民風潮として、
『天皇陛下の御為と国の為に死ぬ事が日本人の美徳と教えられ、
戦死したら靖国神社に神として祀(まつ)られ、
崇(あが)められると信じて疑わない殆どの国民がいた・・』
と当時の時代の風潮の中で生き、亡くなわれた人々に哀悼の意を表しているに他ならない。
いずれにしても、戦争は多くの場合は外交の破綻から発生し、
最悪の場合は戦争となるが、勝戦国となる国民も敗戦国となる国民も余りにも過酷で悲惨である。
私はここ9年ばかり、この15日に於いては、
都心の千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑の碑に刻まれた両陛下の詠まれた歌に、思いを重ねたりしている。
国のため いのちささげし
人々の ことを思えば 胸せまりくる
昭和天皇
戦なき 世を歩みきて
思ひ出づ かの難き日を 生きし人々
平成天皇
私はこの歌を深く拝読するたびに、思わず胸が熱くし、
その時代を少し学んできた歳月に思いを馳せ、まぎれない鎮魂曲のように感じている。

この昭和天皇の歌の思いは、
靖国神社から程近い所にある千鳥ケ淵戦没者墓苑は、
訪れる人も少なく、この季節は蝉時雨が響き渡る情景の中、 詠まれた伝えられている。
平成天皇の歌は、戦後60年の年の歌会始の儀で詠まれた、と報じられていた。
そして昭和天皇の御製の碑と向き合う形で、
2005年(平成17年)9月に平成天皇の御製の碑が完成した、
と確か読売新聞で読んだりし、私はつたない身ながら学び、思いを深めている・・。

私は高校生の時に、近現代史にも関心して以来、数多く本を乱読してきた・・。
どうしてあのような無謀な世界第二次大戦を、日本は開始してしまったのだろうか、
と重く心によどんだりしてきた・・。
私はアメリカが計画してきたオレンジ計画に、日本の軍部の上層部は、深く対処できずに、
怜悧な総合戦略も思案できず、それぞれ思惑で迷走を重ねて、やがて戦争に突入してしまった、
このような思いで、ここ十年ばかり思ったりしてきた。
オレンジ計画はアメリカ海軍が戦間期(1920年代から1930年代)において、
起こり得る大日本帝国(日本)との戦争へ対処するために立案された、
アメリカは交戦可能性のある全ての国を網羅してそれぞれ色分けされ計画されたもので、
日本はオレンジ色に識別したが、日本だけを特別敵視していたわけではない。
そして計画は1919年に非公式に立案され、1924年初頭に陸海軍合同会議で採用されていた。
アメリカはスペインとの戦争によりフィリピン、グアムを獲得した。
そしてアメリカが西太平洋をそのまま西進して行き着く方向には、
日本が日清戦争により朝鮮半島含め大陸へと進出し始めていた。
わずか半世紀前にマシュー・ペリー率いる自国の東インド艦隊が訪問して開国させた日本が、
富国強兵策を取って中国へ進出してきたことは、
スペインとの戦争を終えたアメリカにとって潜在的な警戒すべき問題となっていた。
この頃からアメリカは対日本戦争計画の研究作業を開始する。
日露戦争が終結すると中国問題が日米間で重要問題化しだし、両国間の緊張が高まりだす。
アメリカは日本を仮想敵国とした戦争計画の策定に本腰を入れ始め、
一連のカラーコード戦争計画の一つであるオレンジ計画が誕生する。
オレンジ計画では初期の頃より『日本が先制攻撃により攻勢に出て、消耗戦を経てアメリカが反攻に移り、
海上封鎖されて日本は経済破綻して敗北する』
という日米戦争のシナリオを描いてシミレーションされ、実際の太平洋戦争もこれに近い経緯を辿っていく。
日露戦争の最中、第一次世界大戦といった日本と協調関係にあった時期でも、
対日本戦争計画、オレンジ計画は研究され続けていた。

昨日、私が購読している読売新聞の朝刊に於いて、『戦後70年』の連載記事を読んだりした。
『[戦後70年 あの夏]どう負けた 皆知らない 作家 半藤一利さん 85歳』
と題された記事を襟を正して読んだりした。
もとより作家の半藤一利(はんどう・かずとし)さんは、昭和史研究家として突出されたお方である。
一部を無断ながら、転記さらて頂く。
《・・敗戦の原因は、日本人固有の精神構造にあると思います。
情報を直視せず、自分に都合のいい結論のままどんどん行った。
ミッドウェー海戦では、敵機動部隊は出てこないと決めつけ、
ガダルカナル島の戦いでも、敵はすぐに引くと根拠もなく信じた。
兵站へいたんが限界を超えても出て行った。
陸海軍合わせ240万人の戦死者のうち、7割が餓死か栄養失調か、それに伴う病死でした。
そんな無残な死に方をする戦争なんてありえません。
国全体が集団催眠にかかり、勢いで突き進んだ結果でした。・・》

この後、半藤一利さんにインタビューされた編集委員・服部真さんが、
半藤一利さんの思いの記事が掲載されていた。
《・・「一等国」意識の暴走 背景に国民の熱狂
明治から昭和にかけての歴史は、日露戦争(1904~05年)でいったん切った方がわかりやすいと、
半藤さんは言う。
日露戦争までは、欧米列強に植民地にされるのを回避するため、近代化を急いだ時期だ。
巨額の軍事費をまかなうため、国民は重い負担に耐えた。
ロシアに対して、世界中が日本が負けると思っていた戦争を始めたのも、自衛のためだった。
日露戦争から昭和の初めまでは、日本が大国として振る舞った時期だ。
戦争に勝ち、「一等国」の仲間入りをしたと国民は確信するが、そこから日本が変わっていく。
自分たちは一等国民だという意識で動き始めたようだ。
例えば、第1次世界大戦の戦後処理を決める1919年のパリ講和会議では、
分け前を声高に主張してひんしゅくを買う。
国際社会で孤立を深めた日本は、英米に敵対感情を抱くようになり、33年には国際連盟を脱退する。
当時の指導者たちは、情勢を直視せず、国際法を顧みずに暴走した。
そして、米国を相手に、勝ち目のない戦争へと突き進んだ。
その背景に国民の熱狂があったことが、半藤さんの話から伝わってくる。 (服部)・・》
私はこうしたあの時代に、現世の私は心を痛め、ただ黙祷し、項垂(うなだ)れたりした。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪