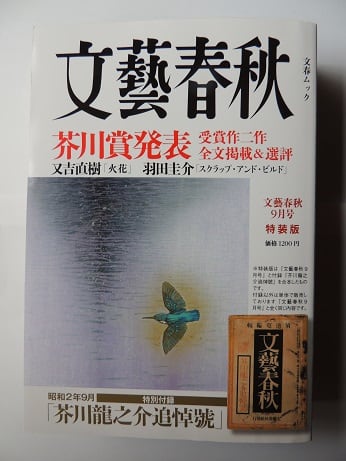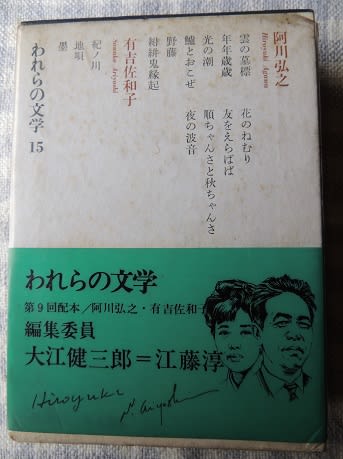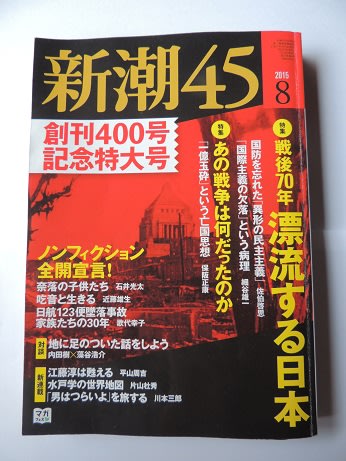私は年金生活の老ボーイの70歳の身であるが、
昨夜のひととき、ときおり愛読しているネットのサイトを見たりしていた。
産経新聞の基幹サイトのひとつの『Sankei Biz』であり、
私は年金生活の中で、企業の動向、暮らし、社会などを多々学んだりしている。
ぼんやりと各記事を見たりした中で、
【高齢者は転倒予防を 散歩、体操、ストレッチ 無理なく】
と見出しを見て、微苦笑したりした。

私は民間会社の中小業の会社に35年近く奮戦し、2004年(平成16年)の秋に定年退職し、
多々の理由で年金生活を始め、早や11年生となっている。
東京の世田谷区と狛江市に隣接した調布市の片隅に住み、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
日常の殆どは私が年金生活の当初から、平素の買物を自主的に専任者となり、
独りで殆ど毎日のように家内から依頼された品を求めて、買物メール老ボーイとなっている。
こうした中、最寄のスーパーに買物に行ったり、
或いは駅前までの片道徒歩20分ぐらいのスーパー、専門店に行ったりしているが、
根がケチなせいか利便性のよい路線バスに乗るのことなく、歩いて往還している。
しかしながら暑い33度以上の日は、熱中症で倒れて救急車で運ばれて、
目覚めたら病院のベットの上だった事態は、何かと単細胞の私でも困苦するので、
路線バスに乗り、車内の冷気に甘えて往復したりしてきた。

その後、私が何よりも怖いのは認知症であり、
もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
独りで自宅から数キロ以内の遊歩道、小公園などをひたすら歩き廻ったりして、
季節の移ろいを享受している。
そして70代入門の初心者して、心身共に自立し健康的に生活できる健康寿命を意識して、
確かな『生きがい』と『健康』、そして『気力』を持続できるように、
ときおり願いながら歩いたりしている。

昨今、家の居間は床は板張りにして半分ほどは絨毯を敷いているが、
この絨毯の片隅に躓(つまづ)いたりしたことが、この1か月に二回ばかりあり、
そして少しボケてきたのかしら、油断大敵だなぁ、ひとり微苦笑したりした・・。
このような状況もあったので、高齢者の転倒予防を学ぼう、とクリックした。
そして配信された記事は、少し古い一昨年の2013年12月1日であったが、
高齢者の私にとっては、大切な今後のテーマと思いながら、精読した。
無断であるが転載させて頂く。

《・・「老化は足から」という言葉があるが、高齢者が転倒すると、
骨折して寝たきりになったり、頭などを打って命を落としたりする危険がある。
元気に年を重ねるために防ぎたい転倒。散歩や体操、ストレッチングなどを無理のないペースで続け、
転びにくい体づくりを目指そう。(竹岡伸晃)
◎衰えの把握が第一歩
厚生労働省の国民生活基礎調査(平成22年)によると、要介護となった人のうち骨折・転倒が原因は10・2%。
脳卒中(21・5%)、認知症(15・3%)などとともに主要原因の一つだった。
人口動態統計(24年)によると、転倒・転落による死亡数は7761人で、増加傾向にある。
「高齢者が転倒すると本人も家族も大変。もっと予防に力を入れるべきだ」。
『いくつになっても転ばない5つの習慣』(青春出版社)などの著者で
「転倒予防医学研究会」世話人代表、武藤芳照・日体大総合研究所(東京都世田谷区)所長はこう話す。

◎高齢者が転倒する主な理由
高齢者が転倒する主な理由は武藤所長によると、
(1)老化による衰弱
(2)運動不足による体の機能低下
(3)病気による体のひずみ-の3つ。
脳梗塞や神経、脊椎の病気などが隠れているケースもあるため、「たかが転倒」と考えず、
必要な検査や治療は受ける。
(1)や(2)は、衰えを把握することが予防の第一歩。
日常生活の中では「片足立ちがしっかりできているかどうか」が判断基準となる。
「立ったままズボンや靴下をはく、道を歩く、階段を上り下りする、
浴槽をまたいで湯に入るなど、日常生活には片足立ちを基本とする動作が数多くある。
これらの動作が難しくなったり遅くなったりした場合、老化が進んでいるサインといえる」(武藤所長)
そのうえで、一つ一つの日常の動作を意識してしっかり行うことを心掛ける。
武藤所長は「例えば、『階段を上るぞ』と意識するだけで筋肉の使い方が変わり、踏み外すリスクが減る。
階段は最後の一段まで気を抜かないことが大事」。
日光を浴びながらの散歩や体操、ストレッチング、プールでの水中歩行、
音楽に合わせて行うリズム体操などで、普段から体を動かすことも大事だ。
自分に合ったものを選び、無理なく楽しく長く続けることを目指す。

◎萎縮せず意欲的に
転倒しやすい場所を知り、対策しておくことも重要だ。
武藤所長は「『ぬ・か・づけ』に要注意」と警告する。
▽「ぬ」れている場所
▽「か」い段・段差
▽かた「づけ」ていない場所-の意味だ。
これらの場所では慎重に歩く、手すりを持つなど十分に注意する。
▽部屋を片付け、コード類は束にして壁側に寄せる
▽浴室の床に滑り止めマットを敷く
▽部屋と廊下の段差を解消する-など、できる対策はしておきたい。
日常生活での注意点をまとめた「転倒予防7カ条」。
第7条に「転んでも起きればいいや」とある。
武藤所長は「転倒・骨折しても正確な診断を受け、適切な治療を受ければ復帰が可能。
『二度と転びたくない』と萎縮するのではなく、意欲的に体を動かしてほしい」とアドバイスしている。

◎転倒予防7カ条(武藤所長提唱)
1、歳々年々、人同じからず(年齢とともに体の機能は変わる)
2、転倒は結果である
3、片足立ちを意識する
4、転ばぬ先のつえ(つえは正しく使う)
5、無理なく楽しく30年(自分に合った運動を継続する)
6、命の水を大切に(こまめに水を飲む)
7、転んでも起きればいいや
・・》
注)記事の原文にあえて改行を多くした

過ぎし私は高齢者入門の65歳を過ぎてから、
心身ともに自立し健康的に生活できる期間の健康寿命は、
男性の平均としては71歳であり、平均寿命は男性の場合は80歳と知った時、
恥ずかしながらうろたえたりした・・。
そして70代となれば、多くの人は体力の衰えを実感して、
75歳まではこれまでどおりの自立した生活ができるが、
80歳が見えてくる頃には介護を必要とするようになり、やがて80代後半では
何らかの介護付き施設に入居する可能性が高くなる、と専門家の人から数多く発言されている。
この後、私は介護については漠然とし、まして費用に関しても殆ど無知であったので、
少し学んだりしてきたりした。
私たち夫婦はお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中、私たち夫婦は幸運にも大病に遭遇せず、今日に至っている。
しかしながら命ながらえば、やがていつの日にか、介護を受ける身となる。

私の希望としては、80歳を迎えた時、益々体力は衰えた身であるが、
我が家から最寄駅まで一キロばかりの道を、路線バスに利用することなく、
何とか歩いて往復したい、と念願している。
そして私が死去する時は、身の回りの世話の一部に手助けが必要で、
立ち上がり時などに、なんらかの支えを必要とする時があり、
排泄や食事は、ほとんど自分でできる 『要支援1』で、この世にお別れをしたい、
と秘かに思ったりしている。
しかしながら自助努力も必要であるが、こればかりは天上の神々の采配に寄る。
そして、この前提必須条件としては、日頃は転倒して骨折し、やがて寝たきりになることは、
避けたいので、今回の記事を読み終わった後、真摯に教示されたのである。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村

昨夜のひととき、ときおり愛読しているネットのサイトを見たりしていた。
産経新聞の基幹サイトのひとつの『Sankei Biz』であり、
私は年金生活の中で、企業の動向、暮らし、社会などを多々学んだりしている。
ぼんやりと各記事を見たりした中で、
【高齢者は転倒予防を 散歩、体操、ストレッチ 無理なく】
と見出しを見て、微苦笑したりした。

私は民間会社の中小業の会社に35年近く奮戦し、2004年(平成16年)の秋に定年退職し、
多々の理由で年金生活を始め、早や11年生となっている。
東京の世田谷区と狛江市に隣接した調布市の片隅に住み、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
日常の殆どは私が年金生活の当初から、平素の買物を自主的に専任者となり、
独りで殆ど毎日のように家内から依頼された品を求めて、買物メール老ボーイとなっている。
こうした中、最寄のスーパーに買物に行ったり、
或いは駅前までの片道徒歩20分ぐらいのスーパー、専門店に行ったりしているが、
根がケチなせいか利便性のよい路線バスに乗るのことなく、歩いて往還している。
しかしながら暑い33度以上の日は、熱中症で倒れて救急車で運ばれて、
目覚めたら病院のベットの上だった事態は、何かと単細胞の私でも困苦するので、
路線バスに乗り、車内の冷気に甘えて往復したりしてきた。

その後、私が何よりも怖いのは認知症であり、
もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
独りで自宅から数キロ以内の遊歩道、小公園などをひたすら歩き廻ったりして、
季節の移ろいを享受している。
そして70代入門の初心者して、心身共に自立し健康的に生活できる健康寿命を意識して、
確かな『生きがい』と『健康』、そして『気力』を持続できるように、
ときおり願いながら歩いたりしている。

昨今、家の居間は床は板張りにして半分ほどは絨毯を敷いているが、
この絨毯の片隅に躓(つまづ)いたりしたことが、この1か月に二回ばかりあり、
そして少しボケてきたのかしら、油断大敵だなぁ、ひとり微苦笑したりした・・。
このような状況もあったので、高齢者の転倒予防を学ぼう、とクリックした。
そして配信された記事は、少し古い一昨年の2013年12月1日であったが、
高齢者の私にとっては、大切な今後のテーマと思いながら、精読した。
無断であるが転載させて頂く。

《・・「老化は足から」という言葉があるが、高齢者が転倒すると、
骨折して寝たきりになったり、頭などを打って命を落としたりする危険がある。
元気に年を重ねるために防ぎたい転倒。散歩や体操、ストレッチングなどを無理のないペースで続け、
転びにくい体づくりを目指そう。(竹岡伸晃)
◎衰えの把握が第一歩
厚生労働省の国民生活基礎調査(平成22年)によると、要介護となった人のうち骨折・転倒が原因は10・2%。
脳卒中(21・5%)、認知症(15・3%)などとともに主要原因の一つだった。
人口動態統計(24年)によると、転倒・転落による死亡数は7761人で、増加傾向にある。
「高齢者が転倒すると本人も家族も大変。もっと予防に力を入れるべきだ」。
『いくつになっても転ばない5つの習慣』(青春出版社)などの著者で
「転倒予防医学研究会」世話人代表、武藤芳照・日体大総合研究所(東京都世田谷区)所長はこう話す。

◎高齢者が転倒する主な理由
高齢者が転倒する主な理由は武藤所長によると、
(1)老化による衰弱
(2)運動不足による体の機能低下
(3)病気による体のひずみ-の3つ。
脳梗塞や神経、脊椎の病気などが隠れているケースもあるため、「たかが転倒」と考えず、
必要な検査や治療は受ける。
(1)や(2)は、衰えを把握することが予防の第一歩。
日常生活の中では「片足立ちがしっかりできているかどうか」が判断基準となる。
「立ったままズボンや靴下をはく、道を歩く、階段を上り下りする、
浴槽をまたいで湯に入るなど、日常生活には片足立ちを基本とする動作が数多くある。
これらの動作が難しくなったり遅くなったりした場合、老化が進んでいるサインといえる」(武藤所長)
そのうえで、一つ一つの日常の動作を意識してしっかり行うことを心掛ける。
武藤所長は「例えば、『階段を上るぞ』と意識するだけで筋肉の使い方が変わり、踏み外すリスクが減る。
階段は最後の一段まで気を抜かないことが大事」。
日光を浴びながらの散歩や体操、ストレッチング、プールでの水中歩行、
音楽に合わせて行うリズム体操などで、普段から体を動かすことも大事だ。
自分に合ったものを選び、無理なく楽しく長く続けることを目指す。

◎萎縮せず意欲的に
転倒しやすい場所を知り、対策しておくことも重要だ。
武藤所長は「『ぬ・か・づけ』に要注意」と警告する。
▽「ぬ」れている場所
▽「か」い段・段差
▽かた「づけ」ていない場所-の意味だ。
これらの場所では慎重に歩く、手すりを持つなど十分に注意する。
▽部屋を片付け、コード類は束にして壁側に寄せる
▽浴室の床に滑り止めマットを敷く
▽部屋と廊下の段差を解消する-など、できる対策はしておきたい。
日常生活での注意点をまとめた「転倒予防7カ条」。
第7条に「転んでも起きればいいや」とある。
武藤所長は「転倒・骨折しても正確な診断を受け、適切な治療を受ければ復帰が可能。
『二度と転びたくない』と萎縮するのではなく、意欲的に体を動かしてほしい」とアドバイスしている。

◎転倒予防7カ条(武藤所長提唱)
1、歳々年々、人同じからず(年齢とともに体の機能は変わる)
2、転倒は結果である
3、片足立ちを意識する
4、転ばぬ先のつえ(つえは正しく使う)
5、無理なく楽しく30年(自分に合った運動を継続する)
6、命の水を大切に(こまめに水を飲む)
7、転んでも起きればいいや
・・》
注)記事の原文にあえて改行を多くした

過ぎし私は高齢者入門の65歳を過ぎてから、
心身ともに自立し健康的に生活できる期間の健康寿命は、
男性の平均としては71歳であり、平均寿命は男性の場合は80歳と知った時、
恥ずかしながらうろたえたりした・・。
そして70代となれば、多くの人は体力の衰えを実感して、
75歳まではこれまでどおりの自立した生活ができるが、
80歳が見えてくる頃には介護を必要とするようになり、やがて80代後半では
何らかの介護付き施設に入居する可能性が高くなる、と専門家の人から数多く発言されている。
この後、私は介護については漠然とし、まして費用に関しても殆ど無知であったので、
少し学んだりしてきたりした。
私たち夫婦はお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中、私たち夫婦は幸運にも大病に遭遇せず、今日に至っている。
しかしながら命ながらえば、やがていつの日にか、介護を受ける身となる。

私の希望としては、80歳を迎えた時、益々体力は衰えた身であるが、
我が家から最寄駅まで一キロばかりの道を、路線バスに利用することなく、
何とか歩いて往復したい、と念願している。
そして私が死去する時は、身の回りの世話の一部に手助けが必要で、
立ち上がり時などに、なんらかの支えを必要とする時があり、
排泄や食事は、ほとんど自分でできる 『要支援1』で、この世にお別れをしたい、
と秘かに思ったりしている。
しかしながら自助努力も必要であるが、こればかりは天上の神々の采配に寄る。
そして、この前提必須条件としては、日頃は転倒して骨折し、やがて寝たきりになることは、
避けたいので、今回の記事を読み終わった後、真摯に教示されたのである。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪