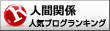使徒言行録8章26節~40節(抜粋)
エチオピアの宦官はイザヤ書53章に記された「神のしもべ」とは誰のことなのか心に引っかかっていました。その5節「彼が、、、いやされた」これはどういうことだろう。12節「多くの人の過ちを担い、、、この人であった」この人とはだれなのだろう、、、、と。
その彼のもとへ主の天使に命じられたフィリポが遣わされます。そして宦官がまさに53章の「神のしもべ」について思いめぐらしたその絶妙のタイミングで、主の霊はフィリポに行けと命じられるのです。不思議ですよね。彼はギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンでしたから、宦官のギリシャ語でのイザヤ書の朗読の声がよくわかりました。
そこで、宦官はフィリポの口をとおして、イザヤ書53章の「神のしもべ」がイエス・キリストであり、この方の十字架の苦難とその死によって、私たちの罪、過ちは償われたのだ、この方こそメシヤであるとの福音を聞くのであります。
ローマ書10章にこういう言葉があります。「主の名を呼び求める者はだれでも救われる」のです。ところで、信じたことのない方を、どうして呼び求められよう。聞いたことのない方を、どうして信じられよう。また、宣べ伝える人がいなければ、どうして聞くことができよう。遣わされないで、どうして宣べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか」と記されているとおりです。(10:13-15)。この「良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか」という一節は「神のしもべ」について記されているイザヤ書53章の前の52章7節からの言葉なのです。宦官がそこを読んでいた時、丁度ご聖霊、神の霊によってフィリポが行けと命じられ走り寄っていった時だと思いますと何だかワクワクしますが。そのように、私たち人の目には偶然にと思えることも、主のお取り計らいがあってなされているみ業であるということを知らされます。
みなさんも初めてキリスト教会の礼拝に出席するようになられた時は、イエス・キリストとはどういうお方なのか。罪とは何か。救いとは何か。などの疑問を抱かれたことと思います。そこで、私は聖書を読んだらよく分かったとか。聖書についての注解書や本を読んだら分かったといった人は多くはいらっしゃらないのではないでしょうか。又、クリスチャンとしての歩みの中でも分からないことや一人では聖書がどうしても読めないということがあります。実際、聖書は一人だけで読んで理解できるものではありません。どんな立派なテキストを使っても必ず行き詰まってしまいます。なぜならみ言葉・神の言葉は生きており私たちの命の営みの中で力を現わすものだからです。聖書は主にある兄弟姉妹との交わりの中で読まれ、それぞれに与えられた証を通して、分かち合われていく中で、その理解が豊かにされ、生活の中に生きていきます。受肉してくるのです。それは頭だけの理解、解説に終わるのではなく、主が私にどのように働かれたか、み言葉が私の生活に何をもたらしたか、ということが隣人との出会いや関わりの中で読まれ、分かち合われることが大切なのであります。聖書の歴史や背景、又原語の注解や文章の解釈は深く読む上でもちろん必要ではありますが。大切なのは聖書の言葉が私たちの生き方、又日常において支えとなり、力となり、祝福となっていくことです。教会の交わりはそのお一人お一人の証が分かち合われていくところにその素晴らしさがあると思います。
エチオピアの宦官はイザヤ書53章に記された「神のしもべ」とは誰のことなのか心に引っかかっていました。その5節「彼が、、、いやされた」これはどういうことだろう。12節「多くの人の過ちを担い、、、この人であった」この人とはだれなのだろう、、、、と。
その彼のもとへ主の天使に命じられたフィリポが遣わされます。そして宦官がまさに53章の「神のしもべ」について思いめぐらしたその絶妙のタイミングで、主の霊はフィリポに行けと命じられるのです。不思議ですよね。彼はギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンでしたから、宦官のギリシャ語でのイザヤ書の朗読の声がよくわかりました。
そこで、宦官はフィリポの口をとおして、イザヤ書53章の「神のしもべ」がイエス・キリストであり、この方の十字架の苦難とその死によって、私たちの罪、過ちは償われたのだ、この方こそメシヤであるとの福音を聞くのであります。
ローマ書10章にこういう言葉があります。「主の名を呼び求める者はだれでも救われる」のです。ところで、信じたことのない方を、どうして呼び求められよう。聞いたことのない方を、どうして信じられよう。また、宣べ伝える人がいなければ、どうして聞くことができよう。遣わされないで、どうして宣べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか」と記されているとおりです。(10:13-15)。この「良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか」という一節は「神のしもべ」について記されているイザヤ書53章の前の52章7節からの言葉なのです。宦官がそこを読んでいた時、丁度ご聖霊、神の霊によってフィリポが行けと命じられ走り寄っていった時だと思いますと何だかワクワクしますが。そのように、私たち人の目には偶然にと思えることも、主のお取り計らいがあってなされているみ業であるということを知らされます。
みなさんも初めてキリスト教会の礼拝に出席するようになられた時は、イエス・キリストとはどういうお方なのか。罪とは何か。救いとは何か。などの疑問を抱かれたことと思います。そこで、私は聖書を読んだらよく分かったとか。聖書についての注解書や本を読んだら分かったといった人は多くはいらっしゃらないのではないでしょうか。又、クリスチャンとしての歩みの中でも分からないことや一人では聖書がどうしても読めないということがあります。実際、聖書は一人だけで読んで理解できるものではありません。どんな立派なテキストを使っても必ず行き詰まってしまいます。なぜならみ言葉・神の言葉は生きており私たちの命の営みの中で力を現わすものだからです。聖書は主にある兄弟姉妹との交わりの中で読まれ、それぞれに与えられた証を通して、分かち合われていく中で、その理解が豊かにされ、生活の中に生きていきます。受肉してくるのです。それは頭だけの理解、解説に終わるのではなく、主が私にどのように働かれたか、み言葉が私の生活に何をもたらしたか、ということが隣人との出会いや関わりの中で読まれ、分かち合われることが大切なのであります。聖書の歴史や背景、又原語の注解や文章の解釈は深く読む上でもちろん必要ではありますが。大切なのは聖書の言葉が私たちの生き方、又日常において支えとなり、力となり、祝福となっていくことです。教会の交わりはそのお一人お一人の証が分かち合われていくところにその素晴らしさがあると思います。