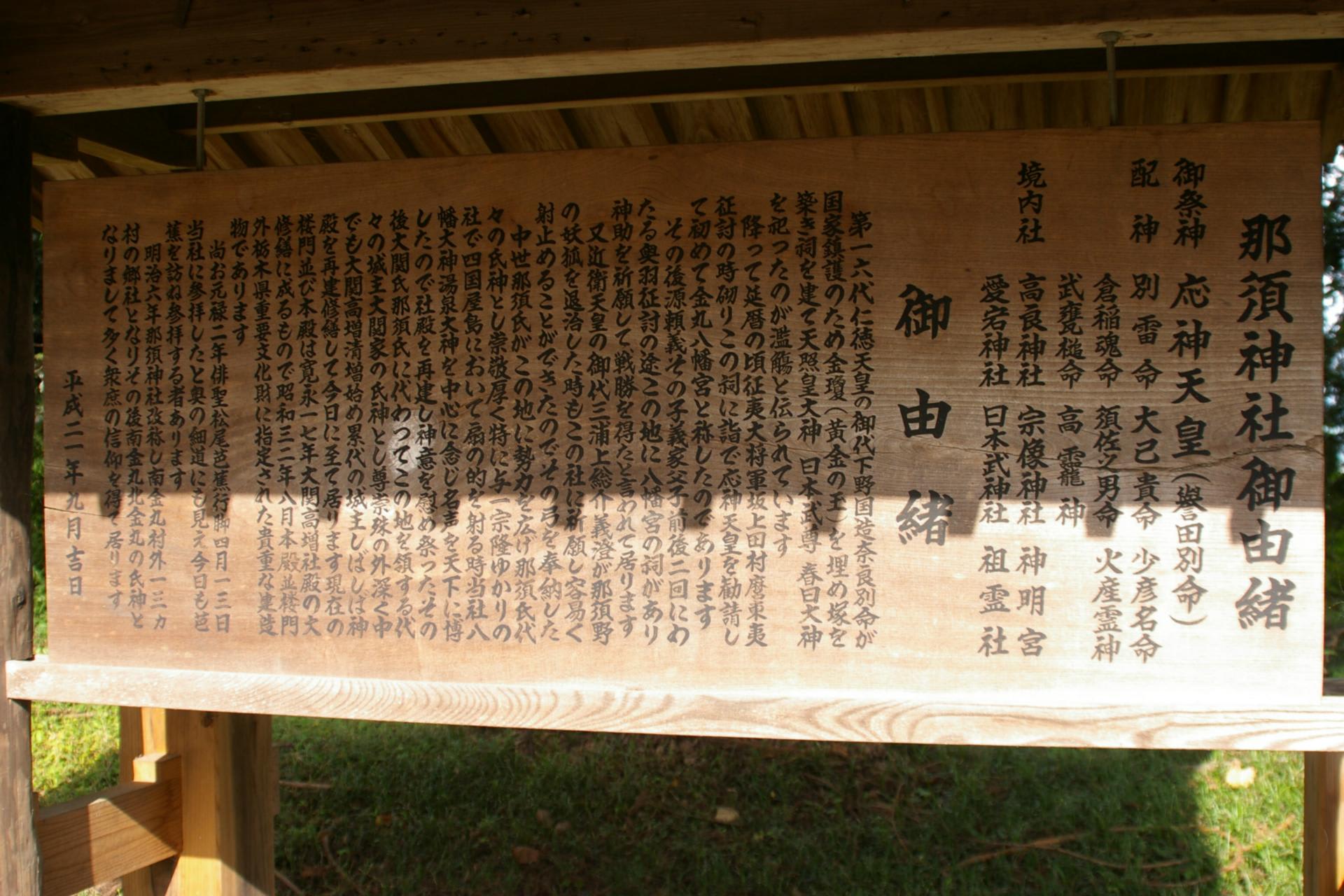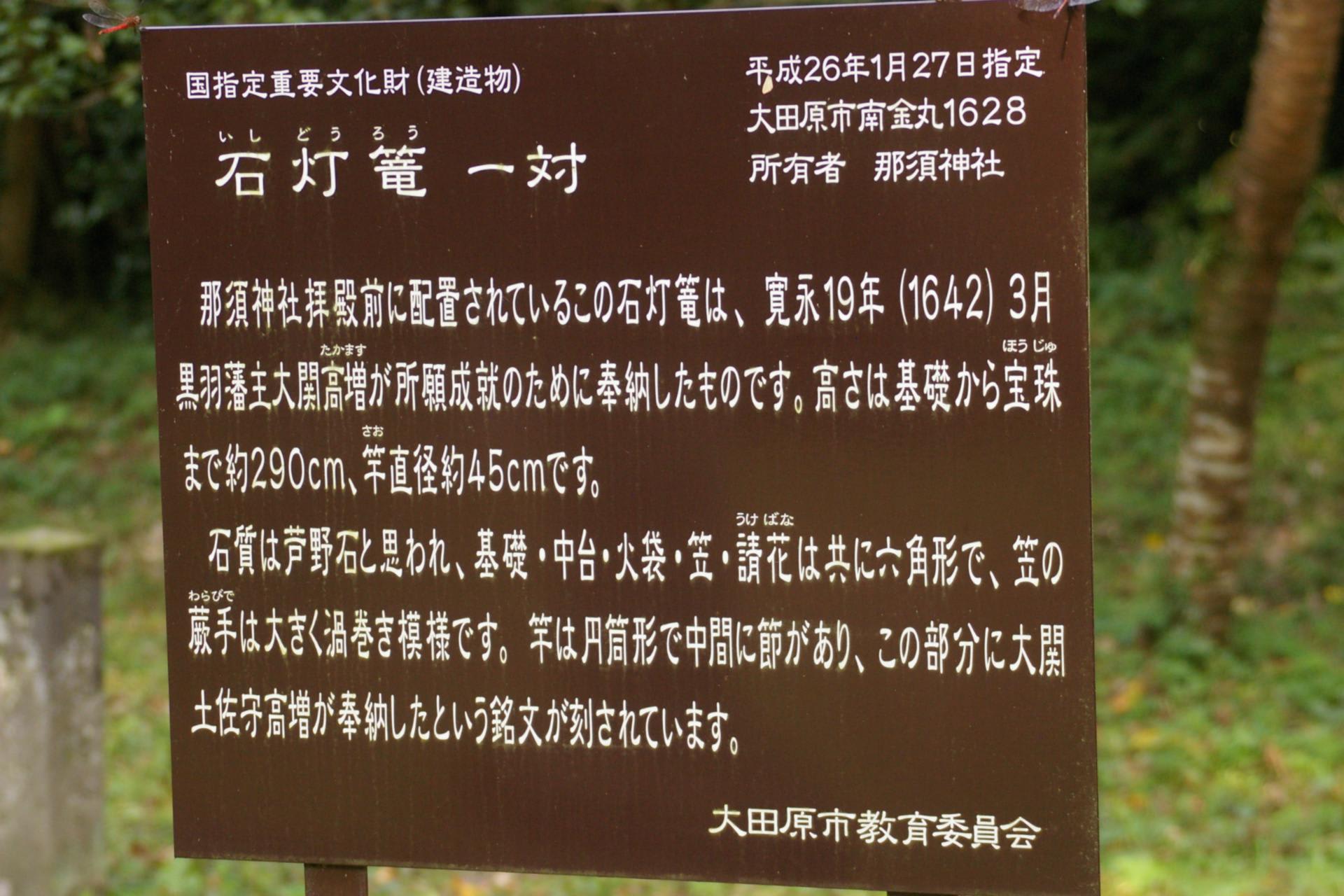下沢渡は、中之条町役場の西北西約5kmのところ
国道353号線を四万温泉方面に向かって
トンネルを貫けて直ぐ県道55線を西へ
四万川の橋を渡ったところです
県道の北側に沢田小学校があります
小学校の西側住宅地の中に諏訪神社参道入り口があります
小学校よりの道路脇に 車を置かせていただきました
車を置かせていただきました

諏訪神社参道入り口の赤鳥居です

石段の上に拝殿です

拝殿の彫刻が綺麗です

手水鉢です

神楽殿です

本殿です




境内南西端に融合木の大杉です、目通り幹周り5mの巨木です




本殿西側のケヤキです


大杉を境内外側から見上げました
では、次へ行きましょう

国道353号線を四万温泉方面に向かって
トンネルを貫けて直ぐ県道55線を西へ
四万川の橋を渡ったところです
県道の北側に沢田小学校があります
小学校の西側住宅地の中に諏訪神社参道入り口があります
小学校よりの道路脇に
 車を置かせていただきました
車を置かせていただきました
諏訪神社参道入り口の赤鳥居です


石段の上に拝殿です


拝殿の彫刻が綺麗です


手水鉢です


神楽殿です


本殿です





境内南西端に融合木の大杉です、目通り幹周り5mの巨木です





本殿西側のケヤキです



大杉を境内外側から見上げました

では、次へ行きましょう