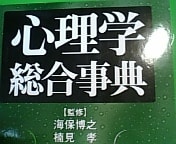はじめにーー人にやさしい文書とは
人にやさしい文書とはどんなものかを考えるには、少なくとも、次の3点を念頭におく必要がある。
一つは、読み手意識である。どんな読み手がどんな状況でその文書を読むかについて、はっきりと意識して文書が作られていることが、人にやさしい文書ということになる。
2つは、読み手に過度の認知的な負担をかけない配慮である。文書の内容を理解するには、関連知識や注意などの認知資源が必要である。できるだけ少ない認知資源の投入で読めてわかるような工夫をすることが、人にやさしい文書ということになる。
これを実現するためには、一つには、想定される読み手に文書を読んでもらう、もっと大掛かりには、ユーザビリティテストをおこなうのが最も有効な方策である。国際標準化機構による インタフェースにかかわる標準規格ISO13407の義務づけが2002年頃から日本でもはじまって以来、マニュアルのユーザビリティテストも避けて通れなくなってきている。
さらに、書き手(作り手)を誰にするかも極めて大事となる。
説明する内容を知悉している人が書き手として、必ずしもふさわしいわけではない。彼等にそもそも文書作成の能力がないということもあるが、さらに、図に示すように、ユーザの知識や状況に配慮した説明をするのが不得意ということもある。マニュアル制作で言えば、最近では、技術の設計者とユーザとの間を介在する形でテクニカル・ライターが、書き手なることが多い。
図1 技術とライターと読み手とユーザと
さて、本稿では、以下、マニュアル作りを想定した、人にやさしい文書作りのための指針を提案してみる。マニュアルには、関連知識の乏しい読み手に専門的な知識や複雑な操作をわかりやすく指示するための文書作りの一般的な技法が豊富に作り込まれているからである。
人にやさしい文書とはどんなものかを考えるには、少なくとも、次の3点を念頭におく必要がある。
一つは、読み手意識である。どんな読み手がどんな状況でその文書を読むかについて、はっきりと意識して文書が作られていることが、人にやさしい文書ということになる。
2つは、読み手に過度の認知的な負担をかけない配慮である。文書の内容を理解するには、関連知識や注意などの認知資源が必要である。できるだけ少ない認知資源の投入で読めてわかるような工夫をすることが、人にやさしい文書ということになる。
これを実現するためには、一つには、想定される読み手に文書を読んでもらう、もっと大掛かりには、ユーザビリティテストをおこなうのが最も有効な方策である。国際標準化機構による インタフェースにかかわる標準規格ISO13407の義務づけが2002年頃から日本でもはじまって以来、マニュアルのユーザビリティテストも避けて通れなくなってきている。
さらに、書き手(作り手)を誰にするかも極めて大事となる。
説明する内容を知悉している人が書き手として、必ずしもふさわしいわけではない。彼等にそもそも文書作成の能力がないということもあるが、さらに、図に示すように、ユーザの知識や状況に配慮した説明をするのが不得意ということもある。マニュアル制作で言えば、最近では、技術の設計者とユーザとの間を介在する形でテクニカル・ライターが、書き手なることが多い。
図1 技術とライターと読み手とユーザと
さて、本稿では、以下、マニュアル作りを想定した、人にやさしい文書作りのための指針を提案してみる。マニュアルには、関連知識の乏しい読み手に専門的な知識や複雑な操作をわかりやすく指示するための文書作りの一般的な技法が豊富に作り込まれているからである。