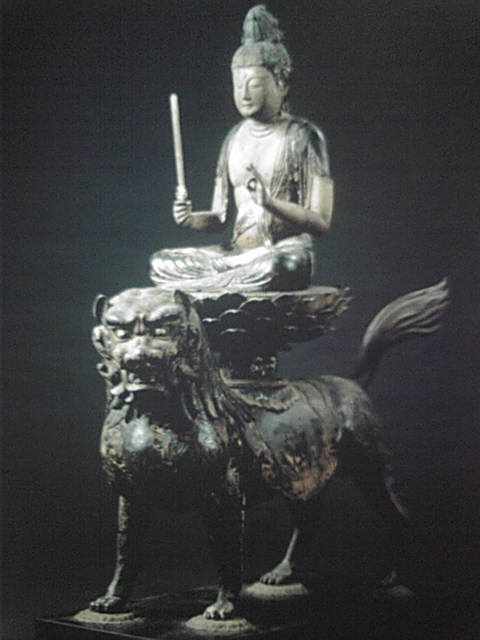今朝の新聞にも、企業年金の未請求が100億もあるとか
さもありなんである
国家公務員共済>私学共済と単純明快なキャリア
黙っていても年金はいただけるものと思っていた
とんでもない話
という話はすでにした
年金機構の相談窓口で、実に丁寧に教えていただき
手続きも、とても複雑だが、昨日、郵送できた
やまとさん、とても親切かつ有能な方にぶつかり
なんとか間に合った
これがあと1月遅れたら と思うとぞっとする
年金は自己申告
時効5年
きもに命じておく

さもありなんである
国家公務員共済>私学共済と単純明快なキャリア
黙っていても年金はいただけるものと思っていた
とんでもない話
という話はすでにした
年金機構の相談窓口で、実に丁寧に教えていただき
手続きも、とても複雑だが、昨日、郵送できた
やまとさん、とても親切かつ有能な方にぶつかり
なんとか間に合った
これがあと1月遅れたら と思うとぞっとする
年金は自己申告
時効5年
きもに命じておく