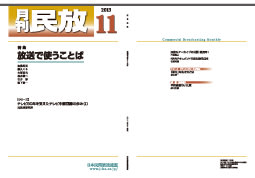「月刊民放」に連載している放送時評。
今回は、この夏、テレビ界の大ヒットというだけでなく、一種社会現象化したドラマ「半沢直樹」を総括しました。
半沢直樹のいた夏
もう忘れかけているが、今年の夏は暑かった。夜になっても気温は下がらず、外で遊ぶ気にもならない。できれば早く仕事を終えて家に帰り、クーラーの効いた部屋に避難したい。そんなふうに思いながら暮らした人も多いのではないか。
夏ドラマが始まった時、初回視聴率の高さに驚いた。テレビ朝日「DOCTORS2」19.6%。フジテレビ「ショムニ2013」18.3%。そしてTBS「半沢直樹」が19.4%。一瞬、高視聴率の原因は連日の猛暑か、と半分本気で思ったものだ。その後、「半沢」は単独でモンスター級ドラマへと成長していく。
7月の放送開始直後、「半沢」を次のように分析した。ポイントは2つあった。まず主人公が大量採用のバブル世代であること。企業内では、「楽をして禄を食む」など負のイメージで語られることの多い彼らにスポットを当てたストーリーが新鮮だ。池井戸潤の原作「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」は、優れた企業小説の例にもれず、内部にいる人間の生態を巧みに描いている。第2のポイントは主演の堺雅人である。フジテレビ「リーガルハイ」とTBS「大奥」の演技でギャラクシー賞テレビ部門個人賞を受賞したが、シリアスとユーモアの絶妙なバランス、特に目ヂカラが群を抜いている。まさに旬の役者だ。
8月に入っても、「半沢」は順調に数字を伸ばしていく。銀行、そして金融業界が舞台の話となれば複雑なものになりがちだが、「半沢」は実にわかりやすくできていた。銀行内部のドロドロとした権力闘争やパワハラなどの人間ドラマをリアルに描きつつ、自然な形で銀行の業務や金融業界全体が見えるようにしている。平易でいながら、奥行きがあった。また、銀行員の妻は夫の地位や身分で自らの序列が決まる。社宅住まいの妻たちの苦労を見せることで女性視聴者も呼び込んだ。8月11日放送の第5回、視聴率は前週の27.6%を超えて29.0%に達した。この頃、すでに「半沢」は堂々のブームとなっている。
ところが、なんと次の日曜日、18日は「半沢」を放送しないというではないか。その理由が「世界陸上」だ。独占生中継とはいえ、このタイミングで「半沢」を1回休むのはもったいないという声も多かった。しかし、結果的には視聴者の飢餓感を刺激し、また話題のドラマを見てみようという新たな層も呼び込むことになった。
前半(大阪編)がクライマックスを迎える頃、このドラマが「現代の時代劇」であることに気づいた。窮地に陥る主人公と、損得抜きに彼の助太刀をする仲間、際立つ敵役。勧善懲悪がはっきりしていて分かりやすい。威勢のいいたんかは「水戸黄門」の印籠代わりだ。主人公は我慢を重ね、最後に「倍返しだ!」と勝負をひっくり返す。視聴者は痛快に感じ、留飲が下がるというわけだ。
さらに半沢はコネも権力もない代わりに、知恵と友情を武器にして内外の敵と戦う。その手法は正義一辺倒ではなく、政治的な動きもすれば裏技も使う。巨額の債権を回収するためには手段を選ばないずるさもある。そんな「清濁併せのむヒーロー像」が見る人の共感を呼んだ。
9月、東京編に移っても「半沢」の勢いは止まらない。半沢の父を死に追いやった銀行常務の香川照之はもちろん、金融庁検査官を演じた片岡愛之助など脇役陣も自分の見せ場を作っていく。そして最後に用意された、運命の対決。半沢を正面からとらえたアップを多用する演出も、ぞくぞくするような臨場感を生んでいた。最終回の視聴率は今世紀最高の42.2%。録画で見た人を加えると膨大なものになる。
こうして振り返ってみて、このドラマが2つの小説を原作としていたことに再度注目したい。やろうと思えば大阪編だけでワンクールの放送は可能だった。しかし、それだと「半沢」が実現した密度とテンポの物語展開は無理だ。それは北三陸編と東京編の2部構成で成功した『あまちゃん』にも通じる。1話に詰め込まれている話の密度が極めて高く、またスピーディだ。それなのにわかりづらくないし、置いてきぼりもくわない。それは脚本や演出のチカラであると同時に、視聴者の情報処理能力のおかげでもある。つまり、2013年の今を生きる我々が日々体験している現実社会の情報量とテンポに、「半沢」は見事に合致していたのだ。やはりドラマは社会を映す鏡のひとつだと、あらためて思う。
(月刊民放 2013年11月号)