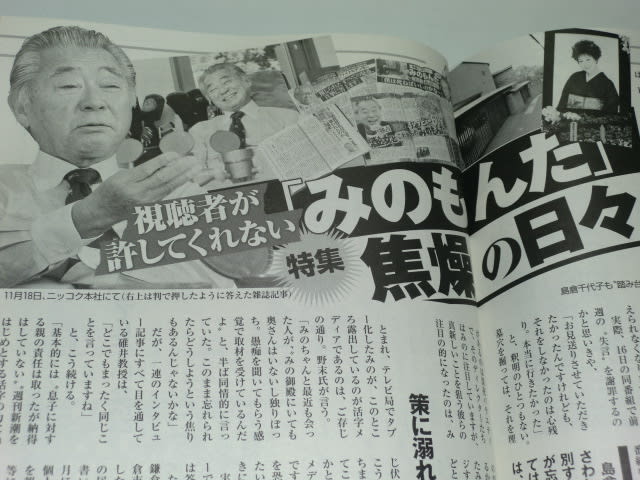日付が変わって、11月25日となりました。
今年もまた、三島由紀夫の命日がやってきたわけです。
昨年、この時期に、東京新聞に連載していたコラムで、以下のような文章を書きました。
42年後の「11月25日」
十一月二十五日は三島由紀夫の命日だった。自決したのは昭和四十五(一九七〇)年。当時私は高校一年で、意識して作品に接したのは没後からだ。
やがて三島自体に興味を持ち、毎年この日の前後に、私が“三島本”と呼ぶ関連書籍の新刊を読む。
たとえば二〇〇二年の橋本治『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』。〇五年は中条省平の編著『三島由紀夫が死んだ日』。椎根和『平凡パンチの三島由紀夫』は〇七年だ。
一〇年には多くの三島本が出て、『別冊太陽 三島由紀夫』には川端康成宛ての手紙が載った。「小生が怖れるのは死ではなくて、死後の家族の名誉です」という言葉が印象に残る。
今年は柴田勝二『三島由紀夫作品に隠された自決への道』を読んだ。「潮騒」から「豊饒の海」までを分析し、その死の意味を探っている。
だが、これを読みながら気づいた。私は三島を理解したい一方で、未知の部分を残しておきたいらしい。新たな三島本でも謎が解明されていないことに安堵しているのだ。
先日の二十五日は日曜だったが、入試があり大学に来ていた。三島が自決した正午すぎ、たまたま上階にある研究室に戻った。
窓外には四谷から飯田橋方面にかけての風景。正面に背の高い通信塔が見える。そこに位置する防衛省本省庁舎、かつての陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に向かって合掌した。
(東京新聞 2012.11.28)
・・・・43年後の今日は、昨年出版された三島由紀夫『日本人養成講座』(平凡社)を再読することにしました。
高丘卓さんの責任編集による、三島の“ひとりアンソロジー”のような本です。
巻末に置かれた「私の中の二十五年」には、有名なあの文章が含まれています。
このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではにかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機質な、からっぽの、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう。それでもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである。

さて、今週の「読んで、書評を書いた本」は、次の通りです。
東野圭吾 『祈りの幕が下りる時』 講談社
石原千秋 『教養として読む現代文学』 朝日新聞出版
半藤一利 ・保阪正康
『そして、メディアは日本を戦争に導いた』 東洋経済新報社
* 書いた書評は、
発売中の『週刊新潮』(11月28日霜降月増大号)
読書欄に掲載されています。