

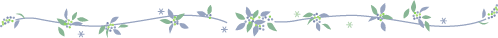
| 「あら、あたしんち、灰皿ってものがなくて、ホゝ」 と笑って加代が、これも桑の茶棚の戸を 開きかけると・・・ (中略) 「はい、これを灰皿になすってよ」 と信也の膝の近くへ差し出したのは、 茶棚から出した、1枚の小皿、 おっとりした白磁に蘭の花の染付け、 いい陶器の質だった。 「ほう、こりゃあ、なかなかいい趣味ですね、 高いでしょう」 「ホゝ、そうでしょうか、 でもお値段は言えないの、万珠堂の半端物の 格安品から見つけて来た代物ですから」 【吉屋信子作「良人の貞操」】 |
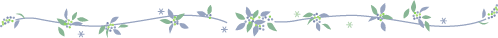
 春酣(たけなわ)、
春酣(たけなわ)、春爛漫(らんまん)、
春麗(うらら)、山笑う・・。
今日は、春の季語を思い切り
並べても飽き足らないほどの
春らしい陽気となりました。
そして何よりほっとした事。
昨日の雨が 「花散らしの雨」
とならなかった事です。
さすがの雨も桜のあまりに
もの美しさに、気を遣って
くれたのかも知れませんね。
こんなお天気ですから
外出したいのはやまやまなの
ですが、今日は生協の日。
留守なら玄関先へ・・
という約束になっていますが、
余程の急用でない限り
在宅する事にしています。
今日は風に揺れる小さな花、
「花韮(ハナニラ)」 が開花しました。
毎年忘れずに同じ場所に。今、続々と開花のスイッチが入ったようです。

さて、吉屋信子作 「良人の貞操」、読了。
これまでに比べ、随分、時間がかかってしまいましたね。
再三、お伝えしていますように、部屋の片付けに追われ、
それより何より冬が終わり春になりますと、
どうしても戸外に気持ちが奪われてしまうのです。
従って家の中でゆっくり本を・・という気持ちに
なかなかなれなくなってしまって。
~なんて言い訳は、この位にして。
この 「良人の貞操」 は以前にも触れましたが、
少々珍しい題名です。「妻の貞操」 はそうでもありませんが。
でも、貞操という言葉自体、
現在では死語になりつつあるのでしょうね。
ある意味、素敵な言葉に思いますけれど。
この小説の時代設定は昭和12年。
当時にすれば、画期的な題名ではなかったのでしょうか。
貞操は女性だけに求められ、男性にまで・・
という社会通念はなかった筈ですから。
この作品は、未亡人の恋を描き、
そこに女の人間としての姿を見ようとした・・。
所謂(いわゆる)、「良人の貞操」 という題名の中で
未亡人の貞操を描いたのでしょう。
図(はか)らずも今日の引用文は、その未亡人(加代)と
邦子の良人(信也)の会話になってしまいました。
加代は色々な事に造詣が深いものですから、つい。
だからと言って加代の方に共鳴した訳ではありません。
妻の邦子の方が私は好きです。
邦子は信也と加代の間に出来た子供を引き取り、
自分の子として育てるという、本当に出来た女性。
そうそう、話が前後してしまいましたが、邦子と加代は親友です。
このパターンは、今でも良くある事ですが、
当然の事ながら1番悪いのは、信也ですね。
邦子の気持ちは、いかばかりだったでしょう。
それにしても、こんな内容の小説でしたら、
ドロドロしたもので、後味の悪いものになったに違いありません。
不思議な事に吉屋信子の作品にはそれがありません。
寧ろ爽やかささえ感じて。
春ですから春物に模様替えをしようと思ったのですが、
セピア色の部屋もあった方がいいかも・・と思い直しました。
今日は、手描きの薔薇に囲まれて。
次は同じく吉屋信子の 「家庭日記」 です。









