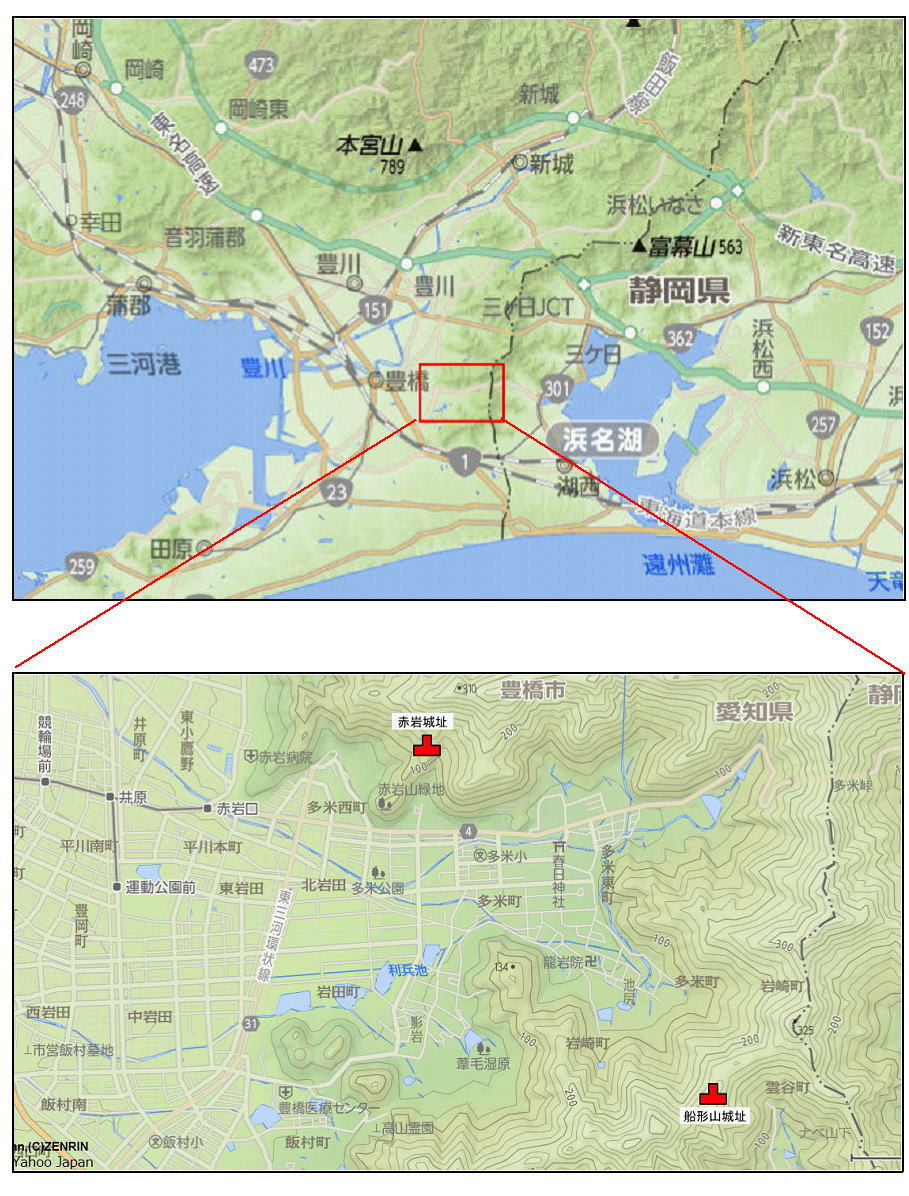工事が終わった後に
10月31日、西尾城に出かけました。というのは、前に行ったときは工事中だったのが、どうなったのか、知りたくなったからです。
過去の記事 西尾城 西尾市


2013年9月に訪れた時の公園の様子。看板によると、平成26年(2014)1月23日には、工事が終了しているので、何かできているはずです。
二の丸を復元
行ってみると工事中の柵はなくなっていて、広々とした芝生公園になっていました。そして、そこは二の丸を復元していたのです。

できた二の丸跡公園の案内図
スマホでCGが見れる
左下に「スマホアプリで石垣の上に西尾城がよみがえる」とあります。テレビで姫路城でもスマホでいろんな場面を復元して見ることができるということをやっていました。今どきは、CGの時代なんだと思いました。しかし、私はスマホを持っていないので、残念ながらCGの西尾城を見ることはできませんでした。
天守台と櫓台を復元
西尾城は、本丸ではなく二の丸に天守閣があったということで有名ですが、その天守台および二の丸の丑寅櫓台が復元されていました。

丑寅櫓台

天守台全景 天主は二の丸の北西に造られていたようです。
石垣の石は、ほとんどが他から持ってきた石ですが、発掘によって出てきた石もあるそうです。

中央の石は、発掘で出てきた石を石垣に使っているそうです。
ということで、やっぱりスマホが必要だなと考えさせられました。
10月31日、西尾城に出かけました。というのは、前に行ったときは工事中だったのが、どうなったのか、知りたくなったからです。
過去の記事 西尾城 西尾市


2013年9月に訪れた時の公園の様子。看板によると、平成26年(2014)1月23日には、工事が終了しているので、何かできているはずです。
二の丸を復元
行ってみると工事中の柵はなくなっていて、広々とした芝生公園になっていました。そして、そこは二の丸を復元していたのです。

できた二の丸跡公園の案内図
スマホでCGが見れる
左下に「スマホアプリで石垣の上に西尾城がよみがえる」とあります。テレビで姫路城でもスマホでいろんな場面を復元して見ることができるということをやっていました。今どきは、CGの時代なんだと思いました。しかし、私はスマホを持っていないので、残念ながらCGの西尾城を見ることはできませんでした。
天守台と櫓台を復元
西尾城は、本丸ではなく二の丸に天守閣があったということで有名ですが、その天守台および二の丸の丑寅櫓台が復元されていました。

丑寅櫓台

天守台全景 天主は二の丸の北西に造られていたようです。
石垣の石は、ほとんどが他から持ってきた石ですが、発掘によって出てきた石もあるそうです。

中央の石は、発掘で出てきた石を石垣に使っているそうです。
ということで、やっぱりスマホが必要だなと考えさせられました。