鳥と魚の大戦争/世界むかし話 太平洋諸島/光吉夏弥・訳/ほるぷ出版/1989年初版
あまり昔話のパターンに見られないミクロネシアの話です。
むかし魚と鳥のあいだに大戦争が起こりました。年よりの鳥が言うには、どうやら争いの原因は割れたヤシの実を鳥がつっついていると、ヤシの実が流され、それを飢えた魚たちが、それをさらっていったというもの。
しかし、小さい魚はどうして争わなければならないか原因がわかりません。
大きな魚は「原因などどうでもいい。ただ、戦えばいいんだ」といいます。
争っている相手がよくわからなくて、魚同士、鳥同士が殺しあうことも。
クジラとオオダコの争いも、なんで争っているかわからず、何時間も争う始末。やっと、味方同士であることがわかると、ばかばかしくなって、どこかへ、行ってしまいます。
「戦争」には、サメやヒラメ、カニ、ウニ、エイ、ウミガメ、ワシ、トリ貝などが戦う場面もでてきます。
やがて争いはやみますが、今度は、戦争をしなかった者をせめます。争いの間中、何もしなかったマスやオオコウモリを卑怯者と呼びます。
どっちが勝ったのかだれにもわからず、たくさんの命が失われたということだけが残ります。
「この戦争は、戦うだけのねうちがあったのだろうか」と無理にたたかわされた小さい鳥がいいます。
このお話、戦争がはじまると、戦うことだけが目的で、それに疑問をもつことがゆるされなかったり、身内の「卑怯者」をせめるところなど現実の世界を風刺しているようで、身につまされます。
昔話にこのような話があると、あらためて昔話の魅力に引き込まれます。ただ「戦争」というのが、あまりにもリアルすぎて、語るには少し工夫が必要なのかもしれません。
木の上にすむ子どもたち/オクスフォード世界の民話と伝説 アフリカ編/キャスリー・アーノット・著 矢崎源九郎・訳/講談社/1978年改訂第一刷
解説ではタンガニーカ(タンザニア)のカンバ族の話となっている。
父親に男の子が二人、女の子が一人。こうした出だしだと、女の子かまたは末の子が活躍するのが昔話のパターンであるが、この話では、父親が最後まで存在感がある。男親の影が薄い昔話で、こうした話があるとほっとする。
おくさんを亡くした男は畑仕事をしたり、狩りをしたりと子どもたちを育てるのに一生懸命。そして、けだものや魔法使いに魔法をかけられないように、大きな木の上に家をつくる。子どもたちは木の上の家に大満足。
父親が仕事にでかけたら、家にのぼる縄梯子を引き上げて、かえってきて約束の歌を歌ったら縄梯子を下すように子どもたちに話す。
ある日、魔法使いやってくるが、声が違っていることに気がついた子どもたちが丸太を下に投げ下ろすと、魔法使いはにげていってしまう。
二度目も子どもたちに気がつかれて魔法使いは縄梯子をのぼることができない。
二度の失敗に魔法使いも考えて、アリやクロアリ、サソリの力をかりて父親と同じ声になり、子どもたちを自分の家に連れ帰る。
家に帰ってきた父親は、子どもたちがいないことにすぐ気づき、まじない師の力をかりて子どもたちの居場所を突き止め、この魔法使いから子どもを助け出すことに成功します。
魔法使いが縄梯子を使わないと木の上の家にたどりつけないのはご愛嬌だが、魔法使いが子どもを連れて行くのは、食べるためではなく、こき使うためというのが面白い。
また、この魔法使い、なかなかいいところがあって、父親に矢で心臓を打ち抜かれたときに、遺言?を残し、遺言どうりすると、魔法使いに食べられたウシ、ヤギ、ヒツジ、人間までが次々とでてくる。
木の上に家をつくるのは、森の中でどうもうな動物から身を守るための知恵で、不思議はない。
魔法使いがアリやクロアリ、サソリの力をかりて父親と同じ声になるというのもアフリカらしい。
また、まじない師が石と種がはいっているヒョウタンをふって、石と種の落ち具合をみて、子どもたちの居場所を発見するのも、ところかわれば、まじないの仕方もかわるということのようだ。
 |
ふしぎな はなや/竹下文子・作 杉浦範茂・絵/フレーベル館/2008年初版
けんたくんのうちは代々続く花屋さん。どのページにも花がいっぱい。それもあまり見たことのない花ばかり。
つんとすました奥さんがくると、おかあさんはウィンク。すると店中の花が花びらを閉じて居眠り。
たばこをふかした紳士がくるとおかあさんはまたウィンク。すると紳士のたばこは飴にかわってしまいます。
花を愛している人にしか売らない不思議な花屋さん。
けんたくんがおとうさんの温室を探検にいくと、小鳥や蝶々がいて、さらにおくにいくとジャングルがあって、そこにはなんとライオンが。
ライオンは花をたべないから安心だ。いもむしのほうがずっとこわいとおとうさんは平気な顔。
花屋なんて女の子みたいといっていたけんたくんも、いろんな花がさいて、いろんな人が買いに来て、おおいそがしの花屋さんになってもいいなあとこのごろ思います。
じつは、このお店は魔法使いの花屋さんです。
けんたくんも魔法使いになったのかどうかはわかりません。
ねこのようなライオンの絵がとってもかわいらしく描かれています。
親が仕事をしているのをいつでも身近にみることができるけんたくんは幸せかも。
 |
つぎはぎ おばあさん きょうも おおいそがし/たかしま なおこ/講談社/2007年初版
なくなったおじいさんや家をでていったこどもとの思い出がたくさんつまった布で、家じゅうのものをつぎはぎでリフォームしてしまったおばあさん。
手を動かすことが大好きなおばあさんが、郵便屋さんのくたびれたカバンをみて、つぎはぎしてあげると、仲間の郵便屋さんもつぎつぎにやってきて、カバンは素敵になります。今度は、郵便屋さんのカバンをみた町の人たちが、おおぜいやってきてつぎはぎがおおはやりです。
おばあさんは丘の上のちいさな家に「おばあさんのおみせ」という看板をだします。次から次へと人々がきて、ちいさなお店はきょうもにぎやかです。
少し昔、ものがなかった頃、つぎはぎは当たり前。でも、いつの間にかつぎはぎもなくなり、少しくたびれると買い替えが当然のようになりました。でも、パッチワークというとしゃれた感じで、今風です。
裏表紙の前には、お婆さんの夢?がつまった写真がかざられています、パッチワークの洋服、バッグはもちろん、おじいさんとの写真のほかに、船の帆や気球、きりんのマフラー、子どもたちがなかよくパッチワークしているものなどなど。
丘の上のちいさなお家に、ねこ、いぬと静かに暮らすおばあさんのところには、たまに郵便屋さんがやってくるだけというでだしと、おおいそがしのお店の落差が何ともいえない。
 |
むかしのこども/五味太郎/ブロンズ新社/1998年初版
絵本のお値段は1千円以上とやや高め。
いろいろ読んであげたいと思っても何冊も購入するのは負担になる金額。これには図書館が最適。種類も数も多い。その中から気に入った絵本を購入するのが賢明のようである。
時々、車や住宅のシェアが話題になることが多いが、図書館では昔からシェアしてきていますね。
この絵本は出版年が1998年で15年ほどたっているが、同じような年に出版されているものでもそれほど借り出されていないのに、この絵本の借り出し回数は断トツで、それだけ人気があるということ。
「むかしのこどもは」とはじまります。
・はやくおきなさい! ぐずぐずしないで!といわれ
・学校のはじまりの時間におくれるとおこられます
・先生がきめたことを、おもしろくてもおもしろくなくても、わかってもわからなくてもまじめにやりました
・学校は努力、がんばれがんばれでした
・いやなことつまらないことでもすすんでやるようにさせられました
・・・
・・・
・雑をごまかすためのいりいろなきまりがあちこちにあったので、こどもはあちこちでおこられました。雑におこられた。
こんなところで、なんでおこられるんだろうというのがよくありました。「むかしの暮らし」は雑なのでした。
・むかしのこどもはいろいろなことがあまりよくわかりませんでした。大人が丁寧にお話したり、おしらせしなかったからです。
こどもは小さいし、ぼんやりしているから、ま、適当でいいだろうと、むかしの大人がかんがえていたからです。
今年の流行語の“今でしょ”がピッタリの、いろいろと大変な状況におかれている子どもたちへの暖かいまなざしと、身勝手な大人への風刺がきいていて人気があるのがよくわかります。
“おやおや” ”やれやれ”がうまく使われていてスパイスもきいています。
ホジャじいさんはトルコ、ゴハじいさんはエジプトの昔話の主人公。
日本でいえば、彦一、吉四六、一休さんといったところか。引用が長くなるが、いくつか抜き出してみた。
彦一、吉四六話は、歴史として比較的あたらし、く藤沢衛彦著「図説日本民俗学全集2」によれば「江戸時代の辻講談や落語家が創作した、時代を反映した創作民話といってよくフィクションがそのまま聞き手にとられて、地方にもって帰られその郷土にいついて、新しい民話の構成をとったものである。例証としては、大阪の噺家彦八が話した「彦八話」が、江戸・兵庫に移入されてはそのまま「彦八話」であったが、九州に移入されでは、「彦八話」「彦一話」「吉四六話」として伝承されていたことである。」と記されているという。
また、吉四六話は、明治時代に地方から伝承を寄せ集めて編纂し、地方紙が読み物としての連載を始めたことで、県民にあまねく広まった。全国区となったのは、昭和50年代のアニメ『一休さん』で巻き起こったとんちブームと呼べる現象と、アニメ『まんが日本昔ばなし』のヒットによって起きた昔話ブームであり、出版各社がこぞって児童文学の中にとんち話や昔話を題材に採り入れたことが大きい。吉四六は、彦一とともにその中で開拓された人物である。そして、国語科教科書にも採用されたこともあって、世間でもよく知られる存在となった。
ホジャじいさん、ゴハじいさんは、ときにかしこく、ときにまぬけ、そしてときには道化役であるが、国によって呼び名がことなり、ホジャ、ゴハは同様のキャクターとして登場しているという。
 |
みずならのいのち/手島圭三郎/リブリオ出版/2008年初版
“みずなら”の木をこの絵本で知ることができました。
近い種類にコナラやクヌギがあるが、寒冷な気候を好み、鹿児島県から北は北海道まで分布するという落葉樹。
高さは、大きなものでは35 mに達する。
5-6月に花を咲かせ、秋にはどんぐりが。このどんぐり、近年までは食用にもされていたという。
高級家具、建築材、洋酒樽などのほか、コナラと同様にシタケの原木などに利用されているという。
***
しまりすが冬の食料として蓄えておいたどんぐりが芽をだします。
100年たって、しずかな秋の日にぽとんぽとんと、どんぐりを落とします。
どんぐりは、えぞしか、しまりす、えぞりす、かけすの大切な食べ物。
200年たつと幹にうろこができて、ふくろうの巣穴に。この巣穴のなかから、子どもたちが巣立ちます。
300年たって、ねもとにできたうろはひぐまの冬籠りの場所に。このうろから子どもたちが巣立ちます。
400年、5000年。山火事にもあいますが、風向きがかわって難をのがれます
600年たつとみずならは力の衰えを感じます。台風がきて、幹のうろがおれてしまいます。半分のからだになったみずならは、どんぐりも落とせなくなくなります。
うさぎがきつねにつかまってしまうのをみたみずならは、木にうまれてきたことをよかったとつくづく思います。
700年、800年たったみずならは、長い命に満足します。
***
力強い版画で描かれた“みずなら”の悠久の営みに、人間の小ささをあらためて思い知らされます。
地球温暖化は産業革命以降、少しづつ進行してきたが、“みずなら“の寿命からすれば、つい最近のこと。
自然のいのちに思いをめぐらせたら、やはり人間のおごりで破壊してはならないと思う。
チベットの民話/W・F・オコナー編 金子民雄・訳/白水社/1999年新装復刊
「アリババと40人の盗賊」の“開け ごま”は何となくワクワク感がある。なぜか他の言葉でなく、“ごま”と穀物の名前が出てくるのか不思議。
子どものころ、こんな類の言葉があったらいいなと思ったことも度々あったような記憶がある。アラビアにちかいチベットのまじないの言葉、それも何かを開けるというのに、いくつか面白いものが。
・ルーム・バチャとバキの物語
“大きな鸚鵡、戸を開けろ“
人食い鬼につかまった若い王子が、洞窟に閉じ込められてしまい、そこで一人の女性とあう。人食い鬼をほろぼすために、このまじないが重要な言葉になる。
・王子と食人鬼の城
“開け、白い壁“
一人の王子が人食い鬼の人質になって城におもむくが、そこに閉じ込められていた婦人から、人食い鬼をほろぼすためにいくつかのアドバイスをうける。そのときにこの言葉がでてくる。
この話がのっている本の訳は、残念ながら語りに適していないのが難点であるが、まじないの言葉だけは、奇妙に印象にのこる。
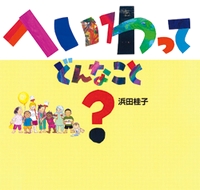 |
へいわってどんなこと?/浜田桂子/童心社/2011年初版
ユーチューブで5歳の娘さんが朗読している動画で見ることができました。
シリアでいまも続く内戦。
あまり報道されていないが、今もこの世界のどこかで、殺し合いが続いています。
日本はさきの戦争が終わってから、殺し、殺されたりしない数少ない国であることに、あらためて思いをめぐらす必要があります。
憲法改正や集団自衛権、秘密保護法案など、きなくさい動きがある今、平和は一人一人の努力で守っていくことが必要に思う。
こどもの視点で描かれているが、何かと理由をくっつけて、言葉を捻じ曲げてしまう大人にこそ、「絶対に、殺したらいけない。 殺されたらいけない。武器なんかいらない」という言葉を味わってもらいたいものです。
金の魚/ウズベクのむかしばなし/鈴木陽子ほか訳/新読書社/2000年初版
カップル誕生の話では、貧しい若者が王女と結婚するか、またその逆の組み合わせがあるが、結末としてはそのあと何不自由なく暮らすというイメージがある。
「金の魚」では貧しい漁師の息子が、生まれてから一度もしゃべらない領主の姫をすくい、結婚するという話であるが、この話の面白いところはその結末。
領主にうとんじられた漁師の息子が、そこにいずらくなって、年とった父親のところにもどるという結末。
おひめさまも息子が故郷にかえりたいという思いをうけとめるあたりは、他の昔話にあまりないものとなっている。
父親の存在感が希薄な昔話が多い中で、しっかりと役割をはたしているのもいい。
 |
まほうつかいのでし/文・大石真 絵・柳原良平/学習研究社/2007年初版
サントリーの広告でおなじみの柳原良平さんの絵というので手に取ってみました。絵は柳原さんの特徴がよくでています。
ドイツの昔話に同じ話があるというのですが・・・・・。
いつになっても、魔法の呪文をおしえてもらえないオトールという魔法使いの弟子の仕事は、家の掃除や畠の仕事ばかり。それでは先生の魔法をぬすんでやろうと、先生の使う呪文をぬすみぎき。3年たって先生は、お風呂の支度をしておいてくれと言いのこし、でかけていきます。3年のあいだに覚えた呪文をためしてみる絶好の機会。
鳥になって大空を飛んだり、魚や虎になったり、お腹がすくとごちそうをとりだして食べたり。
夕方、風呂の支度を忘れていたことに気がつくと、今度は、古ぼうきにバケツを持たせて川の水をお風呂のなかへ。ところがふるぼうきの水汲みをやめさせる呪文が思い出せず、水はお風呂からあふれだします。
いくらたってもふるぼうきが水汲みをやめようとしないので、オトールはふるぼうきをまっぷたつにしますが、ふるぼうきは、二つに。あわてたオトールがまさかりでふるぼうきにきりつけると、ふるぼうきの数はどんどん増え始めます。
どうしようとがたがた震えていたところへ先生がかえってきて呪文をとなえると、またもとどうりに。
ちいさいころ魔法が使えたらと思ったことはなかったでしょうか。魔法という言葉は、あり得ないとわかっていても惹きつけられます。
「とりに なれ、とりに なれ、おおぞらを とぶ とりに なれ」
「ひたひた さらさら ながれよ あふれよ。ふろの 水汲みできるまで」
「とまれ とまれ ふるぼうき おまえのはたらき たしかに みたぞ・・・」
こうした呪文は、リズム感があって、おもわず唱えたくなります。
弟子が様々に変身した絵がほのぼのとしたものになっています。
2013.11.17
第六回とありました。
お寺が会場で、副住職さんの法話もあるというユニークなおはなし会でした。
1 大うそつき(子どもに語るアジアの昔話2 こぐま社)
2 ぬか福と米福(おはなしのろうそく13 東京子ども図書館)
3 石になった狩人(子どもに語るモンゴルの昔話 こぐま社)
4 金の髪(おはなしのろうそく19 東京子ども図書館)
5 へやの起こり(日本昔話百選改訂新版 三省堂)
6 クルミわりのケイト(おはなしのろうそく10 東京子ども図書館)
静かな雰囲気で、ゆったりと聞けました。語る場所も先入観で決めつけることはなさそうです
ビルマのむかしばなし/中村祐子他訳/新読書社/1999年初版
ネットで検索してもでてこないのはめずらしいが、ドラゴンナガというのが登場します。
「ドラゴン王女と三つの卵」の中では、王女の親として出てきます。この王女は太陽の神様と結婚し、三つの卵を産むが、一つ目の卵からはルビーが、二つ目からは虎が、そして三つ目からはワニがでてくるという話。
「ハシバミ鳥」では、海の支配者として現れ、ライオンと力比べをして勝ち、ライオンをむさぼり食うことになるが、大ベータ鳥があらわれ、ドラゴンは深い海に逃げるという話。
「ウサギの鼻はなぜ動く?」では、いい気持ちで寝ていたドラゴンが「おれさまを起こす奴は誰だ」とキュウリや猪、蛇、鴨、ゴマ、かぼちゃ、ウサギを問い詰めます。
「シャパルダー」では、うそつきのシャパルダーを川底から救いだし、空を飛ぶ象までプレゼントするという役割。
「モンポクチャン」では、王女の恋人として出てきますが、主人公からあっさりと殺されてしまうという役どころ。
つかみどころがない存在ですが、多くの昔話にでてくるのをみると、ミャンマーの昔話では、存在感のある登場人物?でしょうか。
ミャンマーの絵本をみるともう少しイメージがわくかも知れません。
先輩?と同じように語るというのは無理とわかっているので、とにかく時間をかけて覚えることに。今は、一つの話だけだと飽きがくるので、複数の話を同時並行でおぼえることにしている。
それでも、とにかく短い話を覚えてみようと取り組んで、人の前で話してみても、今度は大勢の前で話をすると覚えたつもりの内容がとんでしまい散々。
しかし、たまには、それほど読み込まなくても頭の中にすーとはいってくる話もあって不思議な感じがしています。
テキストのことで先輩と話していたら、お話のほうが人を選ぶといわれて、なにか妙に納得した気持ちになりました。
素通りしていた話を他の人が語ると、これが絶妙で聞いていて本当に楽しくなるという経験もしている。
話し手の個性とぴったりあったお話を聞くと何かあったかい気持ちになれる。
そういえば、著名?な語り手の話を聞く機会もあって勉強になるが、かならずしも全部が良いということにならず、違和感もおぼえることがあるのは、その話が語り手を選んでいるのかもしれない。

















