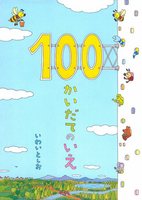・山の上の火(エチオピア)(山の上の火/クーランダー、レスロー・文 渡辺茂男・訳/岩波書店/1963年初版)
あるお金持ちが気まぐれで、冷たい風の吹く山の高い峰で、裸のまま、飲まず食わず一晩過ごすことができたら、土地、家、家畜をやろうとアルハという男にもちかけます。
アルハが賢い老人のところに相談に行くと、老人は山からみえるところで、火をたくから、一晩中火から目を離さないようにしなさいという。
アルハは老人の言うとおり、金持ちの召使いがみつめるなかで、骨の髄まで凍らせるような寒さの中、遠くの方のたき火をじっとみつめ一晩をすごします。
しかし金持ちはいざ土地をあげるとなると惜しくなり、アルハを救ったのはたき火で、条件を守らなかったから賭けは自分の勝ちと宣言する。納得のいかないアルハが、裁判所に訴えるが、裁判官もアルハの負けを宣告。
そこで老人は、アルハをハイルという男に紹介します。
ハイルは、金持ちや裁判官を宴会に招待する。台所からのすてきな食べ物のにおいが流れてくるが、いくらまっても料理がでてこない。招待された客は、なんでこんな風に扱うかと切り出すが、ハイルは、「食べ物がにおうだろう」「遠くのほうにある火で暖まることができるものか? もし、山の上に立っている間、見つめていた火で、暖まれたとするなら、あなたがたは、台所から流れてくるにおいで満腹したはず。」とこたえます。
金持ちも裁判官も自分の誤りにきがつき、土地、家、家畜はアルハのものになるという結末。
完全な瞑想の境地に達すると痛さを感じないようなので、遠くの火を見つめ寒さに耐えるのも実際にありそうです。
・ホジャどんのしっぺがえし(トルコの民話/ギュンセリ・オズギュル 再話・絵 ながたまちこ 訳/ほるぷ出版/1983年初版)
トルコの昔話ではおなじみのホジャ。
「山の上の火」と同じ話型なのですが、丁寧に描かれた絵がトルコの昔の村の雰囲気をよく表しています。
文章だけではなかなか想像できませんが、さすがに、その国の人が描くとイメージがふくらみます。
みんな帽子。家の中ではジュータンに座っています。
トルコのある村に住んでいるとてもとんちのあるおじいさん。みんなから“ホジャ(先生)どん”と呼ばれていました。
冬の寒い夜、長者どんのうちへごちそうに呼ばれ、若い衆が寒さを嘆いていました。
そこで、ホジャどん「このくらいのさむさで なにをいうだね。わしゃ、せたけほどもつもった 大雪の日だって、となり村まであるいていったもんじゃ」と自慢します。
これを聞いた長者どんは、「そんなに自慢するなら、つよいところをみせておくれ。一つ賭けをしよう。村はずれのひろばで、火なしで朝まで我慢できたら またたんとごちそうするわい。だけど我慢できなかったら、ホジャどん、あんたのおごりだよ」
ホジャどんは、火の気無しでひろばの木の下で一晩すごすことになります。
夜がふけていくと、ホジャどんは眠ってしまいます。見張りについていた若い衆が、朝までつきあうのはかなわんと、一計を案じます。
眠っていたホジャどんをおこし、遠くの家にあるローソクの火でぬくまって、いびきをかいていたのでホジャどんの負けと宣言します。
ホジャどんは、「どうして1キロも離れたローソクの火であたたまることができるんかね」と文句をいいますが、若い衆はあいてにせず、とうとうごちそうを振る舞うことになります。
若い衆がホジャどんの家にいってごちそうをまっていましたが、なかなか出てきません・・・・。
なにしろホジャどんローソクでスープが煮えるのをまっていたからです。
会話の部分に味のある訳です。
・アブヌワス(お日さまと世界をまわろう/多賀谷千恵子 訳/ぬぷん児童図書出版/1992年初版)
サウジアラビアの昔話。
アブヌワスという主人公の、いくつかのエピソードの中の一つ。
こじきが、風下にすわって、商人の家のごちそうが料理されている間、においをかぐ。
次の日、こじきが、「おかげでたっぷりごちそうになった気がしましたよ」と話すと、商人は、料理のにおいを盗んだという理由で王さまに訴える。
王さまは、こじきに12枚の銀貨を支払うよう命じる。
もとより銀貨などもたないこじきは、アブヌワスという男に相談する。アブヌワスは、こじきに銀貨を地面に投げるよういう。こじきが銀貨を投げるとチリンチリンと音がする。
アブヌワスは、「この音を聞いたか」と商人にたずね「もしも、人が、においをかぐことで食べ物を台無しにするなら、お金の音を聞くことで支払いを受け取ることもできるだろうよ」
においをかいだことをわざわざ言うのは、何もくれようとしない金持ちの商人への皮肉でしょうか。
・アブヌワスのかしこいはからい(大人と子どものための世界のむかし話13/タンザニアのむかし話/宮本正興:編訳/偕成社/1991年)
アブヌワスが主人公というのはサウジアラビアにかぎらないようです。
あるお金持ちが気まぐれで、氷の張った池のなかに、一晩中つかっていることができたら、おまえに一万ディナールをくれてやろうと貧乏人の子どもにいいました。
貧乏人の子どもはお金がもらえるならと氷の張った池に、一晩つかることにしました。
母親は子どもの覚悟を知ると、池のほとりで夜通し火を焚いて、明るくしてやります。
子どもは氷の張った池に一晩つかり、お金持ちのところへ行って、一万ディナールをくれるようにいいますが、お金持ちは、母親が火をたいていたのは、からだをあたためるためだと とりあいません。
子どもがアブヌワスに相談すると、一万ディナールのうち、三千ディナールくれるならと要求します。そしてまず王さまに相談するようにいいます。ところが王さまは子どもの言い分は認めません。
そこで、アブヌワスは市場であらゆるごちそうの材料を買い込んできました。そして王さまをふくむ たくさんの人々をごちそうにまねきます。
ところが夕方までたっても、料理どころかコーヒーのいっぱいもでてきません。まちきれなくてみんなが台所をのぞくと、火はぼうぼうもえていますが、肉や野菜が入った鍋は火の上にのっかっていませんでした。
王さまは、これではいつまでまっても料理ができないと、はらをたててどなりました。
アブヌワスは、「母親があかりをてらすためにかざしてくれた火で、子どものからだがあたたまったというならば、料理だって火の上にのっていなくても、とっくに煮えていたはずではありませんか」といいます。
王さまはアブヌワスのいうとおりだと思い、子どもの権利を認め、金持ちに一万ディナールをわたすように命令します。そのあとアブヌワスは、いそいで料理をこしらえ、みんなは結構なごちそうにありつきました。
このアブヌワスはちゃっかりした男で、ひそかに分け前を要求してから仕事にかかっています。
・男が娘に結婚を申し込む(カンボジアの民話世界/高橋宏明 編訳/めこん/2003年初版)
題名通り男が結婚を申し込むが、結婚したいなら3晩の間、紐でしばられたままじっと水に浸かっていなさいと娘の両親から注文をつけられます。
二晩たったとき、男は遠くの山で火が燃えているのを見つけ、水に浸かったままで寒くなった男は、ふざけて火にあたるふりをする。
ところがそれをみた娘の両親は火にあたったことを理由に結婚をことわります。不満をもった男は裁判官に不平を申し立てますが、娘の両親から賄賂をもらった裁判官は約束を守らなかったから娘と結婚できない、裁判報酬として食べ物をもってくるように命じます。
男が泣きながら歩いているとうさぎの裁判官にであいます。
うさぎの裁判官は、男に食べ物を用意するとき、塩を入れないように知恵をつけます。
さて料理を裁判官のところにもっていったとき、そのそばに塩をおいておきます。裁判官がどうして塩をいれないかたずねると、うさぎの裁判官は答えます。
「山の頂上で火事がおき、この男が火にあったまったというなら、そばにおいてある塩がどうして料理を塩味にしないことがあるだろうか」
「山の上の火」では、料理のにおいがでてくるが、カンボジア版では、料理にかかせない塩がでてくる。
さらに、男に知恵をつけるのが、ウサギの裁判官というのがカンボジア版らしい。
しかし、古い歴史をもつ国に同じような話があるのは興味深い。
落語にも同じようなのがあったかも。