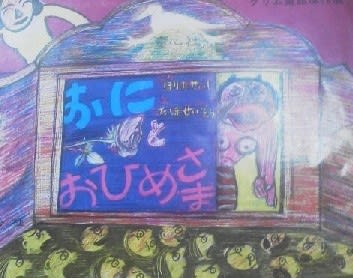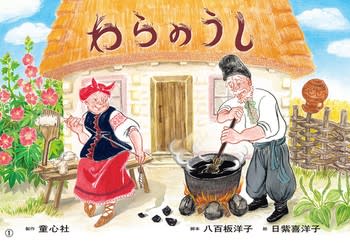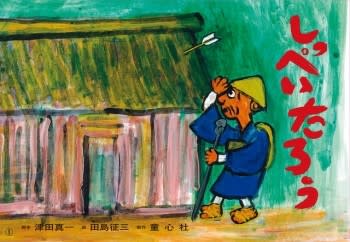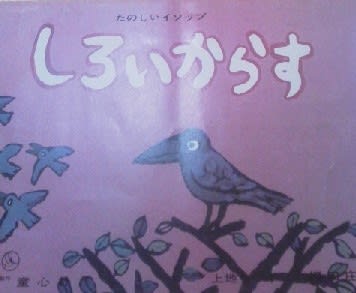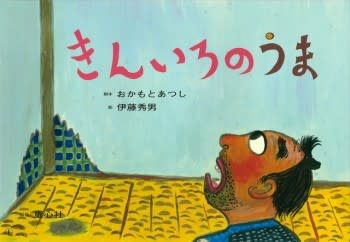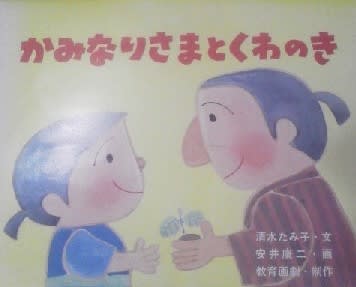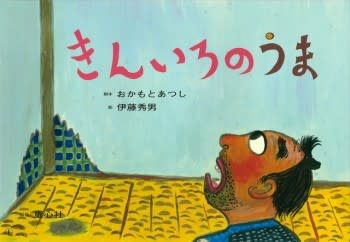
きんいろのうま/脚本・おかもとあつし 絵・伊藤秀男/童心社/2017年(12画面)
「むかしむかし とさの あるむら」とはじまるので、高知の昔話がもとになっているのでしょうか。
ある大晦日かの晩、貧乏で怠け者の吾作のまえに貧乏神があらわれ、「ながいこと せわになっていたが これからいいところへ つれてやってやろう。」と、ひらひらと雪の舞う山のふもとへつれていきました。
シャラリン シャラリンとなにかが 近づいた音がして、金色の馬がやってくると、貧乏神が馬を捕まえるようにいいます。馬はやまのようなたからものを積んでいましたが、みたこともない たからものをみて からだが がちがちで うごけないうちに 馬は とおりすぎていってしもうた。
つぎに、すずのねを ひびかせて 銀色の馬がやってきました。貧乏神は、吾作に捕まえるよう 大声でさけびますが、たからものに目がくらんだ吾作が、まごまごしているうちに、銀色の馬も とおりすぎていきました。そのとき、「コケコッコー」と一番どりの声が聞こえてきて、貧乏神は よその家に いくからと あたふたと 姿をけしました。
おしいことをしたをしたとつぶやく吾作のまえに、こんどは鉛色の馬がやってきました。こんどはなんとか 馬をおさえこみました。鉛色の馬は、たからものはつんでいなかったが、暮らしに役立つ道具や 食べ物を どっさりと つんでおった。
つぎの日、馬は吾作の着物をくわえてたんぼにつれていき、吾作と一緒に 田植えの準備をした。夕方家にもどると、藁束を おしつけてくるので 吾作は、馬小屋の掃除。よくよくみてみると藁の中に 小判。それからというもの、朝から晩まで せいだして働いた時には、小判があるが、なまけると ない。吾作は 馬と一緒に わき目もふらずに働いたので、すっかり 豊かになっていった。
そして月がうつくしい十五夜の晩、なにか音がするので、吾作が馬小屋へ行ってみると、馬がうれしそうに からだを すりよせてきて、ヒヒーンとなくと 金色の馬にかわって、地面を ちからいっぱいけると 月をめがけて 一目散に かけのぼっていった。
なまけものの吾作が働き者になったのを見て、鉛色の馬も 安心して 天に かえっていったもんよのう。
大晦日と貧乏神も、昔話にかかせない組み合わせです。