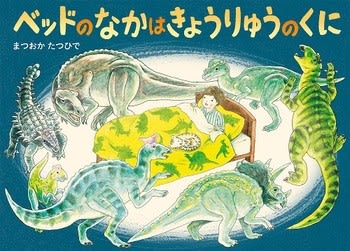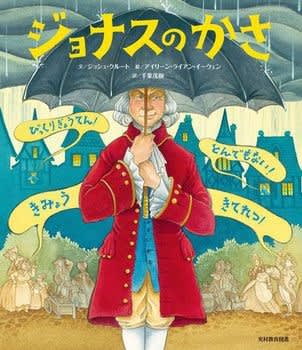誰もが知っている?「花さかじい」ですが、地域や作者によっていろいろなバージョンがあり、さらに絵本も多いので、語る場合は、どれをテキストにするか悩む。
出だしの部分をいくつかあげると
・おじいさんが、つむぎを売りに行き、そのお金でいじめられていた犬を助ける(正月も近づいたころ)
・じさまがお寺まいりに行って串団子を土産に買って帰り、途中いじめられていた犬をこの串団子とひきかえに助ける。
・おばあさんが川に流れてきた柿を家にもちかえり、この柿を臼に入れておくと、子犬が食べてしまう。
・おばあさんが川に流れてきた桃を家にもちかえり、この桃を臼に入れておくと、犬が食べてしまう。
・おばあさんが川に洗濯に行くと、黒い箱と白い箱が流れてくる。白い箱をもちかえるとその中には、子犬がはいっている。
柿や桃がでてくるものがあるが、これは季節によって使い分けができそう。しかし、後半部分で、枯れ木に花を咲かす場面がでてくるので、時期は、晩秋から冬がふさわしいので、桃というのは少しくるしい。
・花さかじい(岐阜のむかし話/岐阜児童文学研究会編/日本標準/1978年)
おばあさんが、川でひろった柿。あまりにおいしいので、お爺さんにも食べさせようと臼においておくと、臼の中から子犬。おおきくなった犬が、ここほれ、ここほれというので、クワでほってみたら小判やたからもの。
意地の悪いおじいさんが、借りてきた臼をつくと、出てきたのはどろどろの水。
意地の悪いおじいさんが、臼をつくと、でてくるのは黒くなったもち。
ほかの話では、ちょとグロテスクなものがでてきますが、こお話しでは、すっきり受け入れやすい。
・むぎからおんじとそばからおんじ(岩手のむかし話/岩手県小学校国語教育研究会編/日本標準/1976年)
タイトルからはわかりませんが、「花咲か爺」型の話で、灰をまくと、花が咲くのではなく、雁がおちてきます。
でてくる人のネーミングが楽しい。魚を捕りにいって白い子犬を助けるでだし。犬の亡骸のところに植えるのは、「コメコノ木」(どんな木でしょうか)
雁が飛んでくるようすも、かぎになったり、さおになったりとイメージがふくらみます。
・かもとり(秋田のむかし話/秋田県国語教育研究会編/日本標準/1974年)
「むかしむかし、じっちゃは山へしば刈に、ばばは川さ、せんたくにいったど」と、「桃太郎」風の出だし。川から拾ったのは、白い子犬。このあとは「花さかじい」ふうの展開。
「花さかじい」では、臼の灰で、枯れ木に花が咲きますが、ここでじっちゃが灰をまくと、鴨の目に灰がはいって、鴨がバタバタと落ちてきて、鴨汁にして食べてしまう。一方へちょへちょじっちゃ(ずるくてけちんぼな じっちゃ)が灰をまくと、自分の目に入り、めがみえなくなってしまう。
・子犬をひろってしあわせになったじいさんの話(まめたろう/愛蔵版おはなしのろうそく10/東京子ども図書館/2010年(森口多里著「黄金の馬」三弥井書店)
花ではなく、雁がおちる話。
下の爺さんが小犬を助け、太郎と名前をつけます。ばあさんが、皿で食べさせれば皿ほどに、お椀たべさせればお椀ほどに、臼でたべさせれば臼のおおきさになった太郎。
やがて、太郎が山へ、下のじいさんと一緒にでかけます。太郎が「あっちの山さ、蜂落ちろ。こっちの山さ、鹿落ちろ」と叫ぶと、爺さんの方に鹿が落ちてきて、その日は鹿汁。
上の爺さんが、太郎を借りて、山へ行くと、落ちてきたのは蜂。上のじいさんは 怒って太郎をうちころしてしまいました。下のおじいさんが、打ち殺された太郎を埋めたあとに植えた木から、臼をつくり、餅をついていると、「金落ちろ、銭落ちろ」と、歌う声が聞こえてきて、じいさんの前に金、ばあさんの前に銭が落ちてきました。
上の爺さんが臼を燃やしてしまったあとの灰を空にふりまくと、雁がおちてきて、雁汁に。
上のばあさんが、厠の屋根から落ちたじいさんを、雁と間違って、しりをへらでたたいて、じいさんをたたきころすという忖度のない おわりかたをします。
雁が出てくる昔話は、「枯れ木に花」タイプより先行していたといいますが、いまは雁は禁猟。語る場合は、一言 必要でしょうか。
イギリスのユングによる世界童話全集2(川端康成 野上彰 編訳/偕成社文庫/1977年初版)のなかに、「花咲じい」がのっているが、ここでは、子どもがいない夫婦が、子犬を大事にかわいがっていたという出だし。
川端康成が名を連ねている童話集であるが、このタイトルが「うらやましがりやのとなりの人」とあって、副題に「花さかじい」とあるのは、訳者が日本の読者に配慮したものか。