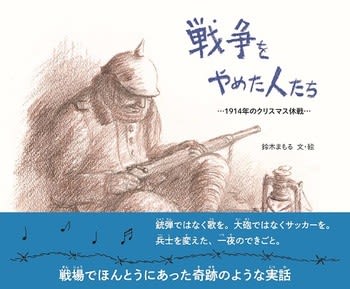冬至と夏至の頃、一年に2回開催されているピッコロさんの夜のお話し会。場所は、「食堂」。照明はろうそくだけ。語る雰囲気も落ち着いています。
お話が語られる場所というと学校、幼稚園、保育園、図書館などですが、食堂というのも珍しいのではないでしょうか。
お話し会は、お知らせをみて参加するケースがほとんどでしょうから、食事にきたら、お話し会というので、びっくりされた方もいたのではないかと思います。
大分前、遠野にでかけ、おもいがけず、囲炉裏のそばで、土地のことばで語られる昔話を聞く機会があって、気持ちが軽やかになったことがあります。
農業が主だった昔、日中は作業に追われ、昔話が語られたのは夜。囲炉裏を囲んで、または炬燵のなかで語られたのが普通だったのでしょうから、やっぱり原点は夜でしょうか。
長い歴史があるおはなし会で土日2回から土曜日(または日曜日)1回の開催にかわっています。
2024.12.20
1 歳神様(かたれやまんば1 藤田浩子の語りを聞く会)
2 ヘルムの雪(やぎと少年 岩波書店)
3 野ばら(小川未明童話集 童心社)
4 とんだぬけさく(山の上の火 岩波書店)
5 赤鬼エティン(愛蔵版おはなしのろうそく8 東京子ども図書館)
午後5時をすぎると真っ暗。午後7時半ごろからの開始ですが、時間帯によってお話しの雰囲気もかわってきます。
2024.6.21
1 あたごの浦(同名絵本 福音館書店)
2 えんどうまめの上のおひめさま(アンデルセン 同名絵本 小学館)
3 ふるやのもり(おはなしのろうそく4 東京子ども図書館)
4 雀の仇討(せんとくの金 山形とんと昔の会)
5 七羽のカラス(おはなしのろうそく10 東京子ども図書館)
6 まほうの馬(同名本 岩波書店)
ようやくの梅雨入り宣言。朝方から午後まで 雨でしたが 夕方からは晴れ。
2023.12.22
1 かさじぞう(同名絵本 福音館書店)
2 おいしいおかゆ(おはなしのろうそく1 東京子ども図書館)
3 北風をたずねていった男の子(子どもに語る北欧の昔話 こぐま社)
4 ほうまんの池のカッパ(同名絵本 BL出版)
5 お月さまの話(おはなしのろうそく25 東京子ども図書館)
6 やまなしもぎ(同名絵本 福音館書店)
7 ガミガミシアールと少年(ファージョン作 ムギと王さま 岩波書店)
風が冷たい一日。コロナで4年ぶりの開催。過ぎてしまえばあっというまの4年。それにしても時間のすぎるのが早い。
2019.12.21
1 かさじぞう(同名絵本 福音館書店)
2 熊の皮を着た男(子どもに語るグリムの昔話① こぐま社)
3 はん天をなくしたヒョウ(アニタ・ヒューエット著 「大きいゾウと小さいゾウ」 大日本図書)
4 くまとやまねこ(同名絵本 河出書房新社)
5 ねこの大王(瀬田貞二訳 世界のむかしばなし のら書店)
6 みどり色のつりがね(プロイスラー 偕成社)
7 ねむりひめ(同名絵本 福音館書店)
このごろ、19時過ぎは真っ暗。春が待ち遠しい時期です。はじめて聞いた「みどり色のつりがね」の中に小さな鈴がでてきますが、雪の中の鈴の音が聞こえてくるようでした。
2019.6.23
1 なんでも信じるおひめさま(ものいうなべ デンマーク 岩波書店)
2 徂徠どうふ(同名絵本 福音館書店)
3 ボタンインコ(ファージョン作 ムギと王さま 岩波書店)
4 まめじかカンチルが穴に落ちる話(おはなしのろうそく8 東京子ども図書館)
5 七羽のカラス(おはなしのろうそく10 東京子ども図書館)
6 金の髪(おはなしのろうそく19 東京子ども図書館)
7 せんとく金(江口ヨシノ とんと昔七十二話 山形とんと昔の会)
昨日は一日中雨、今日は一時雨で曇りの一日。先輩のどれも素敵な語りでした。
このところファージョンの作品を連続して聴く機会がありました。聴きたいと思ったときは聴けなくて、続くと連続するというのも面白い。
2018.12.22
1 ネズミのおおてがら(チベット おはなしのろうそく30 東京子ども図書館)
2 わらしべ三本(岡山 再話 丹波昔ばなし大学)
3 こびととくつや(子どもに語るグリムの昔話6 こぐま社)
4 せかいいちおいしいスープ(同名絵本 マーシャ・ブラウン 岩波書店)
5 ガミガミシアールと少年(ファージョン作 ムギと王さま 岩波書店)
6 十二人の異国人たち(バルバラ・バルトス=ヘップナー 新教出版社)
「クリスマスの贈り物-家庭のための詩とお話の本」
22日は冬至。17時にはもう真っ暗。移転した食堂で19時開始でした。この時期にぴったりのしっとりするおはなし会でした。「こびととくつや」も、この時期に聴くと感じ方がちがいます。
「十二人の異国人たち」は、朗読でしたが、戦争が継続する中での、素敵なクリスマスの贈り物の物語でした。
「わらしべ三本」は、わらしべ長者の岡山版ですが、やはり日本のものは欠かせません。
少年と頑固なおじいさんのほのぼのした交流、ねずみの大活躍のお話とバラエテイにとんでいました。
2018.6.23
1 たまごを売って子ぶたを買って(ブルガリア 吸血鬼の花嫁 福音館文庫)
2 浦島太郎(おはなしのろうそく25 東京子ども図書館)
3 ネギを植えた人(金素雲編 岩波少年年文庫)
4 小さいお嬢様のバラ(ファージョン作品集 ムギと王様 岩波書店)
5 カッパと瓜(おはなしのろうそく31 東京子ども図書館)
6 せかいいちうつくしいぼくの村(同名絵本 ポプラ社)
7 アリ・ムハメッドのお母さん(山室静編 新編世界むかし話集 文元社)
2017.12.26
1 コショウ菓子の焼けないおきさきと口琴のひけない王様の話(レアンダー作 ふしぎなオルガン 岩波少年文庫)
2 歳神様(かたれやまんば第一集 藤田浩子の語りを聞く会)
3 ねむりひめ(同名絵本 福音館書店)
4 ねずみの大てがら(チベットの昔話 おはなしのろうそく30)
5 カメの遠足(新編世界昔話集(1)イギリス編)
6 賢者の贈り物(オー・ヘンリー)
2016.12・18
1 あたごの浦(あたごの浦 福音館書店)
2 モミの木(アンデルセン原作 西村書店)
3 オフェリアと影の一座(魔法の学校 岩波書店)
4 大歳の火(日本昔話百選 三省堂)
2016.6.25
1 くわずにょうぼう(同名絵本 福音館書店)
2 ふるやのもり(おはなしのろうそく4 東京子ども図書館)
3 若返りの水(子どもに語る日本の昔話3 こぐま社)
4 ねずみのしゃもじ(女むかし 君川みち子再話集 ほうづきの会)
5 スミレの葉にもきずつく娘よ(トルコ お月さまより美しい娘 小峰書店)
2016・6.26
1 さるのひとりごと(同名絵本/童心社)
2 かしこいグレーテル(子どもに語るグリムの昔話2 こぐま社)
3 とりのみじい(日本)
4 兵士のハーモニカ(岩波少年文庫 岩波書店)
2015.12.20
1 北風に会いにいった少年(ノルウエー)
2 だめといわれてひっこむな(プロセイン作)
3 モミの木(アンデルセン)
4 カメの遠足(イギリス)
5 大工と鬼六(日本)
6 ねずみの小判干し(日本)
2015.6.20
1 火の鳥と王女ワシリーサ(子どもに語るロシアの昔話 こぐま社)
2 やせた王さまとふとったコックさん(こんどまたものがたり 岩波書店)
3 先におこった者の負け(子どもに語るイタリアの昔話 こぐま社)
4 みそかい橋(子どもに語る日本の昔話1 こぐま社)
2015.6.21
1 旅人馬(日本昔話百選 三省堂)
2 アディ・ニハスの英雄(エチオピア 山の上の火 岩波書店)
3 ラプンツェル(ねずの木・そのまわりにもグリムの話いろいろ2 岩波書店)
4 てんまのとらやん(たなかやすこさんの語りより)
2014.12.20
1 わらしべ長者(日本の昔話① はなさかじい 小澤昔ばなし研究所)
2 きりの国の王女(太陽の木の枝 福音館書店)
3 ふしぎなオルガン(レアンダー作 ふしぎなオルガン 岩波少年文庫)
4 貧乏神(子どもに語る日本の昔話2 こぐま社)
5 火の鳥と王女ワシリーサ(子どもに語るロシアの昔話 こぐま社)
2014.12.21
1 夢を買うた男(日本の昔話(1)岩波書店)
2 みみずの女王(村岡花子作 たんぽぽの目 河出書房新社)
3 十二の月のつきのおくりもの(スロバキア おはなしのろうそく2 東京子ども図書館)
4 ベニスの商人(シェークシピアより)
2013.12.21
1 妖精のぬりぐすり(イギリスとアイルランドの昔話 福音館書店)
2 ゆきんこ(ストーリングについて こども文庫の会)
3 つるにょうぼう(同名絵本 福音館書店)
4 ねずみのすもう(おはなしのろうそく18 東京子ども図書館)
5 夢見小僧(子どもに語る日本の昔話1 こぐま社)
2013.12.22
1 ブドーリネク(おはなしのろうそく1 東京子ども図書館)
2 ヤギとコオロギ(子どもに語るイタリアの昔話 こぐま社)
3 黄金の土(エチオピア 山の上の火 岩波書店)
4 まほうのかさ(同名絵本 福音館書店)
5 みどろいろのつりがね(同名絵本 偕成社)
2012.6.23
1 孫地蔵(語りつぎたい日本昔話7 舌切りすずめ 小峰書房)
2 四つの人形(子どもに語るアジアの昔話2 こぐま社)
3 豆の上に寝たお姫さま(子どもに語るアンデルセンのお話1 こぐま社)
4 小石投げの名人タオ・カム(子どもに語るアジアの昔話2 こぐま社)
2012.6.24
1 あゆはかみそり(子どもに語る日本の昔話3 こぐま社)
2 ボタンインコ(ファージョン作 ムギと王様 岩波書店)
3 だんまりくらべ(子どもに語るトルコの昔話 こぐま社)
4 妖精のぬりぐすり(イギリスとアイルランドの昔話 福音館書店)
5 水晶の小箱(子どもに語るイタリアの昔話 こぐま社)