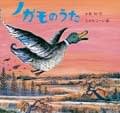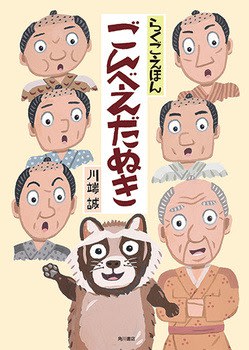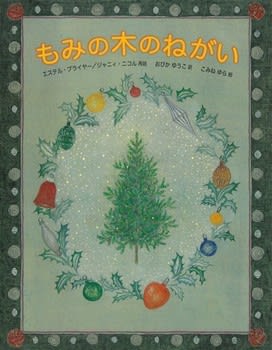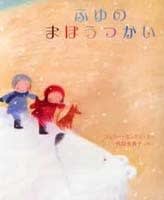梨の子ペリーナ/イタロ・カルヴィーノ・再話 酒井駒子・絵 関口英子・訳/BL出版/2020年
典型的な流れのイタリアの昔話。
ある年、王さまに納める梨が足りなくなり、父にカゴに入れられ、王さまの倉に運ばれた女の子ペリーナ。ペリーナは台所で働くことになり、ほかの召使たちより、てきぱきと仕事をこなせるようになりました。賢く、やさしいペリーナは、だれからも好かれ、同じ年ごろの王子さまとも、それはそれは仲よしになりました。
ところが、ほかの召使がやきもちをやき「ペリーナって、魔女の宝物をとってこられるんですって」という、ありもしない噂を流します。
王さまは「身に覚えがない」というペリーナに、「宝物を持ってかえるまで、なかに入れない」と命令します
しかたなく歩きはじめたペリーナは、梨の木の上で一晩過ごしました。朝になると、梨の木の下に、ひとりのおばあさんがたっていました。ペリーナに話を聞いたおばあさんは、肉のあぶら3ポンド、パン3ポンド、モロコシの穂3ポンド、そしてふしぎなおまじないをおしえてくれました。
まっすぐ歩いていったペリーナは、三人の女が、髪の毛をむしっては、かまどをはいているのをみて、モロコシの穂でそうじするよう、女たちにあげました。
ペリーナが次にであったのは、とうろうとする人に襲いかかる三頭の番犬。もっていたパンを3ポンドなげてやると、犬たちはとおしてくれました。
さらに歩いていくと、血のように赤い水が流れている川がゆくてをさえぎっていました。ペリーナが、おばあさんがおしえてくれた まじないを となえると 川の水は すーっとひいて 道があらわれ 川をわたることができました。
やがて、この世のものとはおもえないほど美しくて立派なお城につきますが、門の扉がすぐに閉じてしまうので、なかに入ることはできませんでした。そこであぶらを3ポンドぬって、ちょうちがいのすべりをよくすると、門はゆっくりとひらき、なかにはいこむことができました。
ペリーナが城のなかに入り、小さなテーブルの上の宝箱をみつけ、うでにかかえて もってかえろうとすると、宝箱がしゃべりだしました。
「扉よ、この子をはさんでおしまい。扉よ、この子をはさんでおしまい。!」。しかし扉は「いやだね、だれがはさんだりするもんか。ながいこと、だれもおいらにぬってくれなかったあぶらを、この子はぬってくれたんだ」
川までやってくると、宝箱は、おぼれさせるよういいますが、川もペリーナを通してくれ、番犬も、かまどの女たちも ペリーナをとおしてくれました。
宝箱をもってお城にかえると、王さまから望みのものをあたえようといわれ、おばあさんから助言されたとおり、地下室の大きな炭箱をくださいなと こたえたペリーナ。
炭箱をあけると、なかには王子さま。王さまは、二人が結婚の約束をすることを 機嫌よくみとめてくれました。
ペリーナは梨の子という意味ですが、イタリア語では果物はみんな女性名詞といいます。
魔女が出てくるのかと思ったら、しゃべる宝箱でした。宝箱の中身は、宝石ではなくメンドリと金のヒヨコ。梨が税というのもはじめてでした。