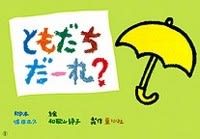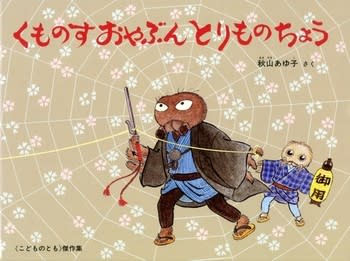やかましい!/アン・マグバガン・作 シムズ・タバック・絵 木坂 涼・訳/フレーベル館/2008年
この「やかましい!」と、次の「ありがたいこってす!」は、おなじシュチュエーションで、出版社の説明にはありませんが、ユダヤの民話が もとのようです。
ある日、ちいさな古い家に一人で住む ひげもじゃのおじいさんは、ベッドが キーキーし、外では、葉っぱが風に揺れて 屋根をひゅんひゅん こすり、やかんが しゅー!と、音を立てるのに、気分がイライラ。
「やかましい」を何とかしようと、村一番の物知り博士のところにいくと、「ウシといっしょに くらしなさい」とのご宣託。
おじいさんがウシを 家に連れて行くと ウシはモーモー。
「ちっともかわらん」と、また博士のところへ行くと、こんどは、ロバと暮らしなさいという。
博士は、なにを企んでいるのやら。次はヒツジ、ニワトリ、イヌ、ネコ。
ネコは ニャーニャー
イヌは ワンワン
ニワトリは コケコッコー
ヒツジは メエメエ
ロバは ヒーホー
ウシは モーモー
ベッドは きーきー
ゆかは みしみし
やかんは しゅー!
おじいさんが博士にくってかかると 全部手放しなさいという。動物がいなくなると、ベッドの音は ちいさいし、床の音は かわいい音、風もやかんの音も気になりません。その夜、おじいさんは あっという間に眠って、しずかなしずかな 夢を みました。
博士は、ほんとうのやかましさを 思い知らせるために 動物を 家の中に いれるように助言した確信犯。
青を基調の絵が、落ち着いた感じを醸し出しています。
一匹一匹動物が増えていくようすは すっかり 描かれていますが、動物が家をでていくのが 一ページですまされているのが やや 物足りない。
子どもや孫が帰省で、手狭になった部屋が、みんなかえると 広くみえるのも、こんな感じ。
原著は、1967年です。

ありがたいこってす!/マーゴット・ツェマック・作 わたなべしげお・訳/童話館出版/1994年
母親と おかみさんと 6人の子どもたちと いっしょに、一部屋しかない小さな家に すんでいた男の話。家の中があんまり狭いので、 男とおかみさんの言い争いが絶えないし、子どもたちはうるさく喧嘩ばかり。 冬になると昼間は寒く、夜は長く、 暮らしはますますみじめになるばかり。
そして我慢できなくなった男が、ラビさま(ユダヤの法律博士・先生)のところへ 相談に行くと、おんどりとガチョウを 家の中にいれて、いっしょに暮すように言う。
さらに、ラビさまのところへ相談に行くと、ヤギ、ウシと いっしょに 暮すようにいう。
一度目は、驚きながら、二度目は「冗談は やめてくれ!」、三度目は「むちゃな!」と、思いながらも、ラビさまにいうとおりにした男。
四度目に「地獄に 落ちたようでがんす!」と叫んだ男が、動物を 家の外に 追い出すと、哀れな男と家族のものは、ぐっすりやすむことができた。
男は最後に、「おれの暮らしを、楽にしてくださって ありがたいこってす!」と、ラビさまにいいます。
子どもたちからしたら、なんで そんなことするの?と、突っ込まれそうですが、形は違えど、同じようなことを していないか ぎょっとするところもあります。部屋が狭い狭いといいながら、いくつもの家電製品、あまり使わない健康器具などを必要以上に買い込んで、狭いといっているようなもの。