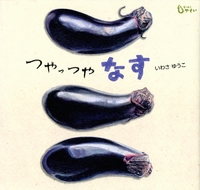漁師とウルマとチャラーナ/太陽の木の枝 ジプシーのむかしばなし/内田莉莎子 訳/福音館文庫/2002年初版
福音館文庫のジプシーのむかしばなしのうちで、ジプシ-という呼称がでてこない少ないもの。
他の話には、ジプシーの若者、ジプシーとその妻、貧乏なジプシーの少年などがでてくる。
ジプシーが差別用語といわれると、やや腰がひける。しかし、なぜそうなのか今一つ納得がいかない。
素敵な表現がでてくるというので読んでみました。
たしかに、少年がでくるところでは、「かみを風になびかせた美しい少年」「きらきらひかるきものをきた美しい少年」「銀いろにひかるマントをきた美しい少年」。
むすめは、「キンポウゲをあんでつくったくつをはき、木の葉をぬいあわせたきもの」など、イメージがひろがる表現が多い話。
内田莉莎子さんの訳が魅力的な話にしあがっているようです。
「おおきなかぶ」からはじまっってなじみのある内田訳。内田さんは69歳でなくなっていますが、もっと仕事をしてほしかったひとりです。
人間だって空を飛べる/アメリカ黒人民話集/金関 寿夫・訳/福音館文庫/2002年初版
中学生以上を対象としたお話で、これというものがあまりないように感じていました。
しかし、この話は、背景がわかっている中学生以上にはうなずける話。
酷使され続けられている黒人奴隷が、ある日、自由の地に向かって、空を飛んでいくというもの。
老いた人も、若者も手をつなぎ、輪のようになって、青い空を黒々としたかたまって飛んで行ったという場面が、印象的です。
飛ぶことができなかった奴隷たちが、飛べた人の話を、自分の子どもたちにしてやったという最後にも余韻が残ります。
13人の若者が旅に出て、木一本もなく、川も小川もなく、草もはえていない砂漠に迷い込みます。
この砂漠を4日間迷っているうち、大きな岩屋の鉄の門にたどり着きます。
ここには悪魔がすんでいたが、なぜか食べ物とごちそうを提供してくれる。さすがに無償で提供してくれたわけでなく、若者が岩屋をでるとき、一人がとりのこされてしまいます。
若者が砂漠を抜け出そうとするが、また岩屋のそばにでてしまう。またごちそうになるが、帰るときまた一人が岩屋にとりのこされてしまう。
これを13回くりかえし、最後の一人が取り残されそうになったとき、最後の一人は、自分の影を悪魔にみせ、「どうです。こいつをつかまえたら!」という。
悪魔が、この影を捕まえようとするあいだに、若者は、この岩屋から逃げ出します。
この話は、残虐なところがなく安心感がある。そして昔話のパターンを踏まえながらも、他の話にあまり見られない展開がいい。
13人目の若者が影をなくしてしまう最後も、意表をつくおちである。
 |
りんごがたべたいねずみくん/作・なかえよしを 絵・上野 紀子/ポプラ社/1975年初版
表紙には8個のリンゴがある高い木があります。
このりんごが一個ずつ減っていきます。
とりは飛べるので、難なく一個を
さるくんは、木をするする登り
ぞうさんは、長い鼻で
きりんくんは、長い首で
カンガルーは、ひょいとひとっとび
さいくんはどしんと、ちからで
残った2個。ねずみは、あしかにひょいとボールのように放り投げてもらって、仲よくわけあいます。
絵の全部に、りんごの木があって、一個ずつ減っていくのを楽しみながら、みていけます。
出版が大分前なので、さまざまの人が、この本に感想を寄せていますが、その一つ一つにうなずけます。
マーティンが来るまで待とうよ/人間だって空を飛べる アメリカ黒人民話集/ヴァージニア・ハミルトン 語り・編 金関寿夫 訳/福音館書店/2002年初版
しゃれたタイトル。よくできた短編小説風で、こんな話を少し大きい子どもたちがどんなふうに反応するか興味をもたせる話。
幽霊が出そうな家に泊まり込んだジョン。
すきま風がヒューヒュー入り、こわれた椅子にすわっていると、ジョンの前にしのびよったネコ。
ネコは、真っ赤に燃えている石炭をなめる。
次に猟犬ぐらいでっかいネコがはいってきて、真っ赤な石炭でほほや鼻をパタパタ。
そしていうことには「そろそろ、やるか?」
すると、ふつうのおおきさのネコがいうには
「マーティンが来るまで待とうよ」
さらに、ばけものみたいな、ばかでかいネコが。
ジョンは、こいつがマーティンにちがいないと思う。
このネコ、燃えている石炭で、目ん玉をきれいにそうじし、
「おまえたち、この野郎をどうするつもりだい?」と、ジョンのそばにすわっているネコにいう。
「マーティンが来るまで待とうよ」
マーテインがどんな怪物か興味をもたせておいて、結局は何者かはわからずずまいでおわる結末。
「マーテインが来るまで待とうよ」という2回のセリフが効果的。
読む人、聞く人に自由に想像させる最後が、にくい。女性には語りにくい文章なので、多分男性が語った方がよさがでそう。
でも、この話、不条理劇を思わせる話で、難解か。好みが分かれそう。
他の人があまり語りそうにないと思って覚えてみたのですが・・・・・。
つむじまがりの子がえる/世界のなぞなぞ話/塩谷太郎 解説/偕成社/1971年初版
つむじまがりの青ガエルの子。
母親が東と言えば西に、山へ行くといえば川にいく子ガエル。
母親が重い病気で、もう助からないとわかり、「死んだら川のそばにうめておくれ」と言い残して亡くなる。
そういえば、つむじまがりの子は、山にうめてくれるだろうと考えてのこと。
ところが、母親がなくなって、これまでのことを反省した子ガエルは、母親のおもいとちがって、遺言通り川にうめることに。
川では、雨がふるとお墓が流される心配があるので、それを気にした子ガエルは、雨がふると母親のお墓の番をすることに。
青ガエルが雨の中ですわって鳴いているのには、こういうわけがあるという。
同じような日本の話を読んだことがあります。昔も今も子を思う親の気持は共通です。
 |
ざっそうの名前/長尾玲子/福音館書店/2013年初版
スイカをもっておじいさんのところへ遊びに出かけた太郎くん。
おじいさんが、雑草の名前をいろいろ教えてくれます。
雑草と言っても名前があるので、一括りで雑草と言っているのに抵抗があったところですが、おじいさんが丁寧におしえてくれるこの絵本をみて、あらためて雑草に興味がでてきました。
この暑さで、少しばかりの菜園には、あっという間に大きくなる雑草。
夏場には、いくらとっても次から次へと伸びてくる雑草の生命力には、驚かされます。
このなかにでてくるもの。
ヘメジョオン、ツユクサ、トキワハゼ、カタバミ
オニノシゲ、シロザ、エノコログサ、オオバコ
イヌビエ、スズメノカタビラ、イヌタデ、コニシキソウ などなど。
エノコログサは、むかしよく遊んだねこじゃらしの正式な名前。小さいうちにとることが多いので、気がつきませんでした。
ヒルガオも雑草の一つ。そしてドクダミが現れたと思ったら当たり一面を占領しています。
あまり知らない名前ばかりでした。
和尚さんと小僧さんがでてくる昔話。
和尚さんが欲張りで、檀家からいただいたものなどを独り占めしようとして、結局、小僧さんに食べられれてしまう笑い話。
柿であったりアユ、まんじゅうだったり、お餅であったりとさまざま。
小僧さんにお餅を食べられてしまうのも、いくつかのパターン。
<民衆の笑い話/日本の民話11/角川書店/1973年初版>にあるのは、和尚さんが、いろりの灰に埋めたお餅を、檀家の建前を見てくるよう言いつけられた小僧が、普請の様子を話すふりをしてお餅を食べてしまうお話。
<定本日本の民話10 埼玉の民話/未来社/1999年初版>には、新座版が。
小僧が自分の名前をパタパタにかえてほしいと和尚さんにいう。和尚さんが夜遅く一人、餅の灰をパタパタたたいてお餅を食べようとすると、それを聞きつけた小僧さんがでてきて、何か御用ですかといいながら、和尚さんのもっているお餅をじろりとながめたことから、和尚さんがきまりわるそうにふっくらと焼けたお餅を食べさせることに。
なんとなく情景が浮かんでくる話です。
 |
だんごむし そらをとぶ/松岡 達英/小学館/2000年初版
近くの子が虫集めに夢中になっているのをみると、なぜかほっとするところがあります。
少しばかりの家庭菜園にはだんごむしがいっぱい。ミニ赤カブをなめたり、草の下からぞろぞろ。
図書館から借り出してきた絵本ですが、大分人気があるようで、多数の人が借り出ししています。利用している図書館の本には返却日がゴム印でしるされていますが、これまで手にした絵本のなかでは、一番の人気。それだけ興味をもてるのでしょう。
デジタルの時代に、いっぱいの絵本をかりだしているお母さん、子どもをみていると、その家庭の親子の絆がうかがわれます。
ところで、この絵本、だんごむしがそらを飛ぶ?と思っていたら、でっかい夢をもっただんごむしが、クモの巣のしたに落ちていたトンボの羽を工夫して”そらとぶマシン”をつくり、旅をします。
ちいさなだんごむしがおおきく描かれて、こんなかたちだったんだとあらためて見直しました。
悪魔とかみの毛/世界のなぞなぞ話/塩谷太郎解説/偕成社/1971年初版
昔話ならではのキャラクターをもった悪魔が登場します。
この悪魔、なにもいらないから休みなしに仕事をだしてもらいたいと条件をだします。そしてもし仕事がとぎれるなら、お前を食い殺すという。
これを聞いた地主は、とほうもない広さのため池を整備するように悪魔にいいつけますが、悪魔は、たった一日ですっかりすませます。
次に、二十の村にまたがっている自分の土地を耕すようにいいつけますが、悪魔はこれもあっという間にやってしまいます。
仕事が種切れになり、地主は次に何をさせたらいいのかわからなくなり、食われる覚悟をしますが・・・・。
地主は、ただで労働力を手にしますが、その結果は?
 |
ソメコとオニ/斎藤隆介・作 滝平二郎・絵/岩崎書店/1987年初版
斉藤隆介さんが亡くなってから出版された絵本。
今のように便利な機械や道具もないなかで、忙しく働いている少し前の農村の原風景が思い出されます。
だれにも遊んでもらえないソメコが、オニに誘拐されます。
しかし、連れて行かれた岩屋は格好の遊び場。
オニは夜も寝られないほどソメコの相手をさせられます。
脅迫状をだすつもりのオニが、父にあてた手紙のオチが楽しい。
軽妙なやり取り、昔話風の方言も楽しく、語ってみたいと思って何回も読み直していますが、これがなかなかものになりそうもない。
そういえば、虎の皮のフンドシというのは、前によく聞いた感じであるが、最近はあまりお目にかかれない。