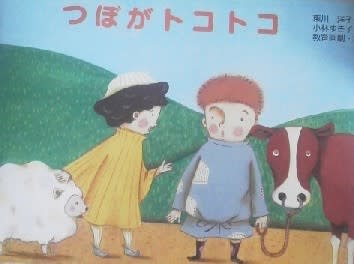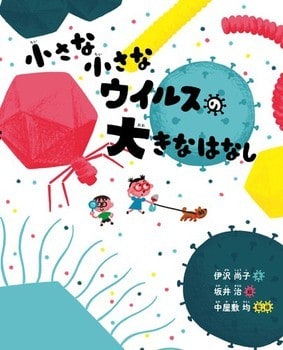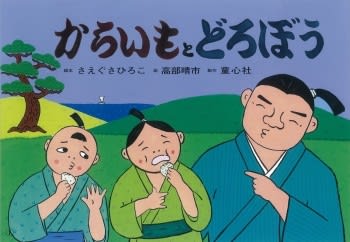北海道のむかし話/北海道むかし話研究会編/日本標準/1978年
江差の町に住んでいた繁次郎のとんち話。背が低く頭と目玉が大きく、甘いもの、お酒、なんでもござれの大食漢でした。
<頭も名人>
ニシンつぶし(とれたニシンの腹をさいて、なかのものを取り出し、カズノコヤシラコをえり分け、魚体は身欠きにまわす作業)の名人というふれこみで、やとわれた繁次郎。
ところがさっぱり働かない繁次郎をぎゅうととっちめてやろうと、大だるにいっぱいニシンをいれて、腕前を見せたら全部くれてやろうと親方がいいます。
すると、繁次郎は人を呼び集め、「これからニシンつぶしの競争だ。つぶしただけは、みんな自分のものだ。さあ、かかれ、かかれ」と、たるのニシンをつかんではなげ、つかんではなげしたので、あっというまにニシンつぶしが終わってしまいます。
くやしがる親方に、繁次郎はいいました。
「親方、おれはニシンつぶしも名人だけど、頭の方もめいじんだね。」
<家宝のハラワン>
おれの家には家宝があるから、いつでも借金をかえせると、けむにまいていた繁次郎。
暮れもおしせまって、借金とりが繁次郎のところにいくと、繁次郎は、頭にはちまき、着物の前を広げて腹をだし、へその上におわんをひとつ のっけていました。
「借金はどうしてくれる。家宝はどこだ」
「これだよ、これだよ」
「これとはなんだ」
「これ。腹の上のわん。ハラワンハラワン。借金はハラワンという家宝だ」
<火がもえている>
夕暮れの町にクリをにるうまいにおい。腹ペコの繁次郎が、いきなり大声で、「そのへん火がもえている」とさけんだので、「火事はどこだ。火事はどこだ。」と、みんな大騒ぎ。
火元がわからないので、繁次郎を問い詰めると「おれは、そこらだ火がもえている、といっただけだ」
「そこらだとは、どこだ。」
繁次郎「その鍋の、クリの下だ。」といって、うまくクリにありついた。
<大飯ぐらいは身の毒>
なまけるわりに、たくさんの飯を食う繁次郎に困った親方が「大飯は身の毒だぞ」と文句をいいます。
次の日から、繁次郎、山から運ぶ薪が半分になってしまった。「どうしてそんなに少なく背負ってきた?」という親方に、繁次郎はいいます。
「親方、大飯ぐらいは身も毒といったべさ。重荷は背中の毒だってばせ。」
<とうふとセンベイ>
繁次郎酒一升のかけを若者にもちかけます。
「とうふ一丁を四十八に切って、ひとつづつ全部食べられたら一升ふるまう。もしくいきれなかったら、そいつは おれに一升出せ。」
繁次郎は、とうふのいっぽうを薄く切り、その一枚を四十七に細かくきざみます。そして残った大きなとうふとともに若者にさしだします。若者は細かいほうは、あっというまに食べますが、大きい方は一口ではたべきれず、賭けは繁次郎の勝ち。
この若者が、繁次郎をやりこめようと、センベイ五十枚を三百までかんじょうする間に食えたら、お前の好きなもの腹一杯ごちそうしてやると、山もりのセンベイを繁次郎の前につきだします。
繁次郎は、台所から、スリばちとスリこぎをもってきて、若者が持ってきたセンベイを粉々にして、水でこね、団子を作って、あっという間にたいらげてしまいます。
この他にもたくさんあります。