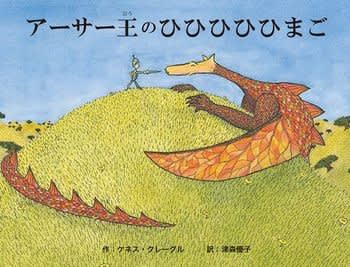新訳チェーホフ短編集/沼野充義・訳/集英社/2010年
いつだって誰かのことが好きで、好きな人なしにはいられないオーレンカ。
町はずれのジプシー村にある家の名義は、遺言状でもすでに彼女の名義になっていて、最初の結婚は同じ屋敷の離れを間借りしていたクーキンという男。
遊園地を経営する興行師で、愚痴ばかりこぼしている男に心を動かされ彼を好きになったオーレンカは、プロポーズを受け入れ結婚。
彼女は知り会いに、この世で一番素晴らしく、一番大切で、一番必要なものは芝居であって、本物の楽しみを味わい、教養ある人情豊かな人間になることができる場所は劇場だけだとまで、いうようになっていました。クーキンが俳優について言うことを、彼女もそっくりそのまま繰り返すのでした。
ところがクーキンは、劇団員を募集するためにいったモスクワで死んでしまう。
三か月後、あまりよく知らない年配のご婦人からすすめられ、プストワーロフと二度目の結婚。
彼は材木商。彼女は材木倉庫に昼時までいて、夕方は事務所で請求書を書いたり商品を引き渡したり。夫の考えがそのまま、彼女の考えに。「もう芝居なんて見に行くヒマ、ありませんわ。お芝居なんて、どこがいいんでしょうね?」
楽しく暮らしていた彼女に、六年後またもや別れが訪れます。プストワーロフは風邪で寝込み、四か月患ってあっけなく亡くなってしまいます。
彼女がまるで修道女のように家に閉じこもった六か月後、今度は家畜の健康について、人間と同じように心を配らなければと言い出します。プストワーロフが生存中、彼女の家の別翼に下宿したスミルニンという連隊付きの獣医の影響でした。スミルニンは結婚して息子も一人いましたが、妻の不倫のせいで、彼女と別れ、今では元妻を憎みながらも、息子の養育費を毎月送っていました。
ところがスミルニンは連隊とともに、どこかとおいところへいってしまい、オーレンカはまたひとりに。
心が空っぽになり、何のために生きているのかわからない日がつづきます。町は四方八方に拡大し、ジプシー村は、いまではジプシー通りと呼ばれるようになっていました。オーレンカの家は黒ずみ、屋根はさびつき、物置は傾き、中庭には雑草が生えていました。
ある暑い七月の夕方、スミルニンが数え年十歳になった息子のワーシャと、よりをもどした妻とあらわれます。
オーレンカの借家に住むことになったスミルニン。スミルニンの妻は姉のところにいったきるで、スミルニンも毎日どこかに肉牛の検疫に出かけ、三日続けて家をあけることも珍しくなかったので、オーレンカはワーシャがまったくほったらしにされているようで、自分の住む離れにひきとり、そこで小さな部屋に住まわせることにしました。
ワーシャを息子であるかのような気がしたオーレンカは、こんどは自分の意見を持ち始めます。中学校の勉強がどんなに大変か!。
学校にもついていったオーレンカ。「あとはもうひとりでいけるからさ」といわれても、サーシャが中学校の玄関口のなかに消えるまで後姿を見送ります。
彼女の内側では母性の感覚が激しく燃え上がり、赤の他人というのに、この子のためなら、そのえくぼ、その学帽のためなら、彼女は自分の命だって喜んで、感動の涙さえ流しながら差し出すことだろう。どうして?それにしても、いったいどうしてなのか?
けれども、サーシャは、ときおりこんな寝言をいっています。
「覚えてろ!お前なんかあっちに行け!ぶつなってば!」
1899年に発表された当時女性の読者から強い憤慨や批判の声があがったといいます。
夫の言うことをそのまま受け入れするオーレンカをみると、歯がゆい感じがするのも、もっとも。
男にとって自己主張せず、自分のいいなりになり従順な女性というのは「可愛い女」となりそう。
ところでオーレンカが、心の底まで男性に一体化していたのかには疑問が残ります。それは結婚にいたる過程がいかにも場当たり。誰でもよかったようにみえます。その背景には、父親は病気でいつの間にか死亡し、母親の姿ははじめからなく、まったく見えないし独りぼっちだったことが影響しているかもしれません。
晩年?はサーシャにも裏切られる予感の終わり方も残酷。