朝日町の昔話集3/朝日町人材養成事業「あさひまち」F21」・編/1998年
秋なのですが、春の話です。
桜が満開で、酒をもって花見に出かけた男が、頭蓋骨を見つけ、酒飲まして念仏をあげます。
そのまま家に帰って昼寝していると、「こんにちわ」と若い娘の声。
若い娘がいうことには、助けてもらった頭蓋骨といいます。家に送ってくれというので長者の家におくっていくと、娘の三回忌の法事中。
長者がいうことには、娘は家出して行方不明だったといいます。
長者は、山の中で一人暮らしをしている男へ、一緒に暮らすようにいいます。
主人公は「づんつっぁ」と表現されているのですが、いくつぐらいでしょうか。
娘がなぜ家出をしたのか、どうして死んでしまったかはでてきません。背景を省略しているのが昔話の特徴でしょうか。
男が長者の家にいったときは、透明人間になって、法事の料理を次から次えと食べてお客をびっくりさせるところもでてくるのですが、話の展開もストレートです。
供養した恩返しと理解するとつじつまはあうのですが、このあたりも詮索無用のようです。
この昔話集の語り手の方は、ほとんどが80歳以上のかた。どんなふうに口承されてきたのかも興味がわきました。

やんちゃもののおでましだい/デイヴィット・メリング・作 山口文生・訳/評論社/2008年初版
やんちゃもののオオカミが9頭。
名まえが、パンクズ、ゴクゴク、ケダマ、ゾンザイ、アミモノ、アホンダラ、ミミアカ、キニヤミ、ゴタマゼとよくもまあつけたという名前です。
あんまりやんちゃなので、みんなから嫌われもののオオカミ。
そこでオオカミがとった方法は、ハブラシ、クシのつかいたから、素敵な服を着て、言葉遣いもあらためて。
スープをピチャピチャするな、前足をあらっているか点検し、食事は終わるまで席をたつなと、他の動物に注意し始めます。
いつもと違うオオカミに戸惑う動物たち。
やんちゃオオカミが懐かしくなります。
でもオオカミは、満月にさそわれていつものオオカミになってしまいます。
でもそのことで、みんな仲直り。
オオカミの服装は大分凝ったもの。
そしてみんなが住むのは戸建て住宅!です。おまけに車まで。
ベランダで入浴、お茶も道路でというふうに、なんともたのしい動物村です。

ふしぎなガーデン/ピーター・ブラウン・作 千葉茂樹・訳/ブロンズ新社/2010年初版
一本の木も、ちいさな草もない町にすむリーアムという外遊びのすきな少年。
ある日リーアムがやってきたのは、今では使われなくなった高架鉄道。
そこで枯れるすんぜんの草木を目にします。だれかがたすけてあげなきゃと、草木の面倒をみることに。
庭師になったようなきがしたリーアムは水をやり、剪定します。
やがて雑草とコケが線路の先まで伸び始めます。
冬の間は、春に備えて準備、準備。
冬の眠りから覚めた草木は、線路の外にも伸び始めます。
やがて町は緑のおおわれるようになるのですが・・・。
リーアムは、まるで人形のように描かれています。
街の人びとの意識も変わり、長い年月をかけて、街のようすがかわっていきます。
結婚したリーアムは、子どもといっしょに廃墟となった高架鉄道の草木の手入れも続けます。
面白いのは草木が擬人化されて、知りたがり屋の草木が、線路の先へ先へ、線路の外に動いていくあたりでしょうか。
はじめに動くのは雑草やコケで、あとをおっておしとやかな草花が動くのもよく目にする風景です。
最初のページは、煙突の煙がモクモクするとても味気ない町の風景。
それが最後のページでは緑におおわれた住みよい街に変貌しています。
空気のにおいもやさしく思わせます。
貧しい島の奇跡/ムギと王さま/ファージョン・作 石井桃子・訳/岩波少年文庫/2001年初版
あるおはなし会のプログラムに、この話があり読んでみました。
そのあと続けてファージョンの他の話を聞く機会がありました。それまではほとんど聞く機会がなかったファージョンでしたが、続くときつづくのは不思議です。
沖にある漁師たちの島。
島の土地は岩だらけで、草や木もなく花は一つもありません。
たった一つあるのは、ロイスのおとうさんが結婚の記念に植えたバラの木。およめさん、ロイスがよく世話をしていました。
島と本土の間は、ひと月に一度、満月の時、潮がひいていききできました。
この島に女王がやってくることになりました。
教会への道には、大きな水たまりがあって、女王が通るには、足が水につかってしまいそうでした。
そこでロイスは、みんなにだまって、水たまりにバラの葉と花を敷きつめます。
島の人たちは、島のたったひとつの美しいもの、バラをみてほしいと女王を案内しますが、そこにはバラはありませんでした。
貧しい島の人びとは、月に一度本土とつながる道をとおって、魚を商っていたのですが、あるとき、帰るとき急に空模様があやしくなって、潮に巻き込まれそうになります。
このときロイスも潮に巻き込まれそうになるのですが、みどりの葉と白い花が島と島のあいだをうずめつくします。
ロイスは、亡くなった女王が、微笑みを浮かべ、みどりの葉と九つの白い花をつけたバラの枝をもっているのを見たのでした。
この女王は悲しみをもっていたとあるのですが、どんな悲しみかふれられていないので、よけいに想像がふくらみます。
バラの花でみずたまりをカバーできるか疑問なのですが、それを感じさせない幻想的な物語です。
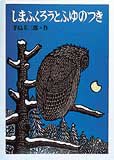
しまふくろうとふゆのつき/手島圭三郎・作/偕成社/1993年初版
ページいっぱいにえがかれたおおきなしまふくろう。広く広げた羽根の一枚一枚が鮮明にえがかれ圧倒的な存在感があります。
雪ですべてがおおわれ、シーンとした森。
真っ黒な空に輝く月。
獲物を狙う目、耳。
躍動と迫力という表現がピッタリぴったりです。
日本では北海道にしか生息しないというしまふくろうは、世界最大のふくろうというのですが、今は絶滅の危機にあるといいます。
最後のページに、木の上に二匹のふくろうが並んでいるのですが、絶滅の危機にあるしまふくろうへの作者の思いが凝縮されているようです。
子どもに贈る昔ばなし5 千葉わらい/再話・南総昔ばなし大学再話コース 小澤俊夫・編・監修/小澤昔ばなし研究所
正直者の母親と息子の話。
ラマダーン月の15日の真夜中に三つのねがいごとを口にだしていえば,神さまが必ずかなえてくださるというので、母親は
「神さま、どうかわたしの息子の頭を大きくしてください」とねがうと、息子の頭はあっという間に、大なべぐらいの大きさに。
びっくりした母親は
「神さま、この子の頭を小さくしてください」とおねがいごとをすると、今度はあわつぶほどの大きさに。
たまげた母親は、三番目のおねがいごとをします。
「神さま、どうぞ、息子の頭をもとにもどしてください」
息子の頭はたちまち、ちゃんともとにもどります。
母親がどうして息子の頭を大きくしてくれと、ねがいごとをしたのかはわかりません。もしかすると賢くなるようにお願いしたかったのかも。
この原話は(世界のメルヘェン図書館5 ソビエト南部のはなし 火の馬 ぎょうせい発行 1981年)ですが、ソビエトとあって、何か時代を感じます。わずか?35年前のことです。

ぞうのたまごのたまごやき/寺村輝夫・作 長新太・画/福音館書店/1984年初版
え!ぞうがたまごをうむのと錯覚させて、最後は、ぞうはたまごをうまないよというオチ。
たまごやきが大好物の王さまに、あかちゃんがうまれます。
王さまは国中の人たちをよんで、たまごやきをふるまおうと大臣に命令します。
ところが国にはそんなにたまごがありません。
ぞうのたまごなら大きそうだと、ぞうのたまごをさがすことに。
たくさんの兵隊たちはラッパをならし行進。
一方大きなたまごやきをつくるには、大きなフライパンが必要と、工場ではフライパンづくり。
おおきなフライパンには、おおきなかまども必要と、かまどづくりも進みます。
見つかったのは子ぞう。そのへんを探せとおおわらわ。
ラッパの響きが
プルルップ トロロット
タララップ ターア
とリズミカル。
そして兵隊が
ぞう。ぞう。ぞう。
たまご うんだ ぞう。
たまごを だいている ぞう。
どこだッ どこだッ ぞう。
はやく でてこい ぞう。
と進むありさまも、もっともらしい。
兵隊があつめた卵から、ことりやだちょう、へび、かめがでてくる場面も楽しい。
名のない花/ムギと王さま/ファージョン・作 石井桃子・訳/岩波少年文庫/2001年初版
なにか考え込んでしまう短編です。
ある日、クリステイという農夫の娘が牧場にいって花をつみます。
ところがその名前がわかなくて、かあちゃん、とうちゃんに聞いてもわかりません。
とのさまのご猟場管理人もわかりません。
さらに若いが学がある記帳係にも尋ねますが、記帳係は調べてみると、その花をあずかります。
記帳係は、外国のえらい人に聞いてみますが、やっぱりわかりません。
一年後、記帳係がいったのは、神が天地をつくったとき、この花を忘れ、イエスキリストが、この花のことも思い出されてお創りになったものだろうということ。
その花は世の中からなくなってしまいます。
その日からそんな花があったのが一人もいなくなるのですが、クリステイは年とってからもときどき思い出しては人にもいいます。
「神さまだけが、あなたに教えてくださるんです。名まえがなかったんですよ」
新種というとすぐに名前をつけることを考えてしまうのですが、名のない花があってもいいのでしょう。

ころころラッコこラッコだっこ/文・石津ちひろ 絵・藤枝リュウジ/BL出版/2003年初版
早口言葉で、ひらがな、カタカナだけだと、うーんとうなるのですが漢字がはいると、スーとはいってくるから不思議です。
きつつきつつくき きずつくき
けむしはむし いもむしもむし まむしはむしでなし
そっくりのくりぽとり ことりびっくり
漢字も入れると
キツツキつつく木 傷つく木
毛虫は虫 芋虫も虫 蝮は虫でなし
そっくりの栗ぽとり 小鳥びっくり
早口言葉が満載で日本語の面白さを再発見です。
読み聞かせでも好評のようです。
小さな仕立て屋さん/ムギと王さま/ファージョン・作 石井桃子・訳/岩波少年文庫/2001年初版
大きな仕立て屋さんの年季奉公人のロタという19歳のお針子。
彼女はデザイナーとしてもすぐれていましたが、自分ではまだそれに気づいていませんでした。
若き王さまが花嫁を選ぶ仮装舞踏会が開催されることになり、ロタは花嫁候補のドレスをつくることになります。
花嫁候補はヨーグルト侯爵令嬢、キャラメル伯爵令嬢、プリン嬢の三人。
ロタがつくることになったのは、日の光と、月の光と、ニジをイメージした3つの夜会服。
火曜日、光のように輝くドレスを作り、花嫁候補にようすをみせるために、ロタはできあがった夜会服を試着してご殿にでかけます。
ご殿につくと、入り口で従僕からダンスを踊ってくれるようたのまれたロタは、踊り始めますが、舞踏会はじまる時間になって、大広間から喝采の音がおこるのを聞いてお店に帰ります。
水曜日、真夜中に照る月のようなドレスをつくってご殿にでかけたロタは、前の若い従僕と同じように踊ります。
木曜日、重なる黒い雲の間に出かかった小さいニジのようなドレスを試着したロタは、またしても若い従僕と踊りますが、プリン嬢がその服を着て、大広間にでかけ、驚嘆のため息がするのを聞きながらお店にかえります。
やがて王さまの結婚式の花嫁衣装をたのまれ、つくったのは雪のように清いドレス。
だれが花嫁にきまったのかわからないまま、ドレスを試着してでかけたロタでしたが、ここでまっていたのは、またもや若い従僕でした。
仮面舞踏会ですから、王さまが若い従僕に変装しているかと思いきや・・・・?。
三回の繰り返しは昔話のパターン。どこかのおはなし会で、話されていましたが、大分長く40分はかかりそうです。
舞踏会、夜会服と華やかな世界ですが、どんな想像をしながら聞くでしょうか。想像するにもベースになる部分がありますから人によってさまざまでしょう。
しかし映像や絵本であったら、くどくどいわなくても一瞬のうちに、華やかな世界を見させてくれます。
情報量の違いをどんなふうにとらえたらよいか迷います。
侯爵令嬢等の名前は作者が楽しんでつけたものでしょうか。
めんどりがやいたパン/中央アジア・シベリアのむかしばなし集/小桧山古男・訳 宮澤ナツ・画/新読書社/2006年初版
中国シンチャンウイグル地区にすむ少数民族サラルの昔話で、後半部は、日本の「絵姿女房」を思わせる話です。
日本版は、百姓の女房に横恋慕した殿さまのはなしですが、サラル版では、おいしいパンをたべた皇帝が、このパンをつくった”草かり男”のよめを自分のものにしようと画策します。
草かり男は、文字通り山の草をかっては、それを売って暮らしをたてていました。
ある日、黒いヘビにしめころされそうなまだらのヘビを助けると、ヘビの御殿にいき、おれいにめんどりを手に入れます。
めんどりは、お礼に金貨、銀貨のどちらがいいかといわれて、助けたヘビの助言で手に入れたものでした。
仕事から帰ってみると、テーブルの上にはおいしいパンがならんでいます。不思議に思った草かり男が、仕事にいくふりをして、すきまからのぞいてみると、めんどりが羽根をぬぐとパンをやいたり、お茶をわかしたりせっせと働いています。
若者がめんどりの羽根を火の中にほうりこんでしまいます。そして娘はそのまま若者のよめになります。
ところがおいしいパンをたべた皇帝は、若者に無理難題をいいつけます。皇帝の馬と競争したり、大きな山を平らにするのですが、若者はよめの協力でこれを切り抜けます。それでも皇帝はよめを御殿につれていってしまいます。
するとよめは一切笑顔を見せなくなります。
しかし、ものもらいがくると、よめは笑い出します。皇帝もよめの笑い顔をみるため、着ているものを取り替えると、よめはすかさず、門番にものもらいを追い出すように命じます。
こうして草をかっていた男は皇帝になり、めんどりの生まれ変わりのよめは女王になります。
昔話にでてくる職業もいろいろです。
草を刈って、売るというのもめずらしいのですが、背景には、草が家畜の貴重な飼料となっていたことがあるのでしょう。

ケーキやさんのゆうれい/ジャクリーン・K・オグバン・作 マージョリー・ブライスマン・絵 福本由美子・訳/フレーベル館/2007年初版
ケーキとゆうれいの取り合わせ、はてなと思いましたが、おいしそうなケーキが次から次へとでてきて思わずなまつばを飲み込むことに。
コーラ・リー・メリウェザーはケーキ屋さん。おいしそうなケーキが並んでいるのですが、コーラ・リーは、素敵なケーキを作る人にみえません。いつもレモンを食べたみたいに口をすぼめ、かみをぎゅっとしばって、小さなおだんごにしていました。
でもお客はケーキだけをみて、コーラ・リーをみていませんでしたから、あまり関係なかったようです。
コーラ・リーが亡くなって、町中の人がお葬式にやってきたのですが、誰も泣いていません。しかし牧師さんが店で売っていたケーキの名前を読み上げると、みんなは、すばらしいケーキがもう食べられないとわかって泣き出します。
家族がいなかったコーラ・リーの店は売りに出されます。
しかしこの店を買った人は、次々に店を手放します。なにしろコーラ・リーがゆうれいになってでてきたからでした。
しばらくして、大きな船の台所でデザートをつくっていたアニー・ワシントンが、この店が気にいって買い取ります。
ここから、コーラ・リーとアニーのバトルがはじまります。
コーラ・リーは仕込みをしている台所に出てきて、ボウルをころがしたり、たまごをパックごと投げつけ、20キロ!もある小麦粉の袋を引きちぎり投げつけたり。
アニーも負けていません。パイ生地の真ん中に顔をだしたコーラ・リーをバターをのせてつつみこみます。
どうしてとさけぶアニーにコーラ・リーがいいます。
「わたしにケーキを作っておくれ。むねがいっぱいになって、なみだがこぼれるほどすばらしいケーキ。わたしなら作れるけど」。
それからコーラ・リーが満足するケーキづくりがはじまるのですが・・・。
最後のページには「ワシントンとメリーウェザーのケーキ店」とあります。
おいしそうなケーキが並んでいる絵には、おもわず食べてみたくなります、

はじまりの日/ボブ・ディラン・作 ポール・ロジャース・絵 アーサー・ビナード・訳/2010年初版
表紙には「forever young」とあって「はじまりの日」とされています。
息子のことを思いながらつくったという曲が絵本になっているようです。
読む場所、読む時期さまざなところでいろいろな受け止めができるようです。
キング牧師、ビートルズがさりげなく描かれています。
(今年のノーベル文学賞がボブ・ディランにきまったというニュース流れた夜にひっぱりだしました)
・幸せ夫婦(子どもに贈る昔ばなし5 千葉わらい/再話・南総昔ばなし大学再話コース 小澤俊夫・編・監修/小澤昔ばなし研究所)
正直な百姓とおとなしい亭主孝行な女房。
ある日、百姓は馬を売って、その金で何か他の仕事をしたいと、馬を連れて町に行きます。
そこで子牛を連れた男とあい、乳もとれるし、肉もとれると、馬と牛を取り替えます。
家に帰る途中、今度は太ったぶたを連れた男にあい、牛とぶたをとりかえます。
ぶたから、にわとり、まんじゅうととりかえていきます。
金持ちの地主にあい、わけを聞かれると、地主はあきれかえって、きっと女房にぶんなぐられるぞといいます。
百姓は、女房はおれのやることになんでも賛成だといいます。これを聞いた地主は、女房に文句をいわれなかったら、おまえたち二人が一生食べるだけの金をやる、文句をいわれたら来年一年間ただばたらきするよういいます。
女房は文句をいうどころか、よろこび、おかげで二人は一生食べられるお金を手に入れます。
究極の夫婦の形ではありますが、この域までいけるでしょうか。
グリムの「しあわせハンス」では年季奉公がおわったハンスが、給金を馬にかえ、牝牛にかえ、豚、だちょう、砥石にかえて、最後は砥石を泉におとし、すべてをなくしてしまうという結末ですが、やっかいな荷物がすっかりなくなって、こころも軽く母親のまつ、村へとかえるハンスは、物や金に左右されるわれわれをやんわりと諭しているようにも見えます。
子どもに贈る昔ばなし5 千葉わらい/再話・南総昔ばなし大学再話コース 小澤俊夫・編・監修/小澤昔ばなし研究所
士農工商の身分差が厳然としていたころ。
さむらいは百姓や町のものにいばりちらし、さむらいも上のものは下っ端にいじめられていたが、大みそかの年越しの行事では、おかめやひょっとこ、鬼の面で、だれがだれだかわからないようにしてうさをはらしていました。
この年越し、地主の悪口や年貢のとりたてへの不平不満が続出。悪い品物を高く売る商人もお面をかぶってこっそり聞くにきていたが、ここではおこることもできません。
殿さまもお面をかぶってきていましたが、「お城の殿さまは頭が悪くて、役立たずから、わしらが苦労する、あんな殿さま、早く死んじまえばいいだ」と散々。
殿さまが場所柄も忘れて「ぶれいもの」と殴り掛かろうとしますが。みんなは大笑いして、「おもしろいおもしろい、殿さまのものまねのうめえことうめえこと」と大喜び。
殿さまは家来をひきつれて、すごすごお城に帰っていきます。
年越しに大笑いしてあたらしい年をむかえるという話ですが、庶民のうさばらしが妙に実感されます。
笑うだけではすまないことも多い昨今です。















