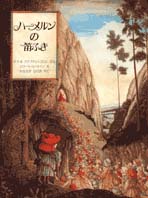 |
ハーメルンの笛ふき/サラ&ステファン・コリン・作 エロール・ル・カイン・絵 かなせき ひさお・訳/ほるぷ出版/1989年初版
絵が助けになる物語です。
町中ねずみだらけで、ねずみを追い払ったら多額の賞金をだすというおふれを出した町に、一人の笛ふき男がやってきます。この男があっという間に、ねずみを川のなかにおぼれさせます。あまりもあっという間に、ねずみを退治してしまったので、町の人たちは賞金をだすのがおしくなってしまいます。
すると、これに怒った笛ふき男は、町中の子どもたちを笛をふきながらどこかに連れて行ってしまいます。
物語の流れだけをみると短い話のようにおもえますが、町がねずみでどんなに困っていたか、子どもたちが連れ去られる場面も詳しくでてきて、かなり長い物語です。
1284年にハーメルンという小さな町で、130人の子どもが、まるで神かくしにでもあったように、きゅうに消えてしまったという事件をもとにつくられた物語で、グリムにも、この話があるというが、手元のグリム昔話にのっていませんでした。
有名といわれているようですが、知らなかった話です(笑)。
後で調べてみましたが、グリム童話集をさがしてもなく、「ハメルンのネズミとり」という題でのっていたのが、講談社から出されているオックスフォード世界の民話と伝説5 ドイツ編。1978年改訂第一刷にありました。
話のながさは適当で、このテキストだったら語ることができそうである。
約束を守らない理由を何とか考え出す人間へのしっぺがえしがきいています。
























