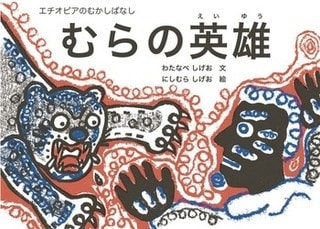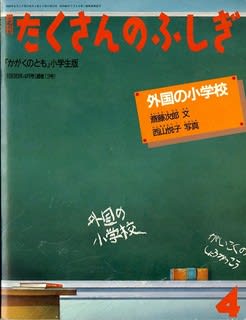どうにも数があわない話。
・百曲がりのカッパ(世界のむかし話⑫ 百曲がりのカッパ/松谷みよ子・作 梶山俊夫・画/学校図書/1984年初版)
百もくねくね曲がっている川。川の曲がりかどに、一匹ずつカッパがいるというので、一匹の子どものカッパが数をかぞえていましたが、どうしても数があわなくて泣いています。
じいさま、泣いているのをみかねて、一緒に数え始めます。
百曲がりをつぎつぎとかぞえていきますが、カッパの数は99です。
数えるのが好きなカッパが、また涙をこぼします。
ひまなじいさま、おれがついているのになんてことだとうでくんで、ひまにあかせてかんがえたら、数えるのが好きなカッパを勘定にいれると、百匹になると、ひざをたたきます。
・勘定のはなし(ジャックと豆のつる/ジェイコブズ・作 木下順二・訳 瀬川康男・絵/岩波書店/1967年初版)
ある村の12人が魚釣りに出かけ、誰かおぼれた者がいないか数え始めると、どうしても一人足りません。みんな自分を勘定にいれなかったからです。ある偉そうな人に数えてもらって、たしかに12人いたことを確認します。
感謝のことばがいい。
「あなたさまが消えた仲間をみつけてくださいまして」・・・・。
・アディ・ニハァスの英雄(山の上の火/クーランダー、レスロー・文 渡辺茂男・訳/岩波書店/1963年初版)
粉をひきに、町に出かけた12人の男が道をかえっていくとき、仲間が確かに12人いるか数えるが、自分を数にいれなかったため11人しかいないと思います。
そのほかの男も数えるが、やはり自分をかぞえなかったため11人しかいません。
道々、男たちはうしなった仲間をなげきかなしみ、勇敢なやつだったといなくなった仲間のうわさをしながら、村に帰っていきます。
だれかが道に迷ってヒョウにやられてしまったとなげくさまがなんとも本当らしく続いていきます。
女の子が、粉の袋の数をかぞえて、「いなくなったやつが、もどったぞ」とよろこぶのですが・・・。
・ロバは何頭?(ゴハおじさんのゆかいなお話/千葉茂樹・訳/徳間書店/2010年初版)
ゴハおじさんが市場でロバを12頭買って、一頭のロバに乗って家に向かいます。ロバの数を確かめるために数えはじめますが、自分ののっているロバを数えなかったので、11頭しかいない。そこでロバをおりて数えると確かに12頭います。
そこで安心してロバにまたがって、また数えはじめると11頭しかいません。
わけがわからなくなったゴハじいさん。どうやらわしがロバからおりると、一頭増えるようだ。それならロバに乗って一頭少なくなるより、ずっといいぞと家までロバのうしろをとことこ歩いてかえります。
すこしとぼけたお話。それにしても三つの話に共通しているのが12という数字。あまり少ない数でも、多すぎる数字でも話としては成立しにくいので、12という数字はよくできています。
「アディ・ニハァスの英雄」は語られている方も多いのですが、他の二つは聞いたことがありません。
そして「むらの英雄」という絵本になっていて、評判も上々です。