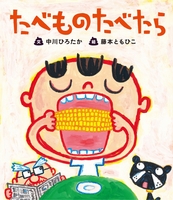日本の民話1 動物の世界/瀬川拓男・松谷みよ子・編著/角川書店/1973年初版
きつねの恩返しの昔話。
柴刈りで生計をたてていたお爺さんが、悪たれわらしにいじめられていたきつねを助けます。
するときつねは、味噌煮釜に化けて、お寺の和尚に売ってくれといいます。
釜に化けたきつねは、砂でごしごしみがかれたり、味噌煮をつくるため、かまどにかけられ、火をぼんぼん燃やされたりとさんざんな目にあって、寺から逃げ出します。
ここまでは「分福茶釜」そのものです。
しかし、話はまだ続きます。
もういいよというお爺さんでしたが、きつねは今度は娘になり、女郎屋に高く売るようにいいます。
高いお金を得たお爺さんでしたが、三度目は馬になって長者に高く売るようにいいます。
ところが、この長者は、人使いもあらければ、馬使いも荒く、きつねは思い荷と長者をのせていったため、歩けなくなります。怒った長者から折檻されて、きつねはその場に倒れて死んでしまいます。
近郷きっての福徳長者になったお爺さんお婆さんは、きつねのために立派なお堂をたてて、きつねの後生を祈ります。
最後がすこしひっかります。そして女郎屋がでてくるので、語るのは二の足を踏みます。
加代の四季/杉みき子・作 村山陽・絵/岩崎書店/1995年
ある日、お昼過ぎから降り出した雨が,夕方になって止み、ルミがおやつを食べていたら、電話がルルンと鳴ります。
「もし、もし。こちら,コスモス通信局。昨日のお礼です。東の空を見てください。」
電話は,それっきりで切れます。わけがわからないけど、とにかく外へ出てみたら大きな虹です。
それから三日目の夕方。また、電話が鳴ります。
「もし、もし。こちら,コスモス通信局。今日は,西の空を見てください。」
空をみるとそこは素敵な夕焼けでした。
前の日、ルミは今にも首を曲げているコスモスをみつけ、近くでスケッチをしていた絵描きさんと竹の棒に、お菓子屋さんからもらった風船の紐でコスモスを結んであげたのです。
コスモスさんからのお礼の電話だったのです。
それからひと月。コスモスの花が枯れて寂しくなったころ、ほんとに久しぶりで,電話が鳴ります。
「こちら,コスモス通信局。明日,デパートの五階へ,絵の展覧会を見に来てください。」
翌日、ルミがお母さんと一緒に,デパートの五階にヘ行ってみると、展覧会の大きな立て札が出ています。
中に入って、正面に掛かっている大きな絵の中には,ルミがいました。
いつかルミと苦しそうなコスモスを竹の棒に結んであげた絵描きさんの展覧会でした。
小学校2年生の国語教科書に載っているというのですが・・・。
コスモスをかわいそうに思ったルミと絵描きさんの素敵な交流です。
やさしさが思わぬ返礼となってかえってくるというほのぼのとする物語です。
 |
ずいとん先生と化けの玉/作:那須 正幹 絵:長谷川 義史/童心社/2003年初版
トン、トン、トン・・・。秋の夜、医者のずいとん先生の家の戸をたたく音がします。見ると、一人の女が立っていて、病気の子どもを診てほしいという。かごにのっていった先は、山の中。
こんな山の中に家があったのかしらと首をかしげるずいとん先生の目の前に大きな屋敷、おおぜいの使用人がでむかえてくれます。
ずいとん先生は、「今夜いっぱいがとおげだろう」とつげますが「わしになおせぬびょうきはない」と秘伝の丸薬で子どもの病気を治します。
今夜は泊まっていってくださいと女にいわれ、酒のもてなしまで。
翌日、先生が目を覚ますと、そこは洞穴の中。まくらもとには一匹のきつねがいます。
きつねは先生にお礼をいい、小判がいいかお酒がいいかとききますが、小判をもらっても木の葉にかわっているだろうし、お酒は馬の小便かもしれないと考えた先生。
「きつねが人を化かすときに化けのかわというのをかぶるそうだが、ひとつみせてくれないか」ともちかけます。
きつねは考え込みますが、子どものいのちを救っていただいたお礼に、化けのかわならぬ化けの玉をみせます。
この玉、うしなえば五日のうちにきつねの神通力がなくなるというもの。
先生、すきをみて化けの玉をふところにいれて、いっさんに山をかけおります。
ここから化けの玉を取り戻そうとするきつねと、そうはさせまいとするずいとん先生のだましあい。
ずいとん(どういう意味でしょうか)先生、評判がよくない割には、化けの玉を持ち去ったのは、村人がきつねに騙されないようにもちかえったようにも思えるし、コレラがはやっているときくと、化けの玉を奥さんにたのんで、駆け付けるあたりは医者の使命感もあるようで、たんにずるいということではかたずけられません。
ここから二転三転。
結末は あららとなるのですが・・・。
化けの玉がタマネギだったというのは、なるほどはじめからきつねの思惑があったのかも。
まさに昔話で、長谷川さんの絵とともに楽しめます。
大人と子どものための世界のむかし話8 インドネシアのむかし話/松野明久・編訳/偕成社/1990年初版
おじさんのところで、森の水牛をおうしごとをしていた、みなしごドゥアンは、おばさんからいじわるをされて、おじさんの家を飛び出します。
森の中をさまよいあるいていると、おおきなイノシシにであい、眠っているすきに、イノシシの首の金のくさりを注意深くはずし、いそいで逃げ出します。
きがついたイノシシから逃れて、海へ飛び込むとイノシシはあきらめて帰っていきます。
この金のくさりをつけると、まるで浮き輪をつけているように、かるがると水にうかびます。そして海の中を歩くこともできました。
ドゥアンは大海原をすいすいおよいで旅に出ます。
海の真ん中でであった船長が不思議に思い、金のくさりを借りて試してみます。
こんな船長がでてくると、魔法のくさりを横取りするのが普通ですが、キチンとかえしてくれるあたりが、いつもの昔話とはちがいます。
やがてドゥアンが小さな島につくと、おじいさんにであいますが、おじいさんはすわって草刈りをながめているだけ。草を刈っているのは剣でした。
おじいさんが金のくさりを試してみると、からだがぷかぷかうくのでうれしくなり、持ち主の命令をなんだってきいてくれる剣と交換してくれるようドゥアンにいうと、ドゥアンは承知するのですが、すぐ旅の手段をなくしたことに気がつき、金のくさりをかえしてくれるようにいいますが、おじいさんはうんといいません。
そこで、ドゥアンは剣にがんこじいさんをたたくように命令します。
剣でたたきのめされたおじいさんが、金のくさりをかえすと、ドゥアンは剣もかえさず、逃げ出します。
やがてついた都。
天を支配している竜が、王さまの一人息子を奪いに、おりてこようとしているところでした。
まわりの人から笑われながらも、王さまのところにいくと、「竜を退治してくれるなら、国のすべてをおまえにやろう。」といいます。
こんな話の展開では、ほとんどが王さまの娘がでてきて、めでたく結ばれるというのが多いのですが、この物語では、珍しく女性がでてきません。
金のくさりで思うところにでかけられ、剣もありますからこの勝負の結果はあきらかです。
語るとなると30分はこえそうですが、男の子むけでしょうか。
いつも思うのですが外国では結構長い話が多く、昔話=口承というのは、どのようにして受け継がれてきたのか知りたいところです。
 |
だれのたまご/作:斉藤 洋 絵:高畠 那生/フレーベル館/2012年初版
たまごがさきにあって、うまれるものを予想するかと思ったら、あららという感じです。
たまごというと、楕円形というイメージですが、瓶からカメがうまれてきたり、白黒のページのあとにはカラーの絵がでてきたり、だんだん形ができてきて、オーケストラの絵では”おんがくのたまご”でした。
おたまじゃくしがでてきて、だじゃれになっています。
不思議なのは見返しの絵で、電信柱にカラス?がとまっています。
最後のページにたまごがからうまれかけているのは、この絵本そのもです。
固定観念を持たず、自由な発想を楽しめますが、こんな世界は絵本ならではです。
大人と子どものための世界のむかし話5 ポリネシア・メラネシアのむかし話/ダイクストラ好子・編訳/偕成社/1989年初版
すごくシンプルに海のはじまりを教えてくれる昔話です。
二人の孫と暮らすおばあさん。
おばあさんが畑に行く前に、孫に囲いに入ってはいけないと言い残してでかけます。
みるなといわれて、何があるだろうと囲いをのぞいた二人。
なかにはサトイモの葉があるだけです。
二人はトカゲがサトイモの葉にとまっているのをみると、矢をはなちます。
矢はサトイモの葉に穴をあけてしまいます。すると葉の中から水がこぼれだし、ゴウゴウと天地をゆりがすほどの音で、囲いの中に水がたまっていきます。
おばあさんが、この音を聞いて「あまねく、そそげ、世界中に」と叫ぶと、囲いの水がおばあさんの家といわず、畑といわずのみこんでしまいます。
それでも水はとまらず、あふれつづけ全世界にひろがっていったというのですが・・・。
サトイモを育てるときは、水やりが大切といわれていますが、逆に水をつくるというのも、どこからきているのでしょうか。
このおばあさんも不思議な存在です。
 |
ぼくは建築家ヤング・フランク/作:フランク・ビバ 訳:まえじま みちこ ばん しげる/西村書店/2015年初版
自称建築家のヤング・フランクはまだ子どもですが、トイレットペーパーで椅子をつくったり、本を積み上げて超高層ビルをつくったり、一つの町全体をデザインしたりしていましたが、おじいさんのオールド・フランクは首をかしげます。
そこで美術館にいって建築家の作品をみることを提案します。
ところが、美術館にはフランクという建築家の作ったくねくねした椅子があり、おなじフランクという名前のねじれたタワー、またこれもフランクという建築家のつくった町全体の大きな模型もあって、オールドはうなります。
そこで二人はいろいろなものを作り始めます。
建築を既成の概念でとらえないでとでもいっているようです。
オールド・フランクの「わしがまちがっていたようだ」という率直な感想。そして「ちょっぴり若く、そして少しかしこくなった気がした」という言葉は、年を感じさせません。
ところで訳が二人で、ひとりは坂茂さん。
いつかテレビで、2011年の地震で被害を受けたニュージーランドのクライストチャーチ大聖堂の仮設教会を紙管で作る様子が放送されていて、はじめて知った方です。
1995年の阪神・淡路大震災後の紙のログハウス(仮設住宅)や、トルコ、インドで起きた地震に際しても仮設住宅の建設を行い、2005年に津波災害を受けたスリランカキリンダ村で復興住宅、2008年に大地震の被害に遭った中国四川省の小学校の仮設校舎、さらに東日本大震災では、体育館などの避難所に避難したものの、ひとつの空間で多くの人々が同居している状態で、プライバシーがまったく無くて苦しんでいるが言いだせない人々のために、紙管と布を使った間仕切りでプライバシーを確保する提案をし、各地の役所職員たちを説得してまわり、また仮設住宅の建設、質の向上にもかかわった。女川町で海上輸送用のコンテナを使い家具を作り付けにした2-3階建仮設住宅は快適で、期限が来てもそのまま住み続けたいと希望する人々が多かったという。(ウイキペデアから)
日本の民話4 民衆の英雄/瀬川拓男・松谷みよ子・編著/角川書店/1973年初版
伝説とありますが、川の氾濫に悩まされた村の人のため泣きながらあっというまに堰を作ってしまった男の話。
阿蘇山のふもとのひのき村というところに、恐ろしく力の強い男が一人。
あるとき、父親が一日中何もせず横になっている息子を、きのことりにいかせると、きのこだけをとるのは面倒ときのこのはえている木を引き抜き、担いで帰ったことから「なば」(きのこ)と呼ばれるようになります。
ある日、”なば”が山で仕事をしている男たちに弁当を届ける途中で腹が減ってしまい、途中で弁当を全部食べてしまいます。
腹が減っていた村人たちは、寄ってたかって”なば”をを殴り、次々に責め立てる。するとなばは「おらが悪かった。みんなの分さ働くばい」と大泣きながら、何十人掛かっても下ろせなかった大松を、軽々と担いで村まで運んでしまいます。
ある年のこと、長雨が降り続き、町の川があふれて堰がくずれ、誰もかれも大弱り。
竹で堰をつくるため”なば”は、町中の鉈を借りて竹を切りにいこうとするが、鉈を貸してくれる者がいない。怒った”なば”が、素手で竹を引き抜き、束ねた竹をひきづりながら町の真ん中をガラガラ竹の音を響かせ通っていくと、店の戸は打ち壊され、品物はひっくり返ってどろまみれ。
遅れて堰をつくるところにくると、集まっている人々が「ぬしゃまたあそんどったじゃろ」「おそいおそい」と口々にののしります。
かっとした”なば”は、「そぎゃんぶつぶついうな。どけどけおらがしてやるけん」とまたたくまに、堰をつくってしまいます。
仕事が終わると”なば”は何も言わずに山へ帰ってしまいます。
町の人はいったそうな。
「あいつはたいしたもんじゃ。泣きながら堰おば作ってしまったばい」
それ以来「なばの泣き堰」といって、知らぬ者がないくらい有名になります。
百人力といいながら、泣くと力がでるというどこかユーモラスな男。
怪力が人々の暮らしの助けになるというのは、どこかほっとする話でしょうか。はじめから出番があるのではなく、人々が困っているところにタイミングよくあらわれます。
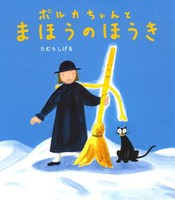 |
ポルカちゃんとまほうのほうき/作・絵:たむら しげる/あかね書房/2007年初版
魔女の女の子ポルカちゃんが、おかあさんが夕食のシチューをつくっているとき、お部屋の掃除をしてくれるよう頼まれます。
ところが、このほうきがポルカちゃんのいうことを聞きません。掃除が大嫌いと逃げ出します。
やだやだとポルカちゃんとねこをのせたほうきは、むちゃくちゃに飛び回り、ガツンと木にあたって、折れてしまいます。
この木、なんと接着剤の木。実をもらって折れたほうきを直しますが、30分はじっとしていなければなりません。
30分立って、テスト飛行。今度は快調です。
森をこえ、雲のお城まで、雲のお城で遊びます。
しかし急に空がくらくなり、土砂降りの雨。あらわれたのは竜でした。
魔女の家が素敵で、三角形をしており、大きなきのこがニョキニョキ。電気は風力発電です。
魔女といえば、やっぱりほうきですが、いつ頃定着したのでしょう。
ポルカちゃんが掃除をしているのが最後ですが、●うしろのひょうしを みてごらん●とあります。
裏表紙にはお母さん、ポルカちゃん、ほうき、ねこがおいしそうにシチューを食べているのですが、こんな仕掛けにはふれないで、読者をうーんとさせる絵本が多いので、一言余計なのかも。
大人と子どものための世界のむかし話5 ポリネシア・メラネシアのむかし話/ダイクストラ好子・編訳/偕成社/1989年初版
一人の少年が、海の底にある大エビをつかまえたいと思っていましたが、人食いザメのため、手をだしかねていました。
一計を案じ、大声で「ほかのサメたちをだます方法を、いちばんしっぽの短いサメがおしえてくれた」といい、岩のかけらを海に投げ込むと、サメたちは少年が海の中へ飛び込んだとおもい、水音のしたほうへおよいでいきます。そのすきに、少年は海に飛び込んで大エビを二匹もちかえります。
一回だけでなく、9回も繰り返す少年。サメは十頭いる計算です。
エビをとる前に、○○のサメから教えてもらったと大声でいうので、怒った一番大きなサメが、仲間を食べてしまったので、サメはどんどん減っていきます。
残ったのは大ザメだけ。
こわいサメと少年の組み合わせ。
少年の知恵がまさっていました。
最後は大ザメにまるごと飲み込まれるよう独り言をいい、大ザメが少年を飲み込むと、少年は両端のとがった棒をサメの口に突き立てたので、サメは口を閉じることができなくなります。
そして、大ザメのはらのなかで、サメの肉を切り取り、料理までしてしまいます。
少年が大ザメのはらのなかからでてきてみると、せまいサメのはらの中で頭をさんざんこすられたので、かみの毛が全部ぬけてしまい、にどと髪ははえてこなかったというオチです。
だまされるサメがいないと話ははじまりません。このサメ、釣り糸を食いきったり、せっかくつれた魚をよこどりしたり、海にもぐった人を食い殺す存在でした。
 |
魔女ひとり/作:ローラ・ルーク 絵:S.D. シンドラー 訳:金原 瑞人/小峰書店/2004年初版
丘の上のひとりの魔女が からっぽのお鍋のふたを取り、シチューパーテイの準備。
素材といえば?
二匹ののらねこからは、ごみすてばのほね
三人の藁人形からは、小鳥のつめ
四人のゴブリンからは、にょろにょろむし
五人のドラキュラからは、真っ赤な血
六人のミイラからは、きたないガ
七羽のフクロウからは、がらがらへび
八人の幽霊からは、髪
九人の骸骨からは、小指のほね
十頭の魔犬からは、くも
となんともどくどくしいものばかりです。
最後に残った一杯は、読者にむかって、さあどうぞ。
具をしっていると「遠慮します」というのが正直なところです。
数え歌らしく展開します。
最後はみんなで盛り上がりますが、小さな少女が印象に残りました。
ごった煮といった感じです。
日本の民話4 民衆の英雄/瀬川拓男・松谷みよ子・編著/角川書店/1973年初版
「三年寝太郎」は、寝ていたばかりの男が、飢饉や不作になやむ村人を救う話で、各地に類話がありますが 山口バージョンは寝ていることがあまり強調されていません。
昔話は主人公の幸せに主眼がありますが、自分のことではなく「民衆」のことを考えた話には、昔話のいきをこえて、リアリテイがあるようにも思います。
体を伸ばせば足が出て、足を隠せば頭が出るような、なんとも小さい家で、空をながめて暮らしていた厚狭の寝太郎。
ある年のこと、長雨やひでりで秋になっても稲が実らず、百姓は飢饉で苦しんでいた。
すると寝てばかりいた寝太郎がふいに起き上がって、「金もうけをしてやるから、米のならない稲を刈り集めてください」と村々をふれまわって稲のわらを集めると数知れぬ草鞋をこしらえます。
草鞋を千石船に積み込んで、向かった先は佐渡ヶ島。
寝太郎は港にあがると、「銭はいらん。はき古しのわらじを新しい草鞋ととりかえる」とおかしな商売をはじめます。
たちまち千石船一艘の新しい草鞋は、土まぶれの古わらじにかわります。
村の人は「寝太郎のあほうにはあきれたもんや。新しい草鞋を古い草鞋に取り替えてきよった」「いよいよ気がふれたかの。金もうけどころかえらい損をしたもんじゃ」と、みんなで寝太郎をばかにします。
寝太郎は気にもかけず。桶屋に頼んではしごをかけて登るほどの大きな桶をつくってもらうと、そこに水を張って、古わらじをドシャドシャと洗い始めます。
十日二十日と過ぎて、古わらじの土もすっかり洗い落とされ、桶の水をあけると、底にたまった泥にまじって、キラキラ光るものが見えます。
はしごを登って中をみた里の衆はたまげます。
キラキラ光るのは金でした。
そのころ、佐渡の金山では一握りの土でも持ち出すのはご法度。
佐渡の土を持つ出すために三年三月寝たまま考えた寝太郎は、砂金で大金持ちになります。
さて、大金を手にした寝太郎は、腕のよい石工を集めて石山の石を切り出します。
「山じゅうの石を切り出してなんにするのじゃろう」と村の人がうわさしていると、寝太郎はありったけの銭をばらまいて、「さあさあ皆の衆、わしに力を貸してくれい。よけいに米がとれるよう、荒れ地に水路を通して厚狭川の水を引こう。泥地や沼地は埋め立てて田んぼにしよう。そうすればひでりや長雨にも参らぬ田ができるぞ。こら大事だから、皆で力を合わせてやらにゃあなるまい。」といいます。
里の衆は寝太郎の深い考えがわかり、力をあわせて頑丈な灌漑溝を完成させます。
やがて、出来上がった水田は、長雨やひでりの年にも、ここらあたりの稲はよう実って、秋には黄金の波がうねり、厚狭の里はよくも栄えます。
小さな町の風景/作・杉みき子 絵・佐藤忠良/偕成社文庫/2011年
学校でバレー部に入り、早朝のジョッキングを続けていた少女が、折り返し地点の橋で、いつか出会うようになった白髪の老女。
ほぼひと月に一回の割合で会う老女が、白い紙きれを川へはなそうとして、風に吹き上げられた紙を拾い上げるのにも苦労しているのをみます。
紙を川に投げるのに苦労しているさまを見て、少女は紙飛行機の要領で飛ばしてあげます。
老女は、その紙に向かってじっと両手を合わせていました。
老女の一人息子が兵隊にとられ、遠い南の海で遺体もあがらぬ死をとげてから、家を出た日を命日ときめて、心をこめた経文を写し、海に流すことがひとつのなぐさめとなった老女。
体はよわり、やっとのことで書き写した経文を投げる力もなくなったと話す老女に、よかったら私がおばあさんのかわりに、ここから紙を投げてあげましょうかと少女はいいます。
一か月後、少女は小さな折り鶴を水に飛ばします。白い折り鶴は<平和>と大きく書かれたつばさを、いっぱいひろげて、矢のように川をくだり、やがて海にむかって見えなくなります。
老女や少女のくわしいことはなにもでてきません。
語っていない部分から想像力を働かせ、思いを巡らせる必要がありそうです。
日本の民話7/妖怪と人間/瀬川拓男 松谷みよ子・編著/角川書店/1973年初版
今はみることがないが、ちょと前までは便所が離れたところにあって、夜などはそこへいくのが怖かった時代もある。
こんな時代背景で、おばあさんが孫に語っている風景がうかんでくる話。
古い屋敷あたりにトーツポテン、トーツポテンといって化け物が歩き回るので、みんなおっかながって、ここらの子どもばかりか大人まで、夜になると小便たれにもいかれない。
勇敢な若者がでかけていくと、やっぱり一つ目の化け物が、トーツポテンとうなりながらでてきて、若者とにらめっこ。
トーツポテンは、きのこで、きのこの頭に栃の実(トッポ)がはまって、痛いのでトッポトッテ、トッポトッテといっているうちに、唸り声が癖になったという。
若者は化け物に、姉さま、次に納豆に化けさせ、納豆をすとんと飲んでしまう。
最後のオチがあって、化け物を飲み込んだ若者が胸も腹もごやごや苦しくなったので、土手の毒消しの草を食べると、ぽがあんと化け物は屁になって吹っ飛んでしまう。
化け物は怖くはないと、おばあさんは話します。