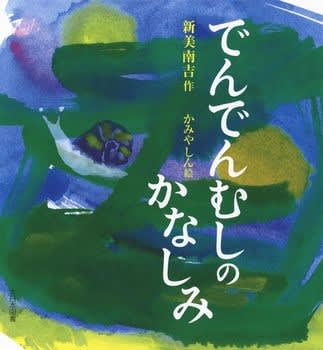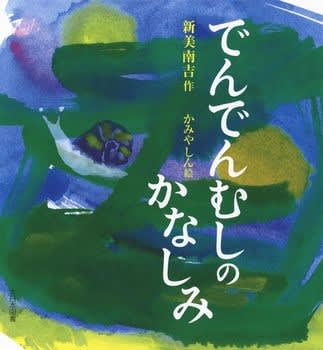
でんでんむしの かなしみ/新美南吉・作 かみやしん・絵/大日本図書/1999年初版
「一年詩集の序」という詩と「でんでんむしのかなしみ」「里の春、山の春」「木の祭り」「でんでんむし」の四つの作品。
・でんでんむしの かなしみ
一匹のでんでんむしが、ふと背中の殻には悲しみがいっぱいつまっているのではないかと気づきます。
おともだちの でんでんむしに 背中の殻の悲しみのことをきくと、ともだちも、「あなたばかりでは ありません。わたしのせなかにも かなしみはいっぱいです。」というこたえがかえってきました。
つぎつぎと 違うともだちのところへ訪ねていきますが、どのともだちの答えも同じでした。
「悲しみは、だれでも もっているのだ。わたしばかりでは ないのだ。わたしは わたしの 悲しみを こらえて いかなきゃ ならない」と、きがついた でんでんむしは もうなげくのを やめます。
でんでんむしの悲しみは、どんなだったでしょう。
一人ぼっちでないことにきがついた先には、希望があるのかも。
・里の春、山の春
仔鹿、春とはどんなものか知りませんでした。お父ちゃんが「春には花が咲くのさ」とこたえると、「花ってどんなもの?」ときくと、「きれいなもの」と、おかあちゃんのこたえ。
仔鹿が、音にひかれて、ひとりで山をおりていくと、野原には桜の花。仔鹿を見るとおじいさんが桜を一枝折って、小さい角に結びつけてくれました。
しばらくすると、山の奥へも春がやってきて、いろんな花はさきはじめました。
何度も春を経験すると、新鮮さが失われますが、一番はじめの春の訪れを感じたわくわく感があります。
・木の祭り
野原の真ん中にぽつんとたつ木に白い美しい花がいっぱい咲きました。けれどもだれひとり「美しいなあ」と褒めてくれません。
ところが木の花の匂いが小川を渡り、崖っぶちをすべりおりて、じゃがいも畑まで流れていくと、そこにいたちょうちょうたちは、木のところへいって、みんなで祭りをしてあげようということになりました。
羽根がいちばん小さなシジミチョウが小川のふちで休んでいると蛍に気がつきました。遠慮する蛍を誘って、木にいくと、ちょうちょうたちは、木のまわりを大きなぼたん雪のようにとびまわり、疲れると白い花の蜜をすいました。夕方になると、蛍が自分の仲間をつれてきて木の一つ一つの花の中に泊まり、ちょうちょうたちは夜遅くまで遊びました。
蛍と蝶が舞う幻想的な世界です。
・でんでんむし
うまれたばかりのでんでんむしの子が、おかあさんに 聞いています。
「あめは ふって いないの?」「ふって いないよ」
「かぜは ふいて いないの?」「ふって いないよ」
「みどりの はっぱよ」
「はっぱの さきに たまが ひかっている」「あさつゆって もの きれいでしょ」
見るもの、何もかもがふしぎなことばかり。
でも、おかあさんにも、こたえられないものも。
空のなかに だれかいるの?
空の向こうに なにが あるの?
おかあさんでも わからない ふしぎな とおい 空を、いつまでも みていた、でんでん虫の赤ちゃんに見えていたものはなんだったのでしょうか。
かみやしんさんの淡い水彩画が、新美南吉の優しい世界を彩っています。