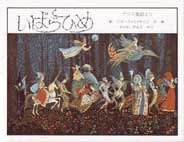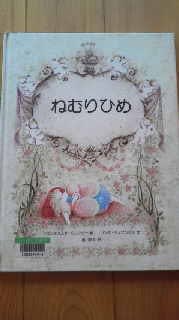天からふってきたお金/アリス・ケルジー・文 岡村和子・訳/岩波書店/1964年
トルコの[ナスレッディン・ホジャ物語」には600ほどのホジャ物語があるといいます。
とんち話が多く、聞いていても楽しそうな話ばかりですが、なぜか話を聞いたことがありません。
おはなし会のプログラムをみてもあまりのっていません。もっと語られてもよさそうなものばかりなのですが・・・。
この「三つの質問」は、昔話によくでてくる難問に答えるというものです。
町にえらい三人の僧がやってきて、町長の依頼で、ホジャが答えることになります。
第一の質問「地球の中心はどこにあるか?」
第二の質問「夜空に輝く星の数はいくらか?」
第三の質問「わしの あごひげの毛の数は何本ありますかな?」
質問した僧も多分答えられないものに、ホジャが切り返していうには
「地球の中心はロバの後ろ足の真下」・・答えがうそだと思ったら、自分で測りなさい。
「星の数は、ロバの毛の数と全く同じ」・・空の数をかぞえ、それからロバの毛を数えなさい。
「あなたの髭の毛の数は、ロバのしっぽと毛の数と全く同じ」・・あなたが、ロバの毛を一本抜いたら、そのたびにわたしは、あなたの髭を一本抜く、こうしてあなたの髭の毛が一本残らずなくなったとき、ロバに毛がのこっていたりしたら、あなたの勝ち」
自分のロバだけで難問にこたえるホジャです。
もともと答えられない質問なのですが、僧はどう思っていたのでしょうか。