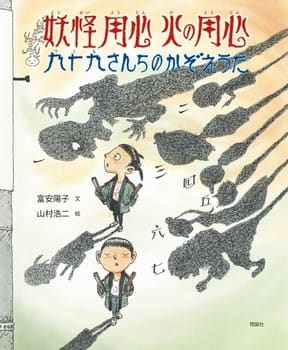動物が助けられたお礼をする昔話も多い。そのなかでツバメなど鳥が主役になるもの。
助けられてから、いったん助けた人の前を去り、翌年にプレゼントをもってくるというのにうまくマッチするのがツバメか。渡り鳥ならではの話ができる。
・腰折れ雀(日本昔話百選 改訂新版/稲田浩二・稲田和子編著/三省堂/2003年)
羽を折られた雀を助けたおばあさんが雀から種をもらい、植えてみると見事なひょうたんができ、その中からお米がでてきて、使っても使ってもつきることがない。
それをみた隣の欲深婆さんが、石をなげて木から落ちた雀に、優しいお婆さんのまねをして米粒をやったり、水をやったり。この欲深婆さんにも、雀が種をもってきます。
欲深婆さんができたひょうたんをあけると、蛇、蜂、むかでがでてきてお婆さんを殺してしまいます。
この話は、1200年代の前半までに作られた「宇治拾遺物語」にものっており、すくなくとも900年までさかのぼることができそうだ。(宇治拾遺ものがたり/川端義明/岩波少年文庫/1995年初版)
・かぼちゃの種(朝鮮民話選/岩波少年文庫/1987年改版)
ツバメを助けた心のやさしい弟が、ツバメからかぼちゃの種をもらう。できあがったかぼちゃから大工や木材が出てきて立派な家を、二つ目のかぼちゃからは百姓や女の召使いがでてきて「なんでも御用を言いつけてください」と声をそろえていい、さらに三つ目のかぼちゃからはたくさんの金や銀がでてきます。
これをみた欲深兄さんもわざとツバメを傷つけ、薬と白い布で介抱してあげるが、翌年ツバメがもってきた種からできたかぼちゃからは、大勢の鬼や借金取り、さらに泥がでてくる。兄弟とあってか、最後には兄弟がなかなおりするという結末。
どちらも「恩返し型」で、登場人物は「ペア型」。一方はおばあさんと欲深おばあさんで、もう一方は兄弟。ペア型の登場人物は、一方は正直で勤勉、もう一方は欲深。対比させることで劇的な構造をもたせるのはペア型の特徴である。
・男の子とつばめ(シルクロードの民話1 タリム盆地/小澤俊夫編 虎頭 恵美子訳/ぎょうせい/1990年初版)
男の子が、翼さが折れていたツバメを助けたことから、翌年ツバメがまくわうりの種をプレゼントしてくれる。大事に育てると、まくわうりのなかから金がでてくるというもの。
まくわうりを育てるのは、男の子ではなく父親。この育て方を丁寧に描いているのがほかの二つとはちがうところです。
この金のことが王さま(パーデシャ)に知られることになり、金がとりあげられてしまいます。王さまはツバメのもってきたまくわうりの種からできたまくわうりをもってきたら、金をかえすという。
最後は、想像できるように、まくわうりから蛇がでてきて、王さまを殺してしまうという結末。似たような話でも微妙な違いがみられる。
・二人の隣人の物語(チベットの民話/W・F・オコナー編 金子民雄訳/白水社/1999年初版)
貧乏な男が、けがをした燕を助け、もらった穀物の種をまくと、宝石が実ります。金持ちの男が無理やり燕を傷つけ、手当てして離してやり、もらった穀物の種をまくと、見るからに恐ろしい顔つきをした男があらわれます。
恐ろしい顔をした男は、「前世に金を貸してあった債権者だ」となのり、金持ちの家や、土地、家畜などの所有物を取り上げ、奴隷の身分に落としてしまう。この話はここで終わらず、さらに続きます。
・金色のカボチャ(世界民話の旅7中国・東南アジアの民話/河野六郎他/さ・え・ら書房/1980年初版)
上と同じくチベットの昔話。
助けた鳥がくれたかぼちゃの種。カボチャの中身は金でした。
欲張りのお爺さんのカボチャからは、こわい顔のおじいさんがでてきて、おじいさんの首をきってしまうというもの。
・金色のカボチャ(チベットの昔話/アルバート・L・シェルトン 西村正身・訳/青土社/2021年)
上記のものと微妙にちがっていて、出典が異なっているものかもしれません。
助けた鳥がくれたかぼちゃの種。やがてできたカボチャは、五人がかりでやっと運ぶ大きさ。カボチャの外側の皮をむくと、それは紙のように薄くて、洗うと純金。老人は、貧しい人々に与えたり、必要とするすべての人を助けけるために、使います。
欲張りのお爺さんのカボチャからは、閻魔大王に頼まれて、お前の重さをはかるためにきたという老人があらわれ、いざ体重をはかり、軽すぎて何の役にもたたんと、老人の首をきってしまいます。
・コウノトリのおはなし(ウズベクのむかしばなし/シェルゾット・ザヒドフ編・再話 落合かこ 他訳/新読書社/2000年初版
コウノトリを助ける貧しい男が、コウノトリからもらったスイカの種をまくと、スイカからは金貨があらわれ、怠け者が無理やり傷つけたコウノトリがもってきた種からは、ミツバツがでてくるという話があった。
怠け者は誰にも見られないようにドアのカギというカギを全部かけたので、ミツバチから逃げ出すことができず、死んでしまう結末になっている。
この手の話はアジアを旅しているのかなとも思う。