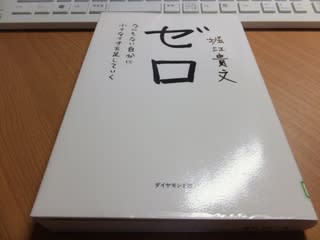
図書館で借りた本
ゼロ/堀江貴文
自分の心に響いた部分を以下抜粋メモとして。
-------
チャンスは誰にでも平等に流れてくる。
川で洗濯をしていたおばあさんは、奇妙な桃だと怖がらず、洗濯中で忙しいと無視せず、とにもかくにも大きな桃に飛びついた。鬼退治の物語はおばあさんが桃に飛びつくところから始まった。
目の前に流れてきたチャンスに躊躇なく飛びつくことができるか。人としての「ノリのよさ」が重要である。
フットワークの軽さ、好奇心の強さ、リスクをとる勇気、これらの総称が「ノリのよさ」である。
必要なものはチャンスを見極める目ではなく、躊躇せず飛び込む「ノリのよさ」。
やりがいのある仕事をしたいというが、やりがいとは「見つける」ものではなく、自らの手で「つくる」ものだ。
長野刑務所服役中に無地の紙袋をひたすら折る仕事を与えられた。担当者から折り方の説明を受け、ノルマとして1日50個を課せられた。どうすればもっと早く、もっと上手く折ることができるのか。教えられた手順に無駄はないか。折り目をつけるときに紙袋の角度を変えてはどうか。担当者から教えてもらった手順をゼロベースで見直し、自分なりに創意工夫をして3日後には79個折ることができた。単純に楽しいし嬉しい。仕事の喜びとはこういうところから始まる。仮説を立て、実践し、試行錯誤を繰り返す。能動的なプロセスの中で「与えられた仕事」は「つくり出す仕事」に変わっていく。やりがいのある仕事にするのは自分自身の取り組み方の問題である。
仕事を好きになるたった一つの方法とは「没頭する」こと。
人は何かに没頭することができたとき、その対象が好きになることができる。
スーパーマリオに没頭する小学生は、ゲームを好きになる。
ギターに没頭する高校生は、音楽を好きになる。
没頭しないまま何かを好きになることはなく、没頭さえしてしまえばいつの間にか好きになっていく。没頭するためには自分の手でルール、目標をつくること。長期的な大きな目標ではなく、短いスパンでギリギリ達成可能なレベルの目標を掲げ、それに向かって猛ダッシュする。
「悩む」と「考える」は違う。
「悩む」とは物事を複雑にしていく行為。人は悩もうと思えばいくらでも悩むことができる。
「考える」とは物事をシンプルにしていく行為。原理原則に従い、理性に耳を傾けること。湧き上がる感情とのせめぎ合いであり、感情を退けて下す決断はときに大きな痛みを伴う。しかし、感情に流された決断は迷いがつきまとい、後悔に襲われる可能性がある。理性の声に従った決断には、迷いも後悔もない。
シンプルだったはずの課題を複雑にしているのは、心であり揺れ動く感情である。自分の人生を前に進めていくためには迷いを断ち切り、シンプルな決断を下していく必要がある。
--------------
「泳ぐのをやめたら死んじゃうマグロみたいに、堀江さんも働くことをやめたら死んじゃうんじゃないですか?」
知人からそう言われたという筆者は、小学生のときから死への恐怖にとらわれてきたという。
死を忘れるために働き、死を忘れるために全力疾走してきた。
他人からみればとんでもない努力家と言われても、そんな努力は当たり前のことと切り捨てる。
感情に流された決断には迷いや後悔がつきまとうとし、感情を退け理性に耳を傾けて、ときに大きな痛みを伴いながらも常にシンプルに決断を下してきた。合理主義に徹し、猛スピードで人生を突進する筆者であるが、こうした価値観を育んだのは彼の生い立ちが深く影響しているのだろう。感情を押し殺し、冷静に、ある意味ではドライに切り捨てる決断をこれまでしつづけてこれたのは、なるほどそういう境遇であったからなのかと納得した。
既得権やしがらみなど世の中にはびこる不合理によって現代社会は閉塞感にとらわれている。だからこそ徹底した合理主義を貫き、裸の王様にはハッキリと裸だと叫ぶ筆者の姿勢に若者は共感し、多くを支持を得る。
以前、洋食を食べるのに箸を使わないのはどうしてなのかとの筆者の記事に触れて目からウロコが落ちた気がした。箸を器用に扱える東洋人は、フォークとナイフを使うよりもずっと上手にキレイにステーキを食べることができる。箸を使うことができるのは、西洋に対して優位な文化だと。
理想の姿を頭の中で思い描くことはできても、実践できず一歩を踏み出せない。そんな若者の背中を本書は押してくれる。筆者の合理的で前向きな生き方には見習うべきところが多く、たくさんの教えがある。
仕事に対する価値観、人生に対する価値観は人それぞれにあり他人に否定されるものでもない。自分の人生観とは千里の径庭があるが、それでもなお、ドライでストイックな筆者をリスペクトせずにいられない。
あっという間に読了。
話題本なのですぐに返しますね。









