




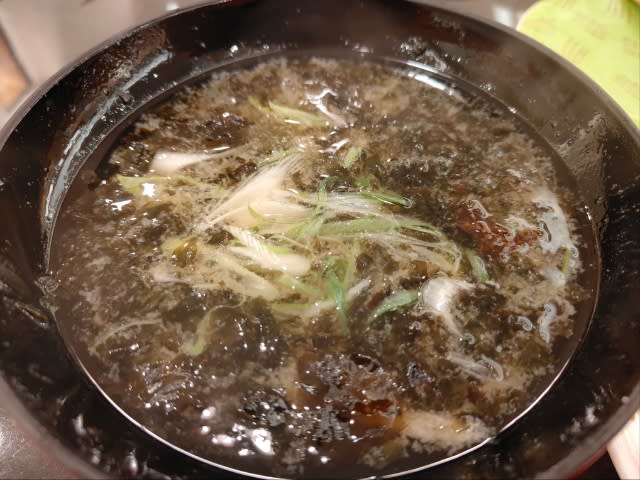

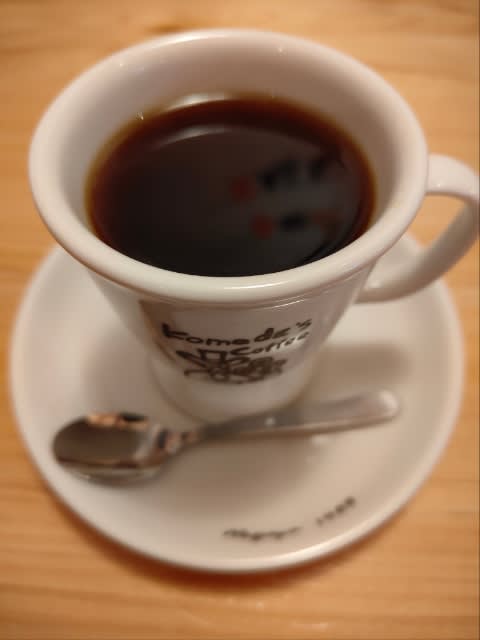
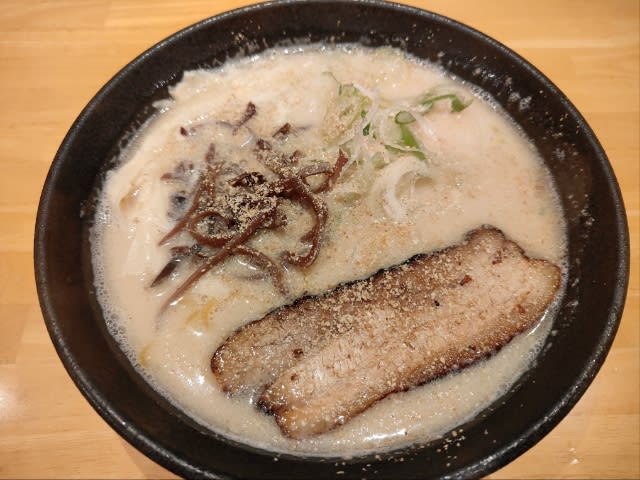









自分は多数派の座ってするタイプ。
飛び散る量が2600滴と聞いてからそうするようになりました。
ネット界隈では様々な意見があるようですが、さて、どっちが正解なのでしょうね。
--------------------------
立っておしっこをすると、目には見えませんが、周囲の床や壁までおしっこが飛び散ってしまいます。ある試験データによると、便器の水たまりを狙った場合に飛び散る量は、1回あたり372滴。1日7回おしっこをすると考えると、毎日約2600滴にもなります(※ライオン調べ)。
--------------------------
ネットでの意見(抜粋)
--------------------------
シャワートイレを使わなわいと、衛生的に気になるようになってしまった自分。
わずか30年前には考えもしなかったことが今や普通になってしまっている。
一度便利なものを手に入れてしまうと、もう後戻りできないのが、人間の性なのですね。

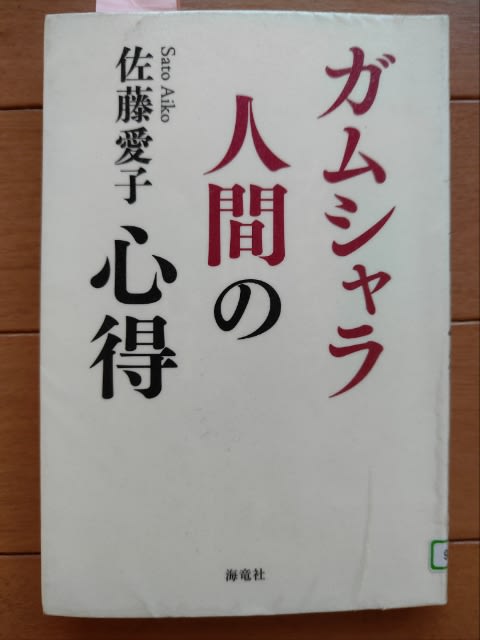
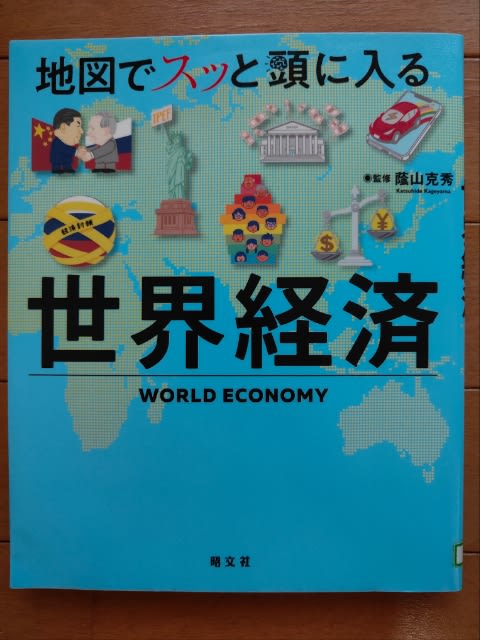
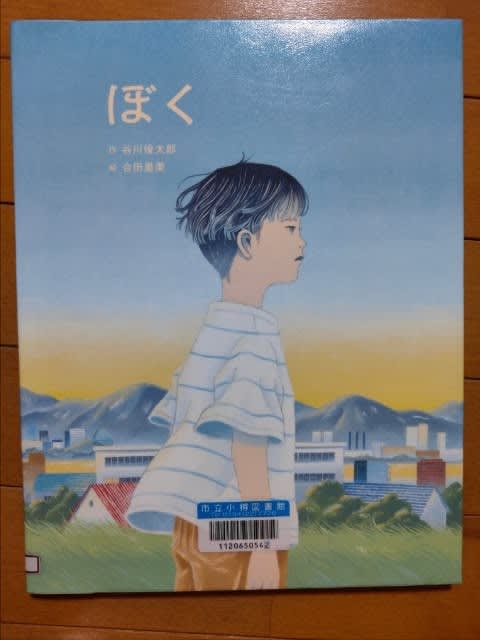
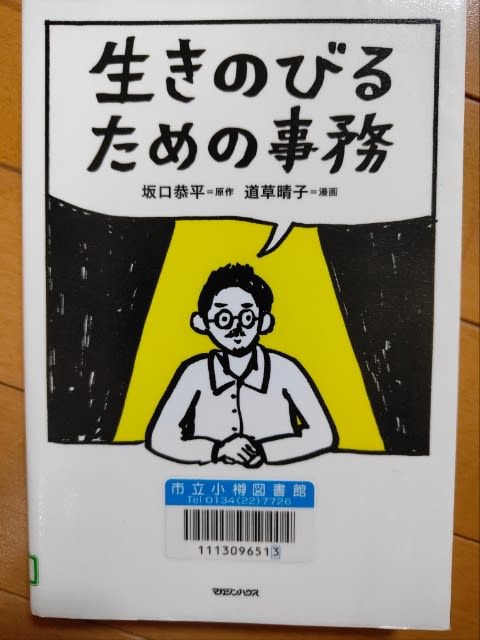
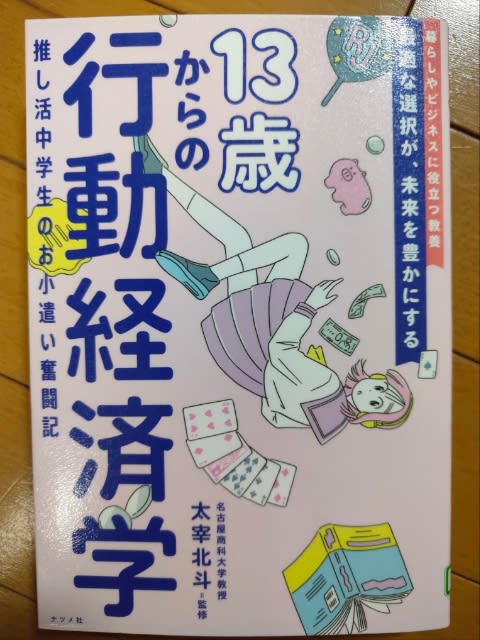

谷川俊太郎の詩は、シンプルな言葉の背後に広がる深い感情が特徴であり、人の心に訴える力を持つ。
彼の作品では、具体的な情景や感覚が詩的イメージとして鮮明に描かれ、それが読者の記憶や感性を呼び覚ます。
例えば、風景や日常の出来事が巧みに描かれることで、普遍的なテーマである生と死、時間の流れ、自己の存在といった問いが浮かび上がる。
谷川の詩はまた、読む人の解釈に自由な空間を提供する。
その言葉は過剰に説明的ではなく、むしろ余白が多い。
この余白が、読者に自分自身の経験や思いを重ねる余地を与え、詩に個別の意味を付加させる。
この構造は、詩を単なる詩人の言葉としてではなく、読者の内面で生きるものに変える。
こうした読者参加型の詩の構造は、谷川作品の魅力を際立たせている。
彼の詩は、日常の中の特別さをすくい上げ、普遍的な人間経験に昇華させる力を持つ。
人の心を震わせる普遍的な美しさを、谷川俊太郎は言葉の中に見事に結晶化している。
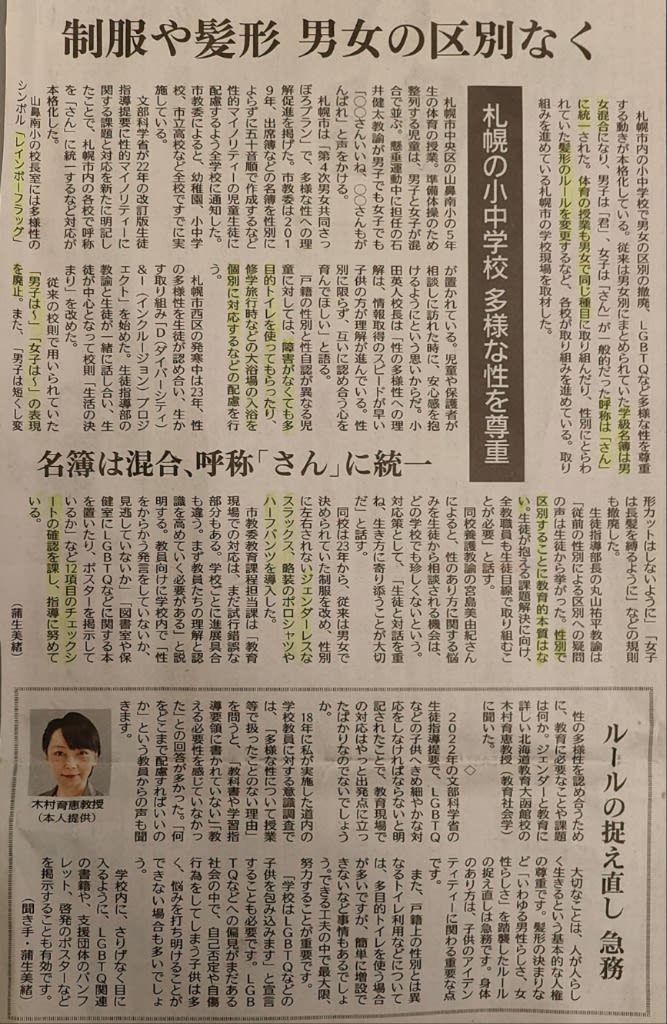
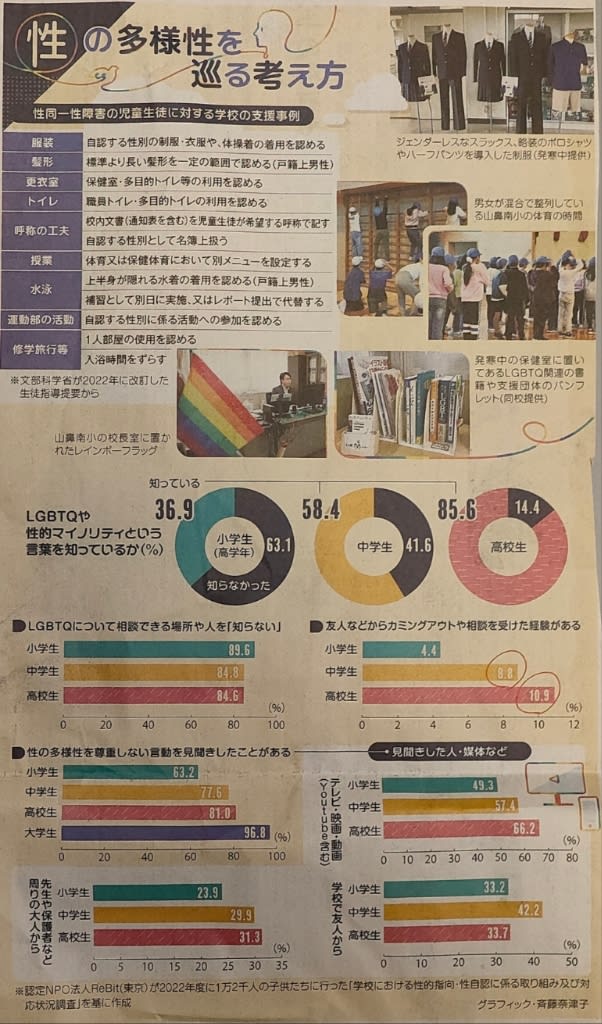

雑誌で読んだメンタルヘルスについての記事が興味深かったので、以下、自分用メモとして。
----------------------------------------------------------------
メンタルヘルス不調になると、回復しても再発率が高く、さらにその後も再発を繰り返す傾向がある。
その結果、病気休暇取得率も高くなっていく。
国や自治体では療養から復職支援までの手引きを作成し支援しているが、何としても、かからないことが重要である。
指導者・管理職は毎日、仕事を通じて職員を見ているのだから、ストレスチェック制度に依存せず、そうなる前に手を打たなければならない。
メンタル不調には原因があり、その多くは職場の対人関係や業務内容にある。
仕事が原因である場合は、仕事で解決するしかない。
本人の状況を把握し、それに応じた仕事の的確な指示、業務分担、報告の仕方など迅速な対応を行い、部下の精神的負担を軽減するのは管理職の義務である。
仕事は60点でよい。
無理する必要はないことを明確に上司が示すべきである。
仕事を指示する場合、期限を示しスケジュールを立てさせ、適宜、上司に進捗状況を報告させ、一人で抱え込ませず問題点を共に考える。
必要があれば自らその仕事の一端を引き受け、率先垂範して共に仕事に取り組む。
組織全体で合格点につくり上げていけばよい。
チームプレイであり、最後は管理職が責任を負う。
育児休業の勧奨と同様、深夜勤務を強いなくてよいようにすることを管理職評価の基準とすべきである。
現行体制では困難であれば、事務の効率化や予算・人員の増員など必要な手を打つことも管理職の務めだ。
人事院勧告でも、業務量に応じた柔軟な人員配置や必要な人員確保に努めることを各省に要請している。
「うまくいけば部下の手柄、失敗すれば自分の責任」と上司が言える職場にはメンタル不調は生まれまい。
職員を信頼し、必要な指導の上、褒めて自信を持たせ職員を育てることが上司の務めである。
職場が楽しく、仕事にやりがいを持つことが職員の心の健康に不可欠である。
今回の人事院勧告でも、公務版の「健康経営」の推進を勧告し職員のwell-beingを喫緊の課題としている。
自分がいないと仕事が回らないと考えるのは間違いで、別の課員でも当該仕事を理解できるように透明化しておくことが重要であり、それが不正を防ぐことにもつながる。
予算も抑制され人員も減少する中で、新型コロナ対策や頻繁化・激甚化する自然災害対応など業務が増加・複雑化している。
IT・デジタル化などで新たな知識を必要とする中、ともすれば自信を失いがちである。
こういう時こそ、職員同士がお互いに尊重し合い、支え合っていくことが大事だ。
厚生労働省は、国民の健康を保持するために広く継続的な医療を提供すべき疾病として、「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「糖尿病」に加え、「精神疾患」を追加し対策に力を入れている。【5疾病(5大疾病)】
■参考
(医療法第30条の4第2項第4号)
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
(医療法施行規則第30条の28)
疾病は、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患とする。
メンタルヘルスに起因する代表的な5つの精神疾患
----------------------------------------------------------------
■参考リンク(過去記事 メンタル関係)










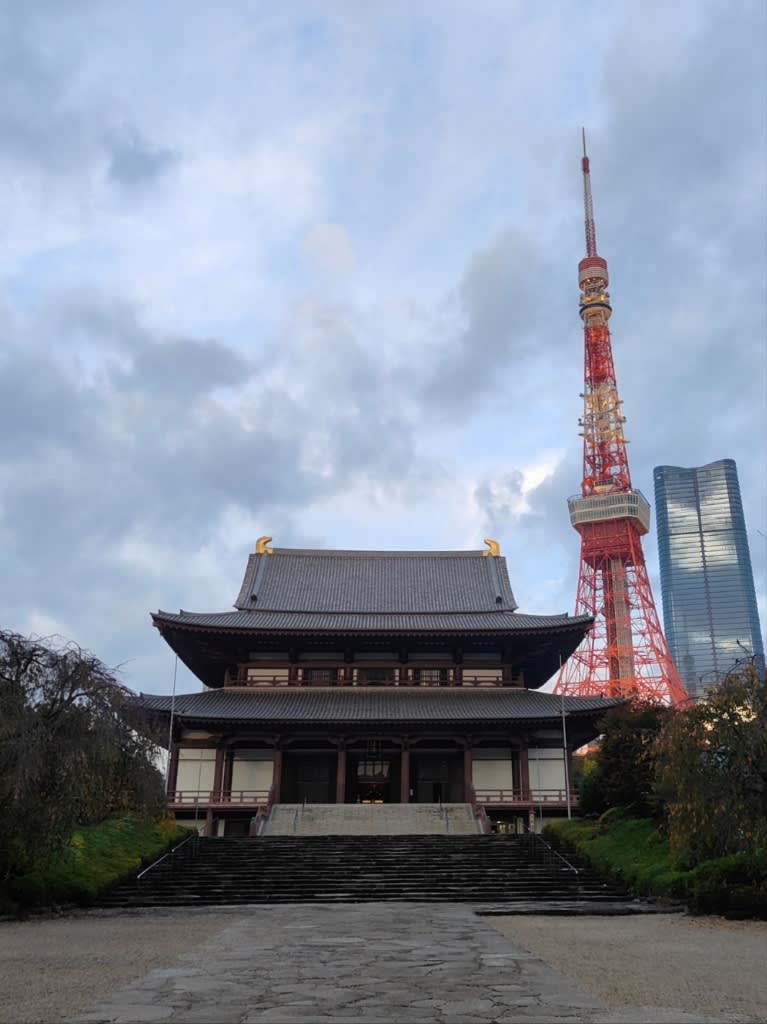



























新聞に掲載されていたエッセイを興味深く読んだ。
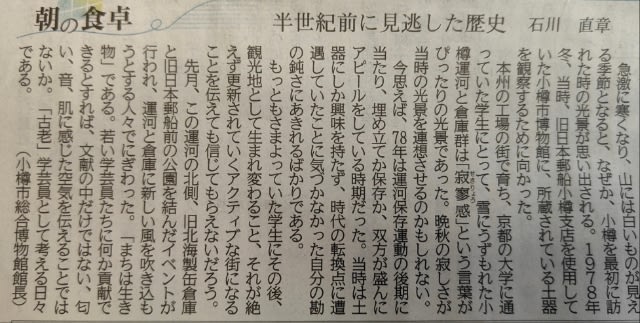
晩秋に感じる寂寥感。
若かりし頃の思い出が、胸に強烈に焼き付いているのが窺える。
若いうちの経験がいかに大切か。
人生観を変えるほどの、その後の人生を左右する分岐点となり得るか。
身を持って知っているからこそ、若い人たちに自分が貢献できるとしたら、肌に感じた空気を伝えることだと説く。
若いうちにしか感じることができない空気感、経験があるのだから、君たちもたくさんの経験を積んでほしい。
各々に空気を憶え、吸収し、人生を切り拓いてほしいと願う。
50半ばにして自分が今職場で思うのもまさに同じで、若い同僚にはできるだけ色んな経験させたい。
それが人材育成につながり、ひいては将来を背負う人材となるかもしれないのだから。
静岡の工場の街で生まれ育った少年が、ひょんなことから北辺にある斜陽の街で歴史を語り継ぐ語り部となっているように。
それにしても、人それぞれに感じる晩秋の寂しさ、寂寥感はあるものなのだな。
私がいつも感じる晩秋の寂しさの情景はこちら