
骨董という作品は飾るだけが目的では決してなく、基本的には使うためのものであろうと思います。筆立てに小さな李朝の壺を使ってみたり、盃洗を花入れにしたり、香合を珍味入れにしたり、醤油差に大きめの水滴を転用したりと人様々な使い方をし、そのセンスの良さに度々驚かされることが多いものです。

その使用目的から入手するのか、入手してからそのような使い方になったかはその作品によって動機もまた様々なのでしょう。本日の作品はその図柄の面白さから購入し、入手してらさて何に使おうかと思案している作品ですが、そもそもこれはなに?という作品の紹介でもあります。
呉須染付梅ニ小禽図馬蹄形陶板
誂箱
最大幅255*最大奥行*厚さ20

本作品の説明には「李朝前期」とあり、さらにメールにて「古い箱は破棄したが、その箱には李朝前期と記されていた。」という連絡がありました。ただ李朝前期にこれほど豊富に呉須(コバルト顔料)を使用するとは考えられないので、図柄から日本で製作されたか、李朝後期の作かと推察するのが無難かもしれません。もしかしたらデルフト焼のタイル・・・???の可能性もありますね。

「李朝前期にこれほど豊富に呉須(コバルト顔料)を使用するとは考えられない」というのは、李朝と呉須(コバルト)には下記の歴史があるからです。
**********************************************
李朝の染付
14世紀、元時代の中国で、焼きものの表面にかけられた釉薬の下に、コバルトを用いて青い模様を描く方法が確立されます。この染付と呼ばれる手法を用いた焼きものは、量産されるようになった15・16世紀以降、中国国内にとどまらず、朝鮮半島や日本へもかなりの量が輸出され、大変な人気を博します。
それだけ需要のある作品となったことから、朝鮮の国王やその側近の人たちが、輸入に頼るだけではなく、何とか自分の国でも作れないかと考えたのは、ある意味で自然な発想だったと言えるでしょう。『朝鮮王朝実録』という朝鮮時代(李朝)の歴史を記録した書物には、15世紀に朝鮮国内で染付磁器を作ろうとして努力していたことが克明に記されており、実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。
しかし、染付を作るのに欠かせない原料のコバルトは、その頃の朝鮮国内では採取されていないものであったため、僅かな輸入品に頼らなければならないのが実情でした。しかも、当時コバルトはかなり高価で、それほどたくさん手に入るものではなかったようです。そのため、17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、「染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない」として使用が禁止されることまであったどうです。
ところが、18世紀に入ると、徐々にコバルトがまとまった量輸入されるようになり、だんだんと染付が量産されるようになっていきます。それでも初期には、まだコバルトの輸入量がそれほど多くなかったためか、器全面に染付で模様が描かれることはほとんどありませんでした。また、コバルトが貴重品であったため、薄めて使っていたらしく、染付の青の発色は全体にくすんでいて、あまり色鮮やかではありません。
これに対して、19世紀の染付は青の色あいがかなり鮮やかとなります。また、コバルトの輸入量が増加したらしく、ふんだんに使われるようになり、器のほぼ全体をコバルトで青く染め上げた瑠璃地と呼ばれるものまで出現します。この瑠璃地は、一見すると青い釉薬がかけられた焼きもののようにも見えますが、実際には器のほぼ全面を染付で青く染め上げているだけで、釉薬自体は透明です。瑠璃地のものをよく見ると、青い色にずいぶんムラがあることが分かりますが、これは釉薬の下に塗ったコバルトの塗りムラです。
なお18世紀の朝鮮の染付はいかにもケチで、貧乏臭い貧相なもののような印象を持たれるかもしれませんが、むしろ大きな余白を残しつつ、簡素な模様を効果的に配置しているところなど、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。またコバルトの鈍い発色も派手さはありませんが、味わいのある渋い色となっています。作り手にとっては単に原料を少なくした結果だったのかもしれませんが、それがまた違った面での良さとなっているのは李朝染付の味わいになっています。
李朝時代を時期区分
初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,
中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,
後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),
末期(1860‐1910)=朝鮮近代
**********************************************

単純に考えると、以上の考察より本作品が李朝ならば李朝後期以降の作と推定されます。ただし、李朝前期の14世紀から15世紀にかけての「実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。」、「17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない。」ということにロマンを見出そうとしているのは、一概に否定できないかもしれません。

「梅ニ小禽図」はどうみても日本的? 絵はうまい。

左の書き銘は古染付風? 古伊万里風?・・・李朝なら後期? デルフト焼などの欧州のタイルの可能性もたしかに捨てきれない・・。周囲の縁の状態からはやはりタイルであったのではないか?というのが当方の現時点の推測です。

当方で入手に至った理由は3点。
1.安かったこと
2.絵がうまいこと
3.馬蹄型というよりハート形

裏面に貼られた紙には何やら書いていましたが判読不能でした。
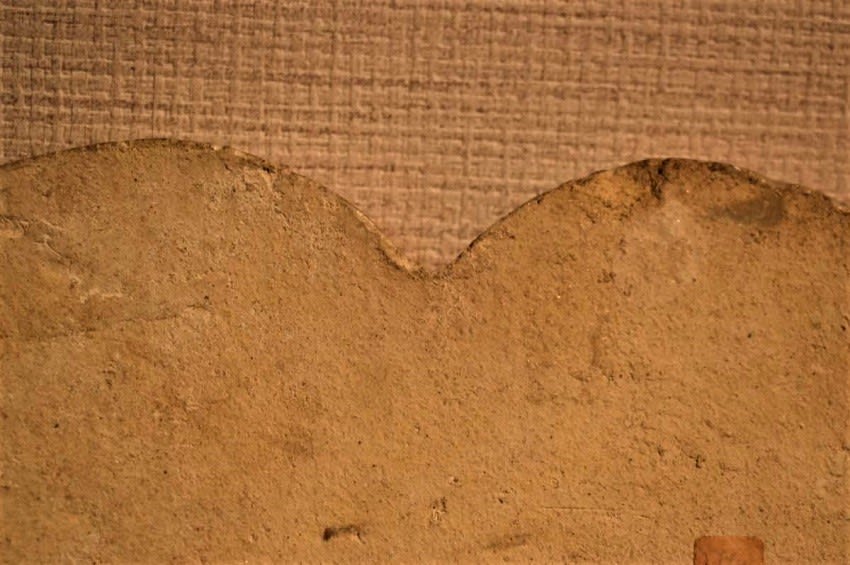
さて、何に使おうかな? また3点候補があがりました。
1.縁を補修して飾る
2.風炉用敷板
3.鍋敷
飾るのは意外につまらない。風炉用敷板だと炉をどけないと肝心の絵が見えない。鍋を載せるまで見える鍋敷かな・・・。その場合の問題は熱の伝導率・・・。
とにもかくにもハート形・・・、愛情の証に贈り物にもいいかもね
本日は亡くなった家内の命日です。郷里に日帰りですが、行の飛行機はあるが、帰りの飛行機は欠航で、帰りは新幹線・・・。

その使用目的から入手するのか、入手してからそのような使い方になったかはその作品によって動機もまた様々なのでしょう。本日の作品はその図柄の面白さから購入し、入手してらさて何に使おうかと思案している作品ですが、そもそもこれはなに?という作品の紹介でもあります。
呉須染付梅ニ小禽図馬蹄形陶板
誂箱
最大幅255*最大奥行*厚さ20

本作品の説明には「李朝前期」とあり、さらにメールにて「古い箱は破棄したが、その箱には李朝前期と記されていた。」という連絡がありました。ただ李朝前期にこれほど豊富に呉須(コバルト顔料)を使用するとは考えられないので、図柄から日本で製作されたか、李朝後期の作かと推察するのが無難かもしれません。もしかしたらデルフト焼のタイル・・・???の可能性もありますね。

「李朝前期にこれほど豊富に呉須(コバルト顔料)を使用するとは考えられない」というのは、李朝と呉須(コバルト)には下記の歴史があるからです。
**********************************************
李朝の染付
14世紀、元時代の中国で、焼きものの表面にかけられた釉薬の下に、コバルトを用いて青い模様を描く方法が確立されます。この染付と呼ばれる手法を用いた焼きものは、量産されるようになった15・16世紀以降、中国国内にとどまらず、朝鮮半島や日本へもかなりの量が輸出され、大変な人気を博します。
それだけ需要のある作品となったことから、朝鮮の国王やその側近の人たちが、輸入に頼るだけではなく、何とか自分の国でも作れないかと考えたのは、ある意味で自然な発想だったと言えるでしょう。『朝鮮王朝実録』という朝鮮時代(李朝)の歴史を記録した書物には、15世紀に朝鮮国内で染付磁器を作ろうとして努力していたことが克明に記されており、実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。
しかし、染付を作るのに欠かせない原料のコバルトは、その頃の朝鮮国内では採取されていないものであったため、僅かな輸入品に頼らなければならないのが実情でした。しかも、当時コバルトはかなり高価で、それほどたくさん手に入るものではなかったようです。そのため、17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、「染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない」として使用が禁止されることまであったどうです。
ところが、18世紀に入ると、徐々にコバルトがまとまった量輸入されるようになり、だんだんと染付が量産されるようになっていきます。それでも初期には、まだコバルトの輸入量がそれほど多くなかったためか、器全面に染付で模様が描かれることはほとんどありませんでした。また、コバルトが貴重品であったため、薄めて使っていたらしく、染付の青の発色は全体にくすんでいて、あまり色鮮やかではありません。
これに対して、19世紀の染付は青の色あいがかなり鮮やかとなります。また、コバルトの輸入量が増加したらしく、ふんだんに使われるようになり、器のほぼ全体をコバルトで青く染め上げた瑠璃地と呼ばれるものまで出現します。この瑠璃地は、一見すると青い釉薬がかけられた焼きもののようにも見えますが、実際には器のほぼ全面を染付で青く染め上げているだけで、釉薬自体は透明です。瑠璃地のものをよく見ると、青い色にずいぶんムラがあることが分かりますが、これは釉薬の下に塗ったコバルトの塗りムラです。
なお18世紀の朝鮮の染付はいかにもケチで、貧乏臭い貧相なもののような印象を持たれるかもしれませんが、むしろ大きな余白を残しつつ、簡素な模様を効果的に配置しているところなど、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。またコバルトの鈍い発色も派手さはありませんが、味わいのある渋い色となっています。作り手にとっては単に原料を少なくした結果だったのかもしれませんが、それがまた違った面での良さとなっているのは李朝染付の味わいになっています。
李朝時代を時期区分
初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,
中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,
後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),
末期(1860‐1910)=朝鮮近代
**********************************************

単純に考えると、以上の考察より本作品が李朝ならば李朝後期以降の作と推定されます。ただし、李朝前期の14世紀から15世紀にかけての「実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。」、「17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない。」ということにロマンを見出そうとしているのは、一概に否定できないかもしれません。

「梅ニ小禽図」はどうみても日本的? 絵はうまい。

左の書き銘は古染付風? 古伊万里風?・・・李朝なら後期? デルフト焼などの欧州のタイルの可能性もたしかに捨てきれない・・。周囲の縁の状態からはやはりタイルであったのではないか?というのが当方の現時点の推測です。

当方で入手に至った理由は3点。
1.安かったこと
2.絵がうまいこと
3.馬蹄型というよりハート形

裏面に貼られた紙には何やら書いていましたが判読不能でした。
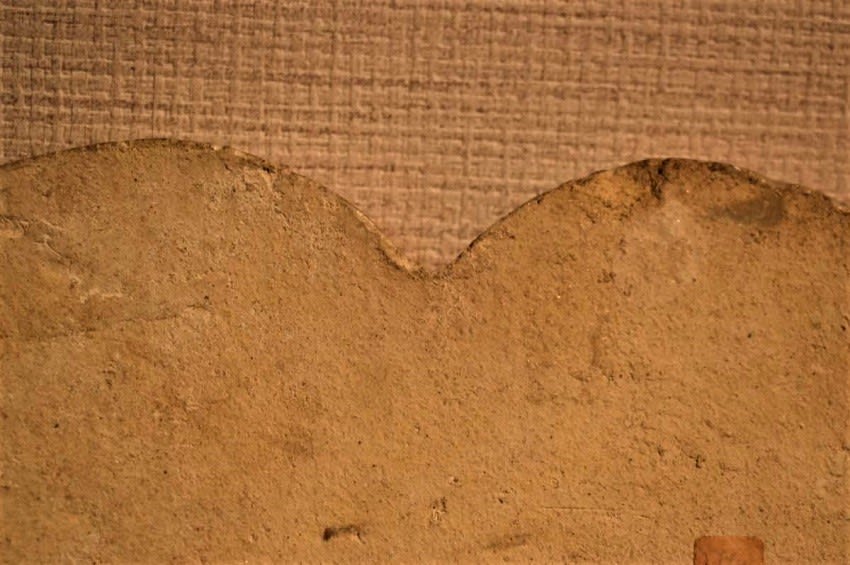
さて、何に使おうかな? また3点候補があがりました。
1.縁を補修して飾る
2.風炉用敷板
3.鍋敷
飾るのは意外につまらない。風炉用敷板だと炉をどけないと肝心の絵が見えない。鍋を載せるまで見える鍋敷かな・・・。その場合の問題は熱の伝導率・・・。
とにもかくにもハート形・・・、愛情の証に贈り物にもいいかもね

本日は亡くなった家内の命日です。郷里に日帰りですが、行の飛行機はあるが、帰りの飛行機は欠航で、帰りは新幹線・・・。



















