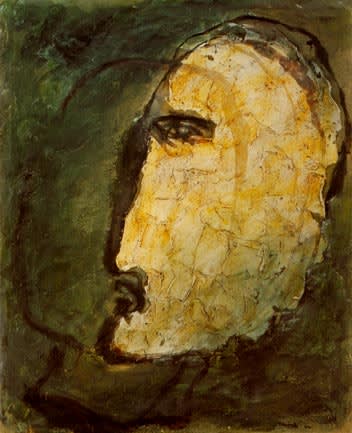ダークスーツに身を包んだ人たちが、足早にテムズ川に架かるロンドン橋を歩いてゆく。
戦闘モードなのか。
17世紀の大火で、木造建築禁止になり、石造建築に立て替えられたとか、現代建築のビルとあいまって、西欧の大都市とあまり差異のない街になっている。
もし、17世紀の大火がなくて、木造建築も許容されていたなら、どんな街になっていたのかと考えると、残念だ。
石造りに加え、街路樹さえあまりなくて、寒々しい様子。
ほっとできる場所は、セント・ポール大聖堂の前庭の緑、やや広めの公園にある木々、それから、ビクトリア朝のアーケード街か。
アーケード街には、飲食店や金融の真っ只中にある鮮魚店、花屋など、人の営みが集約されていた。
勤務中のお昼に、ビールを飲むビジネスマンがいたが、気分転換をするのに適度のアルコール(大きいグラスに2杯程度!)は最適で、酔わなければなんら問題ないといっていた。
全ての業種がそうできるわけでないだろうし、いくら日本人と違ってアルコールに強い西欧人にしても、この緩やかさは憧れてしまう。
みんなが同じようなダークスーツを身に纏っていても、これなら許せる気がする。
しかし、面白いのは、この世界の経済を動かす一つの峰を象徴するシティーのすぐ隣に、下町のイーストエンドがあることだ。
そこに一歩踏み込むと、行き交う人たちもアジア系・イスラム系・アフリカ系と国と人種が様々、街の様相も、一変してしまう。
エスニックな露天商が立ち並び、「バングラシティ」というスーパーマーケットが店を構えている。
かねてより、イーストエンドは労働者と移民の街としての役割を持っていた。
シティのような街を縁の下から支えるのには、このような性格の街が隣接することは、必要なのだろう。
表面化しない階級社会は、今の人権という観念が認められる世にあってなお、連綿と続いている。
人間という不完全な社会性動物にとっては、良しとはしたくなくとも、必要悪な構造なのかもしれない。
それを補っていくのが、個々人のそして為政者の良識というものなのだろ。
この拝金主義に毒されて、利害絡みのグローバリズムが進む世界にあって、「良識」というものが存亡に危機に晒されているようで、大変に不安だ。
時代が産み落とした負の遺産をそのままに、更に増やしていくのか。
真実は、時として残酷だ。
だが、目を背けてはならない。
為政者ならば、真実に真正面から向き合い、最悪の事態を避け、未来を少しでも明るく確保すべく、民衆を上手に導くのが勤めであろう。
目先の対応でお茶を濁し、取り返しのつかない未来を来る子孫に残していいものだろうか。
人の上にたち、人を導こうとする者は、重大な責務を負っているのだ。
歩む道は茨の道なのは、承知の上でないと困る。
羊飼いは、片時も気を抜いてはいけないのだ。
その助手である牧羊犬たちも、同様に。
ロンドンのシティに勤める人々は、高い生活水準を約束される代わりに、経済を上手く循環させなくてはいけなく、イーストエンドに住む人々は、社会生活が快適で順調におくれるように肉体労働に励まなくてはいけない。
各々が受け持った役割を果たすことで、世界が回っていくのではなかろうか。
シティとイーストエンドの対比はの鮮やかさゆえに、自ずと現れる階級社会を意識しないではいられなくなった。
戦闘モードなのか。
17世紀の大火で、木造建築禁止になり、石造建築に立て替えられたとか、現代建築のビルとあいまって、西欧の大都市とあまり差異のない街になっている。
もし、17世紀の大火がなくて、木造建築も許容されていたなら、どんな街になっていたのかと考えると、残念だ。
石造りに加え、街路樹さえあまりなくて、寒々しい様子。
ほっとできる場所は、セント・ポール大聖堂の前庭の緑、やや広めの公園にある木々、それから、ビクトリア朝のアーケード街か。
アーケード街には、飲食店や金融の真っ只中にある鮮魚店、花屋など、人の営みが集約されていた。
勤務中のお昼に、ビールを飲むビジネスマンがいたが、気分転換をするのに適度のアルコール(大きいグラスに2杯程度!)は最適で、酔わなければなんら問題ないといっていた。
全ての業種がそうできるわけでないだろうし、いくら日本人と違ってアルコールに強い西欧人にしても、この緩やかさは憧れてしまう。
みんなが同じようなダークスーツを身に纏っていても、これなら許せる気がする。
しかし、面白いのは、この世界の経済を動かす一つの峰を象徴するシティーのすぐ隣に、下町のイーストエンドがあることだ。
そこに一歩踏み込むと、行き交う人たちもアジア系・イスラム系・アフリカ系と国と人種が様々、街の様相も、一変してしまう。
エスニックな露天商が立ち並び、「バングラシティ」というスーパーマーケットが店を構えている。
かねてより、イーストエンドは労働者と移民の街としての役割を持っていた。
シティのような街を縁の下から支えるのには、このような性格の街が隣接することは、必要なのだろう。
表面化しない階級社会は、今の人権という観念が認められる世にあってなお、連綿と続いている。
人間という不完全な社会性動物にとっては、良しとはしたくなくとも、必要悪な構造なのかもしれない。
それを補っていくのが、個々人のそして為政者の良識というものなのだろ。
この拝金主義に毒されて、利害絡みのグローバリズムが進む世界にあって、「良識」というものが存亡に危機に晒されているようで、大変に不安だ。
時代が産み落とした負の遺産をそのままに、更に増やしていくのか。
真実は、時として残酷だ。
だが、目を背けてはならない。
為政者ならば、真実に真正面から向き合い、最悪の事態を避け、未来を少しでも明るく確保すべく、民衆を上手に導くのが勤めであろう。
目先の対応でお茶を濁し、取り返しのつかない未来を来る子孫に残していいものだろうか。
人の上にたち、人を導こうとする者は、重大な責務を負っているのだ。
歩む道は茨の道なのは、承知の上でないと困る。
羊飼いは、片時も気を抜いてはいけないのだ。
その助手である牧羊犬たちも、同様に。
ロンドンのシティに勤める人々は、高い生活水準を約束される代わりに、経済を上手く循環させなくてはいけなく、イーストエンドに住む人々は、社会生活が快適で順調におくれるように肉体労働に励まなくてはいけない。
各々が受け持った役割を果たすことで、世界が回っていくのではなかろうか。
シティとイーストエンドの対比はの鮮やかさゆえに、自ずと現れる階級社会を意識しないではいられなくなった。