【文中敬称略】
中国では、まず長春で漫才のステージを見た。
照明にムービングが使われ、大音量のサウンドが劇場を揺する、さながらショーアップされた格闘技のような派手な演出にまずド肝を抜かれたが、何より客席がいっぱいなのには驚いた。
日本も“お笑いブーム”だけれど、長春のそれは一時的でなく完全に生活の一部になっているなぁという印象を受けた。



通訳さんに後から聞いたが、長春は言葉が綺麗でスピード感もあり「笑い」のメッカなのだという。そういう意味でいえば、僕らはまさに「なんば花月」に入ったようなものだったのダ。
それから北京では話劇を。(弊ブログ「訪中譚⑨北京その3」07/12/17に詳細)
そして上海では、我々同様、中国公演にやって来た日本のカンパニーの公演を観る機会を得た。
文化座の橘さん、弊団の星野と僕の3人で『恋森』の仕込みを終えた「蘭心大劇院」から徒歩で向かったのは「上海芸海劇院」。
ダウンタウンを抜け、やがて伊勢丹などがある目抜き通りに至り、一気に街の灯が弱まる新興のオフィス街の一角の、新しい劇場へ。
約30分ほどのお散歩になった



観たのは東京ギンガ堂『孫文と梅屋庄吉』(脚本・演出/品川能正)
中国人俳優2人を配し、中国革命に賭けた孫文と、彼との盟約に生きた日本映画界の風雲児で日活の創始者でもある梅屋庄吉との30年に渡る交流を描いた舞台。
東京を皮切りに日本国内7都市を巡ったあと、北京へ。この上海で公演の後、南京へ移動するツアー。
実は、通訳の朱海慶からチケットを貰い、チラシ等の情報を得ずに椅子に座ったので、「ルイルイ♪」の太川陽介が梅屋庄吉役で登場したのに続き、その妻として、劇団昴の米倉紀之子が和服姿で登場したのには驚いた!
僕の


好きな女優さんの一人


であり、少々懇意にしてもいただいている。ので、1~2幕の休憩の間に慌てて花を買いに走るも、時既に遅く、店は閉まっており…仕方なく、日本のビール

を買って差し入れした(笑

)
まあ、そんなミーハーな行為はともかく。
星野も橘氏も、口を揃えて言ったのは「母国語の公演を異国で観て、その客席の反応がすごく勉強になった!」と。
なるほどである

我々制作者は、例えば訪中公演でいえば、中国人のお客様とともに客席にいて「ああ、こんなタイミングで受けるのか」「へえ、こういうシーンで笑うのか」と実感でき、それを出来るだけ役者に伝えるようにはしているが、それは間接的なもので、この日のように直接肌で感じることが自分たちの芝居に大いに参考になったというのである。
それから観劇後・・・孫文役の演技について「日本人があえてたどたどしく話しているんだ」「いや、あのカタコト感は中国人特有ダ」さらには「太極拳もすごかった!」「あれくらいは頑張れば出来る。それよりあの膨大な日本語を覚えるのは無理」と評価が二分した。
結果は冒頭書いたように、中国人俳優の一人、張春祥だった。
日本に帰って解ったのだが、彼は北京の京劇院に13年間所属したのち、フィールドを日本に移している俳優であった。在日京劇団「新潮劇院」を主宰し、京劇の普及に務める傍ら、中島みゆき『夜会』、新国立劇場『セツアンの善人』、野田マップ『パンドラの鐘』などで活躍していたのダ。
なので、どちらも当たり

とも言えますわナ

 ”桜の集いが賑々しく開催されました。
”桜の集いが賑々しく開催されました。





 だったのは、3/11付の弊ブログで少し触れた。。。新宿駅で僕が、東演後援会「ぱら~たの会」会員さんに偶然会って、てっきり“卒業する娘と、それを祝う父と母”と思われた3人をパチリと撮ってあげた。。。何気ない話が、なんと“還暦を迎える男性と、その妻になる33歳年下の女性と、その母親”だったという衝撃発言
だったのは、3/11付の弊ブログで少し触れた。。。新宿駅で僕が、東演後援会「ぱら~たの会」会員さんに偶然会って、てっきり“卒業する娘と、それを祝う父と母”と思われた3人をパチリと撮ってあげた。。。何気ない話が、なんと“還暦を迎える男性と、その妻になる33歳年下の女性と、その母親”だったという衝撃発言 であった
であった
 いやはや事実は小説より奇なり。
いやはや事実は小説より奇なり。 今年も大いに盛り上がったのであった。
今年も大いに盛り上がったのであった。









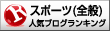


 2002年の訪中公演in上海の会場「上海話劇芸術センター」とホテルの間にあった、小さなお店。
2002年の訪中公演in上海の会場「上海話劇芸術センター」とホテルの間にあった、小さなお店。

 数行前に書いた「従業員控室」は今では個室。それでも足りずにさらに店自体が大幅な拡張&改装で、聞けば支店も出したのだと言う。
数行前に書いた「従業員控室」は今では個室。それでも足りずにさらに店自体が大幅な拡張&改装で、聞けば支店も出したのだと言う。 を所有できるわナ。
を所有できるわナ。 思えば、今回の1ヶ月に及ぶ旅の中でも、美味しいものを随分と食べました・・・長春のホテルのすぐ裏の餃子屋や北京の劇場近くの麺店など庶民的なところから、各地懇親会での少々ハイソなレストランまで・・・でも、やっぱ前者の方がお口に合ったかしら、僕には。
思えば、今回の1ヶ月に及ぶ旅の中でも、美味しいものを随分と食べました・・・長春のホテルのすぐ裏の餃子屋や北京の劇場近くの麺店など庶民的なところから、各地懇親会での少々ハイソなレストランまで・・・でも、やっぱ前者の方がお口に合ったかしら、僕には。



 を買って差し入れした(笑
を買って差し入れした(笑 )
)
 とも言えますわナ
とも言えますわナ
 ◎預園(撮影/笹山栄一)
◎預園(撮影/笹山栄一) 
 )で乱暴に扱うので、実は他の公演地でも、まず劇場に着くと修繕から入っていたのは事実。
)で乱暴に扱うので、実は他の公演地でも、まず劇場に着くと修繕から入っていたのは事実。








 第5回杉並演劇祭参加公演でもあり、第1回から区役所ロビーでの公演を目玉の一つとしている同演劇祭の中で、また新たな動きとしても評価したい試みであった。
第5回杉並演劇祭参加公演でもあり、第1回から区役所ロビーでの公演を目玉の一つとしている同演劇祭の中で、また新たな動きとしても評価したい試みであった。





 劇団東演俳優工房修了公演
劇団東演俳優工房修了公演 劇団東演俳優工房修了公演
劇団東演俳優工房修了公演
 19日20日と連休をいただきました。
19日20日と連休をいただきました。



 と、チグハグな浦和レッズのサッカーを見ながら考えた。
と、チグハグな浦和レッズのサッカーを見ながら考えた。 乞うご期待
乞うご期待
 大久保悠依
大久保悠依 小川由樹枝
小川由樹枝
 03-3419-2871 または
03-3419-2871 または
 左は、中間発表の舞台写真!
左は、中間発表の舞台写真!


 そんな狭き門をくぐり抜け、東演俳優工房で頑張って来た07年度の面々の、修了公演はいよいよ3/21(金)からだ!
そんな狭き門をくぐり抜け、東演俳優工房で頑張って来た07年度の面々の、修了公演はいよいよ3/21(金)からだ!

 3月29日(土)には、劇団と、東演をご愛顧いただいている(含むご愛顧予定?の)方々との
3月29日(土)には、劇団と、東演をご愛顧いただいている(含むご愛顧予定?の)方々との 春の懇親会
春の懇親会 かくいう東演も、新年会-桜の集い-夏のビアパーティーと、年がら年中呑んでいたようですが、近年は『朗読劇/月光の夏』をこだわって8月15日を中心に上演しているため「夏」はお休みしております
かくいう東演も、新年会-桜の集い-夏のビアパーティーと、年がら年中呑んでいたようですが、近年は『朗読劇/月光の夏』をこだわって8月15日を中心に上演しているため「夏」はお休みしております

 今日は完全なインフォメでしたナ。
今日は完全なインフォメでしたナ。 」と言われつつも、訪中レポート、いよいよラストスパートだよ
」と言われつつも、訪中レポート、いよいよラストスパートだよ




