ページの打たれたのは175まで、
ながら次頁は編集後記、
さらに広告が8頁あるから
184頁立ての雑誌ということになる。
図書館で初めてみた「月刊住職」。
誌名はその職業を表すように
なんの捻りもないまっすぐさだ。
たまたま手にした今年の正月号には
高橋源一郎、群ようこという
著名な作家のエッセイも掲載。
「宗教には興味が薄い」という内容を
ともに綴っていたけれど、
あえてそういう人を選んでいるのか、
最初は縁のある作家にお願いしていて、
それじゃつまらんと方向転換したのか、
何しろ初めましてなので解らない。

〈なりすまし住職の提訴に関する真相〉
というスキャンダラスな記事から始まり、
〈老若男女の居場所になる為の実例特集〉
〈明治期の葬儀対立〉など
幅広い内容で滅茶そそられたけれど、
上述の2編を読んだところで時間になり
後ろ髪を引かれながら書架に戻して
みなと図書館を出た。

その名の通り、港区の区役所にも近い
芝公園内にあるライブラリー。
雑誌発行も区内芝大門にある興山舎。
同誌のほかにも仏教系の本を出している
出版社。
「全宗派対応 葬儀実践全書」
「落語で大往生 お説教のススメ」など。
つくづく世の中の広さを、
広いひろい芝公園で東京タワーを
見上げながら、思った。










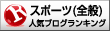






 吃驚
吃驚



 ただ字数を費やしそうなので
ただ字数を費やしそうなので

















 「ジャブジャブサーキット」
「ジャブジャブサーキット」

 さる16日、岐阜に観劇に向かった!
さる16日、岐阜に観劇に向かった!







