昭和39年版の「模型と工作・鉄道模型ガイドブック」から50年前の16番モデル工作とそれ以降のNモデルの思い出を語るある意味支離滅裂な企画(汗)です。
本書で取り上げられている16番の工作記事はその90パーセントがペーパー車体のモデルですが、少ないながらもブラスの工作記事も掲載されています。
今回はその少ない中のひとつであるEF58(初期型)を。
デッキの付いた電機、それも台車枠から自作するという中々本格的な工作記事で金属モデルの工作の入門用としては今でもそれなりに通用しそうです。
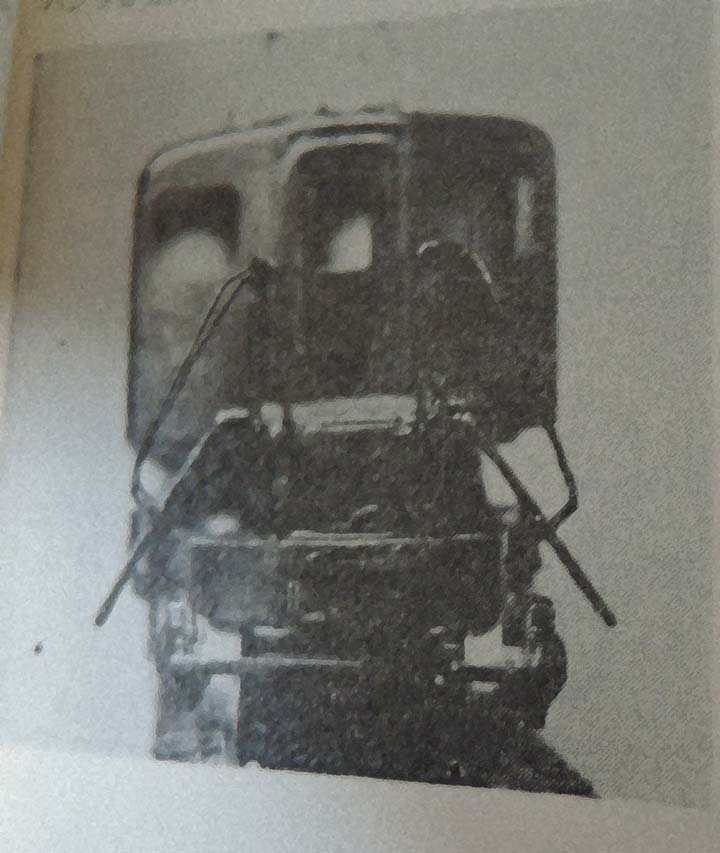
ブラス工作と言うとはんだ付けが付き物ですが、そこでも
「この場合、ペーストではうまく付きませんから塩化亜鉛を使います。塩化亜鉛は希塩酸に亜鉛を入れて作っても良いし薬局に行けば白い粉末の塩化亜鉛を売っています。これは劇薬なので購入の際には印鑑が要ります。これを10倍くらいの水に溶かして使いますとはんだが水の様に流れハンダ付けが楽しくなります」
結構物騒な事をさらっと書いている様に見えますが、あの当時はフラックスを使うのも最先端のテクニックだったという事でしょうか。
とはいえ、当時子供だった私はこのくだりを読んでたかが模型の工作に「購入時に印鑑がいる様な劇薬を使う」と言うのは結構なカルチャーショックではありました(笑)
ですから、ごく最近16番のC58の補修の折に模型屋でフラックスを購入した時にはそれなりに感慨深い物を感じたりしました。
一方でこの記事では台車周りの板バネや細かいパーツの取り付けなどでスーパーセメダインやボンドマスターなどの接着剤も取り入れています。
最近の工作記事などを見るとハンダ付けオンリー、逆に瞬着オンリーの両極端の話を結構聞きますが。
して見ると当時は今以上に適材適所の考えが浸透していたと思います。

さてNゲージのモデルですが流線型のEF58の方はどこのメーカーも手掛けていますし、どこのショップにも必ず置いてあると言っていい位に普及しています。
ところがデッキ付の初期型は量産品としてはマイクロエースから出ているのみ。
あとは金属モデル専門のメーカーが少数のキットや完成品をリリースしているにとどまります。
今回動員したのはワールド工芸の「EF18」
元々はEF58だったのをギア比を変えて貨物機に変更したという曰くがあるので外見上はEF58と大きな違いはありません。
今回はホキ4200の貨物列車を牽いてもらいました。

16番の製作記事もブラスならNのモデルもブラス製。
旧型EF58は不思議とブラスづいた機関車の様です。
本書で取り上げられている16番の工作記事はその90パーセントがペーパー車体のモデルですが、少ないながらもブラスの工作記事も掲載されています。
今回はその少ない中のひとつであるEF58(初期型)を。
デッキの付いた電機、それも台車枠から自作するという中々本格的な工作記事で金属モデルの工作の入門用としては今でもそれなりに通用しそうです。
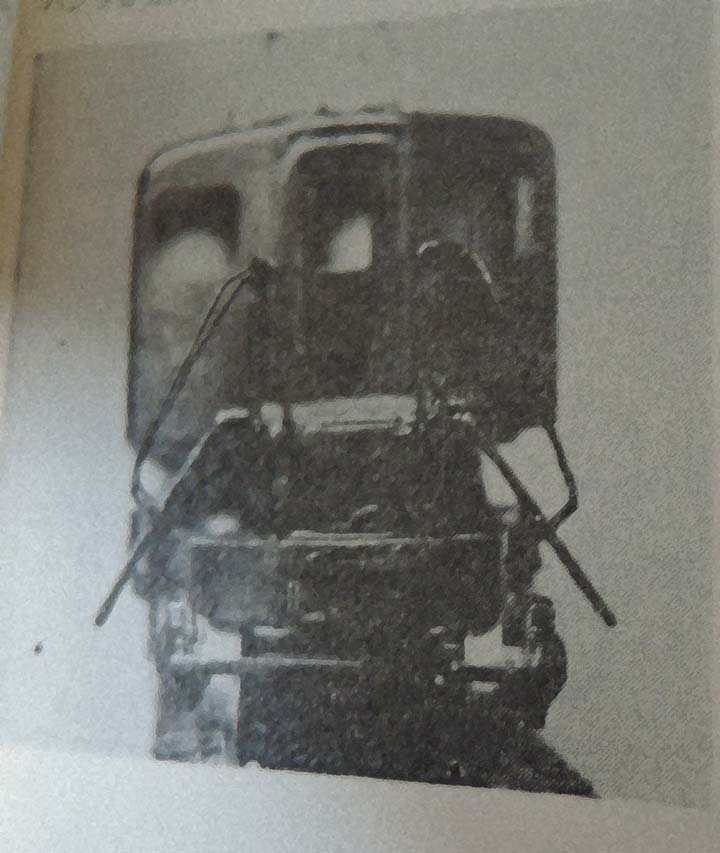
ブラス工作と言うとはんだ付けが付き物ですが、そこでも
「この場合、ペーストではうまく付きませんから塩化亜鉛を使います。塩化亜鉛は希塩酸に亜鉛を入れて作っても良いし薬局に行けば白い粉末の塩化亜鉛を売っています。これは劇薬なので購入の際には印鑑が要ります。これを10倍くらいの水に溶かして使いますとはんだが水の様に流れハンダ付けが楽しくなります」
結構物騒な事をさらっと書いている様に見えますが、あの当時はフラックスを使うのも最先端のテクニックだったという事でしょうか。
とはいえ、当時子供だった私はこのくだりを読んでたかが模型の工作に「購入時に印鑑がいる様な劇薬を使う」と言うのは結構なカルチャーショックではありました(笑)
ですから、ごく最近16番のC58の補修の折に模型屋でフラックスを購入した時にはそれなりに感慨深い物を感じたりしました。
一方でこの記事では台車周りの板バネや細かいパーツの取り付けなどでスーパーセメダインやボンドマスターなどの接着剤も取り入れています。
最近の工作記事などを見るとハンダ付けオンリー、逆に瞬着オンリーの両極端の話を結構聞きますが。
して見ると当時は今以上に適材適所の考えが浸透していたと思います。

さてNゲージのモデルですが流線型のEF58の方はどこのメーカーも手掛けていますし、どこのショップにも必ず置いてあると言っていい位に普及しています。
ところがデッキ付の初期型は量産品としてはマイクロエースから出ているのみ。
あとは金属モデル専門のメーカーが少数のキットや完成品をリリースしているにとどまります。
今回動員したのはワールド工芸の「EF18」
元々はEF58だったのをギア比を変えて貨物機に変更したという曰くがあるので外見上はEF58と大きな違いはありません。
今回はホキ4200の貨物列車を牽いてもらいました。

16番の製作記事もブラスならNのモデルもブラス製。
旧型EF58は不思議とブラスづいた機関車の様です。









