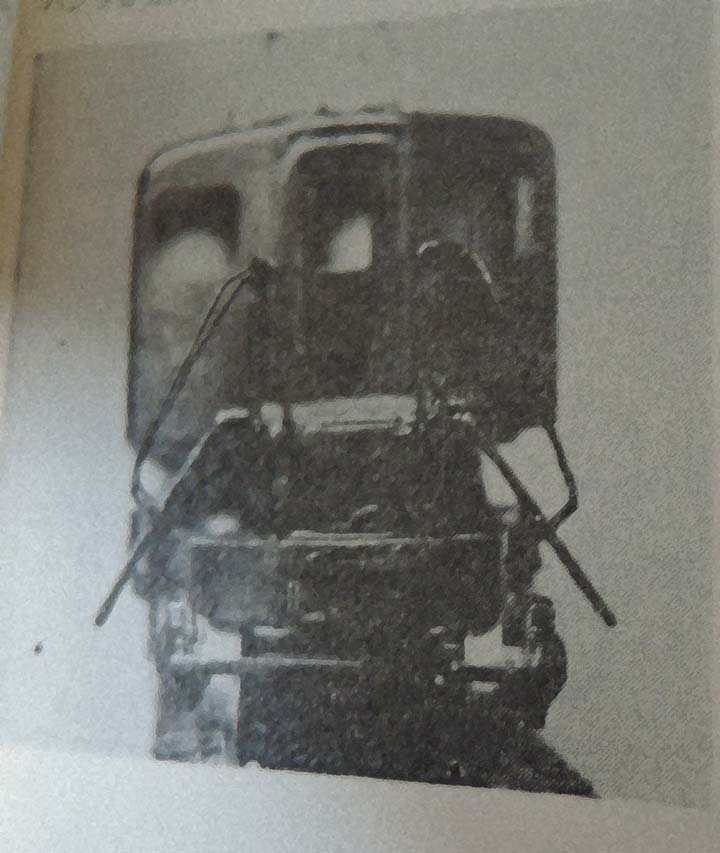夏風邪の方は相変わらずです。
と言いますか今週初め頃よりさらに具合が悪くなっている気が(汗)
単に体調だけではなく最近の不順な気候も関係していそうです。
今日も一日中雨で最高気温は24度を割っていますし。
そんな訳で今回もお茶を濁します(汗)

先日トミカでリリースされたX70系マークⅡ
マークⅡとしては最後の5ナンバーHT仕様のクルマですが、これが出てからもう30年経つ事に時代な流れと言う奴を痛感します。
当時はバブルのちょっと前辺りで「コロナより高級、でもクラウンより格下」な立ち位置だったマークⅡ自体が大衆車並みに売れ始めた時期でした。兄弟車のチェイサー、クレスタも同様で兄弟車でありながら微妙に雰囲気が異なる造形で差別化されたためか相乗効果で3姉妹トータルでの販売台数ではライバル(ローレル、ルーチェなど)を寄せ付けない状態が以後しばらく続くことになります。

本来スペシャリティ性が高くそれまで若者しか買わなかったハードトップボディの方がセダンより売れるという現象が定着したのもこの辺りからです。実際乗ってみると室内の狭さときたら「天井が低く横幅も狭い」とたまったものではなかった記憶がありますが、それでもこのタイプがファミリーカーとして認知されたのだから世の中は判りません。
実車のイメージカラーになり、実際街中で最も見かけたのが今回入手した「白いマークⅡ」です。

この時期、マークⅡのライバルとしては日産のローレルやマツダのルーチェ辺り、FF化したばかりのギャランΣも該当しますがそれらと並べて見るとデザイン的にマークⅡが一番スポーティさと高級感のバランスが取れている感じがします。
(そのせいか、実際に乗って見た時の居住性が一番劣っていたのも確かですが)

あの当時のマークⅡは高級ファミリーカーとしてお父さんが選ぶ車の最右翼でしたがその一方でいい若い者も結構飛びついていた車でもありました。雰囲気的に「4ドアのソアラ」みたいな所もあったからでしょう。
その目で見るとC130ローレルはデザインがぶっ飛び過ぎていましたし、ルーチェは微妙に安っぽく、Σは更に安っぽかった印象があります。この手の「誰でも選ぶ車」として当時のユーザーの期待の最大公約数に近い所にいたのがマークⅡ兄弟だったとも言えます。
このデザインセンスは極めて微妙なバランスの上に成り立っていると思います。このマークⅡのデザインの中の高級感、スポーティさ、保守性のどれかが突出するだけでもここまで売れる車にはならなかったでしょう。
その中で一番犠牲になったのが居住性ですが、歴代のマークⅡで一番居住性に気を配ったと思われる最終GX110系が一番ぱっとしないままに終わってしまったというのも何か皮肉な気もします。
NサイズミニカーのマークⅡは以前これのひとつ前の型のHTがカーコレクションで出ています。
ですが世間での普及と認知度の高さ、言い換えれば「風景の構成要素としての時代の証人」として使うならこれより後の3代くらいのマークⅡが似つかわしい気もします。
と言いますか今週初め頃よりさらに具合が悪くなっている気が(汗)
単に体調だけではなく最近の不順な気候も関係していそうです。
今日も一日中雨で最高気温は24度を割っていますし。
そんな訳で今回もお茶を濁します(汗)

先日トミカでリリースされたX70系マークⅡ
マークⅡとしては最後の5ナンバーHT仕様のクルマですが、これが出てからもう30年経つ事に時代な流れと言う奴を痛感します。
当時はバブルのちょっと前辺りで「コロナより高級、でもクラウンより格下」な立ち位置だったマークⅡ自体が大衆車並みに売れ始めた時期でした。兄弟車のチェイサー、クレスタも同様で兄弟車でありながら微妙に雰囲気が異なる造形で差別化されたためか相乗効果で3姉妹トータルでの販売台数ではライバル(ローレル、ルーチェなど)を寄せ付けない状態が以後しばらく続くことになります。

本来スペシャリティ性が高くそれまで若者しか買わなかったハードトップボディの方がセダンより売れるという現象が定着したのもこの辺りからです。実際乗ってみると室内の狭さときたら「天井が低く横幅も狭い」とたまったものではなかった記憶がありますが、それでもこのタイプがファミリーカーとして認知されたのだから世の中は判りません。
実車のイメージカラーになり、実際街中で最も見かけたのが今回入手した「白いマークⅡ」です。

この時期、マークⅡのライバルとしては日産のローレルやマツダのルーチェ辺り、FF化したばかりのギャランΣも該当しますがそれらと並べて見るとデザイン的にマークⅡが一番スポーティさと高級感のバランスが取れている感じがします。
(そのせいか、実際に乗って見た時の居住性が一番劣っていたのも確かですが)

あの当時のマークⅡは高級ファミリーカーとしてお父さんが選ぶ車の最右翼でしたがその一方でいい若い者も結構飛びついていた車でもありました。雰囲気的に「4ドアのソアラ」みたいな所もあったからでしょう。
その目で見るとC130ローレルはデザインがぶっ飛び過ぎていましたし、ルーチェは微妙に安っぽく、Σは更に安っぽかった印象があります。この手の「誰でも選ぶ車」として当時のユーザーの期待の最大公約数に近い所にいたのがマークⅡ兄弟だったとも言えます。
このデザインセンスは極めて微妙なバランスの上に成り立っていると思います。このマークⅡのデザインの中の高級感、スポーティさ、保守性のどれかが突出するだけでもここまで売れる車にはならなかったでしょう。
その中で一番犠牲になったのが居住性ですが、歴代のマークⅡで一番居住性に気を配ったと思われる最終GX110系が一番ぱっとしないままに終わってしまったというのも何か皮肉な気もします。
NサイズミニカーのマークⅡは以前これのひとつ前の型のHTがカーコレクションで出ています。
ですが世間での普及と認知度の高さ、言い換えれば「風景の構成要素としての時代の証人」として使うならこれより後の3代くらいのマークⅡが似つかわしい気もします。